◆演目について:
元は人形浄瑠璃で、「一谷嫩軍記」というお話しの中の三段目に当たる部分です。
◆人物関係:
今回の戦は初の親子参戦となる、義経の配下の武将:熊谷直実
初陣の息子が心配で本陣まできちゃった熊谷の奥さん:相模
以前、熊谷と相模の縁結びを果たした 敦盛のおっかさん:藤の方(秀太郎さん)
敦盛を助けたくて、熊谷に無言?の圧力をかけた義経さん(梅玉さん)
実は元平家の武士:弥平兵衛宗清で、平家鎮魂の石塔を立て続ける石屋の弥陀六(左團次さん)
熊谷からも相模からも信頼されてる、でも何者なんだろうこの人?な堤軍次(愛之助さん)
◆あらすじもどき:
大雑把に分けると↓こんな感じで。
・熊谷の戦場再現話
手紙も出すなと念を押しといたはずの女房:相模が来ている、
さらには、熊谷の所業を疑う梶原景高が来ている
と知り、まずいと思う熊谷。この2点は熊谷の身代わり計画にとって
誤算だったわけです。
熊谷夫婦の恩人:藤の方の息子:敦盛を討ったと聞き、奥から飛び出して熊谷を
襲う藤の方。
それを制して、戦場の再現話をする熊谷。
・・・すみません、仁左さん張り切ってやってたのに、ウトウトしちゃってました。
結構、メリハリがあって、そう、眠くなるようなもんでもなかったと思うのになぁ(ーー;)
・相模と藤の方の敦盛供養
敦盛の首を 義経公の元にもっていく準備をすると引っ込む熊谷。
残された女二人は、「せめて供養を」と、敦盛の愛笛を藤の方が吹くと
上手の一間のうちに少年の影が浮かび上がる。
気がついた藤の方が上手の障子をあけると、そこには敦盛の鎧。
・首実検
首実検に持っていく前に、せめて最後のお別れをと、せがむ二人の女性を
はねのけ、花道を義経の元へ急ごうとする熊谷。
ところがなぜか、奥から声あって、でてきたのは、たずねる先の義経。
というわけで、この場で首実検とあいなります。
で、熊谷が開けた首桶の中身に相模は一転、藤の方の立場となり、
悲しみのどん底に突き落とされることになります。
ここのところで、有名な熊谷の制札の見得。
今回は制札を逆さにして突く型でした。
本日のこの見得、きざはしに投げ出した長袴が、ちょっとねじくれちゃってました。(^_^;)
・弥陀六VS義経
突然、登場する石屋の弥陀六というじい様。
突然かと思ったけど、原作によると梶原が熊谷の詮議のために、
この館につれてきていたらしい。
身代わり首を注進しようとする梶原景時を石ミノで倒したものの、
義経に弥平兵衛宗清であることを見抜かれ、開き直って義経とやり取り。
この景時を石ミノを投げて倒す場面、景時が花道をひっこみきった後、
弥陀六が上手から出てきて、石ミノをなげ、揚幕のうちから 景時のうめき声が聞こえる
という演出になってます。
これ、ちょっとわかりにくいかも。
若くしてなくなった平家NO2.の小松殿に 促されて武士を捨て、平家の一族の霊を
鎮魂することになった弥陀六。
小松殿には、平家の行く末の危うさが見えてたんですねぇ。ほんと、平家は
惜しい人を早くに亡くしたねぇ
この小松殿、夜の「日向嶋景清」でも、からんできます。
・フィナーレ
敦盛が入った鎧櫃は弥陀六に託され、熊谷はスキンヘッドになり出家します。
・・・ちょっと待て熊谷!
あんたは 奥さんに相談なく息子を身代わりで殺して、また 奥さんに相談もなしに
息子をなくしてただでさえさみしい奥さんを1人残して、自分は出家しちまうのかっ!!
なんだかな~<(ーー;)
ついでに、敦盛が入った鎧櫃ですが、どうみてもあの大きさに齢16・17の兄ちゃんが
入るとは思われませんが・・・(^_^;)
それはさておき、鎧櫃をのぞいた時、敦盛が中にいると気がつき駆け寄ろうと
する藤の方を抑えるのに「中にはなぁんにもない」というのですが、
「なぁんにもない」はマズイのでは(^_^;) 「ほんに敦盛様の鎧だけ」とでも
言えばいいのに。
ちなみに、かの有名な「十六年は一昔」のセリフは、このラストにつぶやかれます。
◆演出・見所:
・幕外のひっこみ
最後の熊谷の出家のところ、送り三重の悲しみあふれる音色に送られる
とてもいい場面なんですが・・・
3階席の悲しさで 花道がほとんど見えないため、本舞台の幕が閉まり始めた時点で
芝居が終わったと思い、席を立ち上がる人が続出。
「まだあるの~っ お願い、立たないで~っ ざわつかないで~っ(>_<)」
と心のうちで叫んでました。(T_T)
「義経千本桜」みたいに「ひっこみがあるよっ!」というのがあると・・・
ってわけにも、いかないですよねぇ、この場面じゃ・・・<(ーー;)
せめて、イヤホンガイドさんが「この先があるので、まだ席をたたないで」と
一言言ってくれると違うと思うんですが・・・
・相模と藤の方
敦盛の供養をするところ、雀右衛門さんもセリフがばっちり入ってるし、
見ごたえのある女形さんの共演で安心してみれる感じです。
・仁左さんのスキンヘッド。
いや、たんに好きなんです。(^_^;)
・愛之助さんの雀右衛門さんサポート
堤軍次役の愛之助さんが、随所で足に不安のある雀右衛門さんに手を貸すところが
あります。
黒子さんが手を貸すより、なんか自然な感じで、いいなと個人的に思いました。
◆花道度:高
数珠を握る熊谷の出は、数珠が見えず<(ーー;)
他には梶原景時がひっこんで、
◆その他:
原作の浄瑠璃では、この場の前に、
・相模が陣屋にやってくる
・藤の方が陣屋に逃げ込んでくる
・梶原が弥陀六をつれて詮議にやってくる
という場面があるそうです。
ここもやってくれると 藤の方や弥陀六の登場に無理というか
唐突感がないんですけどね。
それから、梶原が義経の元へ行くのに花道に 向かおうとしたら、
陣屋の奥から義経が出てきて止めるというのが、「義経さんてば
いつの間に陣屋に来てたの?」と、疑問でした。
その義経さんの来訪にからんだ、弥陀六のセリフがあります
「幽霊の講釈聞いて一安心」
原作では 義経さんが「既に奥の間で敦盛と会い、藤の方に幽霊を見せたと聞いた」
というようなセリフがあるそうで、それを受けてこのセリフがでてくるそうなんです。
文楽だと↑このセリフを省いた場合は
「制札の講釈聞いて一安心」
になるそうですが、なぜか、歌舞伎は「幽霊」のままになってるそうです。
歌舞伎も「制札」にしちゃえばいいのになぁと思ったりもします。
元は人形浄瑠璃で、「一谷嫩軍記」というお話しの中の三段目に当たる部分です。
◆人物関係:
今回の戦は初の親子参戦となる、義経の配下の武将:熊谷直実
初陣の息子が心配で本陣まできちゃった熊谷の奥さん:相模
以前、熊谷と相模の縁結びを果たした 敦盛のおっかさん:藤の方(秀太郎さん)
敦盛を助けたくて、熊谷に無言?の圧力をかけた義経さん(梅玉さん)
実は元平家の武士:弥平兵衛宗清で、平家鎮魂の石塔を立て続ける石屋の弥陀六(左團次さん)
熊谷からも相模からも信頼されてる、でも何者なんだろうこの人?な堤軍次(愛之助さん)
◆あらすじもどき:
大雑把に分けると↓こんな感じで。
・熊谷の戦場再現話
手紙も出すなと念を押しといたはずの女房:相模が来ている、
さらには、熊谷の所業を疑う梶原景高が来ている
と知り、まずいと思う熊谷。この2点は熊谷の身代わり計画にとって
誤算だったわけです。
熊谷夫婦の恩人:藤の方の息子:敦盛を討ったと聞き、奥から飛び出して熊谷を
襲う藤の方。
それを制して、戦場の再現話をする熊谷。
・・・すみません、仁左さん張り切ってやってたのに、ウトウトしちゃってました。
結構、メリハリがあって、そう、眠くなるようなもんでもなかったと思うのになぁ(ーー;)
・相模と藤の方の敦盛供養
敦盛の首を 義経公の元にもっていく準備をすると引っ込む熊谷。
残された女二人は、「せめて供養を」と、敦盛の愛笛を藤の方が吹くと
上手の一間のうちに少年の影が浮かび上がる。
気がついた藤の方が上手の障子をあけると、そこには敦盛の鎧。
・首実検
首実検に持っていく前に、せめて最後のお別れをと、せがむ二人の女性を
はねのけ、花道を義経の元へ急ごうとする熊谷。
ところがなぜか、奥から声あって、でてきたのは、たずねる先の義経。
というわけで、この場で首実検とあいなります。
で、熊谷が開けた首桶の中身に相模は一転、藤の方の立場となり、
悲しみのどん底に突き落とされることになります。
ここのところで、有名な熊谷の制札の見得。
今回は制札を逆さにして突く型でした。
本日のこの見得、きざはしに投げ出した長袴が、ちょっとねじくれちゃってました。(^_^;)
・弥陀六VS義経
突然、登場する石屋の弥陀六というじい様。
突然かと思ったけど、原作によると梶原が熊谷の詮議のために、
この館につれてきていたらしい。
身代わり首を注進しようとする梶原景時を石ミノで倒したものの、
義経に弥平兵衛宗清であることを見抜かれ、開き直って義経とやり取り。
この景時を石ミノを投げて倒す場面、景時が花道をひっこみきった後、
弥陀六が上手から出てきて、石ミノをなげ、揚幕のうちから 景時のうめき声が聞こえる
という演出になってます。
これ、ちょっとわかりにくいかも。
若くしてなくなった平家NO2.の小松殿に 促されて武士を捨て、平家の一族の霊を
鎮魂することになった弥陀六。
小松殿には、平家の行く末の危うさが見えてたんですねぇ。ほんと、平家は
惜しい人を早くに亡くしたねぇ
この小松殿、夜の「日向嶋景清」でも、からんできます。
・フィナーレ
敦盛が入った鎧櫃は弥陀六に託され、熊谷はスキンヘッドになり出家します。
・・・ちょっと待て熊谷!
あんたは 奥さんに相談なく息子を身代わりで殺して、また 奥さんに相談もなしに
息子をなくしてただでさえさみしい奥さんを1人残して、自分は出家しちまうのかっ!!
なんだかな~<(ーー;)
ついでに、敦盛が入った鎧櫃ですが、どうみてもあの大きさに齢16・17の兄ちゃんが
入るとは思われませんが・・・(^_^;)
それはさておき、鎧櫃をのぞいた時、敦盛が中にいると気がつき駆け寄ろうと
する藤の方を抑えるのに「中にはなぁんにもない」というのですが、
「なぁんにもない」はマズイのでは(^_^;) 「ほんに敦盛様の鎧だけ」とでも
言えばいいのに。
ちなみに、かの有名な「十六年は一昔」のセリフは、このラストにつぶやかれます。
◆演出・見所:
・幕外のひっこみ
最後の熊谷の出家のところ、送り三重の悲しみあふれる音色に送られる
とてもいい場面なんですが・・・
3階席の悲しさで 花道がほとんど見えないため、本舞台の幕が閉まり始めた時点で
芝居が終わったと思い、席を立ち上がる人が続出。
「まだあるの~っ お願い、立たないで~っ ざわつかないで~っ(>_<)」
と心のうちで叫んでました。(T_T)
「義経千本桜」みたいに「ひっこみがあるよっ!」というのがあると・・・
ってわけにも、いかないですよねぇ、この場面じゃ・・・<(ーー;)
せめて、イヤホンガイドさんが「この先があるので、まだ席をたたないで」と
一言言ってくれると違うと思うんですが・・・
・相模と藤の方
敦盛の供養をするところ、雀右衛門さんもセリフがばっちり入ってるし、
見ごたえのある女形さんの共演で安心してみれる感じです。
・仁左さんのスキンヘッド。
いや、たんに好きなんです。(^_^;)
・愛之助さんの雀右衛門さんサポート
堤軍次役の愛之助さんが、随所で足に不安のある雀右衛門さんに手を貸すところが
あります。
黒子さんが手を貸すより、なんか自然な感じで、いいなと個人的に思いました。
◆花道度:高
数珠を握る熊谷の出は、数珠が見えず<(ーー;)
他には梶原景時がひっこんで、
◆その他:
原作の浄瑠璃では、この場の前に、
・相模が陣屋にやってくる
・藤の方が陣屋に逃げ込んでくる
・梶原が弥陀六をつれて詮議にやってくる
という場面があるそうです。
ここもやってくれると 藤の方や弥陀六の登場に無理というか
唐突感がないんですけどね。
それから、梶原が義経の元へ行くのに花道に 向かおうとしたら、
陣屋の奥から義経が出てきて止めるというのが、「義経さんてば
いつの間に陣屋に来てたの?」と、疑問でした。
その義経さんの来訪にからんだ、弥陀六のセリフがあります
「幽霊の講釈聞いて一安心」
原作では 義経さんが「既に奥の間で敦盛と会い、藤の方に幽霊を見せたと聞いた」
というようなセリフがあるそうで、それを受けてこのセリフがでてくるそうなんです。
文楽だと↑このセリフを省いた場合は
「制札の講釈聞いて一安心」
になるそうですが、なぜか、歌舞伎は「幽霊」のままになってるそうです。
歌舞伎も「制札」にしちゃえばいいのになぁと思ったりもします。










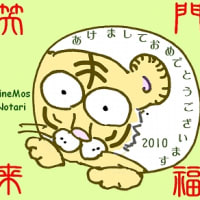







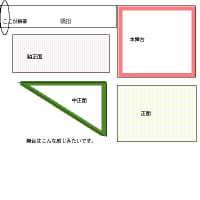




へぇ~ 鳩居堂の創業者は 熊谷直実のお血筋の方でしたか! これはトリビア。
あの、陣幕のハトマーク 結構 目につくんですよね。
私ははとサブレを思い浮かべたりしてましたが(^_^;)
記事自体は歌舞伎とはあまり関係なので恐縮です。
梅玉さんは確かにこの手の役で 右に出るものなし という感じ。気品がありますよね~。
弥陀六は左團次さんのしかみたことないんですが、
最近、左團次さんの当たり役を段四郎さんがやっていて、
どれもなかなかなので、段四郎さんも結構いいかもしれませんね♪
仁左さんは やっぱり、引っ込み、良かったんですね。
あー 観たかった~っ!(T_T)
仁左さん、良いねぇ。僧形もステキ、引っ込みも満足でした。雀様の相模に泣いてしまった。「隅田川」の時もオイオイ泣いたし、母親の心表現するのうまいねぇ。直実に言われて首をとりにいくときの「は、、、い、、」の返事もすごい、真似できない、複雑な気持ちを返事一つにも表していた。首を抱くところも打掛けで隠すところも、気持ちがビンビン伝わる。
それと梅玉の義経も良い、梅幸なき後彼が一番義経役者だわ。弥陀六というと先々代三津五郎を思いだすけど、今だと左團次が良いと思う。
という訳で顔ぶれも揃って見ごたえある一幕でした。