
地御前の町屋は外宮(地御前神社)の祭礼に伴う厳島の神官などの宿泊所や外宮を管理する人達が居住する門前町として成立した町屋であった。
この町屋には犬走りの部分に木柵を設けて軒下の空間を通りから区切るために設けた駒寄せがみられる。
犬垣、犬防ぎ、犬矢来、駒止め、駒留め、駒繋ぎ、牛繋ぎなどとも呼ばれているようであるが、人の寄り付きを避けるためのものとみられている。駒寄せは町屋の意匠に装飾的な要素を与えている装置の一つである。

地御前の町屋は外宮(地御前神社)の祭礼に伴う厳島の神官などの宿泊所や外宮を管理する人達が居住する門前町として成立した町屋であった。
この町屋には犬走りの部分に木柵を設けて軒下の空間を通りから区切るために設けた駒寄せがみられる。
犬垣、犬防ぎ、犬矢来、駒止め、駒留め、駒繋ぎ、牛繋ぎなどとも呼ばれているようであるが、人の寄り付きを避けるためのものとみられている。駒寄せは町屋の意匠に装飾的な要素を与えている装置の一つである。
 Amebaブログに移転
1ヶ月前
Amebaブログに移転
1ヶ月前
 Amebaブログに移転しました。
2ヶ月前
Amebaブログに移転しました。
2ヶ月前
 極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
 極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
 極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
 極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
 極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
極楽寺山-モリアオガエルの卵塊
2ヶ月前
 極楽寺今昔
2ヶ月前
極楽寺今昔
2ヶ月前
 極楽寺今昔
2ヶ月前
極楽寺今昔
2ヶ月前
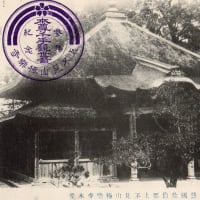 極楽寺今昔
2ヶ月前
極楽寺今昔
2ヶ月前
いつの時代の建物でしょうか?
江戸期末頃に建てられたようですが、現在も生活の場であり内部は改造されているようです。
外部は当時の意匠が残されており、いつまでも保存してほしいものですね。