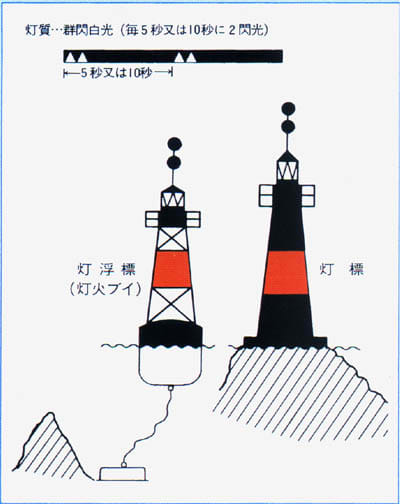今日は・・けいこばぁの・・実技試験の日。多分、介護福祉士の介護試験だと思う・・・。ま、ケアマネさんが通っているので、この試験に落ちても少しもかまわないらしい・・。それだし、あと何年もお仕事を続けることもないのだし・・。

で、高松市内の・・某有名高校の英明まで送って行って来た。何が有名なのかは知らないのだけれど・・。スポーツとか高校野球とかで有名になったこともあるし・・。もとは・・男子高校生の憧れだった「明善」とかいう女子高校だった・・。そこへ今は・・男子高校生が我が物顔で通っているらしい・・・。
朝の7時前に我が家を出て・・・8時前には学校に着いた。それらしい男女がうじゃうじゃと集まっていて、警備員が忙しそうに走り回っていた・・・。
私は・・・そこから・・・トイレを探して・・・山の中に入った。峰山という山には公園もあるし・・ということで・・・栗林トンネル方面に入って峰山に上った・・・。公衆トイレの場所は・・・自然に浮かび上がってくるのが不思議だった・・。

若い頃に・・・「讃岐歴史散歩シリーズ」を書くために・・この山の古墳群を調べたことを思い出した・・。ここの古墳群は、こうした安山岩の自然石を盛り上げた・・「積み石塚古墳」というのが特色。こういう角張った石を盛り上げて・・・前方後円墳や双方中円墳とか、普通の円墳、方墳なんぞもあって、その数は実に・・・200基・・。これは・・・異様な雰囲気だけれど、韓国にもこんな積み石塚古墳があると聞いた・・。

早い時期に盗掘されたようで、石棺などが無造作に放置されている・・・。そのままの状態で保存するのがいいと考えたのだろうが、犬の散歩や中高年のウォーキングで踏み荒らされているのはおかしいぞ・・と思った・・・。荒れ放題だし、踏み荒らし放題だ。少しばかり・・・トラロープで仕切りはしてあるが、そんなもの、何位の役にも立っていない・・・。

こうした・・古墳時代後期の横穴式古墳になると、あ、それらしいかなぁと思うけれど、小塚や猫塚、姫塚古墳などの積み石古墳は・・・単なる山としか思えないものばかり・・。
そこから・・・峰山墓地とか擂り鉢谷墓地とかばあがいけ墓地という・・・累々とした墓石群のなかを下りてくると・・・高松の氏神さん・・「石清尾(いわせお)八幡宮」に出る・・。だから・・先に見た古墳群も実は・・「石清尾山(いわせおやま)古墳群という・・。

まだ・・九時前だったからか・・・人影はほとんどない・・。静寂の中で見る神社は威厳がありそうな雰囲気・・・。「信は荘厳より生じる」という言葉が・・「なるほどなぁ・・」と思わせる。

ここの梅は満開状態・・・。しばらく・・境内を散策するが・・猫の子一匹にも会わなかった・・・。
そこから・・・再び・・・栗林トンネルを抜けて・・帰ってくる途中・・。「あ、そうだ・・」と思い直して・・・高松市一宮町の「田村神社」に寄ってみた・・・。朝から・・坊さんが神社をはしごしてどうするんだ・・。

ここは・・「讃岐一の宮・田村神社」で、赤い袴の巫女さんが・・・新車のお祓いをやってはる・・。いや・・・巫女さんに用がある訳ではなくて・・・。立てかけられた看板の字が見えるかな・・・。「うどん 百五十円」と書いてある。全く・・・「信心のない坊さん」そのものだな・・。

この神社の建物の中で・・・「田村神社日曜市」として、おうどんが販売されている。ここは、日曜日しか営業していない超レアなうどん店として有名。うどん玉がなくなればおしまい・・。「恐るべき讃岐うどん」とかという、攻略本を抱えた若者がにぎやかにうどんをビデオにおさめたりしてる・・。かくいう・・私もデジカメでうどんを撮影している・・・。

右側のおじさんが食券売り場で、150円を出すと食券を渡してくれる。食券を持って、この中程のカウンターでお盆を受け取り、どんぶりを受け取って、テーブルに着いて食べて・・・、この食券売りの向こうにいるおばさんに食器を返却しておしまい。お箸は・・・指定のお箸入れに整頓して並べておく。

こんなもの・・・。ほかにお寿司とか・・天ぷらとかもあるし、バクダン・・というものもあった。バクダンて何じゃろ・・。

で、麺はシンプルなもので、おいしいとかというものではない。麺はやわかくて・・お出汁は軽めの塩分控えめみたいな・・・。

ネギもあらかじめ・・・載せてくれている・・。おなじみさんは玉買いで、5玉とか10玉とかと買っている・・。

そんなんで、じゃぁ、また、明日、会えるといいね。