龍樹の「すべてを陽炎のごとく見よ」という神秘的な言葉を真に受けて、「この世界はまぼろしのようなものだから執着するな」と解釈する向きが多いようだ。まるで感受性が鈍いことが良いというふうなニュアンスで語られているのが気にかかる。空観に対して大きな誤解が敷衍されているような気がする。私は仏教において神秘的な言説というものはないと信じている。神秘的なのはこの世界であって、仏教自体はちっとも神秘的ではないのである。
空観を得て執着を断つというのは、単に無常の理をわきまえるという以上の意味はない。なにごとも永続しないから諦観が必要であるという当たり前の理屈である。
愛する息子の死を受け入れることのできないキサー・ゴータミーという女性に対し、釈尊は一人も死人が出たことのない家から白いケシの実をもらってくるようにと言った。キサーは一日中駆けずり回ったあげく、そんな家は一軒もないことを悟る。彼女はようやく息子の死を受け入れなければならないことを知るのである。命あるものはいつか死ぬ、それは当たり前理屈だが、その理屈がなかなか受け入れがたい。それをうけいれるためにはある程度の修業が必要なのだろう。だから釈尊は彼女に対し一つの修行を課した。「死人が出たことのない家」を探すことは言わば一つの公案と言ってもいいだろう。ゴータミーは一日中その公案に取り組んで、心身共にへとへとになった結果、ようやく無常の理を骨の髄から知らされるのである。
悲しみは悲しみとして受け入れねばならぬものは受け入れる、それが仏教的諦観であろうと思う。「みんなまぼろしだから、なにが起こってもへっちゃらだい。」というようなことではない。
この世界が無常であるならば、すべてははかないということは本当である。しかし、はかないからこそ美しいという見方も成り立つ。栂ノ尾の明恵上人は、あるとき野原に咲く一輪のすみれを見つけて落涙したという。はかないほど小さなスミレに妙を感じたのだろう。この感受性が仏教的慈悲につながっている。
最新の画像[もっと見る]
-
 学歴詐称をするような人が日本の首都の顔で良いのか?
1ヶ月前
学歴詐称をするような人が日本の首都の顔で良いのか?
1ヶ月前
-
 春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
-
 春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
-
 春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
春の野草 その2 ウラシマソウ
3ヶ月前
-
 春の野草
3ヶ月前
春の野草
3ヶ月前
-
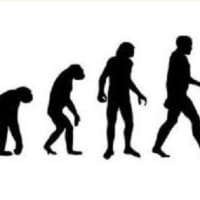 「進化する」と言うが、いったい何が進化しているのか?
5ヶ月前
「進化する」と言うが、いったい何が進化しているのか?
5ヶ月前
-
 100分de名著「偶然性・アイロニー・連帯」
5ヶ月前
100分de名著「偶然性・アイロニー・連帯」
5ヶ月前
-
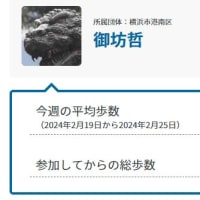 遅ればせながら大台達成
5ヶ月前
遅ればせながら大台達成
5ヶ月前
-
 塩分の摂取コントロールはとても重要
5ヶ月前
塩分の摂取コントロールはとても重要
5ヶ月前
-
 日本はUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)を支援し続けるべし
6ヶ月前
日本はUNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)を支援し続けるべし
6ヶ月前



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます