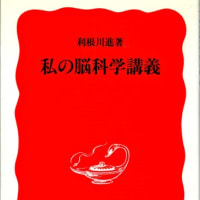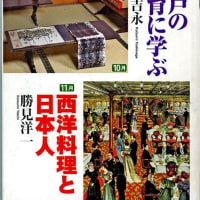K君の選択―医学部学士試験
(本稿の写真はすべて、現在までの団員諸君の「やんちゃ坊主振り」を紹介しています。こんな遊びを毎回重ねながら学んでいます)
前回は「学力」を築きあげるためにもっとも必要なもの、ほんとうにたいせつなものは何か?「中学受験時の難関中学合格力や一時的な偏差値の高さでは決してない」ということをお伝えしました。
それでは団が目指している指導法では、子どもたちはどう育つか? 順調に育ってくれたK君のその後です。
次はK君から依頼を受けた志望大学あての学士入学推薦書です。
京大大学院まですすんだ経歴から考えれば、たいせつな入学願書に同封する推薦書に名を連ねるべき、もっとふさわしい人たちがたくさんいるはずです。ところが、大阪の片隅でちっぽけな個人塾を開いているぼくに依頼してくれました。身に余る光栄で感激しました。
K君との小さいころからのやりとりを思い出しながらつづったのが左記です。「できるだけ、彼の等身大を正確に」と考えながら記しました。
推薦する理由
現職における臨床現場での経験を通じて、社会と人間の一生における医師という存在の責務の重要性を再確認し、その責務を担いたいという熱意と責任感、また新薬の開発経験・医療現場を実地に見聞し、よりいっそう医学の発展に貢献していきたいという本人の強い意志をうけて、この者を推薦するに至った。
大学合格時、私立の進学校で学んだ経験を振り返り、「先生、同級生にはぼくより優秀な人がたくさんいたけど、ぼくは努力ではだれにも負けなかった」とキラキラした目で報告してくれたことが忘れられない。
変革の時を迎えなければならないことがだれの目にも明らかな社会や国の現状を思うとき、その変革を可能にするためのパワーと資質をもっている希有な若者である。
日々仕事に従事しながら自らの思いと願いを実現させようとする強い意志と努力、また自己研鑽を忘れない日ごろの行動、苦しんでいる人・こまっている人を見過ごすことができない優しさは医師として、また医療に携わるものとして、この上なくふさわしい適性と資質であると信じる。
人格・性行
小学生時代から課題の提出の期限はもちろん、指導や指摘に対しても忠実に教えを守り、努力と精進を重ねつづけてくれている、大きな可能性を秘めた存在である。現在の知的レベルもその賜であろう。
社会行動や団体活動の中では決して自己を主張し過ぎることはなく、周囲の意見を柔軟に取り入れながら協調していくことができる。一方で、考えぬかれた自らの意見や主張もしっかり確立しており、理解した上で納得しなければ自説を曲げないという強さも備えている。
今の若者の多くは「自分に甘く他人にきびしく」が通り相場であるが、自身の行動に対しては、彼は曖昧さや妥協を一切許さない。反面、小学生時代の課外学習や合宿での指導体験以来、困っている人や苦しんでいる人に対しては、だれよりも思いやりが深く、優しい性格であることも確認済みである。
学業・研究の状況など
学業にも、妥協や曖昧さを好まないのはもちろんである。単純に暗記に終わるのではなく、解答に行き着く過程を厳密にたどり、事象の真理をも精査に追求する姿勢は特筆ものである。難解な問題を解決しようとする執念および集中力も申し分ない。学習や研究することの意味、学ぶ面白さ・学ぶ喜びが身についた上での学習意欲や知的探究心は、これから学ぶ医学にも十分発揮されることは疑いない。
その他
学生時代には部活動にも精力的に取り組み、文武両道を心掛けていたと聞いている。特に大学生活においては、所属する体育会ヨット部で部長を務め上げ、チームを十数年ぶりに全国大会へと導いた実績もあり、立派なキャプテンシーも兼ね備えていると考えられる。
以上、当人の資質・能力等を客観的かつ冷静に判断して、将来日本のみならず、すぐれた医師としてグローバルに活躍できる人材であると期待している。
「学体力」をともなわない「受験合格!」。その勉強に未来はあるのか?
もう、おわかりだと思います。

彼は京都大学大学院まで進んだのですが、専攻は保健学科でした。迎えられた治験会社で新薬開発のリサーチに現役の医師と臨床現場に同行するなかで、さまざまな疑念や思いを抱き、問題点に目覚めたのでしょう。そこで選んだのが医学の道でした。
26才になっていました。経済面のこともあり、勤務しながらの勉強です。しかし、さすがの彼もそれでは学習時間が十分とれず、昨年受験した学校すべてで失敗しました。強さはそこからです。
会社を退職し一年間を期限と決め、勉強に邁進しました。背水の陣。自分の人生を本当に意味のあるものにしたいという信念と努力。そして、今年。昨年不合格だった国立大学の学士入学試験をすべてクリアしました。
子どもたちみんなに身につけてほしいと願っている「学体力」の成就を体現してくれたK君。今はぼくが元気と大きな夢をもらっています。
これを読んでいただいたみなさんにおたずねしたいのです。
中学入学時の偏差値や難関中学合格という目標。「学体力」の育成をともなわない高い偏差値と受験「合格」勉強。はたして意味をもっていたでしょうか?
是非、子どもたちの本当の力を、そして無限の可能性を信じて指導してください。育ててください。キーポイントは偏差値でも、難関中学でもありません。「環覚」を養うこと、そして「学体力」を育てることです。些細な偏差値の上下や受験のテクニックの押しつけばかりで、子どもたちを、どうか「つぶさないように」してください。