中島敦『山月記』(新潮文庫)
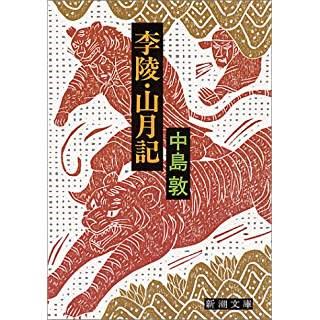
人はいかなる時に、人を捨てて畜生に成り下がるのか。中国の古典に想を得て、人間の心の深奥を描き出した「山月記」。母国に忠誠を誓う李陵、孤独な文人・司馬遷、不屈の行動人・蘇武、三者三様の苦難と運命を描く「李陵」など、三十三歳の若さでなくなるまで、わずか二編の中編と十数編の短編しか残さなかった著者の、短かった生を凝縮させたような緊張感がみなぎる名作四編を収める。(新潮文庫コピー)
◎『山月記』には元ネタがある
中島敦の発表作品は、喘息発作で亡くなる年に集中されています。中島敦は明治42(1909)年に東京で生まれました。父は中学の漢文教師でした。
中島敦は「カフカの変身譚、南方熊楠の民族的説話に触発され、ガーネット、アナトール・フランス、ロレンス、ハックスリー、韓非子、高青邱、王維などに傾倒」し、独自の文学世界を構築しました。(「新潮日本文学小辞典」より)
1934年中島敦は『虎狩』(『文庫版ちくま日本文学012・中島敦』所収)という作品を、「中央公論」懸賞公募に応募しています。残念ながら、選外佳作になりました。このときの入選作は、丹羽文雄『贅肉』(『鮎/母の日/妻・丹羽文雄短篇集』講談社文芸文庫所収)と島木健作『盲目』(青空文庫)でした。
その後教員生活をしながら、作品を発表しつづけました。中島敦の名前が文壇に知られるようになったのは、『山月記』(新潮文庫)からです。『光と風と夢』(『文庫版ちくま日本文学012・中島敦』所収)は芥川賞候補にもなっています。
中島敦の文章は、格調が高いことで知られています。それは幼いころ父親から受けた、漢文の素養があったからです。『山月記』には、元ネタがあります。それをみごとにそしゃくし、自らの文体で新たな作品世界を構築したのです。元ネタは中国の『人虎伝』だといわれています。
戦前の日本で『人虎伝』は、広く知られた作品のようです。島内景二『中島敦「山月記伝説」の真実』(文春新書)には、佐藤春夫も「親友が虎になっていた話」という作品があると書いています。調べてみましたが、文庫ではみつかりませんでした。
『山月記』は、多くの高等学校の教科書に採用されています。岩波ジュニア新書の阿刀田高『短編小説を読もう』でも、とりあげられています。それだけわかりやすい作品である、ということだと思います。
――『山月記』は中国の唐時代、俗悪な役人となって生きることを嫌った男・李徴(りちょう)が詩人として名を後世に残そうと励みましたが、それもままならず家族を捨てて独り山中にこもってしまいます。(阿刀田高『短編小説を読もう』岩波ジュニア新書P100より)
『山月記』については、森見登美彦が『新釈走れメロス』(祥伝社文庫)のなかの一編として、独自な世界を描いています。『夜は短し歩けよ乙女』(角川文庫)はあまり関心しませんでしたが、『新釈走れメロス』は後日「文庫で読む500+α」で取り上げたいと思っています。「山月記」の舞台をお得意の京都にし、主人公を大学生にし、虎を天狗に変えた、ユニークな仕上がりになっています。
◎猛虎が叢の中から躍り出た
主人公は李徴。
――隴西(ろうさい)の李徴は博学才頴(さいえん)。天宝「紀元八世紀」の年末、若くして名を虎榜(こぼう)に連ね、ついで江南慰に補せられたが、性、狷介、自ら恃(たの)む所すこぶる厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった。いくばくもなく官を退いた後は、故山、かく略に帰臥し、人と交を絶って、ひたすら詩作に耽った。(本文冒頭より)
これだけを書き写すのに、ずいぶん苦労してしまいました。結局「かく略」の「かく」の漢字は変換できませんでした。漢字辞書には熟語としてありませんし、手書き検索でみつけましたが、変換することはできない漢字でした。「新漢字林」によると部首は「虍」、総画15、部首内9画で「カク」とでています。
このように中島敦の作品は、むやみに漢字が多いのが特徴です。李徴という男は博学の人ですが、のほほんと賎吏に甘んじていることをヨシとしません。退職して詩作に没頭するために、隠遁生活をはじめた、といたって楽天的ですが。
ところが文筆業では、妻子を養うことができません。李徴はふたたび、官吏の道に舞い戻ることになります。しかし仲間たちは、すでに出世しています。自尊心の強い李徴は、出張の途中で行方不明になってしまいます。
翌年、袁惨(えんさん)という男が、赴任地に向かいます。宿屋に一泊し早朝の暗いうちに出発しようとしますと、「人喰い虎が出没するので、明るくなってから出かけたほうがいい」との助言を受けます。袁惨はそれを無視して出発します。
緊迫の場面を引用してみます。
――残月の光をたよりに林中の草地を通って行った時、果たして一匹の猛虎が叢の中から躍り出た。虎は、あわや袁惨に躍りかかるかと見えたが、忽(たちま)ち身を翻して、元の叢に隠れた。叢の中から人間の声で「あぶないところだった」と繰返し呟くのが聞こえた。(本文P9より)
その声に、袁惨は聞き覚えがありました。「その声は、我が友、李徴子ではないか?」と問いかけます。李徴は「いかにも自分は李徴だ」と名乗り、虎に変身したてんまつを語ります。最後に李徴は、自分の詩を後世に伝えてほしいと懇願します。
そしてラストの場面となります。活字のなかから、映像が浮かんできます。みごとなエンディングだと、思わずうなってしまいました。中島敦のもうひとつの代表作『李陵』も、同系統の作品です。ぜひあわせて読みたいものです。
(山本藤光:2010.07.10初稿、2018.02.14改稿)
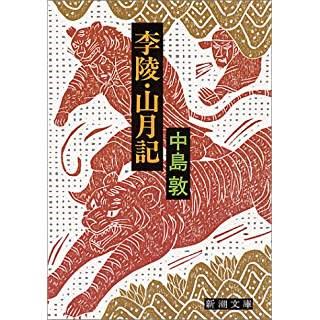
人はいかなる時に、人を捨てて畜生に成り下がるのか。中国の古典に想を得て、人間の心の深奥を描き出した「山月記」。母国に忠誠を誓う李陵、孤独な文人・司馬遷、不屈の行動人・蘇武、三者三様の苦難と運命を描く「李陵」など、三十三歳の若さでなくなるまで、わずか二編の中編と十数編の短編しか残さなかった著者の、短かった生を凝縮させたような緊張感がみなぎる名作四編を収める。(新潮文庫コピー)
◎『山月記』には元ネタがある
中島敦の発表作品は、喘息発作で亡くなる年に集中されています。中島敦は明治42(1909)年に東京で生まれました。父は中学の漢文教師でした。
中島敦は「カフカの変身譚、南方熊楠の民族的説話に触発され、ガーネット、アナトール・フランス、ロレンス、ハックスリー、韓非子、高青邱、王維などに傾倒」し、独自の文学世界を構築しました。(「新潮日本文学小辞典」より)
1934年中島敦は『虎狩』(『文庫版ちくま日本文学012・中島敦』所収)という作品を、「中央公論」懸賞公募に応募しています。残念ながら、選外佳作になりました。このときの入選作は、丹羽文雄『贅肉』(『鮎/母の日/妻・丹羽文雄短篇集』講談社文芸文庫所収)と島木健作『盲目』(青空文庫)でした。
その後教員生活をしながら、作品を発表しつづけました。中島敦の名前が文壇に知られるようになったのは、『山月記』(新潮文庫)からです。『光と風と夢』(『文庫版ちくま日本文学012・中島敦』所収)は芥川賞候補にもなっています。
中島敦の文章は、格調が高いことで知られています。それは幼いころ父親から受けた、漢文の素養があったからです。『山月記』には、元ネタがあります。それをみごとにそしゃくし、自らの文体で新たな作品世界を構築したのです。元ネタは中国の『人虎伝』だといわれています。
戦前の日本で『人虎伝』は、広く知られた作品のようです。島内景二『中島敦「山月記伝説」の真実』(文春新書)には、佐藤春夫も「親友が虎になっていた話」という作品があると書いています。調べてみましたが、文庫ではみつかりませんでした。
『山月記』は、多くの高等学校の教科書に採用されています。岩波ジュニア新書の阿刀田高『短編小説を読もう』でも、とりあげられています。それだけわかりやすい作品である、ということだと思います。
――『山月記』は中国の唐時代、俗悪な役人となって生きることを嫌った男・李徴(りちょう)が詩人として名を後世に残そうと励みましたが、それもままならず家族を捨てて独り山中にこもってしまいます。(阿刀田高『短編小説を読もう』岩波ジュニア新書P100より)
『山月記』については、森見登美彦が『新釈走れメロス』(祥伝社文庫)のなかの一編として、独自な世界を描いています。『夜は短し歩けよ乙女』(角川文庫)はあまり関心しませんでしたが、『新釈走れメロス』は後日「文庫で読む500+α」で取り上げたいと思っています。「山月記」の舞台をお得意の京都にし、主人公を大学生にし、虎を天狗に変えた、ユニークな仕上がりになっています。
◎猛虎が叢の中から躍り出た
主人公は李徴。
――隴西(ろうさい)の李徴は博学才頴(さいえん)。天宝「紀元八世紀」の年末、若くして名を虎榜(こぼう)に連ね、ついで江南慰に補せられたが、性、狷介、自ら恃(たの)む所すこぶる厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった。いくばくもなく官を退いた後は、故山、かく略に帰臥し、人と交を絶って、ひたすら詩作に耽った。(本文冒頭より)
これだけを書き写すのに、ずいぶん苦労してしまいました。結局「かく略」の「かく」の漢字は変換できませんでした。漢字辞書には熟語としてありませんし、手書き検索でみつけましたが、変換することはできない漢字でした。「新漢字林」によると部首は「虍」、総画15、部首内9画で「カク」とでています。
このように中島敦の作品は、むやみに漢字が多いのが特徴です。李徴という男は博学の人ですが、のほほんと賎吏に甘んじていることをヨシとしません。退職して詩作に没頭するために、隠遁生活をはじめた、といたって楽天的ですが。
ところが文筆業では、妻子を養うことができません。李徴はふたたび、官吏の道に舞い戻ることになります。しかし仲間たちは、すでに出世しています。自尊心の強い李徴は、出張の途中で行方不明になってしまいます。
翌年、袁惨(えんさん)という男が、赴任地に向かいます。宿屋に一泊し早朝の暗いうちに出発しようとしますと、「人喰い虎が出没するので、明るくなってから出かけたほうがいい」との助言を受けます。袁惨はそれを無視して出発します。
緊迫の場面を引用してみます。
――残月の光をたよりに林中の草地を通って行った時、果たして一匹の猛虎が叢の中から躍り出た。虎は、あわや袁惨に躍りかかるかと見えたが、忽(たちま)ち身を翻して、元の叢に隠れた。叢の中から人間の声で「あぶないところだった」と繰返し呟くのが聞こえた。(本文P9より)
その声に、袁惨は聞き覚えがありました。「その声は、我が友、李徴子ではないか?」と問いかけます。李徴は「いかにも自分は李徴だ」と名乗り、虎に変身したてんまつを語ります。最後に李徴は、自分の詩を後世に伝えてほしいと懇願します。
そしてラストの場面となります。活字のなかから、映像が浮かんできます。みごとなエンディングだと、思わずうなってしまいました。中島敦のもうひとつの代表作『李陵』も、同系統の作品です。ぜひあわせて読みたいものです。
(山本藤光:2010.07.10初稿、2018.02.14改稿)





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます