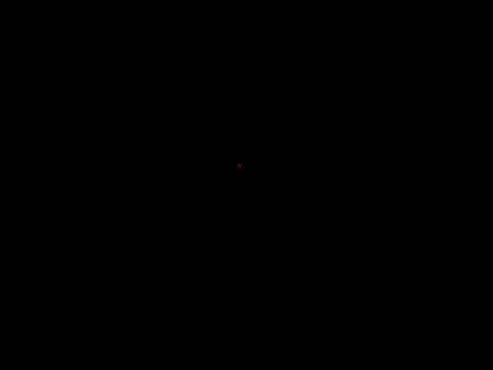今日のキク科の花(2)には、「アゲラタム」、「ユーパトリューム」、「ポンポンアザミ」を挙げてみました。
<「アゲラタム」>
円錐花序に紫、青、白、紅色の花を咲かせます、「菊」に似てもいますが長い糸状の花弁が特徴の一つです。
軟らかい質感の花を次々と咲かせるので、長い期間、愉しめます。
「カッコウアザミ」の別名が付いていますが、名前の由来は、葉がシソ科の「カッコウ」別名「カワミドリ」に似ていて
花が、「薊」に似ているからとか、亦、「アゲラタム」(Ageratum) は、ギリシャ語の Ageratos に因るとのこと
意味は、”年をとらない”、”色褪せない” なので、開花期が長く綺麗な色を保つからでしょうか
キク科、カッコウアザミ属、非耐寒性多年草(一年草)、中南米原産、学名 Ageratum houstonianum
英名 Ageratum、Floss flower
次に挙げる「ユーパトリウム・コエレスティナム」にも似ていますが葉の形状が、多少違うので区別できます。
アゲラタム属は、中南米に40種位自生しているとのことですが
主に植栽されているのは、ホウストニアヌム種を中心とした其の園芸種とのことです。
次も似た花の「ユーバトリウム・コエレスティナム」です。
<「ユーパトリウム・コエレスティナム」>
散房花序に頭花を咲かせて、筒状花から糸状の雌蘂を伸ばすので、「アゲラタム」の花の様に
花の姿が、「アゲラタム」同様、ポンポン状になります。
「フジバカマ(藤袴)/ユーパトリウム」 Eupatorium fortnei の仲間です。
草丈が、120cm位に迄高くなり、草丈が低い(30cm)位の「アゲラタム」との違いです。
亦、葉の形からも両者の違いが解ります、「アゲラタム」の葉が、卵形や丸形に対して
「ユーパトリウム・コエレスティナム」は、葉の先が尖っていて、三角形です。
キク科、コノクリニウム/ユーパトリウム(以前)属、耐寒性多年草、北アメリカ原産
学名 Eupatorium coelestinum=Conoclinium coelestinum、英名 Mist flower
別名「セイヨウフジバカマ」(西洋藤袴)、「ミスト フラワー」
「ミストフラワー」は、花の姿が、”霧” の様に”煙った” 様相からです。
「アゲラタム」と「ユーパトリウム・コエレスティナム」の違いは、下図の様に葉の形の違いです。
前者(左)の葉は、丸味を帯びていますが、後者(右)は、先端が尖った三角形です。
草丈の大小の違いは、前に記した通りです。


左図=「ユーパトリウム・コエレスティナム」の葉、右図=「アゲラタム」の葉
<「ポンポンアザミ」(カンプロクリニウム・マクロケファルム)>
此の「ポンポンアザミ」が、別名で「カオリアザミ」(香り薊)とか「モモイロハナビ」(桃色花火)の
名前が、付いているのだと思っていましたが、間違って覚えていたようです。
花の姿は、似てはいますが、学名が Vernonia glabra var.glabra / Wild heliotrope(ヴァーノニア・グラブラ)が
「香り薊」、「桃色花火」とのこと、「ヴァーノニア・グラブラ」の方が、香りが強いので
英名からも、この方が、「カオリアザミ」に指摘してると思います。
しかし、今更ですので、”花火” により似た「ポンポンアザミ」を
載せて、”花火を思い起こさせる花達” とします。
多数の筒状花が、一斉に開く様は、”花火” の炸裂を思わせます。
尚、愛知県では、侵略外来種と指定して、栽培、移動を禁止しているとのこと
キク科、カンプロクリニウム属、耐寒性多年草、南アフリカ原産、学名 Campuloclinium macrocephalum
英名 Pompom weed、Pompom bossie 別名「カンプロクリニウム」
「ポンポンアザミ」の花は、夜空に弾ける打ち上げ花火です。<以前の記事の最掲載映像>

花火が載った序でに、ヒユ科の「千日紅」の花を線香花火に見立てみました。
「千日紅 ’ファイヤーワークス’ 」 Gomphrena globsa 'Fireworks' / Globe Amaranth
一般の「千日紅」とは違って、筒状の総苞片の先端に黄色い小さな花を咲かせます。
「センイチコウ ’ファイヤーワークス’ 」(千日紅 花火)です。
〝線香花火” に準えた命名でしょうか、線香花火の様に小さな ”花火” です。
「千日紅 ' ファイヤーワークス’」は、線香花火です。<以前の記事の再掲載映像>