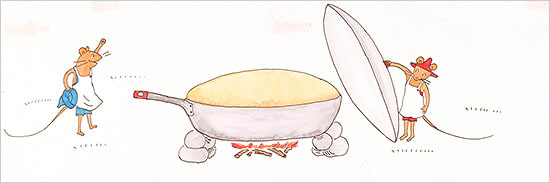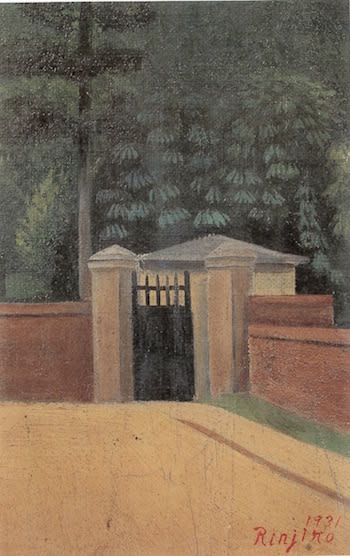ルノアールと言うと、リビングに貼られていた銀行のカレンダーのイメージがある。昭和30年代か40年代頃、高度成長の上り調子の時代に、誰しもが抱いていたステレオタイプの幸せと欲望のコード、欧米並みの生活イメージにそれはマッチしていたのだろう。そういえばルノアールの代表的な絵の主題にもなっているが、ピアノのある生活というのが多くの家庭の夢だった。いずれにしろ、当時、フランス絵画というとまずルノワールの名前が挙がるくらい、日本人には圧倒的になじみのある画家だった。しかし、今はどうだろうか。65歳を過ぎた自分にとってさえ、今「ルノアールが好きです」というのはちょっと憚れるところがある。その意味で120周年の記念企画にルノアールを今、大真面目で取り上げる地元新聞社の行く末が、余計なこととはいえ、ちょっと心配にもなる。
さて、誰にでも愛される絵である。ルノアールは、「絵画とは何か」という探求を主軸においた結果、理屈っぽくもなっていく近代画家とはもともと無縁の感性の画家であった。それは子だくさんの仕立て屋という貧乏な家庭に生まれたことと関わっていると思う。生まれたのが、中部フランス、18世紀以来の陶業の町王室製陶所にも指定されたリモージュであったことも、少なからず関係していることだろう。家族が生活のためパリに移り、ルノアールが13歳になったとき、ルノアールは陶器工場で小僧職人として働きはじめ、陶器の絵付けの仕事を経験する。ルノアールの絵の才は、最初の段階から「稼ぐ」こと、生活と結びついて、花開いていくのだ。
やがて環境の変化がルノアールを画家にする。手仕事に依存して陶器の絵付けの仕事が機械化にともない衰退していく中で、ルノアールは「絵を描いて売る」画家になることに活路を見出していったのだろう。そのために20歳で画学生となる。2年後には職人のときに習得した技術もあって早くもサロンに入選している。その画家としての初期にはコローやクールベ、ドラクロワの影響も受ける。やがて30代にはモネ、ピサロ、セザンヌといった画家に混じって、印象派展に参加する。しかし、その背後にある理論や精神に共感し確信的に印象派グループに加わったのではないのだろう。ルノアールにとってそれは自分の感性的世界を押し広げる新しい技法に過ぎなかったのではないか。
この展示会でもモネやセザンヌといっしょに描いた絵というのがあった。モネといっしょに描いた絵は、黒を効果的に使い、構図の取り方もまさしくモネ風の風景画だった。また、縦長のセザンヌと描いた絵(泉のそばの少女、魚かごを持つ少女)は、めずらしく背景の奥行きが明瞭でセザンヌの影響を感じさせられる絵で、ルノアールの絵の中では比較的自分には好きな部類に入る。(モデルのプロポーションもすらっとしていてエレガントだ。)ところで、こうした近代画家と交わりながら彼は絵画の革新や進歩などほとんど信じていない。だから中期には印象派が否定したはずのアングルに傾倒して、絵は外向の光のもとで描くべきだという印象派のテーゼすらも捨ててしまう。
しかし、ルノアールの好みには説得力ある客観性がない。どれも同じようなふっくらした頬の豊満な田舎風の女性が、どうしていいのかは分からない。この女性がどのような人格であるかなどは全く伝わってこない。そういう意味で同じような顔の、こちらは痩身の女性ばかりを描いたイギリスのラファエロ前派の絵に似たところがある。ただ自分の好みを確信した者の自分の感性に対する強烈な自信は伝わってくる。この趣味が戦後の日本の平和ムードにあったように、個人の快楽に基礎を置いた産業ブルジョアジーの新しい暮らしと趣味にたまたま合致して、画家の生活は成立したのだろう。時代の趣味や流行を独特の感性で射抜いた画家であった。
ルノアールの好みの画家に、ワットー(アントワーヌ)がいた。この画家もルイ王朝の趣味を背景にした宮廷画家だが、そこにはモーツアルトの音楽のような移りゆく哀しみがあって、極東の無常の国の人間にも訴えるものがある。特殊な文化的な衣装の奥底には人間の普遍的な感性があった。だが、ルノアールの絵からはそうしたネガティブな影はことごとく排除されている。貧しく育った者ゆえの臆病なのだろうか。絵画が生活に使われる絵皿の絵と同じであるなら、そんな絵があってはならないのだろう。その意味で彼の本質は、生活に喜びを与えるものを作る絵皿職人なのだ。他の影響を受けなくなる晩年になるとその傾向はますます強まる。ただし、かつてロココ時代のように絵画が宮廷を飾る巨大で華やかな絵皿の絵のようなものだった時代があったと考えれば、決してそれは非難にはあたらない。ルノアールはアノニマスなポンペイの壁画を賞賛しているが、それは絵が個人のものになってやせ細っていく時代へのアンチテーゼだったのかもしれない。
時代の趣味を独特の感性で射抜いた画家であったルノアールは、ゴッホと違って多くのパトロンを得て、生活に不自由することなく家族を養い、存命中に画壇に栄光も得た。だが、展示会の末尾に飾られていたルノアールの肖像(アルベール・アンドレ作)は、なぜか陰気で不幸せそうに見えた。「絵画とは人を幸福にする者でなくてはならない」(ルノアール)ことを倫理として課した者には皮肉な結果だ。しかし、不幸な者にほんとうの喜びは与えられるだろうか。ほんとうの幸福は、ルノアールが関わった印象派の中にも糸口としてあって、モネやセザンヌが謙虚に歩んだ道でもあるが、それはどんなに魅惑的であっても才能ある者の想念のうちにあるのではなく、私たちの前にある不思議な、驚くべき実在の世界との往還の中から生まれてくるものだ。それは写真的な写実とは違う、ついにはVISIONとしか言い得ないものだが、そこにしか描く者も見る者もともにほんとうの意味で幸福にする道はないと思う。
さて、誰にでも愛される絵である。ルノアールは、「絵画とは何か」という探求を主軸においた結果、理屈っぽくもなっていく近代画家とはもともと無縁の感性の画家であった。それは子だくさんの仕立て屋という貧乏な家庭に生まれたことと関わっていると思う。生まれたのが、中部フランス、18世紀以来の陶業の町王室製陶所にも指定されたリモージュであったことも、少なからず関係していることだろう。家族が生活のためパリに移り、ルノアールが13歳になったとき、ルノアールは陶器工場で小僧職人として働きはじめ、陶器の絵付けの仕事を経験する。ルノアールの絵の才は、最初の段階から「稼ぐ」こと、生活と結びついて、花開いていくのだ。
やがて環境の変化がルノアールを画家にする。手仕事に依存して陶器の絵付けの仕事が機械化にともない衰退していく中で、ルノアールは「絵を描いて売る」画家になることに活路を見出していったのだろう。そのために20歳で画学生となる。2年後には職人のときに習得した技術もあって早くもサロンに入選している。その画家としての初期にはコローやクールベ、ドラクロワの影響も受ける。やがて30代にはモネ、ピサロ、セザンヌといった画家に混じって、印象派展に参加する。しかし、その背後にある理論や精神に共感し確信的に印象派グループに加わったのではないのだろう。ルノアールにとってそれは自分の感性的世界を押し広げる新しい技法に過ぎなかったのではないか。
この展示会でもモネやセザンヌといっしょに描いた絵というのがあった。モネといっしょに描いた絵は、黒を効果的に使い、構図の取り方もまさしくモネ風の風景画だった。また、縦長のセザンヌと描いた絵(泉のそばの少女、魚かごを持つ少女)は、めずらしく背景の奥行きが明瞭でセザンヌの影響を感じさせられる絵で、ルノアールの絵の中では比較的自分には好きな部類に入る。(モデルのプロポーションもすらっとしていてエレガントだ。)ところで、こうした近代画家と交わりながら彼は絵画の革新や進歩などほとんど信じていない。だから中期には印象派が否定したはずのアングルに傾倒して、絵は外向の光のもとで描くべきだという印象派のテーゼすらも捨ててしまう。
しかし、ルノアールの好みには説得力ある客観性がない。どれも同じようなふっくらした頬の豊満な田舎風の女性が、どうしていいのかは分からない。この女性がどのような人格であるかなどは全く伝わってこない。そういう意味で同じような顔の、こちらは痩身の女性ばかりを描いたイギリスのラファエロ前派の絵に似たところがある。ただ自分の好みを確信した者の自分の感性に対する強烈な自信は伝わってくる。この趣味が戦後の日本の平和ムードにあったように、個人の快楽に基礎を置いた産業ブルジョアジーの新しい暮らしと趣味にたまたま合致して、画家の生活は成立したのだろう。時代の趣味や流行を独特の感性で射抜いた画家であった。
ルノアールの好みの画家に、ワットー(アントワーヌ)がいた。この画家もルイ王朝の趣味を背景にした宮廷画家だが、そこにはモーツアルトの音楽のような移りゆく哀しみがあって、極東の無常の国の人間にも訴えるものがある。特殊な文化的な衣装の奥底には人間の普遍的な感性があった。だが、ルノアールの絵からはそうしたネガティブな影はことごとく排除されている。貧しく育った者ゆえの臆病なのだろうか。絵画が生活に使われる絵皿の絵と同じであるなら、そんな絵があってはならないのだろう。その意味で彼の本質は、生活に喜びを与えるものを作る絵皿職人なのだ。他の影響を受けなくなる晩年になるとその傾向はますます強まる。ただし、かつてロココ時代のように絵画が宮廷を飾る巨大で華やかな絵皿の絵のようなものだった時代があったと考えれば、決してそれは非難にはあたらない。ルノアールはアノニマスなポンペイの壁画を賞賛しているが、それは絵が個人のものになってやせ細っていく時代へのアンチテーゼだったのかもしれない。
時代の趣味を独特の感性で射抜いた画家であったルノアールは、ゴッホと違って多くのパトロンを得て、生活に不自由することなく家族を養い、存命中に画壇に栄光も得た。だが、展示会の末尾に飾られていたルノアールの肖像(アルベール・アンドレ作)は、なぜか陰気で不幸せそうに見えた。「絵画とは人を幸福にする者でなくてはならない」(ルノアール)ことを倫理として課した者には皮肉な結果だ。しかし、不幸な者にほんとうの喜びは与えられるだろうか。ほんとうの幸福は、ルノアールが関わった印象派の中にも糸口としてあって、モネやセザンヌが謙虚に歩んだ道でもあるが、それはどんなに魅惑的であっても才能ある者の想念のうちにあるのではなく、私たちの前にある不思議な、驚くべき実在の世界との往還の中から生まれてくるものだ。それは写真的な写実とは違う、ついにはVISIONとしか言い得ないものだが、そこにしか描く者も見る者もともにほんとうの意味で幸福にする道はないと思う。