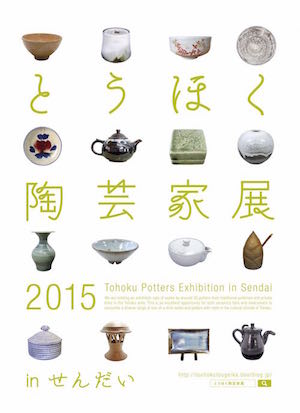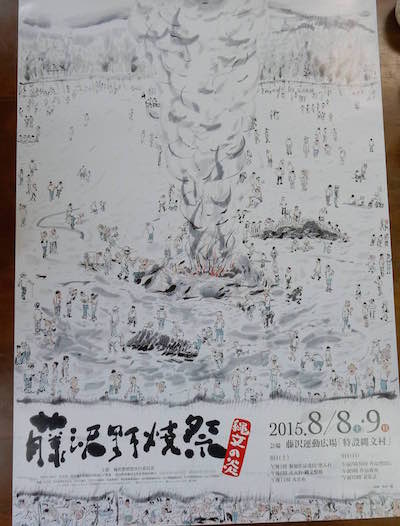ずいぶん前になるがパリのポンピドゥーセンターからしばらく歩いて古い下町マレー地区にあるピカソ美術館を訪れた。貴族の館の内部をモダンに改築した中をぐるっとひとめぐりしたはずだが、狭い入り口を通り抜けた薄暗い一部屋に、すさまじく強い印象の女性の絵があったなという程度で、正直言ってほとんど記憶が飛んでいる。それほどに無感動だったというより、「初期の青の時代」から最晩年に至るまで、20室あまりに展示されている「アヴィニョンの娘たち」をはじめとした傑作の数々を、自分の狭小な脳が2~3時間の鑑賞でカバー出来るわけがない、ということであったのだろう。
もっとも、ルネサンス以来の西洋絵画史の系譜的なカテゴリーを、たった一人の力で横断(縦断ではない)し尽くして、近代絵画にも伏在していたプラトン主義的な流れを完膚なきまでに破壊し解体していった怪物は、凡庸な我々が捉えきれるような者ではない。作品の即物性にならって、あえて喩えていえばつぎつぎ運ばれてくる(=目に飛び込んでくる)動物の肢体(=対象)を鋭いナイフで的確に素早く腑分けしていく、疲れを知らない食肉解体マシーン(そんなものある?)のような存在だ。このような存在は、行為の跡についてはいろいろ言えるが、内面を捉えようとしても難物中の難物、「食えないやつだ」としか言いようがないだろう。小林秀雄でさえ、「近代絵画」の中でピカソに最も大きなボリュームを割いているが、その筆致はドストエフスキーを語るときに似て最終段に至るまで何かぐずぐずした印象を与えている。
その点、この展示会は、褒めているのか、貶しているのか分からない表現となるが、ピカソの膨大な作品群から選りすぐりとは必ずしも言えない約80点しか見られなかったのが自分には良かった。とりわけ晩年の数点は、ピカソという存在を理解するうえで役に立った。そして著作の中でピカソに対する最大級のオマージュを述べている岡本太郎とその作品に関わるちょっとした発見もあった。(続く)
もっとも、ルネサンス以来の西洋絵画史の系譜的なカテゴリーを、たった一人の力で横断(縦断ではない)し尽くして、近代絵画にも伏在していたプラトン主義的な流れを完膚なきまでに破壊し解体していった怪物は、凡庸な我々が捉えきれるような者ではない。作品の即物性にならって、あえて喩えていえばつぎつぎ運ばれてくる(=目に飛び込んでくる)動物の肢体(=対象)を鋭いナイフで的確に素早く腑分けしていく、疲れを知らない食肉解体マシーン(そんなものある?)のような存在だ。このような存在は、行為の跡についてはいろいろ言えるが、内面を捉えようとしても難物中の難物、「食えないやつだ」としか言いようがないだろう。小林秀雄でさえ、「近代絵画」の中でピカソに最も大きなボリュームを割いているが、その筆致はドストエフスキーを語るときに似て最終段に至るまで何かぐずぐずした印象を与えている。
その点、この展示会は、褒めているのか、貶しているのか分からない表現となるが、ピカソの膨大な作品群から選りすぐりとは必ずしも言えない約80点しか見られなかったのが自分には良かった。とりわけ晩年の数点は、ピカソという存在を理解するうえで役に立った。そして著作の中でピカソに対する最大級のオマージュを述べている岡本太郎とその作品に関わるちょっとした発見もあった。(続く)