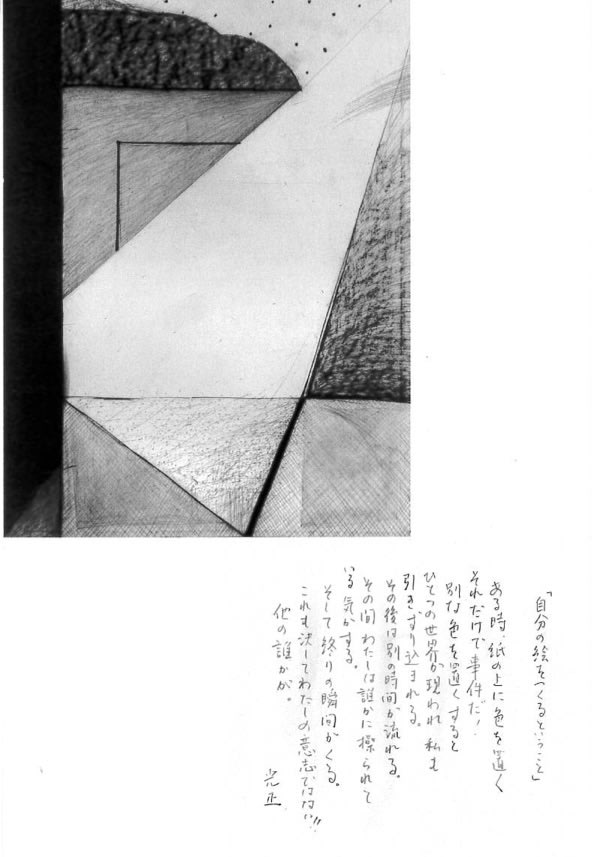オペさんの窯の名「雷窯」は、近くにある神社の来歴と関係がある。折石(さくせき)神社というのがその名だが、大樹に囲まれたこんもりとした丘陵があって、お狐さんの石像を両脇に配した鳥居と社に通じる石段が設けられているのが県道からも見える。オペさんの話だが、社には雷に打たれて割れた大石がご神体として祀られているという。幻妖な趣きの大きなお狐さんといい、鈍感な私にも強い霊気が感じられて、何だかおっかない。勝手な想像だが、古代ケルトの石の文化と近似するものを感じて、オペさんはこのパワースポットを選んだのだろうか?それについては今度会うときに聞いてみることにしよう。
オペさんの窯はこの神社と県道を挟んで向かい側の丘を分け入ったところにある。以前来訪したときの記憶をたどって走ったが、結局行き着けず、折石神社の前まで迎えに来てもらった。彼の工房は立木に埋もれるように建っていた。古代然とした環境と山里の隠れ家のようなこの小さな家で、英国ポップな作品が作られているとは誰も思うまい。
オペブランドは、カラフルなレインボーカラーの釉がけで知られる。雷雨のあとにかかる虹は、工房の場所とも結びつく。オペさんの器には、雨雲が去り光が差して虹がかかるときの晴れやかさが感じられる。しかし、よくある衣裳に走って使いにくい器ではない。とりわけ紅茶茶碗には、英国と日本の用の器の伝統が絶妙に融合されていて、我が家では常用品となっている。
ロンドンの中心部から少しはずれた静かな住宅街に生まれ、大学をドロップアウトして、アルバイトでためた資金を元に世界に飛び出した。様々な仕事をしながら、米国を縦断し、ハワイ、フィリピンを経て、少年時代の焼物修行で中国系の先生から教えられた焼物の本場、日本に行き着いた。それから相馬焼に弟子入りするまでの詳しい経緯は、最近出た雑誌「りらく」を見て欲しい。オペさんにとって極東日本は、思うがまま轆轤を引くための「虹の端」だったのだ。
オペさんはコンクールにも意欲的に挑戦し賞をとっている。訪れたときも4月の半ばから始まる日本現代美術工芸展 に出品するという作品が置いてあった。口を半ば開いた貝のような形状の作品は、外に雲がたなびき、内側にはやはりあのレインボーが描かれていた。
帰り際、鴨居の上にデビット・ボウイのな70年代の傑作「アラジン・セイン」のアルバム表紙が飾られているのが目に入った。虹色のブラシを顔に施したボウイの写真とオペさんとのつながりについても、今度の展示会で聞いて見ることにしよう。
「折石神社」については以下に詳しい。
https://blog.goo.ne.jp/inehapo/e/a15755737e4ad77daf01349d7be361bf
オペさんの窯はこの神社と県道を挟んで向かい側の丘を分け入ったところにある。以前来訪したときの記憶をたどって走ったが、結局行き着けず、折石神社の前まで迎えに来てもらった。彼の工房は立木に埋もれるように建っていた。古代然とした環境と山里の隠れ家のようなこの小さな家で、英国ポップな作品が作られているとは誰も思うまい。
オペブランドは、カラフルなレインボーカラーの釉がけで知られる。雷雨のあとにかかる虹は、工房の場所とも結びつく。オペさんの器には、雨雲が去り光が差して虹がかかるときの晴れやかさが感じられる。しかし、よくある衣裳に走って使いにくい器ではない。とりわけ紅茶茶碗には、英国と日本の用の器の伝統が絶妙に融合されていて、我が家では常用品となっている。
ロンドンの中心部から少しはずれた静かな住宅街に生まれ、大学をドロップアウトして、アルバイトでためた資金を元に世界に飛び出した。様々な仕事をしながら、米国を縦断し、ハワイ、フィリピンを経て、少年時代の焼物修行で中国系の先生から教えられた焼物の本場、日本に行き着いた。それから相馬焼に弟子入りするまでの詳しい経緯は、最近出た雑誌「りらく」を見て欲しい。オペさんにとって極東日本は、思うがまま轆轤を引くための「虹の端」だったのだ。
オペさんはコンクールにも意欲的に挑戦し賞をとっている。訪れたときも4月の半ばから始まる日本現代美術工芸展 に出品するという作品が置いてあった。口を半ば開いた貝のような形状の作品は、外に雲がたなびき、内側にはやはりあのレインボーが描かれていた。
帰り際、鴨居の上にデビット・ボウイのな70年代の傑作「アラジン・セイン」のアルバム表紙が飾られているのが目に入った。虹色のブラシを顔に施したボウイの写真とオペさんとのつながりについても、今度の展示会で聞いて見ることにしよう。
「折石神社」については以下に詳しい。
https://blog.goo.ne.jp/inehapo/e/a15755737e4ad77daf01349d7be361bf