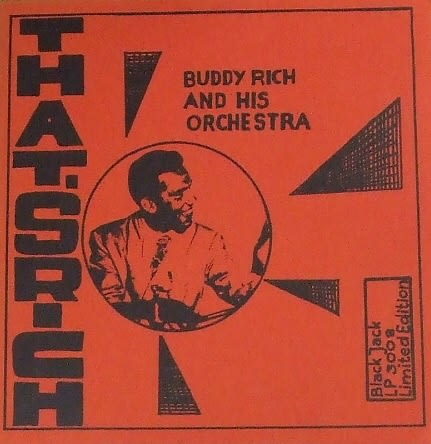
東京芸大出身で元オーケストラ楽員のヴィオラ奏者という経歴を持つ異色の経営学者、大木裕子さんの著書「オーケストラの経営学」(東洋経済新報社刊)は、オーケストラを会社と同様の組織としてとらえ、経営学的に分析している。組織の中で権威を持ち、従業員の仕事や給与をコントロールできる企業経営者と、人事権を持っていない指揮者とはやや異なるが、ともに組織のリーダーという観点からみると興味深い。
小澤征爾やカラヤン等、クラシックのオーケストラをケースとしての内容だが、その分析はそのままジャズのビッグバンドにも当てはまる。勿論音楽性の違いから交響楽団と同列には比べられないが、強力なリーダーシップを持ち得ない指揮官の下ではバンド経営に行き詰るばかりか、バンドメンバーの成長も望めない。1966年に自己のバンドを持ち、以後晩年までバンドリーダーとして手腕を発揮した人にバディ・リッチがいる。多くのビッグバンドが解散を余儀なくされるなか、長年に亘ってバンドを維持したリッチは、ドラマーとしても一流なら、経営者としても超一流といえるだろう。
経営学的に准えてみるとリッチのビッグバンドにはビッグネイムがいない、即ち経費削減になるが、それでいて腕は確かなので音楽性は高い。そして広く受け入れられるポップ・チューンをレパートリーにしている。ウェスト・サイド・ストーリーやソニー&シェールの「Beat Goes On」を取り上げたり、サイモン&ガーファンクルの「Keep The Customer Satisfied」をアルバムタイトルにしたのは、ジャズファン以外へのセールを狙ったものだろう。ポップ曲であっても華麗なアレンジが施されているのでジャズファンは勿論、ビッグバンド・ファン、そしてドラムを学んでいる人でも楽しめるだ。売り上げこそ経営上最も重要視されるのは企業と同じである。
「That's Rich」はリッチが46年に一時期編成したビッグバンドの音源をまとめたもので、「V-Disc Speed Demons」のクレジットから推測すると45年に戦争が終結した後、各国に駐屯する兵向けのVディスク用に録音されたものだろう。この後時期尚早とみたリッチはバンドを解散し、ハリー・ジェイムス楽団のスター・ドラマーとして活躍する。20年の準備期間で学んだビッグバンド経営のノウハウはそのまま生きている。
小澤征爾やカラヤン等、クラシックのオーケストラをケースとしての内容だが、その分析はそのままジャズのビッグバンドにも当てはまる。勿論音楽性の違いから交響楽団と同列には比べられないが、強力なリーダーシップを持ち得ない指揮官の下ではバンド経営に行き詰るばかりか、バンドメンバーの成長も望めない。1966年に自己のバンドを持ち、以後晩年までバンドリーダーとして手腕を発揮した人にバディ・リッチがいる。多くのビッグバンドが解散を余儀なくされるなか、長年に亘ってバンドを維持したリッチは、ドラマーとしても一流なら、経営者としても超一流といえるだろう。
経営学的に准えてみるとリッチのビッグバンドにはビッグネイムがいない、即ち経費削減になるが、それでいて腕は確かなので音楽性は高い。そして広く受け入れられるポップ・チューンをレパートリーにしている。ウェスト・サイド・ストーリーやソニー&シェールの「Beat Goes On」を取り上げたり、サイモン&ガーファンクルの「Keep The Customer Satisfied」をアルバムタイトルにしたのは、ジャズファン以外へのセールを狙ったものだろう。ポップ曲であっても華麗なアレンジが施されているのでジャズファンは勿論、ビッグバンド・ファン、そしてドラムを学んでいる人でも楽しめるだ。売り上げこそ経営上最も重要視されるのは企業と同じである。
「That's Rich」はリッチが46年に一時期編成したビッグバンドの音源をまとめたもので、「V-Disc Speed Demons」のクレジットから推測すると45年に戦争が終結した後、各国に駐屯する兵向けのVディスク用に録音されたものだろう。この後時期尚早とみたリッチはバンドを解散し、ハリー・ジェイムス楽団のスター・ドラマーとして活躍する。20年の準備期間で学んだビッグバンド経営のノウハウはそのまま生きている。











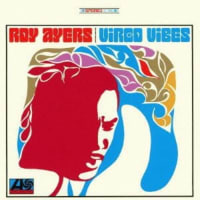

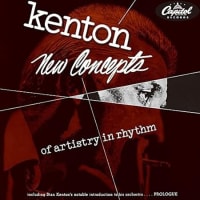


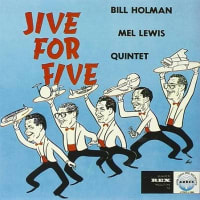









正確に長時間叩き続けることができるバディ・リッチはドラマーとしても一流ですが、ビッグバンド・リーダーとしても手腕を発揮した人です。今週はバディ・リッチ・ビッグバンドのお好みをお寄せください。コンボは別の機会に話題にします。
管理人 Buddy Rich Big Band Best 3
Swingin' New Big Band (Pacific Jazz)
Keep The Customer Satisfied (Pacific Jazz)
A Different Drummer (RCA)
パシフィックやRCA、グルーブ・マーチャントに数多くの作品がありますので、何が挙がるのか楽しみです。
今週も皆様のコメントをお待ちしております。
この様な事態でも音楽を聞くことが出来る自分の環境をありがたく思い、しっかりベスト選出といきます
ジャズに関わる者として新潟の6.16、N.Y.の9.11、日本に住んでいる身として1.17、北海道の人間として7.12という数字の並びが持つ記憶は消せないわけです
At Stadshell Leonberg 86(jazz band)
Big Band Machine(groove marchant)
New One !=Take it away !~?(pacific)
彼もジャズリスナーから正当に評価されていない真のジニアスの1人ですね
あの精神性を無視したはっきりとわかりやすく表現できる精神の強靭さ
手癖や流れで絶対にプレイしないその物語の物への自信ある語り口
生では体験してませんが映像を見るだけでも、特に晩年における軽快な重戦車の攻撃のエンドレスなクレッシェンドぶりは彼がやはり人間ではないことの再確認の安堵に過ぎません
フィリーが好きなくせに彼を、いやぁどうもね、みたく逃げる連中とは心の中で縁を切っています
テクニックについては今さらですが私はあのスティック・ショット(途中でカタカタやる)が大好きで、あれを演る人最近いないですね(当たり前ですか)フィリーの逆ロールとか、こういうのはなにかタップダンスとの深い繋がりの快感があります
しかし、あの筒型のイスであのプレイですから…やっぱり怖い、よくバディ等とあだ名がついたもんです、あんなアンタッチャブルなゴッドファーザーな面構えに(笑)
しかし私は彼のbig bandの良いリスナーではありません、あんな運動会みたいのは苦手で(ベンチャーズは撃ち方を教え、ビートルズは何故撃つかを語って、少年たちは取り敢えず撃ちまくる快感を選んだ、とおっしゃった方がいましたが)、歴代のソロイスト達の軽薄さに耐えられません……
が、彼の、白なのに黒と子分に言わせてしまう親分の魅力は1ミリも失せることは無いのです
正直、私は最高のバディ・リッチより最低のケニー・クラークをこよなく好むのですが(笑)
札幌に来てはじめての揺れで少しばかり慌てました。東北の惨状を見ると言葉がありませんが、おっしゃるように音楽を聴ける環境にあることはありがたいことです。
トップに挙げられた「At Stadshell Leonberg 86」は知らないアルバムです。晩年のライブのようですね。
次いで「Big Band Machine」マーチャント時代、というより通してかもしれませんが、目だったソロイストはいなくてもバンドとしてのまとまりは見事なものです。この一体感を出せるのでスタープレイヤーは必要なかったのかもしれません。ペッパーが参加しても目立たない不思議さがあります。(笑)
New One はジャケからして当時の雰囲気を味わえますね。ロッテン・キッドの勢いがリッチの勢いで、それが魅力と思います。
評価が低いのは日本だけでして、多分にスタープレイヤーがいないことと、ロック路線が受け付けないないのでしょう。選曲は本国好みですが、視覚に訴える派手なドラミングは日本にも三宅裕司氏のようなコアなファンもいるようです。
あのマフィアのボスのような面構えはけっこう好きです。(笑)
Buddy Richは、若い頃にパウエルのGeniusを聴いてガッカリしてしまい、それ以来ちゃんと聴いていないのです。
しかし聴かずにいて良いのかと言う思いはあります。
今回は、皆さんのコメントで勉強したいと思っております。
リッチはパウエルの「Genius」のイメージが強いようですね。何かとローチと比べられ違和感だけの印象ですが、パウエルはそれも何ともせず自身のプレイに徹する姿はやはり天才としか言いようがありません。
コンボに不向きなドラマーがビッグバンドで異彩を放っております。是非この機会にお聴きください。
暫し、ご猶予を。
ブログやジャズは、しばしお忘れになって近辺の対応に専念してください。
ところで、先だって赤いドレスが似合う依田聖子さんの札幌パーククラブのCDを入手しました。平岸生まれとか、声に艶と張りがありますね。ご存知でしょうか。
札幌のボーカルのみなさんはがんばっていらっしゃるし素晴らしいと思います
が、こっそり告白させてもらえばほとんど私は苦手です(笑)というか彼女達がジャズ(カテゴリーとしてではなく)だったことは一度もないだろうし、本人もそう思っているはずなので
常にジャズな連中なら
CDでのピアノの伊達出身のトシさんは私とバディで、私の弟子です(笑)札幌裏ナンバーワンピアニストです
釧路出身の館山さんも親しくさせていただいてます、彼はジョー・モレロと面識があったはずです