
ジャズ・ミュージシャンを目指す若者が世界を放浪する五木寛之著「青年は荒野をめざす」、白人の少年が黒人ばかりのジャズの現場に飛び込んだ時に感じる疎外感や孤独感を描いたナット・ヘントフ 著「ジャズ・カントリー」、チャーリー・パーカーの熱いアドリブがページを捲るたび聴こえてくるジャック・ケルアック著「地下街の人びと」・・・
ジャズを聴き始めたころ読んだ小説である。なかでも今月1日に亡くなった石原慎太郎の「ファンキー・ジャンプ」は何度も読んだ。ブレイキーやガレスピーも絶賛したという日本人ジャズ・ピアニストという設定は身近に感じたし、麻薬中毒のミュージシャンはこの時代当たり前だっただけにドキュメンタリーを見るようだった。本物のビ・バップを追及する現実とヤクによる幻覚は詩的文体で書かれているのでより鮮明だ。守安祥太郎をモデルにしたという主人公が壮絶な演奏の果てに絶命する様は強烈である。
小説の構成はホレス・シルバーのエピック盤「Silver's Blue」を下敷きにしたそうだ。JMから独立直後の録音で、フロントにドナルド・バードとハンク・モブレーを配したセッションと、ジョー・ゴードンとケニー・クラークが参加した録音が収められている。これから自らのバンドを引っ張っていくという意気込みが伝わってくるシルバーの力強い音は見逃せない。オリジナル曲はバップ・エッセンスが散りばめれていて楽しいし、「The Night Has A Thousand Eyes」の解釈は、この後何作もリリースするシルバー・バンドのスタイルの原型といえるだろう。
JMの来日とともに日本でファンキー・ブームが起こり、今はなきスイングジャーナル誌が30万の部数を誇っていたのは60年代初頭である。小説が文芸雑誌「文學界」に掲載されたのは1959年8月のことだった。まだ国内盤も出ていない56年録音の「Silver's Blue」をいち早く聴いていたのは驚きだ。時代の寵児、石原慎太郎。享年89歳。合掌。










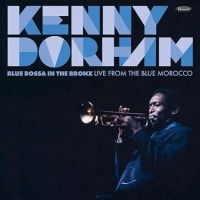

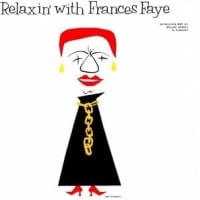

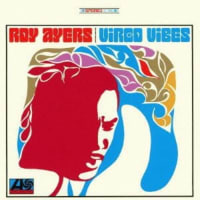

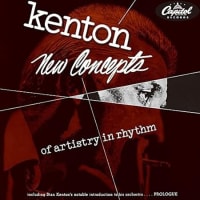


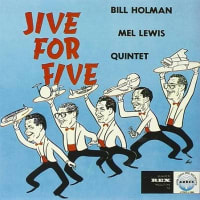
「ファンキー・ジャンプ」を読んだことがある方はご感想をお寄せください。
音の本棚 石原慎太郎作品集 「ファンキー・ジャンプ」 take3
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1J3tg2_fw
私もジャック・ケルアックを読みました。当時、日本の小説はレコードをヒントに書いているのに対して、アメリカのそれはライブをダイレクトに伝えるものでした。「地下街の人びと」や「路上」は昭和43年に新潮社から発刊されたもので読みましたが、「ジャック・ケラワック」と表記されていました。ジャズ誌の表記がジョン・マクローリンやシェイラ・ジョーダンの頃です。こちらのカタカナの方が何故かしっくりきます。
ハンプトン・ホーズと出逢ったとは貴重な体験をされていますね。日本のジャズミュージシャンはモカンボでホーズから多くを学んだことでしょう。守安祥太郎といえば昨年、地元のコレクターにロックウェルのEP盤を聴かせていただきました。世界に通用するピアニストです。三島由紀夫が絶賛した「ファンキー・ジャンプ」をお楽しみください。