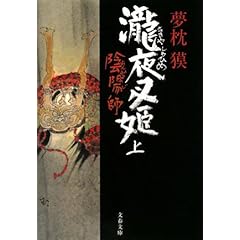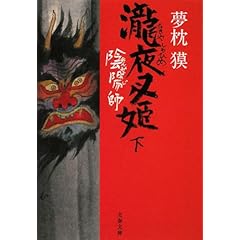宮部みゆきの時代小説、「日暮らし」。
「ぼんくら」の続編です。
時代小説と歴史小説は似てるようでいてまったく異なったジャンルの創作物です。
大まかに区分すると、
時代小説は、過去の時代背景を借りて物語を創作する小説で
他方、歴史小説は、歴史上の人物や事件の史実に沿った小説と
分けることができます。
うまい作家にかかればまたそれぞれに格別の味わいがあります。
宮部みゆきはいろんなジャンルに挑戦して、
それぞれのジャンルで人並み以上の成功を収めている
稀有な作家であるように思います。
「ぼんくら」、「日暮らし」は江戸時代の背景を借りた
ミステリー小説で江戸時代の風俗になじみながら、
なぞ解きを楽しむことができます。
小説の視点は一貫してぼんくら同心井筒平四郎のものですが、
なぞ解きは甥っ子の弓之助がするというものです。
日暮らし(上)講談社文庫

上巻では、短編小説が4本続きますが、
これが中巻、下巻に描かれる本編の伏線になっていきます。
日暮らし (中) 講談社文庫

日暮らしの舞台設定は、「ぼんくら」のその後のてんまつ
という形になっていますので「ぼんくら」を読んでおいたほうがいいでしょう。
日暮らし (下) 講談社文庫

ミステリーとしては、「驚きの結末」とまではいかないものの、
小説自体の出来としては、安定感があり
さすが宮部みゆき、読者を裏切らないですね~という感じです。
文章自体がうまいですし、細かな部分への配慮と描写が
秀逸であるように思います。
「その日暮らし」といってしまえば、
毎日毎日無計画で過ごしているようにも聞こえます。
が、しかし
一日一日を大事に大事に過ごす長屋のさまざまな人々の
人間模様を丹念に描くことで、宮部みゆきは読者に「何か」を
伝えたかったのではないでしょうかねぇ。
世知辛い世の中ですが、
宮部みゆきを読んで一服してみるのも
いいかもしれませんよ!
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
あなたのポチっとがとても励みになっています。


「ぼんくら」の続編です。
時代小説と歴史小説は似てるようでいてまったく異なったジャンルの創作物です。
大まかに区分すると、
時代小説は、過去の時代背景を借りて物語を創作する小説で
他方、歴史小説は、歴史上の人物や事件の史実に沿った小説と
分けることができます。
うまい作家にかかればまたそれぞれに格別の味わいがあります。
宮部みゆきはいろんなジャンルに挑戦して、
それぞれのジャンルで人並み以上の成功を収めている
稀有な作家であるように思います。
「ぼんくら」、「日暮らし」は江戸時代の背景を借りた
ミステリー小説で江戸時代の風俗になじみながら、
なぞ解きを楽しむことができます。
小説の視点は一貫してぼんくら同心井筒平四郎のものですが、
なぞ解きは甥っ子の弓之助がするというものです。
日暮らし(上)講談社文庫

上巻では、短編小説が4本続きますが、
これが中巻、下巻に描かれる本編の伏線になっていきます。
日暮らし (中) 講談社文庫

日暮らしの舞台設定は、「ぼんくら」のその後のてんまつ
という形になっていますので「ぼんくら」を読んでおいたほうがいいでしょう。
日暮らし (下) 講談社文庫

ミステリーとしては、「驚きの結末」とまではいかないものの、
小説自体の出来としては、安定感があり
さすが宮部みゆき、読者を裏切らないですね~という感じです。
文章自体がうまいですし、細かな部分への配慮と描写が
秀逸であるように思います。
「その日暮らし」といってしまえば、
毎日毎日無計画で過ごしているようにも聞こえます。
が、しかし
一日一日を大事に大事に過ごす長屋のさまざまな人々の
人間模様を丹念に描くことで、宮部みゆきは読者に「何か」を
伝えたかったのではないでしょうかねぇ。
世知辛い世の中ですが、
宮部みゆきを読んで一服してみるのも
いいかもしれませんよ!
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
あなたのポチっとがとても励みになっています。











 」とくることはありますね。
」とくることはありますね。 」
」