
[2010-09-30 記事修正]
2SK2231の電気的特性をみてみましょう。
いろいろ書いてありますが、「ドレイン・ソース間オン抵抗」を見てください。Id=2.5Aにおいてオン抵抗は標準で0.12Ωです。ということは、電力損失は2.5^2×0.12=0.75 (W)と、かなり小さく発熱もわずかです。スイッチとして使うのですからオン抵抗が小さいほど良いことは言うまでもありません。
この前、無線機用バックアップ電源に使用した2SJ607というMOS-FETはオン抵抗が0.011Ωでした。これは10A流しても電力損失は1.1 (W)と2SK2231と大差ありません。2SJ607はずば抜けて高性能な半導体スイッチですね。Nchではオン抵抗:0.001Ωというものもありますから、MOS-FETのスイッチとしての性能は計り知れません。なにしろリレー接点や機械式スイッチの接点抵抗よりも、ひとケタ小さいのですから。
【ゲートはコンデンサ】
入力容量 Ciss=Cgd+Cgs
出力容量 Coss=Cds+Cgd
帰還要領 Drss=Cgd
オン抵抗のほかにもう一点、MOS-FETを使用するときの注意点として、G-S間にかなり大きな容量(C)を持っていることです。特性表の「入力容量」を見てください。370pFとなっています。J-FETなら2~3pF程度です。この差はどこから来るのでしょう?
MOS-FETの構造を思い出してください。極めて薄いシリコン酸化皮膜を導体と導体(半導体)でサンドイッチにしてあります。これは正にコンデンサの構造そのものですね。大電流用のパワーMOS-FET等では入力容量が1000pFくらいにまでなります。MOS-FETを使うときは後で痛い目に遭わないように、このG-S間の容量には十分気をつけておきましょうね。入力容量(Cgs)とゲートに接続した電線のL成分による発振(LC共振)はMOS-FETにはつきものです。
MOS-FETの寄生容量については「入力容量」のほかに、「帰還容量」「出力容量」なども記載されています。どれもそこそこに大きな値ですが、これらはどういうものなのでしょう?図を見てください。MOS-FETに寄生して構成される容量は下の回路図のようになります。特に入力容量は値が大きく使用時には注意が必要です。「帰還容量」「出力容量」は特に高周波での使用時に問題となってきます。
ということで、MOS-FETは大きなコンデンサを抱えていると常に思っていてくださいね。
関連記事:デプレッション型とエンハンスメント型(FET) 2010-03-15
2SK2231の電気的特性をみてみましょう。
いろいろ書いてありますが、「ドレイン・ソース間オン抵抗」を見てください。Id=2.5Aにおいてオン抵抗は標準で0.12Ωです。ということは、電力損失は2.5^2×0.12=0.75 (W)と、かなり小さく発熱もわずかです。スイッチとして使うのですからオン抵抗が小さいほど良いことは言うまでもありません。
この前、無線機用バックアップ電源に使用した2SJ607というMOS-FETはオン抵抗が0.011Ωでした。これは10A流しても電力損失は1.1 (W)と2SK2231と大差ありません。2SJ607はずば抜けて高性能な半導体スイッチですね。Nchではオン抵抗:0.001Ωというものもありますから、MOS-FETのスイッチとしての性能は計り知れません。なにしろリレー接点や機械式スイッチの接点抵抗よりも、ひとケタ小さいのですから。
【ゲートはコンデンサ】
入力容量 Ciss=Cgd+Cgs
出力容量 Coss=Cds+Cgd
帰還要領 Drss=Cgd
オン抵抗のほかにもう一点、MOS-FETを使用するときの注意点として、G-S間にかなり大きな容量(C)を持っていることです。特性表の「入力容量」を見てください。370pFとなっています。J-FETなら2~3pF程度です。この差はどこから来るのでしょう?
MOS-FETの構造を思い出してください。極めて薄いシリコン酸化皮膜を導体と導体(半導体)でサンドイッチにしてあります。これは正にコンデンサの構造そのものですね。大電流用のパワーMOS-FET等では入力容量が1000pFくらいにまでなります。MOS-FETを使うときは後で痛い目に遭わないように、このG-S間の容量には十分気をつけておきましょうね。入力容量(Cgs)とゲートに接続した電線のL成分による発振(LC共振)はMOS-FETにはつきものです。
MOS-FETの寄生容量については「入力容量」のほかに、「帰還容量」「出力容量」なども記載されています。どれもそこそこに大きな値ですが、これらはどういうものなのでしょう?図を見てください。MOS-FETに寄生して構成される容量は下の回路図のようになります。特に入力容量は値が大きく使用時には注意が必要です。「帰還容量」「出力容量」は特に高周波での使用時に問題となってきます。
ということで、MOS-FETは大きなコンデンサを抱えていると常に思っていてくださいね。
関連記事:デプレッション型とエンハンスメント型(FET) 2010-03-15
















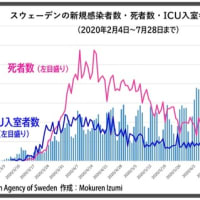








このとき使っていたのは「デュアルゲートMOS-FET」でしたね、たしか。
26才くらいだったかな?
そのときに「スペクトラムアナライザ」の使い方を覚えたんだった!当時、HPの1千万もしたスペアナをひとりでじっくりやらせていただきました。
高周波屋さんでもないのに、そういうこともやらされたんです・・・。
私も初めてパワーMOS-FETを使ったときに、強烈な発振に悩まされて困りました。今を去ること27年前の話ですね。当時はほとんど知識もなく見よう見まねでやってものですから、何個壊したことやら。1個4000円のが壊れた時には涙が出ましたよ。
スペアナは触ったことが無いのですが、同じくHP製のFFTアナライザは私も仕事でよく使っていました。振動制御の会社だったもので対象周波数が低くFFTアナライザで十分でした。値段は確か500万。お、スペアナの半分ですね。
ツェナダイオードにしても、トランジスタにしても「温度特性」は忘れがちですよね。しかもバイアス電流に関連させて検討しないといけない。「電流を流すほどドリフトが大きくなる」というのは今更ながら、新しい知見をいただきました。これは電力損失が大きくなって上昇温度が上がるという意味ですか?
ともかくバイポーラトランジスタの温度ドリフトが一番大きく、MOS-FETがコンデンサであるのと同様、トランジスタは温度センサと考えればいいですね。そういえばトランジスタをセンサとして、Vbeを検出するタイプの温度計がありますね。
しかし電源のレギュレーション精度は、その電源を何に使うかによりますよね。場合によってはレギュレーション無しの「整流、平滑」だけで十分な場合もありますものね。私が今計画しているパワーアンプの増幅段に使う電源は、超高精度、ウルトラハイスピードの電源にしてやろうと画策しています。
やはりJ-FETで回路を構成すると「音がやわらかくなる」のですか。真空管の音に近いというニュアンスなんでしょうね。パイオニアやヤマハやマランツのアンプ回路などを見ても、特に入力段は必ずと言っていいほどJ-FET(デュアル)ですね。2SK30Aも最近では入手しづらいのですか。さすがに古いですものねえ。100個くらい買っておこうかな。初段に使えば結構い音するんですよ、あれ。
そう選別はIDSSでやります。最近では安価なディジタルテスタがあるので楽になりましたよね。下3桁くらいまで合わせればいいかな?
「現役の頃は”角速度”、つまり”2×円周率のパイ×周波数”が基本でしたねぇ~!」
これは ω[rad/sec]/ 2π=f[Hz] ω=2πf ってやつですね。(^^)
仕事では「簡易的にすぐ計算できる方法」を用意しておきますよね。私が記憶としてよく使うツールはフィルタのfcを求める 1/ 2πCR ですね。最近、磁気との付き合いもやや増えてきて e=-N dφ/dt なども、たぶん死ぬまで忘れないでしょうねえ。
中学生の頃からフォークギターをジャカジャカですか。私は高1で始めました。フォークではなくクラシックギターで、最初に覚えたのが「禁じられた遊び」です。オーソドックスですねえ。その後フォークギターも買ったのですが、金欠で安物(YAMAHA)を買ったので、しばらくしたらネックが反り返って使えなくなってしまいました。エレキギターにも憧れたのですが、手が出なかったですねえ。
小六~中学生くらいの頃に、自分で修理した真空管式蓄電器でクラシックを聴いた!すごいですねえ。ほんとに「ラジオ少年」だったんですね。私も友人にラジオ少年がいて、羨ましいというか嫉妬してましたね。私が電気の勉強を始めたのは26歳の時でした。「いつか自分でオーディオパワーアンプを作りたい」というのが夢だったんですよね。
LLのカセットテープもよく使いましたねえ。アナログ末期のカセットデッキは素晴らしくいい音してましたよね。クロームテープやメタルテープなんかがあって。その後MDに取って代わられたものの、店頭から消えたMDに対してカセットテープはまだありますもんねえ。
kaoaruさん、私のブログのトップページの「ブックマーク」の欄に「よもやまBBS」という掲示板を置いています。よろしかったらそちらの方にも是非どうぞ。投稿した後にも編集や削除ができるので、文章が長くなる場合には便利ですよ。
(^^)
「よもやまBBS」
http://www1.rocketbbs.com/210/commux.html