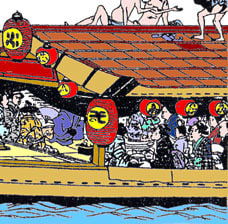133ー「廓丹前」(1857・安政4年)
元禄頃(1688~1707)の伊達男は、廓に通うのに目一杯おしゃれをしたものだ。
廓も全盛で、四季折々の風流なイベントが花盛りだった。
『俳優の 昔を今に写し絵や
及ばぬ筆に菱川の
寛濶出立ち 廓通い
姿彩る丹前は
今日を晴れなる初舞台
よしや男と名に高き
富士の白柄まばゆくも
紫匂う筑波根の
腰巻羽織六方に
振って振り込む
奴のこのこの
酒ならねじ切り色上戸
恋の取り持ち
してこいまかせろ しょんがえ
花にも優る 伊達な風俗』
●菱川某の描いた役者の浮世絵にはとてもかなわぬが、
廓に通う、伊達男を再現してみた。
今日は、花柳寿輔宅の舞台開きなのだ。
男は義也、白柄組、江戸紫の短い羽織を粋に着て、
颯爽と歩く姿の六方振り。
酒を一杯、顔に出る、お供の奴は尻はしょり。
へい、恋の取り持ちまかせろ合点!
花にも勝つぞ、この風俗。
義也とは、旗本奴の三浦小次郎義也のこと。
吉屋組の親分で、金も力もある大変な色男。
金に糸目をつけない華美な衣装は、奴共の羨望の的で、
義也が歩くと見物人が溢れたという、いわば男伊達のスター。
斯くして義也は色男の代名詞となる。
丹前については、8/4、10に詳しい。
〓 〓 〓
tea breaku・海中百景
photo by 和尚

元禄頃(1688~1707)の伊達男は、廓に通うのに目一杯おしゃれをしたものだ。
廓も全盛で、四季折々の風流なイベントが花盛りだった。
『俳優の 昔を今に写し絵や
及ばぬ筆に菱川の
寛濶出立ち 廓通い
姿彩る丹前は
今日を晴れなる初舞台
よしや男と名に高き
富士の白柄まばゆくも
紫匂う筑波根の
腰巻羽織六方に
振って振り込む
奴のこのこの
酒ならねじ切り色上戸
恋の取り持ち
してこいまかせろ しょんがえ
花にも優る 伊達な風俗』
●菱川某の描いた役者の浮世絵にはとてもかなわぬが、
廓に通う、伊達男を再現してみた。
今日は、花柳寿輔宅の舞台開きなのだ。
男は義也、白柄組、江戸紫の短い羽織を粋に着て、
颯爽と歩く姿の六方振り。
酒を一杯、顔に出る、お供の奴は尻はしょり。
へい、恋の取り持ちまかせろ合点!
花にも勝つぞ、この風俗。
義也とは、旗本奴の三浦小次郎義也のこと。
吉屋組の親分で、金も力もある大変な色男。
金に糸目をつけない華美な衣装は、奴共の羨望の的で、
義也が歩くと見物人が溢れたという、いわば男伊達のスター。
斯くして義也は色男の代名詞となる。
丹前については、8/4、10に詳しい。
〓 〓 〓
tea breaku・海中百景
photo by 和尚