
(新潮文庫)
1892年(明治25年)7月に発表された作品集『美奈和集(水沫集)』では、この二つの作品に加え、「文づかひ」を入れ、森鴎外のドイツ三部作とされています。まず、この小説が漢文調と和文調をミックスした雅文体であることに最初閉口します。しかし、短編であることが幸いして、声を出して読んでみると、自ずとすっきり読めてしまうことに我ながら驚いてしまうのです。
明治時代に話しことばと書きことばとを一致させようとした言文一致運動という動きがあり、学校教育・新聞・文学などの各分野で試みられました。明治20年代、三遊亭円朝の人情噺『怪談牡丹燈篭』を速記した文体にヒントを得た二葉亭四迷の『浮雲』(1887-91年)の「だ体」、山田美妙の『胡蝶』(1889年)の「です体」、尾崎紅葉の『多情多恨』(1896年)の「である体」を文学の言文一致運動の成果とみることができるそうですが、「舞姫」が1889年、「うたかたの記」が1890年の作品ですから、森鴎外の時代に流されない作為性がうかがい知れます。
更に、同時代における森鴎外の位置づけを掴んでおくために、Mikio Akamineshi氏の「日本文学、ロシア文学研究」というサイトから参考文を引用しておきます。私は、20代の前半で夏目漱石をほとんど読破したのですが、何故かこの同時代の作家たちの作品には全く手を出しませんでした。
「鴎外の基本的な特徴は、保守的エリートの地位を道徳的に弁護し肯定したことにある。この特徴は、同時代の四迷、一葉、漱石と対照的である」。
「四迷は明治の階級分化の全体を批判的にとらえ、出世主義者と、出世から取り残される者のそれぞれの果実を客観的に描いた。出世には、商品経済の発展がもたらすあらゆる物質的な富と、地位の社会的な力が与えられ、取り残されるものには現実についての深い認識と感情が、個人としての破滅とともにもたらされる」。
「漱石は下層の人間が得る果実を知らなかった。漱石はエリートとして、エリートやブルジョアの得る富や地位の力に反発し、それを拒否することを精神的な価値と考えた。その上で、その道徳的な批判意識が無力であることを具体的に認識することを通じて日本的なエリートの本質をとらえる事が漱石のエリートらしい果実となった」。
「一葉は四迷のように時代を全体的に概括的にとらえることはなかったが、四迷より遅れて、緊密な人間関係から出発して、下層の世界の人間関係の崩壊とそれを代償に得られる果実を力強くとらえた」。
「鴎外は、エリートとして非難される側面を道徳的に弁護した点で漱石とまったく逆の立場にあり、二人がともに文豪と称されるのもそのためである。明治の日本が西欧諸国に追いつくためには、発展を担う人材の育成が急務であり、人材は少なく貴重であったために、一方で実質的に発展を担う優秀な人材を生み出すとともに、他方では、そのエリートの特権的な地位によって堕落する人材をも多数生み出した」。
「鴎外はこのエリート内部の対立のなかで生じる日常生活での瑣末な不満を表明し、また瑣末な批判に対して自己を弁護した。エリートやブルジョアは上からの改革を担う積極的な力をもっていたが、鴎外はその役割を担うことなく、その役割に対立しつつ、エリート内部で生ずる道徳的な批判から自分の地位と名誉を守るための独自の道徳的な精神をまとめあげた」。
「漱石と鴎外の両文豪に見られる対立関係は基本的には明治の必然の反映であった。大正時代には鴎外は自分の使命を終えている。漱石は明治の精神の終焉を客観化して描写し、新しい精神を形成するにいたったが、鴎外にはそれはできず、過去の歴史的な実証的な世界に住処を求めた」。
さて、前置きが長くなりましたが本題へ。
「舞姫」・・・(29歳、1890年1月、「国民之友」)
森鴎外は、1889年3月、写真婚で、海軍中将・赤松則良の長女・登志子と婚約。1890年(明治23年・29歳)1月に『医事新論』を創刊。「舞姫」を「国民之友」に発表。9月、長男於菟(おと)誕生。しかし、まもなく妻登志子と離婚していてしまいます。
鴎外がドイツへ医学を学ぶために1884年から5年間留学したときの体験を下敷きに執筆したのが本作。高雅な文体と浪漫的な内容で初期の代表作。
「19世紀末、ドイツ留学中のエリート官僚、太田豊太郎はさびれたユダヤ人街を散歩していたところ、クロステル街の古寺で涙に暮れる、ユダヤ人の下層階級に育つ、ヴィクトリア座のバレエダンサーの美少女エリスと出会い、一目で心奪われる。父の葬儀代を工面してやり、以後清純な交際を続けるがスキャンダルは広まり豊太郎は免職される。ここに至り、豊太郎のエリスへの愛情は高まり彼女と関係を持つ」。
「その後豊太郎はエリスと同棲し、生活費を工面するためドイツ駐在の通信員という形で新聞社に就職した。エリスはやがて豊太郎の子を身篭る。友人である相沢謙吉の紹介で大臣のロシア訪問に随行し信頼を得ることができた。復職のめども立ち、また相沢の忠告もあり結局エリスとの愛よりも出世のために日本へと帰国することを選ぶ」。
「しかし豊太郎の帰国を心配するエリスに彼は真実を告げられず、その心労で人事不省に陥り、その間に相沢から真実を知らされたエリスは衝撃の余りパラノイアを発症した。真実を伝えた相沢と、豊太郎の事さえ分からなくなるほど病状が悪化したエリスに後ろ髪を引かれつつ、豊太郎は日本に帰国する。『相澤謙吉が如き良友は世にまた得がたかるべし。されど我が脳裡に一点の彼を憎む心今日までも残れりけり』豊太郎の心からの呟きであった」。
この作品について、「舞姫論争」なるものが起こっていました。
<舞姫論争>1890年、石橋忍月と森鴎外との間に起こった文学論争で、最初の本格的な近代文学論争だといわれる。忍月は筆名「気取半之丞」で「舞姫」を書き、主人公太田が意志薄弱であることなどを指摘し批判。これに対し鴎外は相沢を筆名に使い、「気取半之丞に与ふる書」で応戦。その後も論争が行われたが、忍月が筆を絶って収束。
内容についてもう少し探ってみると、石橋忍月の投げかけは次のようなものでした。
「鴎外漁史の「舞姫」が国民之友新年附録中に就いて第一の傑作たるは世人の許す所なり。之が賛評をなしたるもの少しとせず。私家然れども未だ其の瑕瑾(かきん)を発(あば)きたるものは之れ無きが如し。予は二三不審の廉(かど)を挙げて著者其人に質問せんと欲す」。
「『舞姫』の意匠は恋愛と功名と両立せざる人生の境遇にして、此の境遇に処せしむるに小心なる臆病なる慈悲心ある――勇気なく独立心に乏しき一個の人物を以ってし、以て此の地位と彼の境遇との関係を発揮したるものなり。故に「舞姫」を批評せんと欲せば先づ其人物(太田豊太郎)と境遇との関係を精査するを必要となす」。
「抑(そもそ)も太田なるものは恋愛と功名と両立せざる場合に際して断然恋愛を捨て功名を採るの勇気あるものなるや。曰く否な。彼は小心的臆病的の人物なり。彼の性質は寧(むし)ろ謹直慈悲の傾向あり。理に於いて彼は恩愛の情に切なる者あり。
更に、作者・森鴎外と主人公は同一人物だとするものや、ドイツ人女性エリーゼ・ヴィーゲルト(Elise Wiegert)という女性が来日し、滞在一月ほどで離日したことによって、この作品のモデルであったことが話題になったようです。

石橋忍月(にんげつ、慶応元年9月1日(グレゴリオ暦1865年10月20日)-1926年(大正15年)2月1日)は、「日本の文芸評論家、小説家、弁護士、政治家。本名は友吉。号は萩の門、気取半之丞、福洲学人など。三男は文芸評論家の山本健吉。明治23年(1890年)、森鴎外の『舞姫』、『うたかたの記』等をめぐり鴎外と論争し評論の地位を高めた。しかし、壮年以降は文学からはなれ、長崎の県会議員、弁護士として活動した」。(ウィキペディア)
「うたかたの記」・・・(29歳1890年8月、「国民之友」、雑誌「しがらみ草紙」に発表。
「ドイツ・バイエルン王国の首都ミュンヘン。日本画学生の巨瀬は、以前ドレスデンで一目ぼれをした花売り娘のマリー・ハンスルと再会する。巨瀬はマリーの面影が忘れられず、自作のローレライのモデルとしていた。マリーはいきなり巨瀬に接吻する。驚く巨瀬に、同行していた友人のエスキテルは彼女は美術学校のモデルだが狂っていると教える」。
「巨瀬は、自分のアトリエにマリーを呼び彼女への熱い思いを伝える。話をする内に、マリーには高名な画家の父ステインベルグと彼女と同名の美しい母親がいた。母はバイエルン国王ルードヴィヒ2世に懸想されていた。父は国王の毒牙から妻を守って死に、母も悲しみのあまり後を追うようにして死ぬ。孤児となったマリーはアルプス近くのスタルンベルヒ湖の漁師ハンスル家に引き取られたことがわかる」。
「マリーは、父のように美術を学ぶためモデルとなっているが、誘惑の多い都会で身を守るためにわざと狂った振りをしていると明かす。マリーに誘われるまま巨瀬はスタインベルヒ湖に向かう。愛を確認した二人は、雨の湖の周囲を散策し船で遊ぶ」。
「村外れの岸辺に漕ぎ寄せると、母マリーの想い止みがたく狂人となっていた国王がいた。国王は、マリーの姿に母の幻影を見て彼女に襲いかかる。マリーは恐怖のあまり湖に没する。国王も止めようとした侍医グッデンもろとも湖に沈む」。
「巨瀬はマリーを助けるが、杭に胸を打ったのがもとで死んでしまう。国王の葬儀の日、心配したエスキテルが巨瀬のアトリエを訪問すると、彼は憔悴しきってローレライの絵の前に跪いていた」。(ウィキペディア)
「鴎外初期の流麗な文語体で書かれた悲恋物語であるが、『舞姫』では主人公が日本人留学生なのに対して、『うたかたの記』はマリー・ハンスルという美しいモデルであり、日本人巨瀬は狂言廻し的な役割になっている。なお、巨瀬のモデルはドイツ・ミュンヘン留学時代の友人である画学生原田直次郎とされ、ヒロインのマリーは原田の愛人の名前から取っている」。
「この物語のもう一人の重要人物、バイエルン国王ルードヴィヒ2世はルキノ・ヴィスコンティの映画『ルートヴィヒ』にも取り上げられ、大作曲家リヒャルト・ワーグナーのパトロンとしてあるいはノイシュヴァンシュタイン城の造営でも知られているが、1886年の王の水死事故は、鴎外の『独逸日記』に記されている。当時鴎外はミュンヘン大学に在籍していた」。
「ここでは学問に狂う巨瀬、わざと狂った振りをするマリー、思慕の念から本当に狂ったルードヴィヒ2世と、3通りの「狂気」を描くという技巧が見られる」。(同上)
本作のモデルと言われる、原田直次郎に触れておきましょう。

原田直次郎(1863-1899)は、「江戸の武家(岡山藩士)で東京・小石川生まれ。岡山藩の兵学者で、後に貴族院議員となる父のもと、幼少時代からフランス語を習い、20歳のとき、高橋由一が主催する画塾『天絵学舎』で洋画を学び始めます。高橋由一は『絵事ハ精神ノ為ス業ナリ』と唱えた近代西洋画の先駆者。絵を描く精神を支えるのは、画布であり絵の具であり、それを使う技術であるという一貫した信念を持った人物でした」。
「その高橋のもとで学んだ直次郎は明治17年、21歳でドイツに留学します。ミュンヘンアカデミーに入学し、見るもの、聞くもの、すべて貪欲に吸収しながら、めきめきと上達していきます。ドイツ留学は直次郎にとって、まぎれもない青春でした」。

「そして直次郎はこの地で、作家・森鴎外と出会います。鴎外の短編小説『うたかたの記』の中に登場する、ミュンヘン留学中の日本人画家、巨勢のモデルは直次郎です。若き留学生同士、意気投合した直次郎と鴎外は、終生の友として親交を深めていきます」。
「25歳で帰国した後は自宅に画塾を開設し、西洋美術を教える一方で内国勧業博覧会などで作品発表を行った。原田の活動時期は、ちょうど国粋主義的風潮のなかで、日本画に比べて西洋画の立場が低くみられた時期であったが、画塾は活気に満ちており、師弟というより友達のように仲良く勉強したようである。なかでも、モデルを用いた木炭デッサンは、日本で初めて行われた美術教育として重要である」。(「美の巨人たち」他)
そして、こちらはルキーノ・ヴィスコンティ監督による「地獄に堕ちた勇者ども」(1969年)、「ヴェニスに死す」(1971年)と並ぶ「ドイツ三部作」の最終章、「ルートヴィヒ」(Ludwig)も参考まで。私はかなり前に観た記憶があります。

(1973年/イタリア、フランス、西ドイツ合作映画)
監督:ルキーノ・ヴィスコンティ
脚本:ルキーノ・ヴィスコンティ、エンリコ・メディオーリ、スーゾ・チェッキ・ダミーコ
撮影:アルマンド・ナンヌッツィ
出演:ヘルムート・バーガー、トレヴァー・ハワード、ロミー・シュナイダー、シルヴァーナ・マンガーノ

ルートヴィヒ2世(Ludwig II. 1845年8月25日-1886年6月13日)は、「第4代バイエルン国王(在位:1864年-1886年)。若い頃は美貌に恵まれ、多くの画家らによって描かれてきた。『童貞王』と渾名され、生涯にわたって妻帯せず、美しい青年たちを愛した男色家(同性愛者)の君主として名高い」。(ウィキペディア)
1892年(明治25年)7月に発表された作品集『美奈和集(水沫集)』では、この二つの作品に加え、「文づかひ」を入れ、森鴎外のドイツ三部作とされています。まず、この小説が漢文調と和文調をミックスした雅文体であることに最初閉口します。しかし、短編であることが幸いして、声を出して読んでみると、自ずとすっきり読めてしまうことに我ながら驚いてしまうのです。
明治時代に話しことばと書きことばとを一致させようとした言文一致運動という動きがあり、学校教育・新聞・文学などの各分野で試みられました。明治20年代、三遊亭円朝の人情噺『怪談牡丹燈篭』を速記した文体にヒントを得た二葉亭四迷の『浮雲』(1887-91年)の「だ体」、山田美妙の『胡蝶』(1889年)の「です体」、尾崎紅葉の『多情多恨』(1896年)の「である体」を文学の言文一致運動の成果とみることができるそうですが、「舞姫」が1889年、「うたかたの記」が1890年の作品ですから、森鴎外の時代に流されない作為性がうかがい知れます。
更に、同時代における森鴎外の位置づけを掴んでおくために、Mikio Akamineshi氏の「日本文学、ロシア文学研究」というサイトから参考文を引用しておきます。私は、20代の前半で夏目漱石をほとんど読破したのですが、何故かこの同時代の作家たちの作品には全く手を出しませんでした。
「鴎外の基本的な特徴は、保守的エリートの地位を道徳的に弁護し肯定したことにある。この特徴は、同時代の四迷、一葉、漱石と対照的である」。
「四迷は明治の階級分化の全体を批判的にとらえ、出世主義者と、出世から取り残される者のそれぞれの果実を客観的に描いた。出世には、商品経済の発展がもたらすあらゆる物質的な富と、地位の社会的な力が与えられ、取り残されるものには現実についての深い認識と感情が、個人としての破滅とともにもたらされる」。
「漱石は下層の人間が得る果実を知らなかった。漱石はエリートとして、エリートやブルジョアの得る富や地位の力に反発し、それを拒否することを精神的な価値と考えた。その上で、その道徳的な批判意識が無力であることを具体的に認識することを通じて日本的なエリートの本質をとらえる事が漱石のエリートらしい果実となった」。
「一葉は四迷のように時代を全体的に概括的にとらえることはなかったが、四迷より遅れて、緊密な人間関係から出発して、下層の世界の人間関係の崩壊とそれを代償に得られる果実を力強くとらえた」。
「鴎外は、エリートとして非難される側面を道徳的に弁護した点で漱石とまったく逆の立場にあり、二人がともに文豪と称されるのもそのためである。明治の日本が西欧諸国に追いつくためには、発展を担う人材の育成が急務であり、人材は少なく貴重であったために、一方で実質的に発展を担う優秀な人材を生み出すとともに、他方では、そのエリートの特権的な地位によって堕落する人材をも多数生み出した」。
「鴎外はこのエリート内部の対立のなかで生じる日常生活での瑣末な不満を表明し、また瑣末な批判に対して自己を弁護した。エリートやブルジョアは上からの改革を担う積極的な力をもっていたが、鴎外はその役割を担うことなく、その役割に対立しつつ、エリート内部で生ずる道徳的な批判から自分の地位と名誉を守るための独自の道徳的な精神をまとめあげた」。
「漱石と鴎外の両文豪に見られる対立関係は基本的には明治の必然の反映であった。大正時代には鴎外は自分の使命を終えている。漱石は明治の精神の終焉を客観化して描写し、新しい精神を形成するにいたったが、鴎外にはそれはできず、過去の歴史的な実証的な世界に住処を求めた」。
さて、前置きが長くなりましたが本題へ。
「舞姫」・・・(29歳、1890年1月、「国民之友」)
森鴎外は、1889年3月、写真婚で、海軍中将・赤松則良の長女・登志子と婚約。1890年(明治23年・29歳)1月に『医事新論』を創刊。「舞姫」を「国民之友」に発表。9月、長男於菟(おと)誕生。しかし、まもなく妻登志子と離婚していてしまいます。
鴎外がドイツへ医学を学ぶために1884年から5年間留学したときの体験を下敷きに執筆したのが本作。高雅な文体と浪漫的な内容で初期の代表作。
「19世紀末、ドイツ留学中のエリート官僚、太田豊太郎はさびれたユダヤ人街を散歩していたところ、クロステル街の古寺で涙に暮れる、ユダヤ人の下層階級に育つ、ヴィクトリア座のバレエダンサーの美少女エリスと出会い、一目で心奪われる。父の葬儀代を工面してやり、以後清純な交際を続けるがスキャンダルは広まり豊太郎は免職される。ここに至り、豊太郎のエリスへの愛情は高まり彼女と関係を持つ」。
「その後豊太郎はエリスと同棲し、生活費を工面するためドイツ駐在の通信員という形で新聞社に就職した。エリスはやがて豊太郎の子を身篭る。友人である相沢謙吉の紹介で大臣のロシア訪問に随行し信頼を得ることができた。復職のめども立ち、また相沢の忠告もあり結局エリスとの愛よりも出世のために日本へと帰国することを選ぶ」。
「しかし豊太郎の帰国を心配するエリスに彼は真実を告げられず、その心労で人事不省に陥り、その間に相沢から真実を知らされたエリスは衝撃の余りパラノイアを発症した。真実を伝えた相沢と、豊太郎の事さえ分からなくなるほど病状が悪化したエリスに後ろ髪を引かれつつ、豊太郎は日本に帰国する。『相澤謙吉が如き良友は世にまた得がたかるべし。されど我が脳裡に一点の彼を憎む心今日までも残れりけり』豊太郎の心からの呟きであった」。
この作品について、「舞姫論争」なるものが起こっていました。
<舞姫論争>1890年、石橋忍月と森鴎外との間に起こった文学論争で、最初の本格的な近代文学論争だといわれる。忍月は筆名「気取半之丞」で「舞姫」を書き、主人公太田が意志薄弱であることなどを指摘し批判。これに対し鴎外は相沢を筆名に使い、「気取半之丞に与ふる書」で応戦。その後も論争が行われたが、忍月が筆を絶って収束。
内容についてもう少し探ってみると、石橋忍月の投げかけは次のようなものでした。
「鴎外漁史の「舞姫」が国民之友新年附録中に就いて第一の傑作たるは世人の許す所なり。之が賛評をなしたるもの少しとせず。私家然れども未だ其の瑕瑾(かきん)を発(あば)きたるものは之れ無きが如し。予は二三不審の廉(かど)を挙げて著者其人に質問せんと欲す」。
「『舞姫』の意匠は恋愛と功名と両立せざる人生の境遇にして、此の境遇に処せしむるに小心なる臆病なる慈悲心ある――勇気なく独立心に乏しき一個の人物を以ってし、以て此の地位と彼の境遇との関係を発揮したるものなり。故に「舞姫」を批評せんと欲せば先づ其人物(太田豊太郎)と境遇との関係を精査するを必要となす」。
「抑(そもそ)も太田なるものは恋愛と功名と両立せざる場合に際して断然恋愛を捨て功名を採るの勇気あるものなるや。曰く否な。彼は小心的臆病的の人物なり。彼の性質は寧(むし)ろ謹直慈悲の傾向あり。理に於いて彼は恩愛の情に切なる者あり。
更に、作者・森鴎外と主人公は同一人物だとするものや、ドイツ人女性エリーゼ・ヴィーゲルト(Elise Wiegert)という女性が来日し、滞在一月ほどで離日したことによって、この作品のモデルであったことが話題になったようです。

石橋忍月(にんげつ、慶応元年9月1日(グレゴリオ暦1865年10月20日)-1926年(大正15年)2月1日)は、「日本の文芸評論家、小説家、弁護士、政治家。本名は友吉。号は萩の門、気取半之丞、福洲学人など。三男は文芸評論家の山本健吉。明治23年(1890年)、森鴎外の『舞姫』、『うたかたの記』等をめぐり鴎外と論争し評論の地位を高めた。しかし、壮年以降は文学からはなれ、長崎の県会議員、弁護士として活動した」。(ウィキペディア)
「うたかたの記」・・・(29歳1890年8月、「国民之友」、雑誌「しがらみ草紙」に発表。
「ドイツ・バイエルン王国の首都ミュンヘン。日本画学生の巨瀬は、以前ドレスデンで一目ぼれをした花売り娘のマリー・ハンスルと再会する。巨瀬はマリーの面影が忘れられず、自作のローレライのモデルとしていた。マリーはいきなり巨瀬に接吻する。驚く巨瀬に、同行していた友人のエスキテルは彼女は美術学校のモデルだが狂っていると教える」。
「巨瀬は、自分のアトリエにマリーを呼び彼女への熱い思いを伝える。話をする内に、マリーには高名な画家の父ステインベルグと彼女と同名の美しい母親がいた。母はバイエルン国王ルードヴィヒ2世に懸想されていた。父は国王の毒牙から妻を守って死に、母も悲しみのあまり後を追うようにして死ぬ。孤児となったマリーはアルプス近くのスタルンベルヒ湖の漁師ハンスル家に引き取られたことがわかる」。
「マリーは、父のように美術を学ぶためモデルとなっているが、誘惑の多い都会で身を守るためにわざと狂った振りをしていると明かす。マリーに誘われるまま巨瀬はスタインベルヒ湖に向かう。愛を確認した二人は、雨の湖の周囲を散策し船で遊ぶ」。
「村外れの岸辺に漕ぎ寄せると、母マリーの想い止みがたく狂人となっていた国王がいた。国王は、マリーの姿に母の幻影を見て彼女に襲いかかる。マリーは恐怖のあまり湖に没する。国王も止めようとした侍医グッデンもろとも湖に沈む」。
「巨瀬はマリーを助けるが、杭に胸を打ったのがもとで死んでしまう。国王の葬儀の日、心配したエスキテルが巨瀬のアトリエを訪問すると、彼は憔悴しきってローレライの絵の前に跪いていた」。(ウィキペディア)
「鴎外初期の流麗な文語体で書かれた悲恋物語であるが、『舞姫』では主人公が日本人留学生なのに対して、『うたかたの記』はマリー・ハンスルという美しいモデルであり、日本人巨瀬は狂言廻し的な役割になっている。なお、巨瀬のモデルはドイツ・ミュンヘン留学時代の友人である画学生原田直次郎とされ、ヒロインのマリーは原田の愛人の名前から取っている」。
「この物語のもう一人の重要人物、バイエルン国王ルードヴィヒ2世はルキノ・ヴィスコンティの映画『ルートヴィヒ』にも取り上げられ、大作曲家リヒャルト・ワーグナーのパトロンとしてあるいはノイシュヴァンシュタイン城の造営でも知られているが、1886年の王の水死事故は、鴎外の『独逸日記』に記されている。当時鴎外はミュンヘン大学に在籍していた」。
「ここでは学問に狂う巨瀬、わざと狂った振りをするマリー、思慕の念から本当に狂ったルードヴィヒ2世と、3通りの「狂気」を描くという技巧が見られる」。(同上)
本作のモデルと言われる、原田直次郎に触れておきましょう。

原田直次郎(1863-1899)は、「江戸の武家(岡山藩士)で東京・小石川生まれ。岡山藩の兵学者で、後に貴族院議員となる父のもと、幼少時代からフランス語を習い、20歳のとき、高橋由一が主催する画塾『天絵学舎』で洋画を学び始めます。高橋由一は『絵事ハ精神ノ為ス業ナリ』と唱えた近代西洋画の先駆者。絵を描く精神を支えるのは、画布であり絵の具であり、それを使う技術であるという一貫した信念を持った人物でした」。
「その高橋のもとで学んだ直次郎は明治17年、21歳でドイツに留学します。ミュンヘンアカデミーに入学し、見るもの、聞くもの、すべて貪欲に吸収しながら、めきめきと上達していきます。ドイツ留学は直次郎にとって、まぎれもない青春でした」。

「そして直次郎はこの地で、作家・森鴎外と出会います。鴎外の短編小説『うたかたの記』の中に登場する、ミュンヘン留学中の日本人画家、巨勢のモデルは直次郎です。若き留学生同士、意気投合した直次郎と鴎外は、終生の友として親交を深めていきます」。
「25歳で帰国した後は自宅に画塾を開設し、西洋美術を教える一方で内国勧業博覧会などで作品発表を行った。原田の活動時期は、ちょうど国粋主義的風潮のなかで、日本画に比べて西洋画の立場が低くみられた時期であったが、画塾は活気に満ちており、師弟というより友達のように仲良く勉強したようである。なかでも、モデルを用いた木炭デッサンは、日本で初めて行われた美術教育として重要である」。(「美の巨人たち」他)
そして、こちらはルキーノ・ヴィスコンティ監督による「地獄に堕ちた勇者ども」(1969年)、「ヴェニスに死す」(1971年)と並ぶ「ドイツ三部作」の最終章、「ルートヴィヒ」(Ludwig)も参考まで。私はかなり前に観た記憶があります。

(1973年/イタリア、フランス、西ドイツ合作映画)
監督:ルキーノ・ヴィスコンティ
脚本:ルキーノ・ヴィスコンティ、エンリコ・メディオーリ、スーゾ・チェッキ・ダミーコ
撮影:アルマンド・ナンヌッツィ
出演:ヘルムート・バーガー、トレヴァー・ハワード、ロミー・シュナイダー、シルヴァーナ・マンガーノ

ルートヴィヒ2世(Ludwig II. 1845年8月25日-1886年6月13日)は、「第4代バイエルン国王(在位:1864年-1886年)。若い頃は美貌に恵まれ、多くの画家らによって描かれてきた。『童貞王』と渾名され、生涯にわたって妻帯せず、美しい青年たちを愛した男色家(同性愛者)の君主として名高い」。(ウィキペディア)












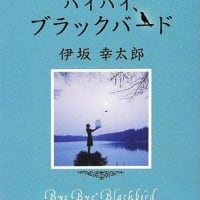







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます