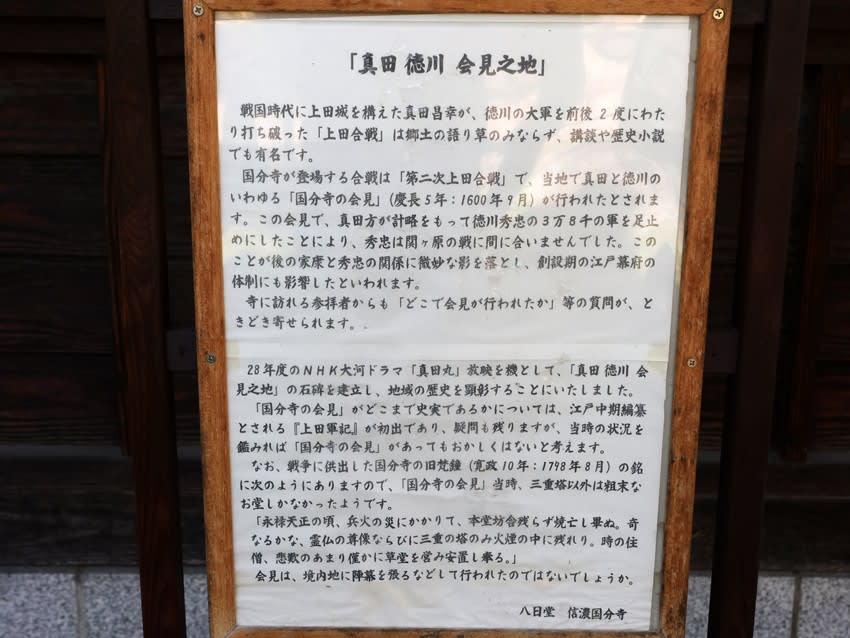訪問日 令和6年10月2日
妙義神社
妙義山の東麓に鎮座し、妙義山信仰の中心となっている神社
今回が2度目の参拝になるが、訪れた2ヶ月後に多くの建造物が重要文化財に追加された
境内は上部の神域と下部の旧寺域に分かれている
第一鳥居
最寄りの道の駅に車を駐め、少し歩くと鳥居が見えてくる

本社まで275段の石段がある

総門(重要文化財)
神仏習合時代、妙義神社には別当として上野寛永寺の末寺である「白雲山 高顕院 石塔寺」があった
現在の妙義神社の総門は、明治の初めに廃寺となった石塔寺の「仁王門」である

扁額には院号の「高顕院」

仁王像




銅鳥居(重要文化財)

稲荷神社(右)と和歌三神社

波己曾社(重要文化財)
現在の社殿は、宝暦年間(1751年 - 1764年)の大改修によるもの
古くは「波己曽(はこそ)神社」といい、『日本三代実録』に記載がある


拝殿内部

天井画


厳島社

手水舎

太鼓橋
太鼓橋を渡ると男坂と女坂に分かれている

男坂と女坂
今回も男坂を選択、165段の石段を上がることにした

随神門・廻廊(重要文化財)

随神像




唐門(重要文化財)
江戸時代後期、宝暦6年(1756年)の建立

上空には神社から許可を受けたカメラ搭載のドローンが飛んでいて、社殿の撮影をしていた
操縦していた2人の若者は映像のプロで、後に話しをする機会に恵まれた

天井画

門扉彫刻


拝殿(重要文化財)


拝殿内部



社殿の彫刻
日光東照宮の彫刻師がここに来て彫りあげたと伝えられている





本殿(重要文化財)
祭神:日本武尊、豊受大神、菅原道真公、権大納言長親卿


帰りは女坂から



水神社

社務所(重要文化財)



撮影 令和6年10月2日
妙義神社
妙義山の東麓に鎮座し、妙義山信仰の中心となっている神社
今回が2度目の参拝になるが、訪れた2ヶ月後に多くの建造物が重要文化財に追加された
境内は上部の神域と下部の旧寺域に分かれている
第一鳥居
最寄りの道の駅に車を駐め、少し歩くと鳥居が見えてくる

本社まで275段の石段がある

総門(重要文化財)
神仏習合時代、妙義神社には別当として上野寛永寺の末寺である「白雲山 高顕院 石塔寺」があった
現在の妙義神社の総門は、明治の初めに廃寺となった石塔寺の「仁王門」である

扁額には院号の「高顕院」

仁王像




銅鳥居(重要文化財)

稲荷神社(右)と和歌三神社

波己曾社(重要文化財)
現在の社殿は、宝暦年間(1751年 - 1764年)の大改修によるもの
古くは「波己曽(はこそ)神社」といい、『日本三代実録』に記載がある


拝殿内部

天井画


厳島社

手水舎

太鼓橋
太鼓橋を渡ると男坂と女坂に分かれている

男坂と女坂
今回も男坂を選択、165段の石段を上がることにした

随神門・廻廊(重要文化財)

随神像




唐門(重要文化財)
江戸時代後期、宝暦6年(1756年)の建立

上空には神社から許可を受けたカメラ搭載のドローンが飛んでいて、社殿の撮影をしていた
操縦していた2人の若者は映像のプロで、後に話しをする機会に恵まれた

天井画

門扉彫刻


拝殿(重要文化財)


拝殿内部



社殿の彫刻
日光東照宮の彫刻師がここに来て彫りあげたと伝えられている





本殿(重要文化財)
祭神:日本武尊、豊受大神、菅原道真公、権大納言長親卿


帰りは女坂から



水神社

社務所(重要文化財)



撮影 令和6年10月2日