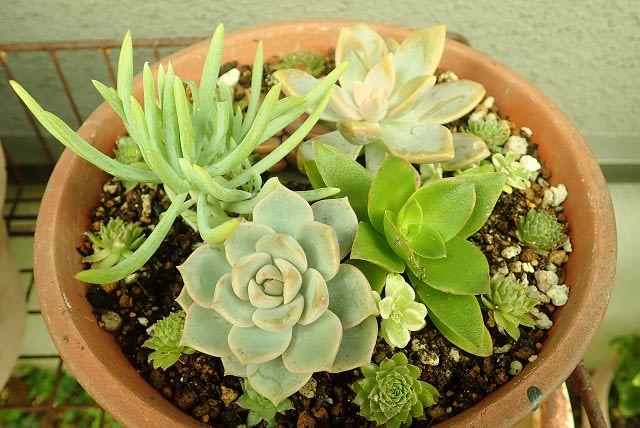この地に植えて10年以上経ちますが、ハンゲショウ・アマドコロ・シラユキゲシ・タツナミソウなどに入り込まれ
根が中々落ち付きませんでした。何年か前に気付き、回わりのお花を取りましたら元気になり始め、花も付ける
ようになり、やっと落ちつきました。今年は初めて変わり枝(枝変わり)の赤が咲きました。
10年以上たつと他のツバキにも沢山出ています。吹上絞り・草紙洗・酒中花・孔雀ツバキ・岩根絞などもすでに
出ております。
花が終わると剪定が始まります。去年、ツボミを間引いたせいか大輪の花が多かったです。
記事は青字で1昨年・昨年の記事を転記します
1昨年の記事 2018/04/08
久留米で「燕返し」を購入したのですが、この椿の特有の斑が入りませんでした。薄いピンク1色です。
それを知り、知人が「偶に、そういうことがある。これは、大丈夫」と言って下さいました。
今は大きくなり地に根を張ったようです。これも福鼓と同じように、根を張る、植物が入り込み中々元気に
なりませんでした。4月2日、暗くなり、一気に、花が開いているのに、気が付き、4月3日に撮影したものです。
燕返しは白地の淡桃地に紅の大小縦絞り、一重、ラッパ咲き、筒しべ、葉はギザギザ、開花3~4月 です。
優しい雰囲気で花弁がやや反ったように開くのが特徴のようです。花びらが中折れした長い樋状(といじょう)で
内弁は斜めに立ち上がり、弁間が透いて不規則に向き合う形を、ツバメが飛び交う姿に見立てたもので名前が
付けられたみたいです。かっこいい名前で、好きな椿です。
昨年の記事 2019/03/27
燕返しの椿の お花は、一重、白地の淡桃地に紅の大小縦絞り、一重、ラッパ咲き、筒しべ、大輪、開花3~4月
花弁がやや反ったように開くのが特徴のようです。 同じ木に赤の多い絞りが有りました。
花びらは中折れした長い樋状で 内弁は斜めに立ち上がり 弁間が透いて不規則に向き合う形をツバメが飛び交う
姿に見立てたもの。ピンク色、5枚、咲くと大きい。ハートの花びら、優しい雰囲気、葉はギザギザ。
全国各地の山間の谷間や林床に生えています、清楚で可憐な花です。かっこいい名前ですね。







3月31日に 咲いていて 気が付きました