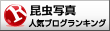〈アメバチモドキの仲間?〉
4月に撮った画像です。
ハッキリとした名前が分かりませんが、この名にたどり着きました。
大きさは、2センチ位だったように記憶しています。
あとは何も判明していません。
まだ、名前の分からないハチの仲間たちがドッサリいます。
そろそろ真剣に調べなければなりません!


※ 皆さんのところでは例年と同じ数の虫さん達がいらっしゃいますか?
当地では、とても少ないようです。
私は、事情があり今は殆んどマイフイールドに行くことが出来ませんが、
カメラを持った仲間たちが同じことを言ってるようです。
コロナが去り、気候も例年と同じようになれば虫達も安心して
出て来てくれると思うのですが、悲しい年ですね!
4月に撮った画像です。
ハッキリとした名前が分かりませんが、この名にたどり着きました。
大きさは、2センチ位だったように記憶しています。
あとは何も判明していません。
まだ、名前の分からないハチの仲間たちがドッサリいます。
そろそろ真剣に調べなければなりません!


※ 皆さんのところでは例年と同じ数の虫さん達がいらっしゃいますか?
当地では、とても少ないようです。
私は、事情があり今は殆んどマイフイールドに行くことが出来ませんが、
カメラを持った仲間たちが同じことを言ってるようです。
コロナが去り、気候も例年と同じようになれば虫達も安心して
出て来てくれると思うのですが、悲しい年ですね!