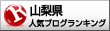ミニカーのブログを書く際にはネット以外にもいろいろな文献を参考にして書くのですが、ことレースの内容になると資料を探すのがけっこう大変です。
そういう中で見つけたのが、2012年8月発行の「ル・マン24時間耐久レース」。
副題に"栄光の時代'70~79"とあるように、私の好きな年代をすっぽりとカバーしてくれる本です。
10年間のル・マン24時間レースに参加したクルマを取り上げカラー写真と共に紹介しています。
表紙も70年のガルフカラー・ポルシェ917Kで格好いいです。
予選5位、決勝はわずか22ラップ、エンジントラブルでリタイヤと結果はイマイチですが、70年代冒頭に衝撃を与えたクルマに間違いはありません。
モデルはブルム製。
本書では優勝したクルマ以外のクルマも詳しく取り上げているので、また新たな視点からレースやクルマ(ミニカー)を振り返ることができるのがいいですね。
例えば、先日書いた「1977年のアルピーヌ」で取り上げた色違いルノー16号車は、ブログでは単に記録集どおりに「一周目にリタイヤ」と書いてありますが、本書では「ミュルサンヌストリートを駆け下りているときにオイルパイプの1本に繋がったジョイント部が外れ、ミュルサンヌコーナーに差し掛かったときには、エンジンルームが猛烈な炎に包まれていた」という記事とともに、車体半分が黒こげになった16号車の写真が掲載されているのです。
うーん、もう少し早く手に入れていれば...。
1972年のレースでは、ヨーストがエントリーしたポルシェ908の記事が載っています。
前年優勝したポルシェ917があまりにも強すぎてルマンから締め出されてしまったポルシェですが、多くの「ポルシェ研究開発センター」社員の協力で亡き、ジョー・シファートが1968年に搭乗したクルマをレストアし、サーキットに持ち込みました。

本書には、レース当日社員の半数が休暇を取ってフランスのサーキットに駆け付け60号車を見守ったとあります。
チーム名も「Siffert ATE Racing」。シファート好きの私からすると、涙なみだのエピソードであります。
モデルはスパーク製。
※別の資料には、シファート搭乗の31号車ではなく、総合3位に入った33号車だとする説もあります。
1974年のル・マンでは、3年目の挑戦になるシグマが日本の「ミスタール・マン」寺田陽次郎さんのドライブで走っています。
最後まで走り切ったものの、トラブルで規定周回数に到達せず、完走扱いになれなかったこのSIGMA MC74のロータリー車ですが、本書では大きく扱われています。

手元にあるビザール製のミニカーと並べて撮ってみました。
今まで何気なく見過ごしてきたミニカーの台座がル・マンのサーキットを模したものだということがよくわかりました。
1975年のル・マンで総合5位、クラス優勝したポルシェ911カレラRSR。
この年ポルシェのクルマは実に26台もエントリーしたのだそうです。
ルール改定で、1回の給油のたびに最低20周はしないといけないという制限と無関係ではないかもしれません。
結果として1975年のル・マンは予選最速タイム、レース中最速タイムとも70年代で最下位なのです。

グループ6や7好きの私なので、この手のミニカーはあまり買わないのですが、オークションで格安に出品されていたので、衝動的に飛び付いてしまいました。
その後、ドライバーとしてG.ヴァン・レネップがドライブしていたことを知りました。
何でこんなことをことさらに書くかというと、それは本ブログの最終節で。
1978年のレースで総合8位に入ったポルシェ935-78。
このグループ5のモンスターマシンには「モビーディック(巨鯨)」というニックネームが付いています。
ミュルサンヌの直線コースで時速336km/hを記録したこの怪物マシンでしたが、本番レースでは不運に襲われ、24時間のうち何と2時間46分もピットでの修理を余儀なくされ、クラス優勝すらできなかったのです。

本書のタイトルにもなった「不運のモビーディック」。
いつかブログで取り上げてみたいと思うマシンですね。
モデルはミニチャンプス製。
年鑑的な本なので、ブログを書く際に有用なデータもたくさん掲載されています。
リタイヤの理由、メーカー別出場台数、ドライバーの国籍や、年代別の走行データなど。
下記の写真は、各ドライバーの年別の記録です。
全ドライバー608名中、この10年間すべてに出走したのはたった4名。
72年から三連覇したマトラのアンリ・ペスカロロとポルシェ、ミラージュ、アルピーヌなどを乗り継いだデレク・ベルなどが目を引きます。
しかし、私が今回注目したのは先ほどご紹介したG.ヴァン・レネップ。
ル・マンは70年のポルシェ917K がデビュー戦でした。
このときはリタイヤでしたが、翌71年にはヘルムート・マルコと組み、マルティニカラーで有名なポルシェ917Kで見事初優勝を果たしています。
さらに翌72年はスウェーデン人ドライバー、ヨアヒム・ボニエと組んでローラT280で参戦。
しかしこのときは相棒のボニエが死亡事故を起こしたためリタイヤしてしまいました。
73年、ポルシェ911カレラRSRで総合5位(クラス優勝)。
74年、同じくポルシェ911カレラRSRで総合2位。
75年、三たびポルシェ911カレラRSRで総合5位(クラス優勝)。
そして76年、「ルマン・マエストロ」ジャッキー・イクスと組んでポルシェ936で総合優勝。

この1976年の優勝を最後にレネップはドライバーを引退してしまいます。
ですからこの70年代、彼はル・マンに七度しか出場していないにもかかわらず二度の優勝、そして総合5位以上の入賞を三回果たしたことになるのです。
引退当時34歳。
今のル・マンのドライバーからは考えられないくらい若くしての引退ですね。
モデルは左のポルシェ917Kがスパーク製、右のポルシェ936はトロフュー製です。
今回ご紹介したミニカーはすべて1/43スケール。
というわけで、色々な情報が手に入るこの本をご紹介しました。
オールカラー350ページ、発行元はSTUDIO TAC CREATIVEという会社。
モータースポーツ専門の出版社というわけではないようで、同社の販売リストを見ても、本書がとても唐突な感じすらします。
ちなみに、本の通販サイトで定価(5,000円)の半額で入手しました。
中古本とは思えない状態で満足です。