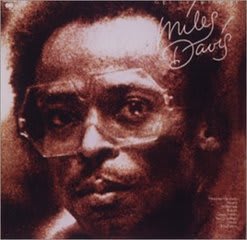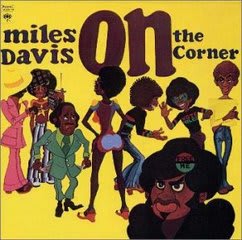4月当初のできごとだけれど。
Jujuはもうすぐ1年生。
学校はまだ春休みだから、昼間は学童保育所で遊ぶんだ。
お姉さんが一緒だし、保育園の時からのお友達も来るし、新しいお友達もたくさんできて、すっごく楽しい。
それからそれから、手作りのお弁当!
ほんとはね、今朝はお父さんが作ってくれる約束だったんだけど…またお寝坊?
今日もお母さんのお弁当だな。楽しみだな。
でも今朝はちょっといやな気持ち。
入学式は明後日だけど、始業式で学校が始まってしまうから、今日と明日は1人で学童へ行かなきゃいけない。
だって、本当はね、ひとりじゃまだ何にもできないし、お姉さんがいないと淋しくって淋しくって(な~んて、お姉さんには絶対知られたくないけど)。
「早く着替えなさ~い!遅刻するよ!」
「はぁ~い!」どたどたどた…。
お姉さんが新しいお洋服を着て降りてきた。
「あー、素敵な服!その服、どうしたの?お姉ちゃんにすごく良く似合ってる~!」
「あ、そ。お母さんにもらったの。」
…え?
よく似合ってるのに、あんまり嬉しくないの?
今日から私は5年生。
クラス換えがあるけど、仲のいい友達とまたいっしょだといいな。
ちょっと気になる男の子は…。
とにかく、今日は始まりの日。
このあいだお母さんが内緒で買ってきてくれた、新しいパーカーを着ていくんだ。
でも内緒だから、妹の服は買ってないんだよね。やきもち焼くだろうな。
…そうだ!お母さんのお古をもらったことにしておこう!私が着られなくなったら、妹にあげるよ、って。
「早く着替えなさ~い!遅刻するよ!」
「はぁ~い!」どたどたどた…。
新しいパーカーを着て階段を駆け下りた。
「あー、素敵な服!その服、どうしたの?お姉ちゃんにすごく良く似合ってる~!」
「あ、そ。お母さんにもらったの。」
…あ、しまった。
なんか、妹が淋しそう。
そんなつもりじゃなかったのに。
でも「いいでしょ?」なんて自慢げに言ったら余計悲しむだろうし、買ってもらったことがばれちゃうし…。
「Jujuが大きくなったらあげるよ」って言うのも忘れてたけど、まぁいっか。
玄関まで来ちゃったし、学校学校!
玄関出ようとしたらお父さんが来た。
「いってきまーす!」
「こら。もう少し妹の気持ち考えてあげなよ。」
「あ、ばれてた?」
錯綜する朝の風景。
もう少し、時間の余裕があれば、フォローできるんだけどね。
Jujuはもうすぐ1年生。
学校はまだ春休みだから、昼間は学童保育所で遊ぶんだ。
お姉さんが一緒だし、保育園の時からのお友達も来るし、新しいお友達もたくさんできて、すっごく楽しい。
それからそれから、手作りのお弁当!
ほんとはね、今朝はお父さんが作ってくれる約束だったんだけど…またお寝坊?
今日もお母さんのお弁当だな。楽しみだな。
でも今朝はちょっといやな気持ち。
入学式は明後日だけど、始業式で学校が始まってしまうから、今日と明日は1人で学童へ行かなきゃいけない。
だって、本当はね、ひとりじゃまだ何にもできないし、お姉さんがいないと淋しくって淋しくって(な~んて、お姉さんには絶対知られたくないけど)。
「早く着替えなさ~い!遅刻するよ!」
「はぁ~い!」どたどたどた…。
お姉さんが新しいお洋服を着て降りてきた。
「あー、素敵な服!その服、どうしたの?お姉ちゃんにすごく良く似合ってる~!」
「あ、そ。お母さんにもらったの。」
…え?
よく似合ってるのに、あんまり嬉しくないの?
今日から私は5年生。
クラス換えがあるけど、仲のいい友達とまたいっしょだといいな。
ちょっと気になる男の子は…。
とにかく、今日は始まりの日。
このあいだお母さんが内緒で買ってきてくれた、新しいパーカーを着ていくんだ。
でも内緒だから、妹の服は買ってないんだよね。やきもち焼くだろうな。
…そうだ!お母さんのお古をもらったことにしておこう!私が着られなくなったら、妹にあげるよ、って。
「早く着替えなさ~い!遅刻するよ!」
「はぁ~い!」どたどたどた…。
新しいパーカーを着て階段を駆け下りた。
「あー、素敵な服!その服、どうしたの?お姉ちゃんにすごく良く似合ってる~!」
「あ、そ。お母さんにもらったの。」
…あ、しまった。
なんか、妹が淋しそう。
そんなつもりじゃなかったのに。
でも「いいでしょ?」なんて自慢げに言ったら余計悲しむだろうし、買ってもらったことがばれちゃうし…。
「Jujuが大きくなったらあげるよ」って言うのも忘れてたけど、まぁいっか。
玄関まで来ちゃったし、学校学校!
玄関出ようとしたらお父さんが来た。
「いってきまーす!」
「こら。もう少し妹の気持ち考えてあげなよ。」
「あ、ばれてた?」
錯綜する朝の風景。
もう少し、時間の余裕があれば、フォローできるんだけどね。