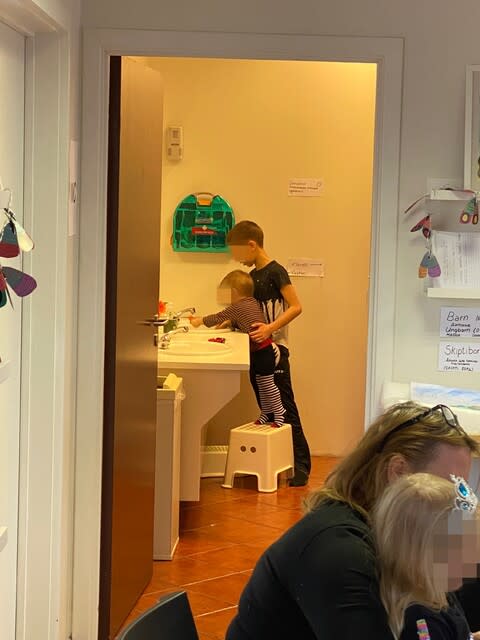こんにちは/こんばんは。
今日は8月15日。お盆休暇の真っ最中ですね。っていうか、もう終わりか?地域によっては雨も激しくなるそうですし、また別の場所では暑さが激しくなるとか。お盆明けで、渋滞の中を長距離ドライブという方もあるかと思います。くれぐれも気をつけて運転されますよう。

清涼感アップ用ピック
Myndin er eftir Rostyslav_Savchyn@unsplash.com
そういうお盆とはまったく関係のないレイキャビク。シーズン開始前にしては月並みな日々を重ねています。が、ひとつ特別なことがありました - あります。現在進行形です。
ワタシ、コロナに感染しました。ついに捕まったか。という感じ。土曜日の夜にチラッと喉がひりついたのですが、夜明けになって頭痛と発熱。過去二十年以上、まったくインフルエンザにもかからないできた私も、「これはコロナかも」と認めざるを得なくなり、簡易キットで調べると陽性。
日曜の朝でしたので、まずもって教会関連のウェッブで「日曜日の礼拝中止」のアナウンスをし、そのあと人が絶対に起きているだろう時間を待って個別に連絡をしました。
特に大切な行事や重大な課題もない週なので、それほど打撃はないのが幸い。昨日の日曜日は、それなりに頭痛と寒気の連続で、まともなことはなんにもできませんでしたが、今日はかなり回復しています。
皆様も大雨&猛暑のかたはら、コロナにも気をつけてお過ごしくださいますよう。
さて、前回はレイキャビクでどうやって焼き魚を喰らうかという、実に誰にもなんの得にもならないトピックについて書かせていただきました。
ここ二週間以上、私は「焼き魚」に取り憑かれて過ごしています。四年前に日本へ帰った時にコンビニで売っている「サバの塩焼き」「しゃけのなんとか焼き」の「半レトルトパック」を初めて食しました。
その頃はケト・ダイエットにはまっていて、お米やパン、麺類を断っていまいた。容易に摂取できる良いタンパク源は?と探していて出会ったのですが、この、なんというか「半レトルト」的な焼き魚が、思った以上のクオリティだったことに感激。さすがニッポン!

これは番外編 イワシとワカサギの唐揚げ
そのことを思い起こして気がつきました。「だったら、同じような焼き魚をアマゾンで買えるのではないか?」そしてネット通販に没頭。
「骨まで丸ごと食べられる焼き魚」的なものがいくつかあることを学びました。だいたい干した魚の焼き魚を真空パックにしたもののようで、常温保存で三ヶ月くらいは大丈夫だとのこと。
アジ、サバ、サンマ、ホッケ等々、種類もかなりあるし、値段も安いのでいくつかを試験的に注文してみました。まだ手元には届いていません。アジ、サンマ、ホッケとかは、他の方法では手に入らないですからね。楽しみです。
前回のブログの更新の後、何人かの知人の方々から、Facebook等を通じて「フライパンにクッキングシートを敷いて焼けば?」とか「アルミに包んでオーブントースターで焼いたらいいよ」とか、アドバイスをいただきました。ありがとうございます。
実は、前回書いている最中から進展していることがありました。前回は「スモークしたサバを、オーブンで炙り直して食べると、かなり焼き魚に遜色ないサバ焼きになった」というところまででした。
その後の展開は、Ninjaのグリル&エア・フライヤー用の調理器具を購入したことによります。Ninjaという、いささかいかがわしいブランド名はどれほど日本で知られているのでしょうか?
私もNinjaのちいちゃななミキサー -あの、プロテインとかミックスして、そのまま容器から飲めるやつ- を数年前から持っていましたが、メーカーそのものについては、去年までほとんど無知でした。去年の夏に圧力鍋とスロークッカー等に使える調理器を購入したのですが、調べてみると、一応アメリカの会社とのこと。


かなりゴツイ調理器 Ninjaの室内グリル器
そのNinjaの圧力鍋調理器具製品にも、一応グリルとかも付いてはいるのですが、おまけのように私に目には見えます。
Ninja圧力鍋についてはこちらも - デジタル化とテクノロジーの発展 そして老人
そこで、もう一台「グリル!」に特化したタイプを購入したわけです。安くはないんですけど、クレジットカードのサービスポイントが27000クローネも溜まっていたので、それを投入。
まずやってみたのが、前回ご紹介しました「肉厚のサバのスモーク」を、このグリル機で焼き直して食してみることです。
ちょっとだけ前史を付け足しますが、一番初めに開いたサバを電子レンジで温めた時には、変に水っぽくなってしまいました。どういうことなのか、いまだに理由はわかりません。スモークト・サバは干物ではないので、水分はもちろんあります。温めると水が出てくるのかな?
二回目、普通のオーブンで炙り直した時のことが、前回のブログでご紹介したものです。味は十分美味しいし、スモーク臭もほとんど気にならないくらい。ただ、「焼きあと」はつかなかったです。
そしてNinja登板の三回目。今回は「炙り直す」ではなくて、「グリルする」感じでトライ。
結果は...? これはですね、言うことなし。焼き魚ですよ、まったくの。


これは「焼き魚」でしょう?
スモーク臭は気にならない、のではなくて、まったく消えてくれました。スモーク好きの人には気に入らないでしょうが、私には朗報。
今回もたっぷりの大根おろしでいただきました。もともと大きなサバなのですが、今回きちんと「焼いた」ことによって、脂身もきちんと溶け出して、トロトロ感があります。しかも、皮はパリパリになって、これも美味しい。
大きな骨を残して、ほとんどが私のお腹の中に消えていきました。シ・ア・ワ・セ。満足、満足。
ここで突如現れたのが「貪欲」。貪欲は身を滅ぼす、と言います。貪欲は誘惑の呼び込み役です。ですが、それだけではなく「貪欲は道を開く」こともあります。満足感の中で、私は思いました。「これなら、生の魚を焼いてもいけるんじゃないか?」
実は、スモークのサバと同じサイズの丸々冷凍サバも購入してあるのです。これを焼いてみない手はない。
しかしです。それにはひとつの越えるべき山があります。それは魚を捌くことです。私は料理好きですが、魚の捌きはまったくのトーシロ。八王子育ちのシチー・ボーイの私にとって、肉とは部位別に分かれて鎮座しているもの、魚とは刺身になっているか開きになって横たわっているものなのです。
アイスランドにも切り身になっている魚はあります。タラとか、シャケとか。でも種類は限られていますし、必ずしも焼き魚に適した形態には切られていません。サバを喰らいたかったら、自分で捌くしかありません。幸いなことに、サバに関しては大きな丸々冷凍があるではないか。サンマやホッケはこうはいかない。
なら、やってやろうではないか! 捌きにトライ! 今どき、庶民にはYoutubeというつよ〜い味方があるのだ。しかも拾い見したYoutubeでは、講師の和食の板さんが「サバは比較的捌きやすい魚です」とおっしゃっておられるのです。
とうわけで、次のステージは魚を捌いて焼き魚を試すことです。「貪欲」は道を開くのです。この新チャレンジについては、次回以降にご紹介してみたいと思います。進展があれば、ですが。(^-^;
*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。
藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com
Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation
Facebook: Toma Toshiki
今日は8月15日。お盆休暇の真っ最中ですね。っていうか、もう終わりか?地域によっては雨も激しくなるそうですし、また別の場所では暑さが激しくなるとか。お盆明けで、渋滞の中を長距離ドライブという方もあるかと思います。くれぐれも気をつけて運転されますよう。

清涼感アップ用ピック
Myndin er eftir Rostyslav_Savchyn@unsplash.com
そういうお盆とはまったく関係のないレイキャビク。シーズン開始前にしては月並みな日々を重ねています。が、ひとつ特別なことがありました - あります。現在進行形です。
ワタシ、コロナに感染しました。ついに捕まったか。という感じ。土曜日の夜にチラッと喉がひりついたのですが、夜明けになって頭痛と発熱。過去二十年以上、まったくインフルエンザにもかからないできた私も、「これはコロナかも」と認めざるを得なくなり、簡易キットで調べると陽性。
日曜の朝でしたので、まずもって教会関連のウェッブで「日曜日の礼拝中止」のアナウンスをし、そのあと人が絶対に起きているだろう時間を待って個別に連絡をしました。
特に大切な行事や重大な課題もない週なので、それほど打撃はないのが幸い。昨日の日曜日は、それなりに頭痛と寒気の連続で、まともなことはなんにもできませんでしたが、今日はかなり回復しています。
皆様も大雨&猛暑のかたはら、コロナにも気をつけてお過ごしくださいますよう。
さて、前回はレイキャビクでどうやって焼き魚を喰らうかという、実に誰にもなんの得にもならないトピックについて書かせていただきました。
ここ二週間以上、私は「焼き魚」に取り憑かれて過ごしています。四年前に日本へ帰った時にコンビニで売っている「サバの塩焼き」「しゃけのなんとか焼き」の「半レトルトパック」を初めて食しました。
その頃はケト・ダイエットにはまっていて、お米やパン、麺類を断っていまいた。容易に摂取できる良いタンパク源は?と探していて出会ったのですが、この、なんというか「半レトルト」的な焼き魚が、思った以上のクオリティだったことに感激。さすがニッポン!

これは番外編 イワシとワカサギの唐揚げ
そのことを思い起こして気がつきました。「だったら、同じような焼き魚をアマゾンで買えるのではないか?」そしてネット通販に没頭。
「骨まで丸ごと食べられる焼き魚」的なものがいくつかあることを学びました。だいたい干した魚の焼き魚を真空パックにしたもののようで、常温保存で三ヶ月くらいは大丈夫だとのこと。
アジ、サバ、サンマ、ホッケ等々、種類もかなりあるし、値段も安いのでいくつかを試験的に注文してみました。まだ手元には届いていません。アジ、サンマ、ホッケとかは、他の方法では手に入らないですからね。楽しみです。
前回のブログの更新の後、何人かの知人の方々から、Facebook等を通じて「フライパンにクッキングシートを敷いて焼けば?」とか「アルミに包んでオーブントースターで焼いたらいいよ」とか、アドバイスをいただきました。ありがとうございます。
実は、前回書いている最中から進展していることがありました。前回は「スモークしたサバを、オーブンで炙り直して食べると、かなり焼き魚に遜色ないサバ焼きになった」というところまででした。
その後の展開は、Ninjaのグリル&エア・フライヤー用の調理器具を購入したことによります。Ninjaという、いささかいかがわしいブランド名はどれほど日本で知られているのでしょうか?
私もNinjaのちいちゃななミキサー -あの、プロテインとかミックスして、そのまま容器から飲めるやつ- を数年前から持っていましたが、メーカーそのものについては、去年までほとんど無知でした。去年の夏に圧力鍋とスロークッカー等に使える調理器を購入したのですが、調べてみると、一応アメリカの会社とのこと。


かなりゴツイ調理器 Ninjaの室内グリル器
そのNinjaの圧力鍋調理器具製品にも、一応グリルとかも付いてはいるのですが、おまけのように私に目には見えます。
Ninja圧力鍋についてはこちらも - デジタル化とテクノロジーの発展 そして老人
そこで、もう一台「グリル!」に特化したタイプを購入したわけです。安くはないんですけど、クレジットカードのサービスポイントが27000クローネも溜まっていたので、それを投入。
まずやってみたのが、前回ご紹介しました「肉厚のサバのスモーク」を、このグリル機で焼き直して食してみることです。
ちょっとだけ前史を付け足しますが、一番初めに開いたサバを電子レンジで温めた時には、変に水っぽくなってしまいました。どういうことなのか、いまだに理由はわかりません。スモークト・サバは干物ではないので、水分はもちろんあります。温めると水が出てくるのかな?
二回目、普通のオーブンで炙り直した時のことが、前回のブログでご紹介したものです。味は十分美味しいし、スモーク臭もほとんど気にならないくらい。ただ、「焼きあと」はつかなかったです。
そしてNinja登板の三回目。今回は「炙り直す」ではなくて、「グリルする」感じでトライ。
結果は...? これはですね、言うことなし。焼き魚ですよ、まったくの。


これは「焼き魚」でしょう?
スモーク臭は気にならない、のではなくて、まったく消えてくれました。スモーク好きの人には気に入らないでしょうが、私には朗報。
今回もたっぷりの大根おろしでいただきました。もともと大きなサバなのですが、今回きちんと「焼いた」ことによって、脂身もきちんと溶け出して、トロトロ感があります。しかも、皮はパリパリになって、これも美味しい。
大きな骨を残して、ほとんどが私のお腹の中に消えていきました。シ・ア・ワ・セ。満足、満足。
ここで突如現れたのが「貪欲」。貪欲は身を滅ぼす、と言います。貪欲は誘惑の呼び込み役です。ですが、それだけではなく「貪欲は道を開く」こともあります。満足感の中で、私は思いました。「これなら、生の魚を焼いてもいけるんじゃないか?」
実は、スモークのサバと同じサイズの丸々冷凍サバも購入してあるのです。これを焼いてみない手はない。
しかしです。それにはひとつの越えるべき山があります。それは魚を捌くことです。私は料理好きですが、魚の捌きはまったくのトーシロ。八王子育ちのシチー・ボーイの私にとって、肉とは部位別に分かれて鎮座しているもの、魚とは刺身になっているか開きになって横たわっているものなのです。
アイスランドにも切り身になっている魚はあります。タラとか、シャケとか。でも種類は限られていますし、必ずしも焼き魚に適した形態には切られていません。サバを喰らいたかったら、自分で捌くしかありません。幸いなことに、サバに関しては大きな丸々冷凍があるではないか。サンマやホッケはこうはいかない。
なら、やってやろうではないか! 捌きにトライ! 今どき、庶民にはYoutubeというつよ〜い味方があるのだ。しかも拾い見したYoutubeでは、講師の和食の板さんが「サバは比較的捌きやすい魚です」とおっしゃっておられるのです。
とうわけで、次のステージは魚を捌いて焼き魚を試すことです。「貪欲」は道を開くのです。この新チャレンジについては、次回以降にご紹介してみたいと思います。進展があれば、ですが。(^-^;
*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。
藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com
Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation
Facebook: Toma Toshiki