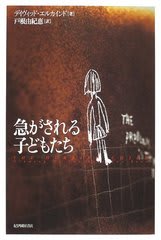これは許せませんね。岐阜の話から…
岐阜県の裏金問題、最初は、お役所体質のひとつぐらいに思っていたのですが、その受け皿の一部が、“教職員組合”というではありませんか。労組というのは、本来弱者が集まって、権力者に対抗するチェック機能を果たすのが目的で存在しているはずです。
それが、こともあろうに、生徒を教育するはずの教職員が、県(権力者) と一緒になって、一般市民から税金泥棒を働いていたという構図です。しかもばれたあと、“裏金は焼却した” と子どもじみたうそまでつく。あきれます。
岐阜県の公立高校と養護学校は合計85校、そのうち何と30校が、裏金つくりに参加。多い年は年間3600万円というではないですか。この数と金額はどうですか。“一部の不心得者が…”という言い訳じゃすまないでしょう。完全に組織ぐるみだと思いませんか。
これまでも、さまざまな問題を起こしているのに、なぜしっかり教員組合に、監査が入らないのか。税金ですよ、税金。総裁選にからめて、消費税UPを取り上げる前に、どうしてマスコミは、税金横領撲滅キャンペーンを張らないのでしょうか。不思議でなりません。当然、岐阜県だけの問題ではないはずです。
そして、こういった役所の裏金事件の不可解なところは、いつも、それがバレてもお金を返すだけ。(行儀悪いけど、)“ざけんなよ~!”と言いたくなります。なんで関わったもの全員クビにしないんですか、なんで逮捕しないんでしょう。
どこから見ても、立派な横領とか背任でしょう。飲み食いやタクシー代に使っていたというのですから。役人の組織ぐるみの裏金作りは、外務省でもありましたし、北海道庁他、いろいろありましたよ。いつも、せいぜい、とかげのしっぽ切りで終わります。
私は今でも、小・中学校の恩師と年賀状のやりとりをさせていただいており、学校の先生が好きでしたし、実の姉とその子どもは岐阜県に住んでおります。ですから、ここまで書く気はなかったのですが…、
この岐阜県教員組合のブログを見て、大人げないけど、“切れました”。じっくりお読み下さい。
→
http://gifukyoso.blog58.fc2.com/blog-entry-49.html
おかしくないですか、この理屈?批判覚悟で書かせていただきます。
外から客観的に見れば、自分たちが積極的に関わってきた犯罪行為を、全く反省していないばかりか、最後は
『とりわけ、修学旅行の下見や自主的な研修に行けない実情を改善するため、旅費を増額すること』 と要望しています。
本気で反省し、書いた人物が潔白なのなら、この卑劣な事件に関わった教員の氏名公表や、辞職を要求するのが先ではないですか。そもそもあなた方は、生徒のほうを向いているのか!仲間をかばう気しかないのではないか。
怒りを通り越して、絶望感さえ感じます。でも、遠慮していたらますますまじめな納税者がバカを見ますし、教員組合はつけ上がる。自分の子どもを学校に預けていらっしゃる親御さんは、直接、言いにくいでしょう。そう思い、あえて書かせていただきました。
乱文お許し下さい。
そういう訳で、前置きが長くなりましたが、ひょっとして教員組合が支配する学校現場の問題を、ご存じない方もいらっしゃるのかと思い、ためらいましたが、本書をご紹介します。もう数年前のできごとですが、この本を読んだ時の衝撃は、いまだに覚えています。
東京国立市で起こった『
校長土下座要求事件 』 をご記憶でしょうか。ごく普通の公立小学校のできごとでした。卒業式当日、屋上に国旗を掲げた校長先生を一部の児童が取り囲み、「土下座」して謝ることを要求したとされる事件ですが、その真相を当事者がまとめたショッキングな内容です。
国立のある学校では、日の丸の赤は血の色、白は骨の色と教え、紅白の幕は日の丸を連想するからだめ。運動会での玉入れは、紅白の玉の代わりに青と黄色の玉入れをさせた、などという話もきいたことがあります。
こういうことは、過去のことだと思っておりましたし、私の友人にも学校に立派に勤めている人間が何人もいるのですが、岐阜県の事件を聞くにおよび、やはり、本質が変わっていない、本書しかないかなという一冊です。
(ホントに長くてすいません。)
さて、この本のレビューを実は、同僚の “
genio” が書いております。私と違って、彼は学校の教師を経験し、実態を知っていますので、私なんかよりずっと本書紹介の適任です。私も言いたいことはたくさんあるのですが、今日は、尊敬する genio さんの書評を、了解を得て以下に掲載させていただきました。お読み下さい。
■■■■■
『理念先行の危うさ』
文教都市・国立での「土下座要求事件」当時の教育長石井昌浩氏が、なんと現職という立場のままで、事件のいきさつについて明らかにした 『 学校が泣いている(扶桑社) 』が先般出版されました。このような形で、児童を含めた一連のやり取りや教職員集団の教育に対するかかわり方などを公にしたのは例外的な出来事です。
長年にわたり国立市では「子ども中心主義」の理念のもとで、人権教育・平和教育・
ジェンダーフリー教育などの「進歩的」取り組みが行なわれてきました。確かに子どもが主体的に考え、意見表明すること自体は悪いことではありません。でもそれが過度な権利意識を育て、政治的に偏った教育が行なわれていたとしたらどうでしょうか。
たとえ国旗・国歌を好ましくないものと考えたとしても、子どもたち自身が自らの判断で「土下座要求」するのはあまりに不自然です。これを子どもの意見表明として肯定的にとらえる大人がいたということは何を意味しているのでしょうか。
また国立市は中学生の不登校の数が東京都で一番多く、全国平均の二倍にも上るということは一体何を意味しているのでしょうか。
国立市は「新左翼の解放区」と言われています。体罰や学級崩壊をマスコミに公表するような管理職は、教員の身分を危うくするものとして裏切り者扱いされ、つるし上げにあうそうです。
一方、ジェンダーフリー教育の一環として
男女混合名簿が全国に先駆けて導入されたり、権威を徹底的に否定するために卒業証書授与式が排除されたり、強い党派性を感じさせる教育が行なわれてきました。
詳細な情報は公にされず、教育内容に関するチェックは一切行なわれず、閉鎖的な環境の中で一部の教員が主導する反権力を旗印にした過激な教育理念が実践されてきたといえるのです。
教育委員会の職員が学校に来るのは、監視であり、昔の
特高警察と同じだから教室には入れない。校長の授業視察は、管理体制の強化のためだから教室には入れないそうです(都議会議事録)。石井氏の著作はそのような教育行政に風穴を開ける画期的なことだと思います。
公教育として税金で運営されている以上、偏向教育は論外ですし、それを包み隠すような理念先行型の教育論争は無意味であるどころか有害です。個性を育てるという教育目標は、言葉は美しいですが評価のしようがありません。
少なくとも将来の社会の形成者として要請される基礎学力を身につけさせることが何より大切で、それが定着しているかどうかを数値として公表することによってはじめて、納めた税金が適正に使われているかどうかを正当に評価できるのだと思います。
理想論だけで教育を語ることに胡散臭さを感じるのは私だけでしょうか。理念先行の教育がもたらす弊害は次々と明らかになっています。教育の荒廃が叫ばれる昨今、理念に酔うのではなく、公教育の中で子どもたちが何を身につけることが出来るのかを具体的に語るべき時ではないのでしょうか。
本書は、勇気ある著者が、この事件をもとに、教育を世に問いかける、記憶すべき一冊であると思います。
■■■■■
 | 学校が泣いている―文教都市国立からのレポート扶桑社詳 細 |
genio さんのブログです。ぜひご覧下さい。→ 『
入試に出る!時事ネタ日記 』
http://tokkun.net/jump.htm
『 学校が泣いている 』 石井昌浩
扶桑社:209P:1500円
■■ たまには怒ろう!
■■
日本の教育を良くするには、塾や私立の隆盛ではなく、公立校の復活こそが必要だと、信じて疑っておりません。もし賛同いただければ
1 クリック、いただけるとうれしいです
→
にほんブログ村 本ブログ 人気blogランキングへ