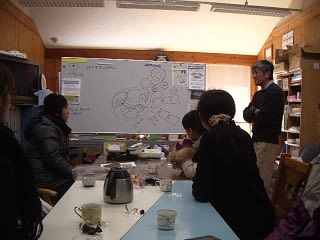ザンビア事務所の瀬戸口です。
最近のザンビアで一番ホットな話題はアフリカンカップ です。
です。
今日は準決勝なので、ザンビアの人たちはみんなテレビにかじりついて大盛り上がりすることでしょう

まだ試合は始まっていないのに、ブブセラの音が聞こえてきます
私はサッカーにほとんど興味がないので、初戦の頃は「見た?見た?」ってしつこいくらいに
会話に誘われていたのですが、最近は全くお呼びがかからなくなりました
ということで(?)、今日はモンボシ地域で活躍中の自転車救急車 にまつわるお話
にまつわるお話
ヘルスポストまで徒歩で4-5時間かかる村もたくさんあるモンボシでは、
患者さんや妊婦さんをヘルスポストまでどう搬送するか、というのが大きな課題でした。
それを少しでも解決すべく、半年ほど前に導入されたのが自転車救急車です。
*導入された時のブログ記事はこちら。

そしてこの上の写真に写っている自転車救急車を作ったのがディサケアという団体。

ロゴにもあるように車椅子なんかも作ってますが、
この団体は障害者を雇用し、そういった製品を製造・販売することで、
彼らの自立を目指している団体でもあります。

▲ディサケアの施設内のトイレ
ここの作る自転車救急車は、とても丈夫でモンボシのような道でもなんのその

▲車輪の部分

▲ストレッチャーの部分。車体から取り外し可能のため、患者をそのままベッドに移動できる。
モンボシのための自転車救急車が、実は障害者支援にもつながっていた、というのは、
ちょっと出来すぎた話でしょうか
*本事業は「チボンボ郡地域住民が支える安全な妊娠/出産の支援事業」としてJICAの委託を受けています。
文責:ザンビア事務所(瀬戸口)
最近のザンビアで一番ホットな話題はアフリカンカップ
 です。
です。今日は準決勝なので、ザンビアの人たちはみんなテレビにかじりついて大盛り上がりすることでしょう


まだ試合は始まっていないのに、ブブセラの音が聞こえてきます

私はサッカーにほとんど興味がないので、初戦の頃は「見た?見た?」ってしつこいくらいに
会話に誘われていたのですが、最近は全くお呼びがかからなくなりました

ということで(?)、今日はモンボシ地域で活躍中の自転車救急車
 にまつわるお話
にまつわるお話
ヘルスポストまで徒歩で4-5時間かかる村もたくさんあるモンボシでは、
患者さんや妊婦さんをヘルスポストまでどう搬送するか、というのが大きな課題でした。
それを少しでも解決すべく、半年ほど前に導入されたのが自転車救急車です。
*導入された時のブログ記事はこちら。

そしてこの上の写真に写っている自転車救急車を作ったのがディサケアという団体。

ロゴにもあるように車椅子なんかも作ってますが、
この団体は障害者を雇用し、そういった製品を製造・販売することで、
彼らの自立を目指している団体でもあります。

▲ディサケアの施設内のトイレ
ここの作る自転車救急車は、とても丈夫でモンボシのような道でもなんのその


▲車輪の部分

▲ストレッチャーの部分。車体から取り外し可能のため、患者をそのままベッドに移動できる。
モンボシのための自転車救急車が、実は障害者支援にもつながっていた、というのは、
ちょっと出来すぎた話でしょうか

*本事業は「チボンボ郡地域住民が支える安全な妊娠/出産の支援事業」としてJICAの委託を受けています。
文責:ザンビア事務所(瀬戸口)













 !もちろんそれぞれの大陸の国々の間で格差はあるので、このデータが世界のすべての状況を正確に映し出しているとは一概には言えませんが、可視化することによってわかりやすくとらえられました。
!もちろんそれぞれの大陸の国々の間で格差はあるので、このデータが世界のすべての状況を正確に映し出しているとは一概には言えませんが、可視化することによってわかりやすくとらえられました。





 まだ外が真っ暗な中、畑へ向かい里芋を掘り出しました。畑のかぶを丸かじり!あまーい
まだ外が真っ暗な中、畑へ向かい里芋を掘り出しました。畑のかぶを丸かじり!あまーい