木下龍也の歌集『つむじ風、ここにあります』を読んで、久しぶりに面白かった。面白かったのは、この作者の危うさである。世界のシステムに準拠する振りをして、実は全力で拒否したがっているところである。
じっとしているのではない全方位から押されてて動けないのだ
全部屋の全室外機稼働してこのアパートは発進しない
一首目の「押されている」のは、何に押されているのか。膨大な情報に押されているのだと読む。人間は良心的であろうとすればするほど、客観性を求めるものだ。インターネットが発信する世界中の情報の(それは世界中の主張、と言い換えても良い)、何が正しくて何が不正なのか、何に準拠して動けば良いのか、考えれば考えるほど動けなくなる。それは作者の純情であって、私などはそこに感動する。
だが、実のところ、正しさなんてものは、ほぼ無い。誰もが自己正当化を正義であると誤認し、そしてその正義が無数に殖え続ける現状において、本当は二首目に「発進しない」と詠う諦めを捨て、住んでいる小さな部屋の室外機をジェットエンジンに見立てて、アパートの他の住人を巻き込んで虚空へと発進しても良いのだ、歌においては。
此処ではない何処かへ行きたいのは、若者の普遍的な欲求であろうが、世界のシステムが整う程、その欲求は空砲に終わる。今の時代の不幸とは、何もかもが忽ち見出され、喰い尽くされることにあろうか。
カードキー忘れて水を買いに出て僕は世界に閉じ込められる
ハンカチを落としましたよああこれは僕が鬼だということですか
一首目は、通常なら「世界へ締め出される」というべきところ、「閉じ込められる」を使ったあたり、作者にとっては、世界よりも一夜の宿に過ぎないホテルの一室の方が広い。仮住の束の間の個人の領域の方が、世界よりも開放感を持つのは、世界の整ったシステムが、作者にとって息の詰まるものであるからだ。
それは二首目の、自身を「鬼」だと認識していることに依ろう。この「鬼」には二重の意が籠められていて、一つには「ハンカチ落とし」の鬼として、誰か或いは何かを追わねばならない定めを持つ者、そして一つには、「鬼」本来の意、はみ出し者、追われる者、異種の意である。この二つの意は補完し合っていて、追わねばならぬ定めゆえに異種であり、追われ、はみ出すがゆえに追わねばならぬ。その「鬼」性は、ハンカチを拾ってしまう性質に依る。他者に関わろうとする善意が異種性に直結してしまう、それは現今の世界に対する皮肉でもある。
後ろから刺された僕のお腹からちょっと刃先が見えているなう
あ 殺してやろうと思い指先で押した ガラスの外側にいた
B型の不足を叫ぶ青年が血のいれものとして僕を見る
殺したい、殺されたい、この表明は実は破壊したい、破壊されたいの意だろう。一首目の、後ろから(=目に見えぬものから)刺された瞬間を「なう」nowと報告したい軽さ。二首目の、生殺の選択から、ガラスという透明にして硬質な物(=システムという境界)に阻まれているもどかしさ。三首目の、自己への即物的な視線。売血ではなく、献血の風景なのがミソで、受ける側与える側共に全くの善意の行為においても、もはや善を信じられない何かが混じる。
あまりにも絡み合い過ぎた世界のシステムは、もはや真っ平らになる事でしか、人間に生(なま)を実感させないのかもしれぬ。手っ取り早いのは戦争であり、核兵器であるが、そこで破壊されるのは、世界のシステムではなく、システムに疑問を抱く個人の心であり、肉体である。恐らく、システムは揺るぎもしない。戦争はシステムを維持するためのビジネスだからだ。
銃弾は届く言葉は届かない この距離感でお願いします
撲殺よりも刺殺の方が、刺殺よりも銃殺の方が、銃殺よりも爆殺の方が、より罪悪感を覚えずに済む。相手を殺すのに要する労力が少ないほど楽で、それは相手の心と交わらずに済むからだ。銃弾は届くが言葉は届かない距離感とは、殺し合う双方の「言葉=心」が届かない状況での殺し合い、という現代の気楽さだ。これが明治以前なら、兵には名乗りを上げて殺し合う理想がまだ残されていた。現代の兵士の不幸とは、銃の発明によって己が誇りが見えなくなる点にあるが、それは戦争屋にとっては大変効率が良い。
戦争はビジネスだよとつぶやいて彼はひとりで平和になった
平和なるものの仕組みは、よくよく見れば判るのだ。世界が根本では、金と暴力のみによって、そのシステムを稼働させている事は。
この歌における「彼」は、作者自身であると仮定して、そして敢えて「彼」と、己を突き放したのだと読んで、「平和になった」との皮肉を、健気にも己自身に向けているのだと深読みして、(なぜなら「ひとりで」と言っているから。戦争はビジネスであると本当に割り切れる者達は、「ひとり」ではなく、軍産複合体などに関わる一員であり、彼ら一人一人は顔を持たず、容易に替えの利く歯車に等しいから)、その上でなお、「ひとりで」という措辞に、疑問を感じる。「みんなで」ではないだろうか。もっと言うなら、「わたしたちみんなで」ではないだろうか。
即ち、システムとは大衆に容認されることによって稼働し続けてきたのだ。ここで、どの国のどんな高度成長が戦争によって支えられてきたか、あげつらうつもりはない。何処の国だって、いざとなれば似たり寄ったりだ。戦争とビジネスの関係ではなく、ビジネスよりももっと深い処、本能との関係において、戦争とは何であるか。
パチンコ屋がビジネス足り得るのは、賭け事が本能化している人々がいるからだ。売春がビジネス足り得るのは、性欲が本能だからだ。戦争がビジネス足り得るのは、人々の意識下で塔のように積み上がった怨念を、与えられた「正義」の名において堂々と晴らせるから、つまり、戦争とは人間の怨念にとって本能である。
その圧倒的な現実をどう越えてゆくか。叶うなら、あの青空へ逃げるか。
重力がひるんだ隙に人々は一部地域を除いて空へ
飛び上がり自殺をきっとするだろう人に翼を与えたならば
飛び降りて死ねない鳥があの窓と決めて速度を上げてゆく午後
一首目、「一部地域」とは何かを考える。重力がひるんだとして、それでも空に逃げない地域とはどこだ。その地域の載っている地図は、人間の心の分布図ではないか。
肉体に作用する重力ではなく、心に作用する重力が問題だと観照するのであれば、重力がひるんでも恐らく逃げない。心に作用する重力が、人間の業(カルマン)、或いは二元対立の思考だと知っている心は。なぜなら、空に逃げても問題は何一つ解決しないからだ。
そして、多くはまるでパチンコ屋か酒場へ逃げるように空に逃げるだろう。或いは、二首目のように、「よだかの星」の如く、何処までも昇ってゆくだろう、真空の領域になり、肺が潰れ血が沸騰して弾けるまで。または、三首目のように、午後の陽に煌めくどこかの窓(多分、高層ビル街の、小さく安定した枠組みの一つ)に向かって、あらかじめ失敗すると判っているテロのように突っ込んでゆくだろう。
燃えさかる傘が空から降ってきてこれは復讐なのだと気付く
核の傘と考えるのは厭らしい。途端に平和の御題目(シュプレヒコール)と、それに伴う既得権益と、権益を覆い隠す欺瞞が聞こえてくる。ここは、あらゆる御題目が一切無効となる、滑稽な黙示録とでも捉えたい。実際に、傘以外の何物でもないもの(それが五百円のビニール傘であれば最高だ)が燃え盛りつつ無数に降って来る光景。そんな状況の真っ只中では、あらゆる批判が弾劾が糾弾が正義が、あらゆる御題目が、ムダだ。それは復讐だ。黙示録とは、実は正義を信じて裏切られてきた心の、総決算の復讐なのだから。
雨のなか傘をささないあの人の前世はきっと砂漠でしょうね
「あの人」と、他人事のようにいうのは、若者の恥じらいだろう。例え他人を見てそう思うにせよ、砂漠の如く無限に渇く心を思いやるのは、作者が同じ類だからだ。人間は心の渇きを、何を以て癒そうとするか。通常はやがて世界のシステムを受け入れる事により、その渇きを誤魔化すのであるが、誤魔化され得ないとすれば、或いは恋を以て癒すか。
電気つける派?つけない派?もしかしてあなた自身が発光する派?
雨ですね。上半身を送ります。時々抱いてやってください。
愛してる。手をつなぎたい。キスしたい。抱きたい。(ごめん、ひとつだけ嘘)
「愛してる。」が嘘なのだと考えて笑う者に、作者は何も言わないだろうが、実際は「抱きたい。」が嘘かも知れぬ。
こんな話がある。アメリカのスラム街で暴動を見物してきた男が、帰宅した途端、女房に罵られた。「あんた、また女を抱いてきたろ!」悲しいことに、男の性欲とは、往々にして暴力の恍惚と通底している。
愛すれば愛するほど、下半身の事情を交えたくないと考えるのは、上半身と下半身が別になりがちな男性特有の哀れさである。最後の「抱きたい。」が作者にとっては嘘か、と考える理由は、一首目で「発光する派?」と問うているからで、行為の際、相手が光を放つかもと思うのは、恋人を神秘として観ているからだ。また、雨の静けさに恋人を慰めるなら、上半身だけで良い、(下半身は邪魔だ)、と二首目で詠っているからだ。
青年はそれで良い、と思う。恋は精錬されてしかるべきだ。若いときに精錬していれば、中年になったとき、実際に、「抱きたい。」だけが嘘になるだろう。
ここでアガペーとエロースの違いについて語るほど厚顔無恥ではないが、ウィリアム・ローの言葉を思い出す。「愛にはそれ自体のほかに目的がなく、愛そのものを増やすことしか願わないので、愛の焔にとってすべてのものはさながら灯油のようだ。」愛とは自己の不在であると付け加えても良かろうか。
空を買うついでに海も買いました水平線は手に入らない
水平線とは実は「不在」そのものである。空の不在であり、海の不在である。そして、作者が一番欲しいものは、空でも海でもなく、水平線であろう。ランボーの詩を思う。「また見つかった、何が、永遠が、海と溶け合う太陽が」
それは風、もしくは言葉寸前の祈りに近い叫びであった
巧者な作者としては異色な、たどたどしいこの歌に、しかし一寸だけ涙する。一寸だけである。私は感情というシステムなど信じていないからだ。だが、ここで作者は世界のシステムをすっ飛ばして、何かの根っ子に向き合っていると思う。次の一首も思い出す。内容に通ずるものがあろう。
歌はただ此の世の外の五位の声端的にいま結語を言へば 岡井隆
ここで「詩客」の2013年9月6日号に載っている作者の歌を見る。
「神様にやめとけよって言われたろ、子どもってすぐマジになるから」
「子ども」を世界のシステムにあくまで固執する大人たちの暗喩と見るか、それとも、システムに疑問を感じ続ける作者の、客観的な自画像と見るかによって、歌の解釈は逆になるが、これは正反対の意味を同時に含む歌と考えれば、深みが出る。「子ども」を、固執する大人の幼稚さと見るならば、この神様は生(なま)の神様であり、システムに利用されて迷惑している神様である。「最終戦争(ハルマゲドン)を待望する人々」に困惑する神、と考えると一番わかりやすい。
「子ども」を作者のいささか謙遜した自画像と見るならば、神様は、「神と名付けられたシステム」に過ぎない。キリスト教徒が圧倒的多数を占め、旧新約聖書が圧倒的ベストセラーである現代において、恐らく、「唯一にして全能の」神という概念さえも、二千年間に膨張し絡み合った「教義」というシステムの一部分でしかない。アルトーのように「神の裁きと訣別するため」に、マジになれるだけマジになって、「神様というシステム」とのチキン・レースをするか。
あとがきに「ぼくを嫌いな奴はクズだよ」と書き足すイエス・キリスト
書き足すのは、果たしてどちらのイエス・キリストか。二千年前の生身のキリストか、それとも概念としてのキリストか。
救世主(キリスト)であるイエスには、本来、好きも嫌いもない、クズも悪党も善人も聖人もないはずだ。でなければ、人類という種の原罪を背負う意味がない。
全人類の、罪科とされるものを御破算にしたい、そう願うのがキリストの愛であるなら、実はキリストは一神教をはみ出している。
だが、この一首のイエス・キリストを、二千年前の人の子であるイエス、例えば神殿で暴れまくって、商人たちを追い出したイエスではなく、二千年の間にキリスト教世界のシステムを支える一部と化した、概念としてのキリストと考えるなら、納得は行く。キリストを嫌いな奴はクズだからどう処分しても構わないという論理は、キリスト教世界が現代にいたるまで散々やってきた十字軍の論理だ。
ひびとして君の過失を見せているすべての窓を割ってあげよう
割る事によって、罅もガラス自体も御破算に出来るのは確かだが、その結果が次の歌のような、増え過ぎたレミングが崖へ突進するような、人間という生物の本能が無意識に望んでいる、想定内の結末になるならば。
人類が0へと着地する冬の夕日を鳥は詩にするだろう
これを人類のカタストロフと読むなら、残念ながら、もはや詩にはならない。核兵器が生じて七十年経った今では、カタストロフは既に予定調和でしかないからだ。そして予定調和ほど、詩から遠いものもあるまい。詩が生ずるとすれば、カタストロフ回避の可能性においてであろう。それは或いは、世界のシステムの無化か。
なぜこの歌を取り上げたかといえば、この「0」がカタストロフではなく、創世記を表わすかもしれぬという読みに賭けるからだ。斃れるのではなく、「着地する」のだから。そうであるならば、重力という「惑星のシステム」に、飛ぶ本能によって抗する鳥は、人類の着地の状況を詩にするかもしれぬ。
ただ、「冬」が気になる。どうしても「核の冬」という、散々手垢の付いた状況を想起するからだ。だが、これを人間の心の冬と解釈するなら、ほとんどの者にとって創世記、生(なま)の神へと到達する過程は、冬を進むが如しであろうから、納得出来ない事はない。
十一世紀、ヘラート(今のアフガニスタン北西部)に生きたイスラム・スーフィー派の聖者アンサリは、次のような美しい詩篇を残している。
「主よ、一人の乞食として私は、千人の王でもお願いできぬ事を、あなたにお願いするのです。人はみな何かを欲して、あなたにそれをおねだりする。私は、あなた御自身を私に下さいと、お願いしに伺ったのです。」
作者の可能性を最も秘めている歌は、次に挙げる一首だと思う。だが、いつも次の歌のように詠えとは言わない。そんな風に力めば、却って閉塞するだろう。この論には敢えて取り上げなかった数多の「お洒落に上手いこと言ってやった歌」或いは「開き直って最低(サイテー)を志す歌」(実はこの二種は、作者にとって同じ動機から出ているだろう)を詠いまくって、その隙間に時折、ふっと何かが見えて来ているはずだ。そんなとき、作者が次のように詠えれば素晴らしい。
山火事は好きかいアダムよく見てろ燃え残る木でイブが寝ている
御破算となった後の創世記、いや、そもそも御破算すらなかったことになる創世記の山火事。アダムは君、即ち読者だ。林檎は? システムと共に燃えたか。だが、イブが暢気に寝ているなら、何も問題はない。
じっとしているのではない全方位から押されてて動けないのだ
全部屋の全室外機稼働してこのアパートは発進しない
一首目の「押されている」のは、何に押されているのか。膨大な情報に押されているのだと読む。人間は良心的であろうとすればするほど、客観性を求めるものだ。インターネットが発信する世界中の情報の(それは世界中の主張、と言い換えても良い)、何が正しくて何が不正なのか、何に準拠して動けば良いのか、考えれば考えるほど動けなくなる。それは作者の純情であって、私などはそこに感動する。
だが、実のところ、正しさなんてものは、ほぼ無い。誰もが自己正当化を正義であると誤認し、そしてその正義が無数に殖え続ける現状において、本当は二首目に「発進しない」と詠う諦めを捨て、住んでいる小さな部屋の室外機をジェットエンジンに見立てて、アパートの他の住人を巻き込んで虚空へと発進しても良いのだ、歌においては。
此処ではない何処かへ行きたいのは、若者の普遍的な欲求であろうが、世界のシステムが整う程、その欲求は空砲に終わる。今の時代の不幸とは、何もかもが忽ち見出され、喰い尽くされることにあろうか。
カードキー忘れて水を買いに出て僕は世界に閉じ込められる
ハンカチを落としましたよああこれは僕が鬼だということですか
一首目は、通常なら「世界へ締め出される」というべきところ、「閉じ込められる」を使ったあたり、作者にとっては、世界よりも一夜の宿に過ぎないホテルの一室の方が広い。仮住の束の間の個人の領域の方が、世界よりも開放感を持つのは、世界の整ったシステムが、作者にとって息の詰まるものであるからだ。
それは二首目の、自身を「鬼」だと認識していることに依ろう。この「鬼」には二重の意が籠められていて、一つには「ハンカチ落とし」の鬼として、誰か或いは何かを追わねばならない定めを持つ者、そして一つには、「鬼」本来の意、はみ出し者、追われる者、異種の意である。この二つの意は補完し合っていて、追わねばならぬ定めゆえに異種であり、追われ、はみ出すがゆえに追わねばならぬ。その「鬼」性は、ハンカチを拾ってしまう性質に依る。他者に関わろうとする善意が異種性に直結してしまう、それは現今の世界に対する皮肉でもある。
後ろから刺された僕のお腹からちょっと刃先が見えているなう
あ 殺してやろうと思い指先で押した ガラスの外側にいた
B型の不足を叫ぶ青年が血のいれものとして僕を見る
殺したい、殺されたい、この表明は実は破壊したい、破壊されたいの意だろう。一首目の、後ろから(=目に見えぬものから)刺された瞬間を「なう」nowと報告したい軽さ。二首目の、生殺の選択から、ガラスという透明にして硬質な物(=システムという境界)に阻まれているもどかしさ。三首目の、自己への即物的な視線。売血ではなく、献血の風景なのがミソで、受ける側与える側共に全くの善意の行為においても、もはや善を信じられない何かが混じる。
あまりにも絡み合い過ぎた世界のシステムは、もはや真っ平らになる事でしか、人間に生(なま)を実感させないのかもしれぬ。手っ取り早いのは戦争であり、核兵器であるが、そこで破壊されるのは、世界のシステムではなく、システムに疑問を抱く個人の心であり、肉体である。恐らく、システムは揺るぎもしない。戦争はシステムを維持するためのビジネスだからだ。
銃弾は届く言葉は届かない この距離感でお願いします
撲殺よりも刺殺の方が、刺殺よりも銃殺の方が、銃殺よりも爆殺の方が、より罪悪感を覚えずに済む。相手を殺すのに要する労力が少ないほど楽で、それは相手の心と交わらずに済むからだ。銃弾は届くが言葉は届かない距離感とは、殺し合う双方の「言葉=心」が届かない状況での殺し合い、という現代の気楽さだ。これが明治以前なら、兵には名乗りを上げて殺し合う理想がまだ残されていた。現代の兵士の不幸とは、銃の発明によって己が誇りが見えなくなる点にあるが、それは戦争屋にとっては大変効率が良い。
戦争はビジネスだよとつぶやいて彼はひとりで平和になった
平和なるものの仕組みは、よくよく見れば判るのだ。世界が根本では、金と暴力のみによって、そのシステムを稼働させている事は。
この歌における「彼」は、作者自身であると仮定して、そして敢えて「彼」と、己を突き放したのだと読んで、「平和になった」との皮肉を、健気にも己自身に向けているのだと深読みして、(なぜなら「ひとりで」と言っているから。戦争はビジネスであると本当に割り切れる者達は、「ひとり」ではなく、軍産複合体などに関わる一員であり、彼ら一人一人は顔を持たず、容易に替えの利く歯車に等しいから)、その上でなお、「ひとりで」という措辞に、疑問を感じる。「みんなで」ではないだろうか。もっと言うなら、「わたしたちみんなで」ではないだろうか。
即ち、システムとは大衆に容認されることによって稼働し続けてきたのだ。ここで、どの国のどんな高度成長が戦争によって支えられてきたか、あげつらうつもりはない。何処の国だって、いざとなれば似たり寄ったりだ。戦争とビジネスの関係ではなく、ビジネスよりももっと深い処、本能との関係において、戦争とは何であるか。
パチンコ屋がビジネス足り得るのは、賭け事が本能化している人々がいるからだ。売春がビジネス足り得るのは、性欲が本能だからだ。戦争がビジネス足り得るのは、人々の意識下で塔のように積み上がった怨念を、与えられた「正義」の名において堂々と晴らせるから、つまり、戦争とは人間の怨念にとって本能である。
その圧倒的な現実をどう越えてゆくか。叶うなら、あの青空へ逃げるか。
重力がひるんだ隙に人々は一部地域を除いて空へ
飛び上がり自殺をきっとするだろう人に翼を与えたならば
飛び降りて死ねない鳥があの窓と決めて速度を上げてゆく午後
一首目、「一部地域」とは何かを考える。重力がひるんだとして、それでも空に逃げない地域とはどこだ。その地域の載っている地図は、人間の心の分布図ではないか。
肉体に作用する重力ではなく、心に作用する重力が問題だと観照するのであれば、重力がひるんでも恐らく逃げない。心に作用する重力が、人間の業(カルマン)、或いは二元対立の思考だと知っている心は。なぜなら、空に逃げても問題は何一つ解決しないからだ。
そして、多くはまるでパチンコ屋か酒場へ逃げるように空に逃げるだろう。或いは、二首目のように、「よだかの星」の如く、何処までも昇ってゆくだろう、真空の領域になり、肺が潰れ血が沸騰して弾けるまで。または、三首目のように、午後の陽に煌めくどこかの窓(多分、高層ビル街の、小さく安定した枠組みの一つ)に向かって、あらかじめ失敗すると判っているテロのように突っ込んでゆくだろう。
燃えさかる傘が空から降ってきてこれは復讐なのだと気付く
核の傘と考えるのは厭らしい。途端に平和の御題目(シュプレヒコール)と、それに伴う既得権益と、権益を覆い隠す欺瞞が聞こえてくる。ここは、あらゆる御題目が一切無効となる、滑稽な黙示録とでも捉えたい。実際に、傘以外の何物でもないもの(それが五百円のビニール傘であれば最高だ)が燃え盛りつつ無数に降って来る光景。そんな状況の真っ只中では、あらゆる批判が弾劾が糾弾が正義が、あらゆる御題目が、ムダだ。それは復讐だ。黙示録とは、実は正義を信じて裏切られてきた心の、総決算の復讐なのだから。
雨のなか傘をささないあの人の前世はきっと砂漠でしょうね
「あの人」と、他人事のようにいうのは、若者の恥じらいだろう。例え他人を見てそう思うにせよ、砂漠の如く無限に渇く心を思いやるのは、作者が同じ類だからだ。人間は心の渇きを、何を以て癒そうとするか。通常はやがて世界のシステムを受け入れる事により、その渇きを誤魔化すのであるが、誤魔化され得ないとすれば、或いは恋を以て癒すか。
電気つける派?つけない派?もしかしてあなた自身が発光する派?
雨ですね。上半身を送ります。時々抱いてやってください。
愛してる。手をつなぎたい。キスしたい。抱きたい。(ごめん、ひとつだけ嘘)
「愛してる。」が嘘なのだと考えて笑う者に、作者は何も言わないだろうが、実際は「抱きたい。」が嘘かも知れぬ。
こんな話がある。アメリカのスラム街で暴動を見物してきた男が、帰宅した途端、女房に罵られた。「あんた、また女を抱いてきたろ!」悲しいことに、男の性欲とは、往々にして暴力の恍惚と通底している。
愛すれば愛するほど、下半身の事情を交えたくないと考えるのは、上半身と下半身が別になりがちな男性特有の哀れさである。最後の「抱きたい。」が作者にとっては嘘か、と考える理由は、一首目で「発光する派?」と問うているからで、行為の際、相手が光を放つかもと思うのは、恋人を神秘として観ているからだ。また、雨の静けさに恋人を慰めるなら、上半身だけで良い、(下半身は邪魔だ)、と二首目で詠っているからだ。
青年はそれで良い、と思う。恋は精錬されてしかるべきだ。若いときに精錬していれば、中年になったとき、実際に、「抱きたい。」だけが嘘になるだろう。
ここでアガペーとエロースの違いについて語るほど厚顔無恥ではないが、ウィリアム・ローの言葉を思い出す。「愛にはそれ自体のほかに目的がなく、愛そのものを増やすことしか願わないので、愛の焔にとってすべてのものはさながら灯油のようだ。」愛とは自己の不在であると付け加えても良かろうか。
空を買うついでに海も買いました水平線は手に入らない
水平線とは実は「不在」そのものである。空の不在であり、海の不在である。そして、作者が一番欲しいものは、空でも海でもなく、水平線であろう。ランボーの詩を思う。「また見つかった、何が、永遠が、海と溶け合う太陽が」
それは風、もしくは言葉寸前の祈りに近い叫びであった
巧者な作者としては異色な、たどたどしいこの歌に、しかし一寸だけ涙する。一寸だけである。私は感情というシステムなど信じていないからだ。だが、ここで作者は世界のシステムをすっ飛ばして、何かの根っ子に向き合っていると思う。次の一首も思い出す。内容に通ずるものがあろう。
歌はただ此の世の外の五位の声端的にいま結語を言へば 岡井隆
ここで「詩客」の2013年9月6日号に載っている作者の歌を見る。
「神様にやめとけよって言われたろ、子どもってすぐマジになるから」
「子ども」を世界のシステムにあくまで固執する大人たちの暗喩と見るか、それとも、システムに疑問を感じ続ける作者の、客観的な自画像と見るかによって、歌の解釈は逆になるが、これは正反対の意味を同時に含む歌と考えれば、深みが出る。「子ども」を、固執する大人の幼稚さと見るならば、この神様は生(なま)の神様であり、システムに利用されて迷惑している神様である。「最終戦争(ハルマゲドン)を待望する人々」に困惑する神、と考えると一番わかりやすい。
「子ども」を作者のいささか謙遜した自画像と見るならば、神様は、「神と名付けられたシステム」に過ぎない。キリスト教徒が圧倒的多数を占め、旧新約聖書が圧倒的ベストセラーである現代において、恐らく、「唯一にして全能の」神という概念さえも、二千年間に膨張し絡み合った「教義」というシステムの一部分でしかない。アルトーのように「神の裁きと訣別するため」に、マジになれるだけマジになって、「神様というシステム」とのチキン・レースをするか。
あとがきに「ぼくを嫌いな奴はクズだよ」と書き足すイエス・キリスト
書き足すのは、果たしてどちらのイエス・キリストか。二千年前の生身のキリストか、それとも概念としてのキリストか。
救世主(キリスト)であるイエスには、本来、好きも嫌いもない、クズも悪党も善人も聖人もないはずだ。でなければ、人類という種の原罪を背負う意味がない。
全人類の、罪科とされるものを御破算にしたい、そう願うのがキリストの愛であるなら、実はキリストは一神教をはみ出している。
だが、この一首のイエス・キリストを、二千年前の人の子であるイエス、例えば神殿で暴れまくって、商人たちを追い出したイエスではなく、二千年の間にキリスト教世界のシステムを支える一部と化した、概念としてのキリストと考えるなら、納得は行く。キリストを嫌いな奴はクズだからどう処分しても構わないという論理は、キリスト教世界が現代にいたるまで散々やってきた十字軍の論理だ。
ひびとして君の過失を見せているすべての窓を割ってあげよう
割る事によって、罅もガラス自体も御破算に出来るのは確かだが、その結果が次の歌のような、増え過ぎたレミングが崖へ突進するような、人間という生物の本能が無意識に望んでいる、想定内の結末になるならば。
人類が0へと着地する冬の夕日を鳥は詩にするだろう
これを人類のカタストロフと読むなら、残念ながら、もはや詩にはならない。核兵器が生じて七十年経った今では、カタストロフは既に予定調和でしかないからだ。そして予定調和ほど、詩から遠いものもあるまい。詩が生ずるとすれば、カタストロフ回避の可能性においてであろう。それは或いは、世界のシステムの無化か。
なぜこの歌を取り上げたかといえば、この「0」がカタストロフではなく、創世記を表わすかもしれぬという読みに賭けるからだ。斃れるのではなく、「着地する」のだから。そうであるならば、重力という「惑星のシステム」に、飛ぶ本能によって抗する鳥は、人類の着地の状況を詩にするかもしれぬ。
ただ、「冬」が気になる。どうしても「核の冬」という、散々手垢の付いた状況を想起するからだ。だが、これを人間の心の冬と解釈するなら、ほとんどの者にとって創世記、生(なま)の神へと到達する過程は、冬を進むが如しであろうから、納得出来ない事はない。
十一世紀、ヘラート(今のアフガニスタン北西部)に生きたイスラム・スーフィー派の聖者アンサリは、次のような美しい詩篇を残している。
「主よ、一人の乞食として私は、千人の王でもお願いできぬ事を、あなたにお願いするのです。人はみな何かを欲して、あなたにそれをおねだりする。私は、あなた御自身を私に下さいと、お願いしに伺ったのです。」
作者の可能性を最も秘めている歌は、次に挙げる一首だと思う。だが、いつも次の歌のように詠えとは言わない。そんな風に力めば、却って閉塞するだろう。この論には敢えて取り上げなかった数多の「お洒落に上手いこと言ってやった歌」或いは「開き直って最低(サイテー)を志す歌」(実はこの二種は、作者にとって同じ動機から出ているだろう)を詠いまくって、その隙間に時折、ふっと何かが見えて来ているはずだ。そんなとき、作者が次のように詠えれば素晴らしい。
山火事は好きかいアダムよく見てろ燃え残る木でイブが寝ている
御破算となった後の創世記、いや、そもそも御破算すらなかったことになる創世記の山火事。アダムは君、即ち読者だ。林檎は? システムと共に燃えたか。だが、イブが暢気に寝ているなら、何も問題はない。










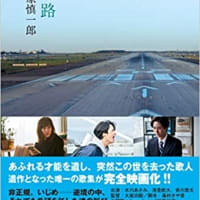
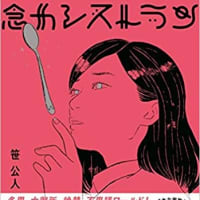
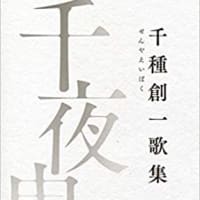
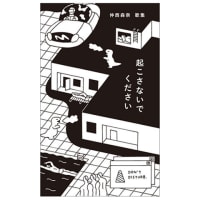
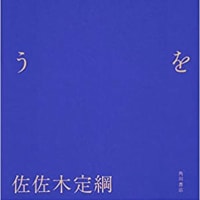
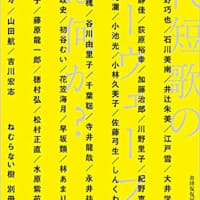

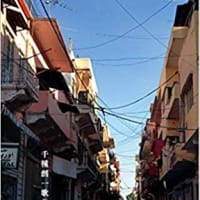

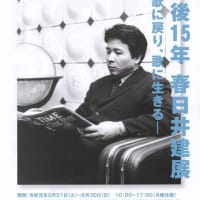
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます