この「短歌評」にもこれまで何度か書いたように、流行り病のような崩れ口語短歌にはもう十二分に飽きた。最初のうちは、「ああ、こんなところにまで短歌は来てしまっていたのね」という驚きが却って快感で正直面白く読めた。というのも俵万智以降、30年近くも短歌に関しては空白で、穂村弘『シンジゲート』『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』などをちらちらっと見たくらいで、僕の平成短歌経験は終わっていたのだから。
ところが、その後いくつか評してゆくうちに「ほんまにこれでええのか?」という気持ちになってきた。誰が悪い、ということではない。みんなが悪いんだろう。何の気骨もなくなってきている。短歌はそんなものじゃない、と言っている人達もきっと多いのだろうが、そんな人達の声は届かないだろう。
もちろんそれには理由もある。「流行り病的短歌」は嫌になったなら、極めてオーソドックスなのを読んでみれば?という心の声に従って、角川書店の極めてオーソドックスそうな歌集を買って読んでみたのだった。ところがそれは介護体験をひたすら綴ったものに過ぎず、僕は辟易した。「老・病・死」という、若いころ偏見のように持っていた短歌の嫌な
イメージがそのままそこには書かれていた。それは生きる上で重要な体験であり直面する問題だ。だがそんなことばかり書いて何になるというのだ。僕はその歌集を読むのを途中でやめてしまった。つまりは「面白いものを作ろう」「もっと軽いものを目指そう」という方向性自体は、流行り病の人たちも別に間違ってはいないということなのだろう。「老・病・死」にまみれるよりはるかにいいことだと僕も思う。しかし残念なことに、現在のある種の書き手たちは、まじめな主題を面白く読ませる技術を持ち合わせていない。技術以前に、文学という態度を喪失してしまっている。
この短歌評の僕の担当もカウントダウンが近づいてきて、あと今回を含めて2回となったので、ぜひ改めてそのことを書いておきたいと思った。短歌の世界は、詩の世界に随分遅れている。口語で書くこと自体がまだ問題になっている。冗談じゃない。詩はそこから始まったのだ。
本稿では比較的最近―と言っても1年以内くらいの意味での最近でしかないが―出された仲西森奈『起こさないでください』千種創一『千夜曳獏』笹公人『念力レストラン』萩原慎一郎『滑走路』の中から、合わせて20首ピックアップしてみた。ようやく僕にも、面白い詩や詩集を見つけるのと同じくらい、面白い歌や歌集を見つけるのは大変だということがわかってきた。この業界もタイヘンだね。どん詰まりでしょ、という印象がある。
仲西森奈『起こさないでください』
おしゃれな装本だと思って手に取った本書が、実は重い思想を内包しているのかもしれないと気づいたのは本書中ほどの「2018年9月2日(金)」という日付のついた日記のような文章を読んだ時であった。後半を抜粋する。
人を大きな括りでカテゴライズして語るのはあまり好きではない(わたしも、括られがちな性質を多く持つ人間なので)のですが、ある年代より上の世代とは、性別問わず、お互いの価値観を分かち合うことはできないのではないか、と、諦めかけているこのごろです。わたしは女性になりたいのではなく、女性だから外科的な処置を望むのであり、願望や癖や倒錯の果ての「そういう生き方」ではないということを、あと何百回、人に伝えたり、伝えられずに笑ってやり過ごしたらいいのだろう、と、途方もない気持ちになるこのごろです。男性を、女性を、とくべつうらやましく思うことは、日に何度もあります。何周も回って、もはや男になりたいと思うこともあります。身体が男性なのに男になれない自分の性質が、たまらなくめんどうくさく、気持ち悪く、鬱陶しくなる日が、今もたまにあります。
男友達も、女友達も、どちらでもない友達もわたしはだいすきです。
みんなどうかしあわせになってください。(後半)
僕もまた偶然ながら「人を大きな括りでカテゴライズして語るのはあまり好きではない」ので、「ある年代より上の世代とは、性別問わず、お互いの価値観を分かち合うことはできない」というように、露骨に世代をカテゴライズする人の言うことは信用できないと思った。少しがっかりした。それはともかくの引用部分は「ある深刻な問題意識を抱えながら生きている著者によって書かれた作品だという情報」としては読むことができる。ただ、そう言う問題意識が作品にどう反映しているのかどうかは僕には判断できなかった。そもそも「男だから」「女だから」と思って歌を読むことはない。それよりも、やはり面白いかどうかというひとことに尽きるのだろう。歌集全体として、下の引用中の「陰毛を」の歌のようにさらりと撫ぜるような印象が強くした。悪くない。でもさりげない日常から瞬間を切り取り色濃く染め上げるような歌に疼くように出会いたい。「しょうもない」の歌の「飼いそうになる」も、ああそういうことあるだろうなと共感はする。しかし現実を大きく超えてはいない。食べるつもりで家に買ってきたものを実際にペットとして過ごすということくらい、実際にあるだ。僕にもあった。歌である以上、圧倒的に現実を超えないとそれはだめだ。あるある、と自分の体験を思い出す一方で、短歌とはこんなんでいいのか?と思う。物足りない、物足りな過ぎると思う。ここにはなだらかな5首を選んだ。上手いけれど、世界が小さすぎるだろ。歌の後の数字はページ数。以下同様。
熱湯を注いで3分待ってから1時間半寝ちゃったら春 12
ひとがすきなのかなすきなひとなのかな すきだからひとにみえているのかな 13
陰毛をなでる仕草で米を研ぐ 守りたい人の数えきれない 65
しょうもない連中のことを潮抜きの浅蜊に話す 飼いそうになる 68
夕暮れのミスタードーナツ背を向けて行く行く行くは大人になる娘 121
2019年11月 さりげなく刊
千種創一『千夜曳獏』
昨年、この短歌評に千種の第1歌集『砂丘律』について書いた。僕にとって、或いはかなりの数の日本人にとっても余りなじみのない中近東の香りのするいい歌集だった。当然次を期待した。そして、期待は大きく外れてはいなかった。しかし、やはり同じ興奮を維持させるには至ってはいない。異国情緒だけで評価されたくはないという意識がもしかしたら本人にもあったのだろうか。この歌集の舞台はみんな日本である。違うのもあるのかもしれないが、そのように読めた。日本人が海外に出てふつうに働く日。そんなグローバル(死語)な枠組みの中で語られる海外の風物と日本人的感性の接触点。そういう一大特色を外した時、その代わりになる柱は何なのか。今のところ僕は、恋愛感情の重さとしかしそれに反するかのような滑らかな歌い口だと捉えている。「名前の美しい駅があるのは希望」「なんどでも輪廻しようね」などの表現はスマートだな、と思う。同時にもっと強い核が欲しい。そうも思った。この時代にそういう願い自体が無粋なのか。未だに核が「恋愛」でいいのか。いいようにも思う。いいようにも思うけれども、それならそれでもっと強く押し出されなければならないはずだ。「もっと強い核」とは何なのか。難しいと思うけれどもそれを探し出さない限り新しい時代は来ないのだと思う。舞台を中東に置き、斬新さを出すという点で成功した著者が、次に打ち出す核を見出せるかどうか。次の歌集が正念場なのだろう。以下の5首がいい。
雲雀丘花屋敷という駅
路線図の涯(はて)に名前の美しい駅があるのは希望と似てる 44
すげえとか少しの語彙で雪だとか梨とか磁器とか愛を語った 100
永久に会話体には追い付けないけれど口語は神々の亀 164
青林檎に残る噛み跡、先生の、色褪せていく、記憶のように 180
なんどでも輪廻しようね また春にオニオンリング、上手に食べる 216
2020年 5月 青磁社刊
笹公人『念力レストラン』
この本こそ、上で僕が書いた「強い核」を持っていそうな感じがした。少なくとも装丁に関しては。何かある。確かにそんな感じはした。しかし、実際にはまやかしであった。内容は完全なエンターテイメントで文学ではない。ざれ歌?そう、ざれ歌。もちろんそれが悪いわけではない。面白い。めっちゃ面白いと思う。だが短歌ではない。何なんだろう、この不思議なジャンルは。と思う。というのは、あらかじめ存在する笑いのツボに依拠しすぎていてその意味で創造性が皆無だからだ。ちゃくちゃやっているかのように見せかけて、あざとい計算だけに支えられている。いやらしいと思う。面白いが、好きになれない。短歌ではない。これって何というジャンル5首。
もし君がキエーーと奇声あげながらヤシの実割ったとしても 好きだよ。 14
草食男子の精子のごとくわずかなり百円ショップの修正液は 41
またしても八代亜紀の言霊が大雨降らす県民ホール 55
歴代のセンターの遺影に囲まれてきらめくAKB100周年ライブ 72
童貞力極まりて兄は透視するポスター美女の白き裸身を 81
2020年7月 春陽堂書店刊
萩原慎一郎『滑走路』
この『滑走路』のことは書店でも手にとって、書きたいなと思っていたが、僕がこの短歌評を担当したのは2019年からだった。だからやや時期を逸していたような印象があった。折よくこの9月に文庫化されたので読んでみたのだった。何者もかなわない純真が刻まれている。読み終えてそう思った。僕は小説があまり面白くなかったので又吉直樹のことを軽く思っていたが、巻末にある解説は結構よかった。単行本の解説で三枝昂之が非正規/正規と労働環境の事に拘泥して短歌を読み誤っていることに比してはるかにましであった。
短歌を書く、詩を書くというのは弱さを内包していることの証でもある。その弱さとどうかかわってゆくのか。歌人にも詩人にも大切な問題だと思っている。「何者もかなわない純真が刻まれている。」と上に書いたが、この純真をもとに世界を切り開いて行くことをしなければ世界が停滞する。その意味で僕はこの歌集の「弱さ」に共感はしつつも、同意するつもりはさらさらない。狂人にも近い強靭さで以て世界に抵抗してゆくものを詩人と呼ぶ。歌人もまた同じはずだからである。
まだ早い、まだ早いんだ 焦りたる心は言うことを聞かない犬だ 27
十代の青年である。どちらへと行くか迷える紋白蝶は 91
完熟のトマトの中に水源のありて すなわち青春時代 91
紙片には詩の断片の書かれいて「どうだ?」と僕に問いてくる友 99
達成はまだまだ先だ、これからだ おれは口語の馬となるのだ 107
2017年12月角川書店刊 2020年9月文庫化










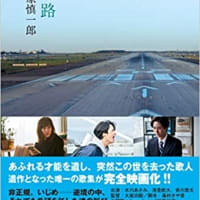
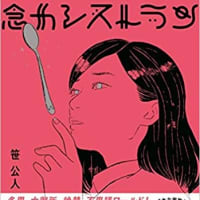
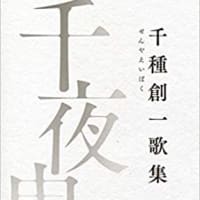
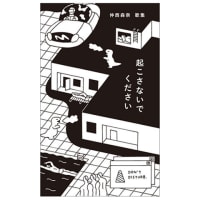
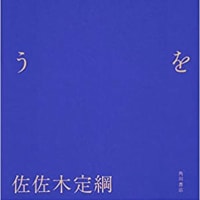
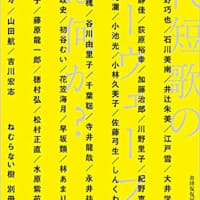

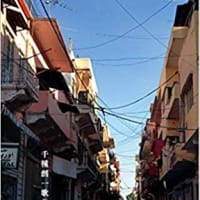

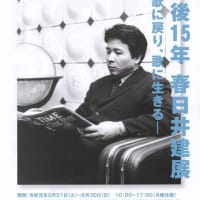
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます