第一詩集『眠り椅子』(1953年)の初編「しごと」は、「きんいろのぺんでゑがく/この いっぽんの道」で、始まる。それから、どれほど多くの、豊かな作品が生み出されたか…、深く尊敬の念を抱かずにはおれない。すでに、多くの優れた詩人によって語られている新川和江さんの詩を、わたしが述べることは、分不相応と思うのだが… その金色のぺんで描かれた秀逸な作品群を眺めると、道には、野の花が広がり、街があり、いのちの水があり、そして、海へ、悠々と入ってゆく大河のようで、まばゆく、魅了される。だが、海は、涙の海であったし、増してゆく寂寥の潮であった。 海を詠った詩は数多くあるが、その中で、異彩を放っているのが、「いちまいの海」。
うつくしい海をいちまい/買った記憶がある/青空天井の市場で/絨毯商人のようにひろげては巻き/ひろげては巻きして/海を売っていた男があったのだ/午睡の夢にみた風景のようで/….(新選現代詩文庫122『新選新川和江詩集』1983年思潮社刊)
この海は、詩人の内に抱える海ではない。憧憬していた詩の光景、わたしは、新川さんが女学生の頃、疎開されていた西條八十氏から影響を受けたランボー、ヴェルレーヌといった西欧の象徴詩、と秘かに想ってしまう。緩やかな記憶の波に揺られながらも、ふいに現れた情景に、瞬きもせず、じっと見入ってしまうのは、海を絨毯に見立て、うつくしい海をいちまい…と数える、発想の大胆さに、心がひっくり返され、つかまれたからに他ならない。そして、露店でもなく、青空市場でもない、青空天井の市場という語法。その空間の広がりと風景描写は、絶妙である。「ひろげては巻き/ひろげては巻き…」このリフレインも、寄せては返す波を感じさせるものだが、心地よく揺られていると、いきなり、床に落とされたかのような衝撃で、突き放される。
その海に/溺れもせずにわたしが釣り合ってゆけたのは/進水したての船舶のように/けざやかに引かれた吃水線をわたしが持っていたからだ
他者性への明白な認識は、自己を深く見つめずには成り立たず、その深い洞察力と峻厳な眼差しが、「けざやかに引かれた吃水線…」 に表れている。吃水線、という、きりりとした言葉の響きと相まって、なんと、魅力的な詩句であろうか。
「しかしそれも一時期のこと/引っ越しの際にまたぐるぐる巻きにして/新居の裏手の物置へ/がらくたと一緒にしまいこみ/忘れたままでいたのだが…」と、又しても、日常性へ突き放される。忘却の彼方へ置き去りにするは、日々生きている者の性である。ところが、だ。非日常性であったはずの海が、まるで、実在の翼を得たかのように、立ち現れてくる。「一羽の鷗が物置の戸の隙間から/けさ不意に羽搏き 飛び立ち わたしをひどく狼狽させた…」、思い出すという行為以上の在り様は、うつくしい海が色褪せもせず、乾涸びもせず、その形象を保っていたからで、詩人の意識は、自己の、吃水線がはげおちているという哀しい現実の方にあり、日常性と非日常性が反転して、裏庭を水びたしにしはじめていることに狼狽する。そして、この詩は、「あの海を どうする」、という、問いかけで終わる。海を恣意性から開放することで、うつくしい海は、永遠の輝きに満たされて、心に残る。
この詩の次に、詩「海をうしろへ…」がある。自分の立ち位置を確認するかのような詩句の後に、ひとつの決断が下される。「わたしを呼ぶ者の声に答えるのだ/身じまいをして すずやかに「はい」と」
新川和江さんの詩が好きな理由は、また、その音楽性にある。イメージを美術性と捉えるなら、それが、程よく釣り合い、海浜ホテルのように響きの美しい詩句を織り交ぜながら、リズムや変調といったことにまで、細やかに詩を創られているから。創るというより、生まれてくる歌。
真摯なことばへの向き合い方、対象物への深い洞察力。言い尽くせないことがたくさんあるが、次の「お米を量る時は…」という詩は、日々の暮らしのなかで息づいている。今では、升を使って量る、という行為自体が、既に日常性から失われたかも知れないが、毎日、お米を量るときに升を使うわたしは、はたと立ち止まる。そら豆や大豆を量る時のスキマ分への配慮を怠らない村人の手は、実直で、優しい。言葉が実体に見合っているか、と常に自分に問いかける詩人の自省の厳しさも反響する。お米のように、ことばもまた、生きてゆく糧なのだ。当たり前のようで、難しい。
米を量る時はすりきり/そらまめや大豆を量る時は/スキマの分もいれて 山もりいっぱい…/村びとたちの手つきを真似たく思ふのですが/なかなか うまくゆきません/いつでもことばが/足りないか 夥しくこぼれてしまふかして (『ひきわり麦抄』1996年花神社刊)










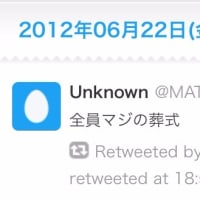
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます