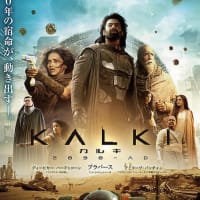(1)
フランス革命のあと二人の無名の男が「帝王」となった。一人は皇帝ナポレオン・ボナパルト。そして、もう一人は「料理の帝王」と呼ばれたアントナン・カレームだ。この時代、王侯貴族たちを料理で、饗(モテナ)し説得する、いわゆる「料理外交」が頻繁に行われていた。この物語は、料理の力で、つまり平和的な力で、血を流すことなくフランスを守った人々(とりわけタレーランとアントナン・カレーム)の物語だ。平和的な料理の力つまり「スプーンの盾」によって戦争を阻止する。
(2)
アントナン・カレームMarie-Antoine(Antonin)Carême(1784-1833):貧困のどん底から「シェフの帝王かつ帝王のシェフ」(the king of chefs and the chef of kings)と呼ばれるに至った人物。貧しい家に生まれ、10歳でパリの路上に捨てられるが、住み込みで料理人になり頭角を表す。破天荒な天才で、自由な発想の持ち主。ある日、彼の噂を聞きつけたナポレオンの右腕である名外交官タレーランから声がかかり、国家の威信を背負った「料理外交」の場に駆り出される。ナポレオンの敗北後も、1814年に始まったウィーン会議の間、タレーランはたびたび夕食会を主催し「料理外交」を行った。そこで出されたカレームの料理は出席者の評判をさらい、「料理外交」は成功し、ウィーン会議でタレーランの「正統主義」の理念が受け入れられるにいたった。かくてフランスは領土を失わず、つまり領土分割されず独立を維持した。ウィーン会議が終わるとカレームはイギリスの摂政皇太子(後のジョージ4世)の料理長としてロンドンに赴く。その後カレームは、サンクトペテルブルクでロシア皇帝アレクサンドル1世、ウィーンでオーストリア帝国皇帝フランツ1世などに仕えた後、パリに戻って銀行家ジェームス・ロスチャイルド邸の料理長に就任した。カレームは料理文化の普及にも努力し、多数の著作がある。彼は1833年、パリにおいて48歳で没した。
(3)
ナポレオン・ボナパルトNapoléon Bonaparte(1769-1821):コルシカ島の田舎貴族から皇帝にまで上り詰めた男。だが彼はついに戦に敗れ、皇帝の座を追われエルバ島で死を待つだけの幽閉生活を送る。ナポレオンは根っからの軍人であり、文化芸術に関心を示さず心は常に戦場にあった。最初は料理などに興味がないナポレオンも次第にカレームの料理の魔法に魅せられる。
(4)
マリー・グージュ(架空の人物):盲目ながら、カレームの右腕である少女。カレームがマリーに言った。「ドン・ピエール・ペリニョンは盲目だったがゆえに、最高のシャンパンを生み出した。お前の目は、一般人の目では見ることができない料理の王国を見ることができる」。ナポレオン、カレームという二人の全く異なる「帝王」の側(カタワラ)にいて、彼女にしか見えない目線で物語を語る。
(5)
モーリス・ド・タレーランCharles-Maurice de Talleyrand-Périgord(1754-1838):ナポレオンの腹心、天才外交官である。彼が得意としたのが「料理外交」だった。「365日同じ食材で違うメニューを出せ」という要求に難なく答えたカレームの才能をタレーランは確信し、カレームの名をヨーロッパ中に轟かせた。タレーランは、あらゆる王侯貴族が一度は口にしたいと思い描く「料理の帝王」カレームを生み出し、かつそれを利用し外交を有利に進めた。1814年にナポレオンが失脚すると、タレーランはブルボン王家の側につく。そしてタレーランの働きによってフランスに敵対した連合国はブルボンの復権を認める。ルイ18世(在位1814-1824)の即位後はタレーランは、フランスの外務大臣となり、ウィーン会議に出席した。この会議では、タレーランは「正統主義」を唱えて大国(英墺露普)の利害対立を利用し、巧みな外交手腕で、連合国によるフランスの領土分割を阻止し国益を守った。
(6)
ウィーン会議(1814-1915):フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序再建と領土分割を目的とし、オスマン帝国を除く全ヨーロッパ各国代表が集まり開催された。「正統主義」と「勢力均衡」がウィーン会議の基本原則だった。「正統主義」とは、フランス革命・ナポレオン戦争以前、すなわち1792年より以前の状態に戻すことをめざす理念だ。それは「正統な」統治者を復位させ、旧体制を復活させた。「正統主義」の理念は、フランス代表タレーランによって主張された。かくてタレーランはフランスの領土分割を阻止し、フランスの独立を確保した。なおウィーン会議ではフランス革命以前の体制の完全な復活でなく、大国による「勢力均衡」を踏まえた形での「正統主義」の実現が目指された。例えば、革命によって神聖ローマ帝国が解体しナポレオンが整理・統合した「ドイツ諸国」(ドイツ圏の35の諸侯国と4つの自治都市)は、オーストリアとプロイセンの二大国を中心とした「ドイツ連邦」として再出発した。ウィーン会議によって、大国同士が相互に均衡を維持し合う国際秩序「ウィーン体制」が構築され、ヨーロッパにはおよそ30年間の平和がもたらされた。
フランス革命のあと二人の無名の男が「帝王」となった。一人は皇帝ナポレオン・ボナパルト。そして、もう一人は「料理の帝王」と呼ばれたアントナン・カレームだ。この時代、王侯貴族たちを料理で、饗(モテナ)し説得する、いわゆる「料理外交」が頻繁に行われていた。この物語は、料理の力で、つまり平和的な力で、血を流すことなくフランスを守った人々(とりわけタレーランとアントナン・カレーム)の物語だ。平和的な料理の力つまり「スプーンの盾」によって戦争を阻止する。
(2)
アントナン・カレームMarie-Antoine(Antonin)Carême(1784-1833):貧困のどん底から「シェフの帝王かつ帝王のシェフ」(the king of chefs and the chef of kings)と呼ばれるに至った人物。貧しい家に生まれ、10歳でパリの路上に捨てられるが、住み込みで料理人になり頭角を表す。破天荒な天才で、自由な発想の持ち主。ある日、彼の噂を聞きつけたナポレオンの右腕である名外交官タレーランから声がかかり、国家の威信を背負った「料理外交」の場に駆り出される。ナポレオンの敗北後も、1814年に始まったウィーン会議の間、タレーランはたびたび夕食会を主催し「料理外交」を行った。そこで出されたカレームの料理は出席者の評判をさらい、「料理外交」は成功し、ウィーン会議でタレーランの「正統主義」の理念が受け入れられるにいたった。かくてフランスは領土を失わず、つまり領土分割されず独立を維持した。ウィーン会議が終わるとカレームはイギリスの摂政皇太子(後のジョージ4世)の料理長としてロンドンに赴く。その後カレームは、サンクトペテルブルクでロシア皇帝アレクサンドル1世、ウィーンでオーストリア帝国皇帝フランツ1世などに仕えた後、パリに戻って銀行家ジェームス・ロスチャイルド邸の料理長に就任した。カレームは料理文化の普及にも努力し、多数の著作がある。彼は1833年、パリにおいて48歳で没した。
(3)
ナポレオン・ボナパルトNapoléon Bonaparte(1769-1821):コルシカ島の田舎貴族から皇帝にまで上り詰めた男。だが彼はついに戦に敗れ、皇帝の座を追われエルバ島で死を待つだけの幽閉生活を送る。ナポレオンは根っからの軍人であり、文化芸術に関心を示さず心は常に戦場にあった。最初は料理などに興味がないナポレオンも次第にカレームの料理の魔法に魅せられる。
(4)
マリー・グージュ(架空の人物):盲目ながら、カレームの右腕である少女。カレームがマリーに言った。「ドン・ピエール・ペリニョンは盲目だったがゆえに、最高のシャンパンを生み出した。お前の目は、一般人の目では見ることができない料理の王国を見ることができる」。ナポレオン、カレームという二人の全く異なる「帝王」の側(カタワラ)にいて、彼女にしか見えない目線で物語を語る。
(5)
モーリス・ド・タレーランCharles-Maurice de Talleyrand-Périgord(1754-1838):ナポレオンの腹心、天才外交官である。彼が得意としたのが「料理外交」だった。「365日同じ食材で違うメニューを出せ」という要求に難なく答えたカレームの才能をタレーランは確信し、カレームの名をヨーロッパ中に轟かせた。タレーランは、あらゆる王侯貴族が一度は口にしたいと思い描く「料理の帝王」カレームを生み出し、かつそれを利用し外交を有利に進めた。1814年にナポレオンが失脚すると、タレーランはブルボン王家の側につく。そしてタレーランの働きによってフランスに敵対した連合国はブルボンの復権を認める。ルイ18世(在位1814-1824)の即位後はタレーランは、フランスの外務大臣となり、ウィーン会議に出席した。この会議では、タレーランは「正統主義」を唱えて大国(英墺露普)の利害対立を利用し、巧みな外交手腕で、連合国によるフランスの領土分割を阻止し国益を守った。
(6)
ウィーン会議(1814-1915):フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序再建と領土分割を目的とし、オスマン帝国を除く全ヨーロッパ各国代表が集まり開催された。「正統主義」と「勢力均衡」がウィーン会議の基本原則だった。「正統主義」とは、フランス革命・ナポレオン戦争以前、すなわち1792年より以前の状態に戻すことをめざす理念だ。それは「正統な」統治者を復位させ、旧体制を復活させた。「正統主義」の理念は、フランス代表タレーランによって主張された。かくてタレーランはフランスの領土分割を阻止し、フランスの独立を確保した。なおウィーン会議ではフランス革命以前の体制の完全な復活でなく、大国による「勢力均衡」を踏まえた形での「正統主義」の実現が目指された。例えば、革命によって神聖ローマ帝国が解体しナポレオンが整理・統合した「ドイツ諸国」(ドイツ圏の35の諸侯国と4つの自治都市)は、オーストリアとプロイセンの二大国を中心とした「ドイツ連邦」として再出発した。ウィーン会議によって、大国同士が相互に均衡を維持し合う国際秩序「ウィーン体制」が構築され、ヨーロッパにはおよそ30年間の平和がもたらされた。