この世の中って、ほんとうに情報が氾濫している。
あまりの多さに処理能力がついていかなかったり、ノイズが入ったり、選別する能力が麻痺したりしている。
ヒトって思いの外、感覚を鈍らせる行為に走ることが多いように、ワタシの経験上感じる。
刺激を麻痺させるために、新たなる刺激で補う。という行為は、身体に相当のダメージを与えるが、意識下では快楽と変換されている場合が多いので、更なる刺激を求めたりするのかも知れない。
感覚として感知した刺激は、なるべく生の刺激のままで受け止めたい。
その感覚に対して抱く感情は、己の思考に支配されて湾曲している。
そこからアウトプットされたものは、すでに生の刺激とはまるで別のモノとなっている場合が多い。
ヒトは経験の裏付けにより、刺激に対して反射する。
反射のパターンは、ヒトの思考パターンに影響を受ける。
意識していても、していなくても、アウトプットしたものは、すでに思考の範疇で踊ってしまっており、そこのみに着目して、自分が、他人が、修正なり変化を促していくことは、根本的なモンダイからは遠ざかる行為である、と思う。
自分の中に生まれる感情は、それはそれで、自分自身が抱いているモノそのものでもあるが、それを負の循環に持っていっている場合は、自分自身のパターンを省みる余地が大いにあるだろう。
その感情は、刺激に対してあらゆるスパイスを混ぜ合わせて配合したモノであるのだから、自分自身で調合を変えることは可能である。
もともと、情報が氾濫しやすい体質のものにとっては、入力の際の弁別法を、自分自身で会得するところから始まるような気がするが、こういうのはなかなかムズカシイ。
鋭敏な感覚と、鈍磨な感覚。
これを律する方法というのは、やはり自分自身で会得するしかないのだろう。
「見えている」から「見る」に。
「聞こえている」から「聞く」に。
「臭っている」から「嗅ぐ」に。
「味がする」から「味わう」に。
「触れている」から「触れる」に。
意識の集中と拡散のリズムを、自分自身で作っていくことが、感覚を体感することに繋がるような気がしている。
そこに、思考や感情をブレンドするからややこしくなる。
まずは素の感覚に馴染むこと。
ヒトは頭で生きているのではなく、全身で生きているということ。













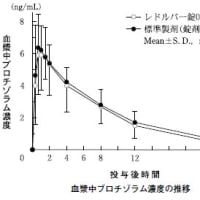

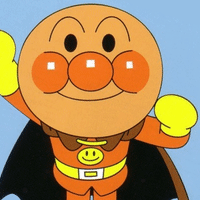
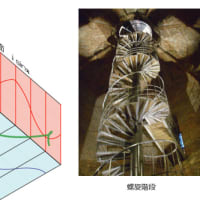

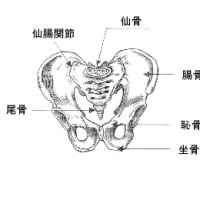
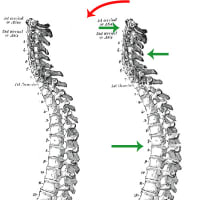
はい、気をつけます!と、教えて頂いた感じがします(^-^)
>自分自身で調合を変えることは可能である。
これは、本当にわかりやすい『たとえ』ですね。子供達に説明するときに使用させていただいてもいいですか?
今回の文章も、拝読しながら、反省したり、うんうんと頷いたり、できました。
ありがとう、です。
こんばんは。
何かこのブログも自戒をテーマにしているのが、自分自身でも堅苦しいな、と思うことがあります。
言葉ってのはエネルギーを持ってるな、とつくづく感じます。
お返事は、いいですよ。