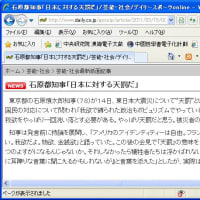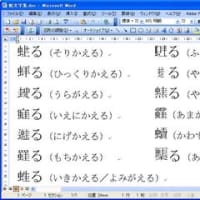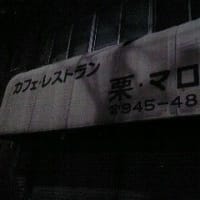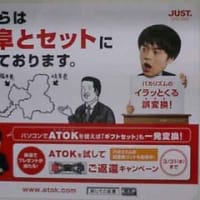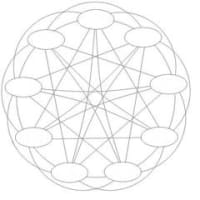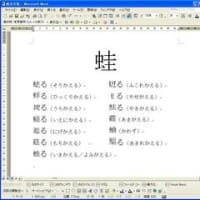弁当屋の場合、9~13時に停電されると商売にならない。
居酒屋の場合、18~22時に停電されると商売にならない。
オフィスは多少融通は利くが、それでも停電時間はできる仕事が激減する。
故に、電気を停められそうな日は休業した方が良い、というよりも、せざるを得ない。
しかし、東京電力の定める計画停電予定は、5日サイクルである。そのため、「毎週○曜日は計画停電のため休業」とすることはできない。「3月のお休みは16、21、26、31日。4月のお休みは5、10、15、20、25、30日を予定しております」という形で告知するしかない。
こんなやり方では予定が分かりにくいし、商売に差し障りがある。この節電戦争を長期間戦い抜くことが難しい。
一つの案としては、東京電力が5グループ分類をやめ、7グループにする。
これにより、一週間という7日サイクルを採る現行の社会制度と合致させ、各店舗は、最も商売に差し障る時間帯に停電が予定される日に合わせて、「定休日:○曜日」といった具合に告知することができる。
もう一つの案としては、曜日という7日サイクル制度自体を見直す。すなわち、関東地方の社会全体を、5日で一週間という制度にするのだ。
「定休日:第2停電日」「第1,2停電日は外回り、第3,4停電日はデスクワーク、第5停電日は休み」「アルバイト募集。第5停電日に働ける方を歓迎」といった具合である。
よく考えてみれば、キリスト教国家でもない日本が、週7日なんていう勘定しにくい数字のサイクルにすることはなかったのである。一週間が5日でも良いではないか。
毎週日曜日に教会に通う敬虔なキリスト教徒は閉口するかもしれないが、今までが優遇され過ぎていたのである。例えばイスラム教徒が金曜日に礼拝をしなければならない。それに較べてみれば、キリスト教徒が、いかに優遇されて来たかが分かるだろう。
停電日に合わせて休業日を設ける制度には、利点もある。
それぞれの会社・店舗・学校によって停電日が異なり、従って休日が異なる。
これにより、休暇を取るタイミングが社会全体で分散し、役所・銀行での手続きがしやすくなり、レジャー施設が混雑しなくなる。
一方で、欠点もある。
休日が分散するために、シンポジウムやイベントに人を集めることは難しくなる。
しかし、その代わり、会場費は、今のように休みが集中する土日に借りるよりは安くなるだろう。
如何であろうか。
この際、「一週間は七日」といった呪縛から逃れてみようではないか。
居酒屋の場合、18~22時に停電されると商売にならない。
オフィスは多少融通は利くが、それでも停電時間はできる仕事が激減する。
故に、電気を停められそうな日は休業した方が良い、というよりも、せざるを得ない。
しかし、東京電力の定める計画停電予定は、5日サイクルである。そのため、「毎週○曜日は計画停電のため休業」とすることはできない。「3月のお休みは16、21、26、31日。4月のお休みは5、10、15、20、25、30日を予定しております」という形で告知するしかない。
こんなやり方では予定が分かりにくいし、商売に差し障りがある。この節電戦争を長期間戦い抜くことが難しい。
一つの案としては、東京電力が5グループ分類をやめ、7グループにする。
これにより、一週間という7日サイクルを採る現行の社会制度と合致させ、各店舗は、最も商売に差し障る時間帯に停電が予定される日に合わせて、「定休日:○曜日」といった具合に告知することができる。
もう一つの案としては、曜日という7日サイクル制度自体を見直す。すなわち、関東地方の社会全体を、5日で一週間という制度にするのだ。
「定休日:第2停電日」「第1,2停電日は外回り、第3,4停電日はデスクワーク、第5停電日は休み」「アルバイト募集。第5停電日に働ける方を歓迎」といった具合である。
よく考えてみれば、キリスト教国家でもない日本が、週7日なんていう勘定しにくい数字のサイクルにすることはなかったのである。一週間が5日でも良いではないか。
毎週日曜日に教会に通う敬虔なキリスト教徒は閉口するかもしれないが、今までが優遇され過ぎていたのである。例えばイスラム教徒が金曜日に礼拝をしなければならない。それに較べてみれば、キリスト教徒が、いかに優遇されて来たかが分かるだろう。
停電日に合わせて休業日を設ける制度には、利点もある。
それぞれの会社・店舗・学校によって停電日が異なり、従って休日が異なる。
これにより、休暇を取るタイミングが社会全体で分散し、役所・銀行での手続きがしやすくなり、レジャー施設が混雑しなくなる。
一方で、欠点もある。
休日が分散するために、シンポジウムやイベントに人を集めることは難しくなる。
しかし、その代わり、会場費は、今のように休みが集中する土日に借りるよりは安くなるだろう。
如何であろうか。
この際、「一週間は七日」といった呪縛から逃れてみようではないか。