 いま根津美術館で《誰が袖図 描かれたきもの》というのをやっている。「誰が袖(たがそで)」が何なのかというと、英語では「Whose sleeves?」。衣桁や屏風に、誰かの脱いだ着物がかかっている無人図のことである。安土桃山時代、江戸時代初期に流行した。「先ほどまで、かの人はいた」「だけど、もういないよ」という淡い時間推移の戯れを描くという点で、日本的でありつつも超現代的なジャンルと言える。脱ぎ捨てられた着物、置かれたままの文房具、読みかけの書物、そして、まだ匂い立つ香炉。「その着物に梅の花弁が触れたらしい。その残り香が、その人のおもかげを際立たせる」といった繊細な感覚は和歌でも詠われてきたが、無人ショットを1枚の画で見せられるインパクトは、小津安二郎の映画を思い出せばいい。
いま根津美術館で《誰が袖図 描かれたきもの》というのをやっている。「誰が袖(たがそで)」が何なのかというと、英語では「Whose sleeves?」。衣桁や屏風に、誰かの脱いだ着物がかかっている無人図のことである。安土桃山時代、江戸時代初期に流行した。「先ほどまで、かの人はいた」「だけど、もういないよ」という淡い時間推移の戯れを描くという点で、日本的でありつつも超現代的なジャンルと言える。脱ぎ捨てられた着物、置かれたままの文房具、読みかけの書物、そして、まだ匂い立つ香炉。「その着物に梅の花弁が触れたらしい。その残り香が、その人のおもかげを際立たせる」といった繊細な感覚は和歌でも詠われてきたが、無人ショットを1枚の画で見せられるインパクトは、小津安二郎の映画を思い出せばいい。画面上こそ無人ショットかもしれないが、フレームを少しだけずらしてみると、男女のあられもないマグワイが写りこんでしまうかもしれない。あるいは、お付きの者に手伝わせて湯浴みの最中なのかもしれない。しかし、画面に少し前まで人がいた気配が漂っているのに、現にいまはいなくなっている、というのが肝心である。
ヴェンダースが20年前に出した写真集『かつて…』(PARCO出版)は、完全に「誰が袖」である(過去のヴェンダース記事を請参照)。画面に「映る、写る」とはつまり、「移る」と同じことなのだから。画面内の存在は写っていることによって、移ろいゆき、いつしか変化し、溶け出していってしまう。着物、香炉、文房具といった証拠物品だけを丹念に描きこむ「誰が袖図」は、単に不在を示すものではない。ゼロではない。ワンプラスワンプラスワンプラスワンプラス…=ゼロとしてのゼロなのだ。
このことは今春、久世光彦の遺著『死のある風景』について書いた記事のなかで、久世が「演劇の空舞台(カラブタイ)が好きだ」と述べていることについて触れた時ともつながっている。
今展では同館所蔵の3点の「誰が袖」を中心に、これらの着物の持ち主である女たちの実態、正体を追い求めるかのように宮川長春、歌川広重の美人図を動員する。伊万里焼の色絵婦人人形まで持ち出している。しかしそれが空しい試みであることは、主催者も鑑賞者も分かっている。そして…、この点が肝心なのだが、これらを見る私たち鑑賞者自身もまた、「誰が袖」的不在に秒刻みで近づいていることを意識せざるを得ないのだ。
《誰が袖図 描かれたきもの》は根津美術館(東京・南青山)で12/23(火・祝)まで
http://www.nezu-muse.or.jp

















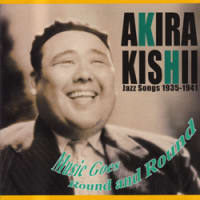


路上観察といえば、今週火曜に千葉市美術館の《赤瀬川原平の芸術原論》を見てきました。こちらの記事も近日中にアップできればと考えています。