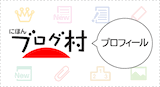さて、問題です。 100円のパンが、2回続けて、10%の値上げをしました。いくらになったでしょうか? 正解は121円です。 1回目の値上げで110円になり、2回目の値上げでは、110×1.1=121円になるからです。 それでは、5回続けて値上げをしたら?100×1.1×1.1×1.1×1.1×1.1=161.051円です。 もう勘弁して下さい、10%5回やから、150円でええやないか、ということですが、勘弁してあげますよというのが、近似値計算なのです。 とりあえず、この計算から始まります。
ここで、α、βが、2つとも、とってもとっても小さい数だったら、この計算の最後に出てくるαβは、とってもとってもとってもとっても小さい数になります。(たとえば、0.01×0.02=0.0002) どれくらい小さいかというと、無視しても構わないくらい小さくなりますね。本当に無視すると、(1+α)(1+β)=1+α+βになります。例えば、こんなことに。
αやβが、マイナスになっても構いません。例えば、
1近辺の数どうしを掛けるときに使えますね。 といっても、あくまでも近似値であって、本当の値ではありませんけど。 1の前後10%、つまり、0.9から1.1の間の数ばかりを掛けるとき、真の値にかなり近くなります。 特に、1より小さいものと1より大きいものが均等に混じっていれば、本当に真の値に近くなります。 たとえ0.9から1.1の範囲を超えていても、まあ、目安にするなら十分使えます。そこで、前回の肢4です。
肢4は、「2013年の各国の物価を100とした2018年の指数を比較すると、最も小さいのはC国である。」でした。 例えば、A国の2013年の物価を100とすると、A国の2018年の物価は、100×1.011×1.010×1.013×1.021×1.022を計算すれば分かるのですが、電卓もないのにこんな計算できません。近似値で構わなければ、100×(1+0.011+0.010+0.013+0.021+0.022)=100×1.077=107.7(近似値)。 しかしながら、これは大小の比較をするだけなので、A国は、1.1+1.0+1.3+2.1+2.2=7.7、B国は、2.3+1.8+2.0+1.6+2.2=9.9のように、表の数字を、横に足していくだけでよいことになりますね。 C国は、0.6+0.5-0.1+0.7+1.3=3.1。 D国は、1.3+0.7+0.5+1.8+1.6=5.9。 E国は、0.6+0.6+0.7+2.7+2.7=7.3。 C国が、ダントツで最小ですので、肢4は、正しいと判断できます。 ここをポチッとお願いします。→

ここで、α、βが、2つとも、とってもとっても小さい数だったら、この計算の最後に出てくるαβは、とってもとってもとってもとっても小さい数になります。(たとえば、0.01×0.02=0.0002) どれくらい小さいかというと、無視しても構わないくらい小さくなりますね。本当に無視すると、(1+α)(1+β)=1+α+βになります。例えば、こんなことに。

αやβが、マイナスになっても構いません。例えば、

1近辺の数どうしを掛けるときに使えますね。 といっても、あくまでも近似値であって、本当の値ではありませんけど。 1の前後10%、つまり、0.9から1.1の間の数ばかりを掛けるとき、真の値にかなり近くなります。 特に、1より小さいものと1より大きいものが均等に混じっていれば、本当に真の値に近くなります。 たとえ0.9から1.1の範囲を超えていても、まあ、目安にするなら十分使えます。そこで、前回の肢4です。

肢4は、「2013年の各国の物価を100とした2018年の指数を比較すると、最も小さいのはC国である。」でした。 例えば、A国の2013年の物価を100とすると、A国の2018年の物価は、100×1.011×1.010×1.013×1.021×1.022を計算すれば分かるのですが、電卓もないのにこんな計算できません。近似値で構わなければ、100×(1+0.011+0.010+0.013+0.021+0.022)=100×1.077=107.7(近似値)。 しかしながら、これは大小の比較をするだけなので、A国は、1.1+1.0+1.3+2.1+2.2=7.7、B国は、2.3+1.8+2.0+1.6+2.2=9.9のように、表の数字を、横に足していくだけでよいことになりますね。 C国は、0.6+0.5-0.1+0.7+1.3=3.1。 D国は、1.3+0.7+0.5+1.8+1.6=5.9。 E国は、0.6+0.6+0.7+2.7+2.7=7.3。 C国が、ダントツで最小ですので、肢4は、正しいと判断できます。 ここをポチッとお願いします。→
にほんブログ村