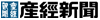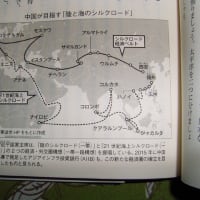↑よろしかったらクリックをお願いいたします。
家畜泥棒が関東で多発しているということです。
700頭以上も盗まれているのに、追跡があますぎるのでは?
日本における外国人犯罪で第一位が中国人ということです。
殺人、強盗、窃盗、などなどすべての項目で第一位が中国人。
元警察官の坂東忠信氏も以前から書籍や講演会でお話しています。
ところが、犯人が中国人となると、新聞やテレビでの取り扱いが
微妙になりますね。
中国人だとわかっていても外国人だとか。どこの国の外国人かわからなくしたりしています。
ひどいのは、日本で取得した通名で犯人の名前がニュースになるほどです。この程度の情報提供の仕方で、日本人の生命と安全を
日本のマスコミは守れましょうか?
警察が中国人の名前を新聞記者やテレビ局に人間に発表しても
新聞では名前を出さないことが多いと、警察署員から聞きました。
すでに中国人が運営する会社が、日本からt買い(トン買い)
した食料を山形県の酒田港から船で中国に輸送しているというニュースも
ありましたから、その700頭の子豚や子牛も、船で中国に
輸送されているかもしれませんね。
なにしろ、中国では今、食料難ですからね。それもニュースになりませんね。中国に不利なことは徹底して報道されません。
日本は、こんな情報提供の仕方で大丈夫でしょうか?
中国人犯罪に甘い対応を取り続けたらどうなるでしょうか?
中国人を日本政府はどんどん日本に来させていますから、日本では
過去聴いたことがないような事件が、今後多発するということです。
恐ろしく、残酷な事件が多発するということですよ。
日本人とは民度が、違いすぎるのですからね。
コロナで感染したというだけで、殺されるのが中国ですよ。
中国では人身売買も頻繁に行われていますから、日本人の赤ちゃんや子供がさらわれて
中国人に人身売買されるかも知りませんよ。
中国では、赤ちゃんの肉を滋養強壮剤として販売されたりする国ですからね。
日本は、悪を食い止める意識と言葉を持たなくてはいけないでしょう。
おとなしすぎるから馬鹿にされるのです。
そもそも、日本政府が、どんどん中国人を日本に入国させてます。
日本政府は、特段の事情で、中国人の印象が悪くなるようなことをしないように、各省庁やマスコミに指令でもだしているかもしれませんね。
日本国民の生命と安全と人権は、いったい誰が守るのですかね?
これでは、公共機関に税金を支払っている意味がないではないですか。
中国人はブタや牛の肉ばかりではなく、
人肉を食べる文化もありますから、警戒を高めてゆきたいものです。
以下、産経新聞からの抜粋です。ご覧ください。
相次ぐ家畜ドロボウ 被害は700匹以上 牛、豚、鶏はどこに…
北関東を中心に畜産農家で飼育されている子牛や豚などが持ち去られる事件が相次いで発生している。これまでに700匹以上が盗まれ、被害額は2千万円を超えるとみられる。警察は窃盗事件として捜査しているが、誰が何のために家畜を盗み、どこに持ち去ったのか。専門家は「畜産の知識がないと難しい」とし、組織的犯行によるとの見方を強めている。(根本和哉、大渡美咲)
■突然消えた牛
8月22日深夜。栃木県足利市にある牛舎の防犯カメラには、子牛を持ち去る3人の人影が写っていた。牛舎付近にワゴン車を止めた後、2人が中へ侵入。子牛の足を持って逆さづりにして、車へ運んだ。3頭の子牛を運び去るまでわずか10分ほどだったという。
被害に遭った「鶴田ファーミング」(同市羽刈町)の代表取締役、鶴田一弘さん(58)によると、6月にも子牛2頭が盗まれており、いずれも生後1カ月以内の黒毛和牛で時価総額は約230万円にも上る。
鶴田さんは「育てるにはプロの技術が必要なので食べるためかもしれないが、子牛なので食べられる部分は少なく、おいしいかもわからない」と困惑する。
カメラに写った子牛はぐったりしており、鶴田さんによると、薬は肉質に影響が出るため、スタンガンなどを用いて気絶させられたのではないかという。
強引な犯行に鶴田さんは「わが子を失った気持ち。早く犯人を捕まえてほしい」と唇をかんだ。
■4県で被害
こうした被害は今年に入り群馬、栃木、茨城、埼玉の4県で続発。各県警などによると牛、豚、鶏など700匹以上が盗まれた。各県警は、一連の犯行に関連性があるかどうかも含めて捜査を続け、犯人の行方を追っている。
中でも被害が大きいのは豚の飼育頭数が全国上位の群馬県。前橋市の養豚場4カ所で計570頭が盗まれるなど、約680頭もの豚が盗まれた。いずれも簡易な「ユニット型」と呼ばれる豚舎が狙われたという。
農林水産省によると、牛は、牛トレーサビリティー制度で、生後すぐに10桁の個体識別番号を割り振られ、耳に番号が印字された耳標がつけられる。ない牛は出荷や食肉処理などをすることはできない。
豚は個体識別番号はないが、生きた豚の輸出は禁止されており、関係者は「殺して持っていくのも常識的には不可能」とする。
■「知識や経験必要」
「空いている豚舎があり、豚を飼える施設や知識、経験がある人の可能性がある」。そう分析するのは養豚に詳しい農畜産物コンサルタントの青木隆夫氏だ。昭和35年に約80万戸あった養豚農家は現在、約4300戸まで減少。農家数の減少が続いており、空いている豚舎もあるとみられる。
さらに、青木氏によると、子豚でも1日2〜3キロのエサを食べる上、糞尿の処理など経験や知識が必要となる。「国産の豚肉の相場は高くなっているが、養豚は素人が扱えるほど簡単ではない。狭い業界なので、一般の人が突然、食肉処理場に持ち込むことは難しく、闇ルートの存在も考えにくい」と指摘する。
元警視庁捜査1課理事官の大峯泰広氏も「家畜を保管する場所があり、取り扱いに慣れている同業者によるものか、その関係者による犯行の可能性があるのではないか」と分析する。
大峯氏は、指示役や盗難役、運搬役など最低でも4〜5人のグループの組織的犯行とみて「解体して販売するカネ目当てだろう」と指摘。「個体識別番号があって国内市場に出回らないのであれば、解体から販売までの闇のルートが確立されていることもあり得る。いずれにせよここまで大規模な家畜盗難事件は聞いたことがない」と話した。