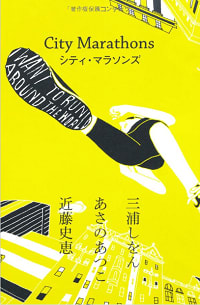あの名著 銃・病原菌・鉄 の著者ジャレド・ダイアモンド様による本です♪
ヒトのセクシュアリティに対する進化的アプローチの重要性と魅力と困難さがDEEPにかつマニアックに書かれてます♪
ペニスに機能は応用絵気圧モデルに基づく生体機能学的な実験をすることによって簡単に解決されるような単なる生理学上の問題ではなく、進化上の問題をも含んでいる。その進化上の問題とは700万~900万年をかけてヒトのペニスが推定される祖先のサイズから、なぜ4倍にも拡大したかということだ。これほど大きくなった理由を考えるには歴史的な説明と機能的な理由づけがぜひとも必要なのである。ここまで女性の乳汁分泌、隠された排卵、社会における男性の役割、閉経についてじっくりと検討してきたように、どのような淘汰圧が働いたためにヒトのペニスが時代を経て拡大し、その多く名サイズが今日も保たれているのかを問いかけなくてはならない。
ヒトの性は実はかなり特殊です。
たとえば霊長類約250種内において女性の胸が膨らんでいるのはほぼヒトだけ(他には唯一ボノボだけが少し膨らんでます。) 女性の許可を得ずに交尾しようとするのもほぼヒトだけ(他には唯一オランウータンだけ) 等々。
理由の一つにはヒトの赤ん坊は育てるのが超大変なことがあげられていますが...
700万年かけて、すさまじいレベルまで高められたヒトのオスとメスの複雑な関係もそれに拍車をかけてます...
実は恋愛なんて、氷山の一角的に表層に現れてるちっぽけなオマケ的なもの...
意識の潜在下等で行なわれている莫大なエネルギーのDNAの戦いがちょっと怖いです。
他にも先週はこんな本を読みました。

題名: 混浴と日本史
著者: 下川耿史
YAYAは記憶にある限り、過去に一回だけ東北で混浴経験あります。
意外に普通に入浴できた印象ありますが、それもそのはず 実は混浴は日本の文化であり、その歴史は実に長く、奥深いものでした。
著者は多感な学生の頃、風呂屋さんに覗きに行ったら同級生の女の子が同世代の男の子と混浴の風呂場で普通に会話しているのを見て、大きな衝撃を受けました。
その衝撃をもとに混浴を研究し続け、本作を書きあげたのでした。
混浴を不埒なものとして殲滅しようとするお上とお風呂屋さんの数百年にわたる戦いとか、海外の文化人から混浴なのに下賤な行いがない高いモラルを絶賛されたりとか...
混浴というよりは日本の大衆文化のすばらしさに心打たれます♪

題名: ビルマ・ハイウェイ 中国とインドをつなぐ十字路
著者: タンミンウー
世界の経済力の中心が東洋に移っているなか、アジアの地理も変わりつつある。そうした地理の中心にあるのがビルマだ。
ビルマのラムリー島近くの海岸から中国雲南の昆明に至る鉄道と石油・天然ガスパイプラインが建設されています。(パイプラインは完成)
いままでは深いジャングルと国境付近の紛争により遮断されていたルート。
それが中国のアキレス腱である内陸部の脆弱な経済とマラッカ海峡ジレンマ等への対策として開発が進められました。
しかし
ビルマはちょっとデンジャラス...だけでなく
数多くの少数民族の紛争と貧困、60年代の中印紛争リターンマッチの影、黄金の三角地帯の麻薬組織等々
あまり馴染みの無いこのエリアの、実に複雑な状況と歴史がすごくよく分かります。
ビルマに交差点は生まれるが、それは危険な交差点である。

題名: 誰も戦争を教えてくらなかった
著者: 古市憲寿
「あちこちがただれてくるような平和」が続く世界で、世界の戦争博物館はどのように、戦争という非日常を現在へと伝えているのだろうか。
今の若者達は実は日本プロパー的で、むしろYAYA的な世代が実はイレギュラーなのではないかという印象な話題作 「絶望の国の幸福な若者たち」 の著者の新作ということで読みました♪
アウシュビッツ博物館から数キロしか離れていないモールでは、当たり前だけど日常そのの光景が広がっていた。ソフトクリームを買おうかどうか迷ってやめた。
アウシュビッツ(意外にフツーな所らしい)、中国(意外にマイルドらしい南京の博物館)、韓国(ディズニーランド的な楽しい所らしい)などの戦争博物館見学と地元の人たちとの交流。
戦争とはなにかという、たぶん誰もがそれぞれにバイアスかかってて、他人とは真に共感できない難問について、各国の戦争博物館をもとにして考察するという本書は、ちょっとシュールですが興味深く読めました。

題名: 新完全ヒモマニュアル
著者: 鍵英之
だれでも知ってる一流企業を脱サラし、ヒモとなった方のマニュアル本です。
ヒモられさんの見分け方やアタックのかけ方など実践的な内容もありますが、YAYA的には本書のメインはヒモという生き方の記述だと思います。
ヒモという軟派なイメージとは異なり、17年もの長きにわたりヒモを貫くことは、時には命がけでもあり、想像以上に過酷な世界...

題名: クレイジー・ライク・アメリカ
著者: イーサン ウォッターズ
ほとんどの人が年に一回は心理療法を受けるアメリカ。
だから きっと世界中の人たちも皆 心の病 を持ってて、ケアや投薬が必要なはず。
で 日本でもアメリカの製薬会社が大活躍してSSRIのメガマーケットに...
「各国の文化を考慮に入れない療法は間違っている」 と著者は言われてます。