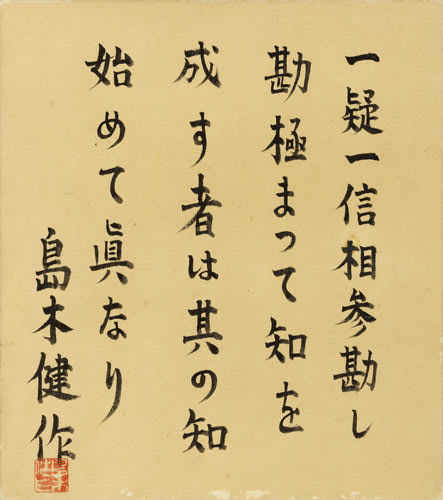ギリシャ問題についてのメモ――フェイスブックより (美津島明)

チプラス首相とメルケル首相
この一年ほどは、当ブログで時事ネタを扱うことがめっきり少なくなりました。おもに文化ジャンルにシフトしていたのですね。心境に変化があったわけではありません。時事ネタはフェイスブックに、やや息の長い文化ものはブログに、という書き分けをしていた結果です。まあ、そのままでもいいといえばいいのですが、当ブログをごらんにはなるが、フェイスブックを利用なさらないという方も少なからずいらっしゃることと思われるので、今後は、フェイスブックで書き溜めたものを、適宜当ブログにアップして、少しでもより多くの方の目に触れるようにしようかと思います。あまりカチッとした構成の論考にはなっておりませんが、あるひとつのテーマをめぐっての感想を時系列に沿って並べるとおのずと浮かび上がってくるものがあるのかもしれません。
●六月三〇日(火)
http://newsphere.jp/world-report/20150629-2/「“ギリシャは犠牲者”英紙、クルーグマンから擁護の声 ユーロの構造的問題を指摘」
ギリシャ問題の本質は、クルーグマンがいうとおり「緊縮財政こそが、ギリシャ経済にダメージを与えてきた」ことである。このうえさらに緊縮財政を押しつけられたら、ギリシャは、債務不履行・EU脱退の道を歩むほかはない。今回の事態の真犯人は、マスコミが喧伝したがっているように、ギリシャのチプラス首相ではなく、EUの設計ミスであり、ドイツの緊縮財政思想である。先進国首脳は、この事態から、「緊縮財政は、わざわいの元」という教訓を学ばなけばならない。マスコミは、これ以上、ギリシャ叩きという愚かなマネをしないように。
ついでながら、この事例は、「域内自由貿易は、国家間格差を拡大するだけで、結局は失敗に終わる」ことを示しているので、TPPの未来を予告している、とも言える。
●七月六日(月)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150706-00000018-mai-eurp 『<ギリシャ>国民投票「ノー」疲弊国民が選んだ「尊厳」』
ギリシャ国民の「EUの緊縮財政を拒否する」という選択は、ごく当たり前のことである。ドイツ国民以外でこれを非難する者は、救いがたい経済音痴であるとしかいいようがない(ドイツ国民のギリシャに対する不満は心情的には分かる)。ギリシャのGDPは、緊縮策が導入された2010年から14年までに25%も縮小し、25歳未満の若者の失業率は国民平均(25.6%)の約2倍にあたる49.7%に上り、大学を卒業したものの就職できない若者が国中にあふれているのである。この惨状の根本原因は、緊縮財政を是とするEUのエリートたちの経済思想なのであるから、ギリシャ国民がそれにNOを突きつけるのは当たり前のこととしかいいようがないではないか。
今後の展開は、予断を許さないものがあるが、私は、遅かれ早かれ、EU離脱→独自通貨発行という流れは不可避なのではないかと思っている。ドラクマ安は、ギリシャの危機を促進するのではなく、むしろ、(紆余曲折を経るとは思われるものの)ギリシャ経済を好転させるものと思われる。目の前の、明らかに起こると考えられる事態を想定してみよう。ギリシャは、幸いにも、世界で最も魅力的な観光資源に恵まれた国である。ドラクマ安は、世界からの観光客の増加が見込まれるのである。通貨安が観光客の増加につながることは、日本がいま経験していることなので、わかりやすい話だろう。ドラクマは一時的に劇的に下がるはずだから、相当な増加が実現するはずである。通貨安は、輸出にもプラスである。
日本は、ギリシャのEU離脱がもたらすものと思われるデフレの大津波の影響を最小限に抑えるために、金融緩和のみならず積極的な財政出動よって、内需拡大の経済的防波堤を築いておく必要がある。財務省や東大教授好みの緊縮財政をやっている場合ではない。
〈コメント欄〉
コメントA: ドラクマに復帰しても流通しない、と思います。
美津島明: ということは、ギリシャは、EUを離脱したら、いわゆるハイパーインフレションに見舞われるとお考えなのですね。渡辺さんは、ギリシャはEUに踏みとどまるほかない、というご意見でしょうか?
●七月七日(火)
ギリシャ問題について、個人の借金がどうの、怠け者がこうの、といった個人のふところぐあいや心がけのアナロジーで、一国の経済や世界経済を語ろうとする向きが絶えない。または、ギリシャ国民の意思決定にデモクラシーありやなしや、といった的外れな議論が展開されたりしている。事の本質は、マクロ経済政策としていかなる方策が妥当なのか、ということなのである。マクロ経済に関する最低限の知見が欠如したままで、当問題を語ろうとするのは百害あって一利なしであると言わざるをえない。ギリシャ問題は、EUによって、緊縮財政を強いられ続けたギリシャ国民の全般的な購買力(商品をどんどん買う力)、すなわち、有効需要の不足によって、経済の規模が収縮し、EUからの借金を返す力が減退していることによって生じているのである。そこをつかまえた議論をしないと、この問題の解決の糸口はいつまでたっても見えてこない。私が言っていることは、人によってはエラそうに感じるのかもしれないが、なんのことはない、マクロ経済を論じるうえでのイロハを指摘しているだけのことである。
●書き足し分
藤井聡氏・三橋経済新聞掲載(七月七日配信)『「アンチ緊縮」という民衆運動』
引用〈日本ではあまり取り沙汰されることはありませんが、今、ヨーロッパでは、「アンチ緊縮運動(アンチ・オーステリティ運動:Aiti-austerity movement)が大きな民衆運動として様々な国で盛んに展開され、様々に報道されています。
このアンチ緊縮運動がとりわけ激しく展開されているのが、イギリス、ギリシャ、スペイン、イタリア等の欧州の国々です。
これらの国々はいずれも、2008年のリーマンショックを契機として、政府の「財政再建」、つまり、「政府の借金返済」のために増税をして政府支出を削る「緊縮財政」路線が強力に推進され、その「結果」として国民経済の疲弊が深刻化した国々です。
つまり、これらの国々は、「政府のせいで庶民が困窮している」わけで、これに対する反対運動として、アンチ緊縮運動が一気に広がったという次第です。
たとえば、激しい緊縮財政を行い、失業率を過去最高水準にまで達していたスペインでは、「アンチ緊縮」を旗頭に14年にパブロ・イグレシアスが結党したポデモス党が、熱狂的な国民支持を受けています。結党からわずか20日間で10万人以上の党員を集め、僅か一年後には国内で第二番目の党員を宿す大政党にまで一気に成長しています。
同様に、リーマンショック後の緊縮路線によって経済が大いに低迷したイタリアでも、人気コメディアンのベッペ・グリッロ氏が2009年に立ち上げた「五つ星運動」という政党が、同じく「アンチ緊縮」路線を打ち出し、国民からの熱狂的支持を得ました。そして2013年に行われた国政選挙では、「第二党」にまで大躍進しています。
昨年、世界の注目の的となったスコットランドの独立運動ですが、これもまた政府が進める緊縮路線に対する「アンチ緊縮運動」として巻き起こったものと位置づける事ができます。
そして、「アンチ緊縮」の急先鋒といえば、もちろんギリシャ。
ギリシャでチプラス政権が誕生したのはまさに、「アンチ緊縮」という国民運動の一環ですし、何と言ってもこの度、EUからの緊縮案に対して「No」を突き付けた国民投票結果も、アンチ緊縮の国民運動の帰結です。
(中略)
そもそも、EUが押しつけようとする「緊縮」を拒めば、EUからの支援が受けられず、ギリシャ国民はさらなる経済被害を受ける事になります。いわばEU側は、この「緊縮策を飲めばカネをやる、飲まなきゃつぶれろ」と言わんばかりの「脅し」をかけたわけで、投票前はその「脅し」に屈し、「今回だけは折れて受け入れないと、さすがにヤバイのでは……」という声がかなり多く、アンチ緊縮派を上回る勢いがあったわけです。
ところがいざ投票となった途端、多くのギリシャ国民はEUからの緊縮要請に対して圧倒的な「No」を突きつけました。つまりギリシャ国民は、EUからの緊縮要請を「こんなもの、食べればもっと酷くなる最悪の『毒まんじゅう』じゃないか!」と拒絶したわけです。
これからギリシャがどのような道をたどるのか、ますますわからなくなってきました。ただし、現時点でも「言える事」はいくつかあります。
まず、この結果を受けて、「ギリシャのユーロ離脱」の可能性が増進することになりました。無論それでギリシャのみならず、EUもまた(そして最悪のケースでは世界経済そのものもまた)痛手を一時的に被ることになりますが、その果てにギリシャ国民は、「通貨発行権」という尊い権利を手に入れることが出来るようになるでしょう(ただし、ギリシャの離脱は、ギリシャがロシアと接近する可能性が高まることを意味しますから、このリスクについて、欧米がどのように対応するかが今後の鍵となります)。
またそれと同時に、ギリシャにとって最も今求められている「国内産業育成」を見据えた「今回の提案よりも、より望ましい再建策」が模索される可能性が増進したとも言えます。ギリシャのユーロ圏離脱やロシアとの接近といったリスクを考えた場合、そういう声が、今よりも強くなることも期待できます(ですが無論、ドイツ国民はじめ、支援国の人々がそれに強く反発することもまた明白ですから、その反発がどの程度なのかもまた、今後の鍵となります)。
……と言うことで、ギリシャを巡る諸事態は予断を許さない状況です〉引用終わり
今回のギリシャの動向は、イギリス、スペイン、イタリア等の欧州の他の国々における〈アンチ緊縮運動〉の一環である、という側面は見逃せない。というのは、この視点から、EUにおける〈EUエリートの緊縮路線VS「負け組」諸国民のアンチ緊縮運動〉という構図が浮かび上がってくるからだ。この構図は、EUの今後を占ううえで、頭の片隅に置いておくほうがよいような気がする。

チプラス首相とメルケル首相
この一年ほどは、当ブログで時事ネタを扱うことがめっきり少なくなりました。おもに文化ジャンルにシフトしていたのですね。心境に変化があったわけではありません。時事ネタはフェイスブックに、やや息の長い文化ものはブログに、という書き分けをしていた結果です。まあ、そのままでもいいといえばいいのですが、当ブログをごらんにはなるが、フェイスブックを利用なさらないという方も少なからずいらっしゃることと思われるので、今後は、フェイスブックで書き溜めたものを、適宜当ブログにアップして、少しでもより多くの方の目に触れるようにしようかと思います。あまりカチッとした構成の論考にはなっておりませんが、あるひとつのテーマをめぐっての感想を時系列に沿って並べるとおのずと浮かび上がってくるものがあるのかもしれません。
●六月三〇日(火)
http://newsphere.jp/world-report/20150629-2/「“ギリシャは犠牲者”英紙、クルーグマンから擁護の声 ユーロの構造的問題を指摘」
ギリシャ問題の本質は、クルーグマンがいうとおり「緊縮財政こそが、ギリシャ経済にダメージを与えてきた」ことである。このうえさらに緊縮財政を押しつけられたら、ギリシャは、債務不履行・EU脱退の道を歩むほかはない。今回の事態の真犯人は、マスコミが喧伝したがっているように、ギリシャのチプラス首相ではなく、EUの設計ミスであり、ドイツの緊縮財政思想である。先進国首脳は、この事態から、「緊縮財政は、わざわいの元」という教訓を学ばなけばならない。マスコミは、これ以上、ギリシャ叩きという愚かなマネをしないように。
ついでながら、この事例は、「域内自由貿易は、国家間格差を拡大するだけで、結局は失敗に終わる」ことを示しているので、TPPの未来を予告している、とも言える。
●七月六日(月)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150706-00000018-mai-eurp 『<ギリシャ>国民投票「ノー」疲弊国民が選んだ「尊厳」』
ギリシャ国民の「EUの緊縮財政を拒否する」という選択は、ごく当たり前のことである。ドイツ国民以外でこれを非難する者は、救いがたい経済音痴であるとしかいいようがない(ドイツ国民のギリシャに対する不満は心情的には分かる)。ギリシャのGDPは、緊縮策が導入された2010年から14年までに25%も縮小し、25歳未満の若者の失業率は国民平均(25.6%)の約2倍にあたる49.7%に上り、大学を卒業したものの就職できない若者が国中にあふれているのである。この惨状の根本原因は、緊縮財政を是とするEUのエリートたちの経済思想なのであるから、ギリシャ国民がそれにNOを突きつけるのは当たり前のこととしかいいようがないではないか。
今後の展開は、予断を許さないものがあるが、私は、遅かれ早かれ、EU離脱→独自通貨発行という流れは不可避なのではないかと思っている。ドラクマ安は、ギリシャの危機を促進するのではなく、むしろ、(紆余曲折を経るとは思われるものの)ギリシャ経済を好転させるものと思われる。目の前の、明らかに起こると考えられる事態を想定してみよう。ギリシャは、幸いにも、世界で最も魅力的な観光資源に恵まれた国である。ドラクマ安は、世界からの観光客の増加が見込まれるのである。通貨安が観光客の増加につながることは、日本がいま経験していることなので、わかりやすい話だろう。ドラクマは一時的に劇的に下がるはずだから、相当な増加が実現するはずである。通貨安は、輸出にもプラスである。
日本は、ギリシャのEU離脱がもたらすものと思われるデフレの大津波の影響を最小限に抑えるために、金融緩和のみならず積極的な財政出動よって、内需拡大の経済的防波堤を築いておく必要がある。財務省や東大教授好みの緊縮財政をやっている場合ではない。
〈コメント欄〉
コメントA: ドラクマに復帰しても流通しない、と思います。
美津島明: ということは、ギリシャは、EUを離脱したら、いわゆるハイパーインフレションに見舞われるとお考えなのですね。渡辺さんは、ギリシャはEUに踏みとどまるほかない、というご意見でしょうか?
●七月七日(火)
ギリシャ問題について、個人の借金がどうの、怠け者がこうの、といった個人のふところぐあいや心がけのアナロジーで、一国の経済や世界経済を語ろうとする向きが絶えない。または、ギリシャ国民の意思決定にデモクラシーありやなしや、といった的外れな議論が展開されたりしている。事の本質は、マクロ経済政策としていかなる方策が妥当なのか、ということなのである。マクロ経済に関する最低限の知見が欠如したままで、当問題を語ろうとするのは百害あって一利なしであると言わざるをえない。ギリシャ問題は、EUによって、緊縮財政を強いられ続けたギリシャ国民の全般的な購買力(商品をどんどん買う力)、すなわち、有効需要の不足によって、経済の規模が収縮し、EUからの借金を返す力が減退していることによって生じているのである。そこをつかまえた議論をしないと、この問題の解決の糸口はいつまでたっても見えてこない。私が言っていることは、人によってはエラそうに感じるのかもしれないが、なんのことはない、マクロ経済を論じるうえでのイロハを指摘しているだけのことである。
●書き足し分
藤井聡氏・三橋経済新聞掲載(七月七日配信)『「アンチ緊縮」という民衆運動』
引用〈日本ではあまり取り沙汰されることはありませんが、今、ヨーロッパでは、「アンチ緊縮運動(アンチ・オーステリティ運動:Aiti-austerity movement)が大きな民衆運動として様々な国で盛んに展開され、様々に報道されています。
このアンチ緊縮運動がとりわけ激しく展開されているのが、イギリス、ギリシャ、スペイン、イタリア等の欧州の国々です。
これらの国々はいずれも、2008年のリーマンショックを契機として、政府の「財政再建」、つまり、「政府の借金返済」のために増税をして政府支出を削る「緊縮財政」路線が強力に推進され、その「結果」として国民経済の疲弊が深刻化した国々です。
つまり、これらの国々は、「政府のせいで庶民が困窮している」わけで、これに対する反対運動として、アンチ緊縮運動が一気に広がったという次第です。
たとえば、激しい緊縮財政を行い、失業率を過去最高水準にまで達していたスペインでは、「アンチ緊縮」を旗頭に14年にパブロ・イグレシアスが結党したポデモス党が、熱狂的な国民支持を受けています。結党からわずか20日間で10万人以上の党員を集め、僅か一年後には国内で第二番目の党員を宿す大政党にまで一気に成長しています。
同様に、リーマンショック後の緊縮路線によって経済が大いに低迷したイタリアでも、人気コメディアンのベッペ・グリッロ氏が2009年に立ち上げた「五つ星運動」という政党が、同じく「アンチ緊縮」路線を打ち出し、国民からの熱狂的支持を得ました。そして2013年に行われた国政選挙では、「第二党」にまで大躍進しています。
昨年、世界の注目の的となったスコットランドの独立運動ですが、これもまた政府が進める緊縮路線に対する「アンチ緊縮運動」として巻き起こったものと位置づける事ができます。
そして、「アンチ緊縮」の急先鋒といえば、もちろんギリシャ。
ギリシャでチプラス政権が誕生したのはまさに、「アンチ緊縮」という国民運動の一環ですし、何と言ってもこの度、EUからの緊縮案に対して「No」を突き付けた国民投票結果も、アンチ緊縮の国民運動の帰結です。
(中略)
そもそも、EUが押しつけようとする「緊縮」を拒めば、EUからの支援が受けられず、ギリシャ国民はさらなる経済被害を受ける事になります。いわばEU側は、この「緊縮策を飲めばカネをやる、飲まなきゃつぶれろ」と言わんばかりの「脅し」をかけたわけで、投票前はその「脅し」に屈し、「今回だけは折れて受け入れないと、さすがにヤバイのでは……」という声がかなり多く、アンチ緊縮派を上回る勢いがあったわけです。
ところがいざ投票となった途端、多くのギリシャ国民はEUからの緊縮要請に対して圧倒的な「No」を突きつけました。つまりギリシャ国民は、EUからの緊縮要請を「こんなもの、食べればもっと酷くなる最悪の『毒まんじゅう』じゃないか!」と拒絶したわけです。
これからギリシャがどのような道をたどるのか、ますますわからなくなってきました。ただし、現時点でも「言える事」はいくつかあります。
まず、この結果を受けて、「ギリシャのユーロ離脱」の可能性が増進することになりました。無論それでギリシャのみならず、EUもまた(そして最悪のケースでは世界経済そのものもまた)痛手を一時的に被ることになりますが、その果てにギリシャ国民は、「通貨発行権」という尊い権利を手に入れることが出来るようになるでしょう(ただし、ギリシャの離脱は、ギリシャがロシアと接近する可能性が高まることを意味しますから、このリスクについて、欧米がどのように対応するかが今後の鍵となります)。
またそれと同時に、ギリシャにとって最も今求められている「国内産業育成」を見据えた「今回の提案よりも、より望ましい再建策」が模索される可能性が増進したとも言えます。ギリシャのユーロ圏離脱やロシアとの接近といったリスクを考えた場合、そういう声が、今よりも強くなることも期待できます(ですが無論、ドイツ国民はじめ、支援国の人々がそれに強く反発することもまた明白ですから、その反発がどの程度なのかもまた、今後の鍵となります)。
……と言うことで、ギリシャを巡る諸事態は予断を許さない状況です〉引用終わり
今回のギリシャの動向は、イギリス、スペイン、イタリア等の欧州の他の国々における〈アンチ緊縮運動〉の一環である、という側面は見逃せない。というのは、この視点から、EUにおける〈EUエリートの緊縮路線VS「負け組」諸国民のアンチ緊縮運動〉という構図が浮かび上がってくるからだ。この構図は、EUの今後を占ううえで、頭の片隅に置いておくほうがよいような気がする。