今日は、けっこうゴリゴリと理屈っぽい書き方になっています。論じる相手をとっちめてやりたいときの私のどうしようもないクセなので、笑ってお見逃しを。また、一部分レイアウト上お見苦しい箇所があることをお詫びいたします。
4月5日(木)に、当ブログで、日銀審議委員の欠員の後任にBNPパリバ証券経済調査本部長の河野龍太郎(47)を充てる政府の人事案が、参議院本会議で否決されたことを肯定的に扱う投稿をアップしました。ゴリゴリの新自由主義者で、野田政権の増税路線の賛同者で、日銀の事実上のデフレ・ターゲット路線を容認する人材の登用が阻まれたことは、デフレ不況という国難に直面した日本国民にとって、国民の意思の所在を示す朗報であると論じました。もし、すべてを知ったならば、この人事に賛成する一般国民はまずいないでしょう。その意味で、今回の参議院の意思表示は、国民の一般意思に即した妥当なものであると評するべきです。
そんな受け止め方をしていた私の目に、次の社説が飛び込んできました。
朝日(2012年)4月11日社説「日銀人事否決―国会同意のはき違えだ」
まずは、その見出しの意味をとらえかねて、私は一瞬目をシロクロさせてしまいました。どうやら、この記事を書いた朝日新聞の論説委員は、参議院が今回の人事案を否決したことをけしからんと怒っていて、参議院の野党議員たちの「国会同意のはき違え」を厳しく糾弾しようと意気込んで腕まくりをしているらしい。でも、「国会同意のはき違え」って?と思いつつも、まあ先に進んでみました。
日本銀行の政策決定に携わる審議委員の人事案が、国会で否決された。日銀人事の国会同意は、日銀の独立性を尊重しつつ、金融政策に貢献できる能力や識見がある人物かどうかをチェックするのが役割だ。
「日銀の独立性」をどうとらえるかは大きな問題ですが、それはそれとして、ここで言っていることは一般論としてその通りです。問題は次です。
ところが、国会は「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案を蹴った。国会同意の意味をはき違えた愚挙というほかない。
参議院が「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案を否決したこと=「国会同意の意味のはき違え」というのは、文脈からすれば、参議院の①否決の理由付けが日銀の独立性を尊重していない、あるいは、②否決の理由付けが、当人物に金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックしていない、という意味になります。
①の意味で言っているとすれば、政府案の審議員の金融政策についての考え方がどのようなものであろうと、それが国会議員のよしとする政策と合わないという理由で反対することは日銀の独立性を尊重していないことになるわけですから、金融政策の中身を決めるのは日銀である、言いかえれば、論説委員が、日銀の独立性に金融政策の目標・内容が含まれると考えていることになります。それは、論説委員が、金融政策に関して、日銀にフリーハンドを与える、言いかえれば、日銀の金融政策に関する責任の所在を不問に付すことを意味します。
また、②の意味ならば、参議院議員が「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案に反対することは、政府案の審議員に「金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェック」していないことであると論説委員が主張していることになります。
ここは重要な論点です。議会制民主主義において、国会議員とは主権の存する国民が選挙で選んだ代表者です。つまり、国会議員は、国民主権の代行者なのです。だから、「自分たちが求める政策」とは、「国民主権の代行者が求める政策」を意味します。とすると、国会議員にとって重要なのは「いかなる」金融政策が国民のためになるのかですね。つまり、議員にとっては、政府案の審議官に、国民のためになる金融政策に「貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックすること」が同意のポイントになりますよね。そういう能力や識見がないと判断したならば、議員は同意してはならない。そうなりますね。これは、国民主権を尊重する立場から当然に出てくる結論です。金融政策は、国民の暮らしに直結する最重要事項のひとつなのですから、それを担当する責任者の金融政策観について、国権の最高機関としての国会による厳しいチェックを受けるのは当たり前のことです。
だから、論説委員が、「金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックすること」という文言の中の「金融政策」の前に「国民のためになる」という限定条件をつけない場合にのみ、彼の批判は成り立つことになります。それは論説委員が「どういう金融政策を遂行するのかは日銀が決める」という立場に立っていることになりますね。そこは①の結論とおなじです。とするならば、それは、日銀の独立性に金融政策の目的・内容の決定権を含むという極端に日銀の寄りの立場を意味する、と同時に、議会制民主主義の否定をも意味します。国権の最高機関としての国会による厳しいチェックを否定するのですから、当然そうなります。
なぜ国会が国権の最高機関なのか。念のために言っておけば、国会が国民の代表者で構成され、憲法が国の政治の最終意思決定権(主権)は国民に存すると規定しているからです。
「民主主義の砦」を標榜してきた朝日が、ついに議会制民主主義を否定するようになったのですね。そんなつもりはない、というのならば、もう少し高校生レベルのものでいいから民主主義のお勉強をしてください。けっこう恥ずかしいことですよ、言論にたずさわる者が民主主義の初歩も知らないなんて。それがわからないうちは、決して「民主主義」といつもの癖で口走らないようにしようね。
もちろん政治家が金融政策を議論するのは結構だ。しかし、「政策が合わない」というだけで人事を葬るのでは、政治による日銀への脅しである。
これは、まさしく「面白うてやがて哀しき鵜飼かな」の世界です。これでは、まるであの日銀の白川総裁の魂が憑依して書いているとしか思えません。けっこうオカルトじみていますよ。言論人としてのバランス感覚を完全に失ってしまったうわ言と断じざるをえません。ブラック・ギャグとしては笑えますが、言論人としては、やはりうら悲しい姿というほかはありません。国会による国民主権の代行的遂行が、「政治による日銀への脅し」を意味するのならば、「日銀の独立性」のために日本は民主主義をやめなければならなくなります。天下の朝日の論説委員が口走るべき言葉ではありません。それとも、手を抜いた馬鹿なことを言っても、一般国民はわからないとても思っているのでしょうかね。やはり、ちょっと頭を冷やして勉強したほうがよいようです。お国のために筆を折ってしまうほうが手っ取り早いとは思いますが。
以下は、ねつ造記事のオンパレードで、目も当てられません。
何より重要なのは全体のバランスだ。金融政策が一方に偏って、バブルを引き起こしたり、過度な引き締めで経済を失速させたりしないための知恵だ。 現状では、金融緩和に積極的なメンバーはいるが、一貫した慎重派は昨春に須田美矢子・元学習院大教授が退任してからは見当たらない。多様性という点で今回は妥当な人選だった。
これについて、宮崎岳志民主党衆議院議員が次のようにツイートしています。
現実は「積極=不在、中立=宮尾、過激な慎重派=白川総裁、白川派=その他大勢」
そういうメンバー構成だからこそ、日銀は、長年にわたって日本国民を苦しめつづけているデフレを克服するための積極的な金融政策に踏み出せないでいるのですね。だから、今回の人事案否決はとても重要な出来事だったのです。うっかりすると、つい記事を見過ごして間違った事実を刷りこまれて、問題の本質を見失ってしまいますね。そこが、どうも狙いのようですが。「妥当な人事」とは恐れ入りました。
衆参ねじれ国会では、参院で多数を持つ野党が拒否権を持つに等しい。これを人事でも振り回すなら、金融政策の中身に野党が介入することになる。これは明らかな越権だ。日銀の独立性と相いれない。
ここでは、次の事実がなかったことにされてしまっています。
民主党の財金部門会議が全会一致で「反対」を決めた人事案に、野党も反対し可決が絶望的となり、案を取り下げるほかはないところまで民主党執行部は実のところ追い込まれていたのです。が、当日、参院で採決すること、また、党としては「賛成」の意向であることが突然民主党員に知らされました。民主党執行部の異様な意思決定と振る舞いですね。「ねじれ国会」以前のところで、この人事案は事実上破たんしていたのです。党利党略の野党に責任を問う前に、問題のある人選と異様な振る舞いをした民主党執行部の責任をこそ問うべきなのです。朝日は、そこをごまかしてはいけません。
長らく見ない間に、朝日新聞は、すっかり権力側にべったりと寄り添うどころかへばりつきさえする絵に描いたような御用新聞に成り下がっていたのですね。民主党が政権を取った段階で予想していたこととはいえ、いやあ、すさまじい。いっそのこと、これからは、社説の執筆陣に、財政政策については財務省の勝栄二郎事務次官を、金融政策については白川方明日銀総裁を、それぞれ主筆としてお招きして、思うところを存分に論じていただいてはどうでしょうか。その方が、あなたたちも余計な仕事が減るし、国民にとっても朝日新聞の意向がよく分かるし、万々歳なのではありませんか?なに、それでは無辜の国民を騙せなくなくなって、ご主人さまにアピールできなくなるって?そんな贅沢を言ってはいけません。
最後に、社説中で論説委員がやたらと振り回した「日銀の独立性」についての私見を述べておきます。
憲法が国民主権を規定し、議会制民主主義と議院内閣制とを採ること、および金融政策が国民生活に重大な影響を及ぼすことから、日銀の独立性は、国民生活の向上のために、政府が定めた金融政策の目標・内容を達成するための「手段を選ぶうえでの独立性」に限定すべきである、と私は考えます。また、その目標を達成することができない場合、および、達成のための努力を怠っていると客観的に判断される場合は、内閣に日銀総裁を罷免する権限を与えることが、その限定された独立性の実効性を保つために必要であると考えます。以上を明記した日銀法改正を早急に超党派で決議し間を置かずに実施すべきである、とする立場です。
事情をよく知る国民で、今私が述べた考え方に反対する人はそう多くないと思われます。だから、行政府と立法府の日銀法をめぐる、そういったスピーディな措置は、国民の政治に対する信頼を高める良い機会になるでしょう。これは、解散・総選挙がいつになるのかという政局とは別に、すぐに着手できることですし、着手しなければならないことです。それは、被災地の復旧・復興を加速するためにも重要なことです。増税などと寝言を言っている場合ではありません。日銀法改正をマニフェストに盛り込んで票をかせぐことばかりに腐心している場合でもありません。なにを置いても真っ先に着手しなければならないことです。また、そういうすばやい動きをする政治家に国民は次の清き一票を投じるはずです。そうは思われませんか。心ある政治家たちよ、決断を!
4月5日(木)に、当ブログで、日銀審議委員の欠員の後任にBNPパリバ証券経済調査本部長の河野龍太郎(47)を充てる政府の人事案が、参議院本会議で否決されたことを肯定的に扱う投稿をアップしました。ゴリゴリの新自由主義者で、野田政権の増税路線の賛同者で、日銀の事実上のデフレ・ターゲット路線を容認する人材の登用が阻まれたことは、デフレ不況という国難に直面した日本国民にとって、国民の意思の所在を示す朗報であると論じました。もし、すべてを知ったならば、この人事に賛成する一般国民はまずいないでしょう。その意味で、今回の参議院の意思表示は、国民の一般意思に即した妥当なものであると評するべきです。
そんな受け止め方をしていた私の目に、次の社説が飛び込んできました。
朝日(2012年)4月11日社説「日銀人事否決―国会同意のはき違えだ」
まずは、その見出しの意味をとらえかねて、私は一瞬目をシロクロさせてしまいました。どうやら、この記事を書いた朝日新聞の論説委員は、参議院が今回の人事案を否決したことをけしからんと怒っていて、参議院の野党議員たちの「国会同意のはき違え」を厳しく糾弾しようと意気込んで腕まくりをしているらしい。でも、「国会同意のはき違え」って?と思いつつも、まあ先に進んでみました。
日本銀行の政策決定に携わる審議委員の人事案が、国会で否決された。日銀人事の国会同意は、日銀の独立性を尊重しつつ、金融政策に貢献できる能力や識見がある人物かどうかをチェックするのが役割だ。
「日銀の独立性」をどうとらえるかは大きな問題ですが、それはそれとして、ここで言っていることは一般論としてその通りです。問題は次です。
ところが、国会は「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案を蹴った。国会同意の意味をはき違えた愚挙というほかない。
参議院が「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案を否決したこと=「国会同意の意味のはき違え」というのは、文脈からすれば、参議院の①否決の理由付けが日銀の独立性を尊重していない、あるいは、②否決の理由付けが、当人物に金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックしていない、という意味になります。
①の意味で言っているとすれば、政府案の審議員の金融政策についての考え方がどのようなものであろうと、それが国会議員のよしとする政策と合わないという理由で反対することは日銀の独立性を尊重していないことになるわけですから、金融政策の中身を決めるのは日銀である、言いかえれば、論説委員が、日銀の独立性に金融政策の目標・内容が含まれると考えていることになります。それは、論説委員が、金融政策に関して、日銀にフリーハンドを与える、言いかえれば、日銀の金融政策に関する責任の所在を不問に付すことを意味します。
また、②の意味ならば、参議院議員が「自分たちが求める政策と合わない」という理由で人事案に反対することは、政府案の審議員に「金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェック」していないことであると論説委員が主張していることになります。
ここは重要な論点です。議会制民主主義において、国会議員とは主権の存する国民が選挙で選んだ代表者です。つまり、国会議員は、国民主権の代行者なのです。だから、「自分たちが求める政策」とは、「国民主権の代行者が求める政策」を意味します。とすると、国会議員にとって重要なのは「いかなる」金融政策が国民のためになるのかですね。つまり、議員にとっては、政府案の審議官に、国民のためになる金融政策に「貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックすること」が同意のポイントになりますよね。そういう能力や識見がないと判断したならば、議員は同意してはならない。そうなりますね。これは、国民主権を尊重する立場から当然に出てくる結論です。金融政策は、国民の暮らしに直結する最重要事項のひとつなのですから、それを担当する責任者の金融政策観について、国権の最高機関としての国会による厳しいチェックを受けるのは当たり前のことです。
だから、論説委員が、「金融政策に貢献できる能力や識見があるかどうかをチェックすること」という文言の中の「金融政策」の前に「国民のためになる」という限定条件をつけない場合にのみ、彼の批判は成り立つことになります。それは論説委員が「どういう金融政策を遂行するのかは日銀が決める」という立場に立っていることになりますね。そこは①の結論とおなじです。とするならば、それは、日銀の独立性に金融政策の目的・内容の決定権を含むという極端に日銀の寄りの立場を意味する、と同時に、議会制民主主義の否定をも意味します。国権の最高機関としての国会による厳しいチェックを否定するのですから、当然そうなります。
なぜ国会が国権の最高機関なのか。念のために言っておけば、国会が国民の代表者で構成され、憲法が国の政治の最終意思決定権(主権)は国民に存すると規定しているからです。
「民主主義の砦」を標榜してきた朝日が、ついに議会制民主主義を否定するようになったのですね。そんなつもりはない、というのならば、もう少し高校生レベルのものでいいから民主主義のお勉強をしてください。けっこう恥ずかしいことですよ、言論にたずさわる者が民主主義の初歩も知らないなんて。それがわからないうちは、決して「民主主義」といつもの癖で口走らないようにしようね。
もちろん政治家が金融政策を議論するのは結構だ。しかし、「政策が合わない」というだけで人事を葬るのでは、政治による日銀への脅しである。
これは、まさしく「面白うてやがて哀しき鵜飼かな」の世界です。これでは、まるであの日銀の白川総裁の魂が憑依して書いているとしか思えません。けっこうオカルトじみていますよ。言論人としてのバランス感覚を完全に失ってしまったうわ言と断じざるをえません。ブラック・ギャグとしては笑えますが、言論人としては、やはりうら悲しい姿というほかはありません。国会による国民主権の代行的遂行が、「政治による日銀への脅し」を意味するのならば、「日銀の独立性」のために日本は民主主義をやめなければならなくなります。天下の朝日の論説委員が口走るべき言葉ではありません。それとも、手を抜いた馬鹿なことを言っても、一般国民はわからないとても思っているのでしょうかね。やはり、ちょっと頭を冷やして勉強したほうがよいようです。お国のために筆を折ってしまうほうが手っ取り早いとは思いますが。
以下は、ねつ造記事のオンパレードで、目も当てられません。
何より重要なのは全体のバランスだ。金融政策が一方に偏って、バブルを引き起こしたり、過度な引き締めで経済を失速させたりしないための知恵だ。 現状では、金融緩和に積極的なメンバーはいるが、一貫した慎重派は昨春に須田美矢子・元学習院大教授が退任してからは見当たらない。多様性という点で今回は妥当な人選だった。
これについて、宮崎岳志民主党衆議院議員が次のようにツイートしています。
現実は「積極=不在、中立=宮尾、過激な慎重派=白川総裁、白川派=その他大勢」
そういうメンバー構成だからこそ、日銀は、長年にわたって日本国民を苦しめつづけているデフレを克服するための積極的な金融政策に踏み出せないでいるのですね。だから、今回の人事案否決はとても重要な出来事だったのです。うっかりすると、つい記事を見過ごして間違った事実を刷りこまれて、問題の本質を見失ってしまいますね。そこが、どうも狙いのようですが。「妥当な人事」とは恐れ入りました。
衆参ねじれ国会では、参院で多数を持つ野党が拒否権を持つに等しい。これを人事でも振り回すなら、金融政策の中身に野党が介入することになる。これは明らかな越権だ。日銀の独立性と相いれない。
ここでは、次の事実がなかったことにされてしまっています。
民主党の財金部門会議が全会一致で「反対」を決めた人事案に、野党も反対し可決が絶望的となり、案を取り下げるほかはないところまで民主党執行部は実のところ追い込まれていたのです。が、当日、参院で採決すること、また、党としては「賛成」の意向であることが突然民主党員に知らされました。民主党執行部の異様な意思決定と振る舞いですね。「ねじれ国会」以前のところで、この人事案は事実上破たんしていたのです。党利党略の野党に責任を問う前に、問題のある人選と異様な振る舞いをした民主党執行部の責任をこそ問うべきなのです。朝日は、そこをごまかしてはいけません。
長らく見ない間に、朝日新聞は、すっかり権力側にべったりと寄り添うどころかへばりつきさえする絵に描いたような御用新聞に成り下がっていたのですね。民主党が政権を取った段階で予想していたこととはいえ、いやあ、すさまじい。いっそのこと、これからは、社説の執筆陣に、財政政策については財務省の勝栄二郎事務次官を、金融政策については白川方明日銀総裁を、それぞれ主筆としてお招きして、思うところを存分に論じていただいてはどうでしょうか。その方が、あなたたちも余計な仕事が減るし、国民にとっても朝日新聞の意向がよく分かるし、万々歳なのではありませんか?なに、それでは無辜の国民を騙せなくなくなって、ご主人さまにアピールできなくなるって?そんな贅沢を言ってはいけません。
最後に、社説中で論説委員がやたらと振り回した「日銀の独立性」についての私見を述べておきます。
憲法が国民主権を規定し、議会制民主主義と議院内閣制とを採ること、および金融政策が国民生活に重大な影響を及ぼすことから、日銀の独立性は、国民生活の向上のために、政府が定めた金融政策の目標・内容を達成するための「手段を選ぶうえでの独立性」に限定すべきである、と私は考えます。また、その目標を達成することができない場合、および、達成のための努力を怠っていると客観的に判断される場合は、内閣に日銀総裁を罷免する権限を与えることが、その限定された独立性の実効性を保つために必要であると考えます。以上を明記した日銀法改正を早急に超党派で決議し間を置かずに実施すべきである、とする立場です。
事情をよく知る国民で、今私が述べた考え方に反対する人はそう多くないと思われます。だから、行政府と立法府の日銀法をめぐる、そういったスピーディな措置は、国民の政治に対する信頼を高める良い機会になるでしょう。これは、解散・総選挙がいつになるのかという政局とは別に、すぐに着手できることですし、着手しなければならないことです。それは、被災地の復旧・復興を加速するためにも重要なことです。増税などと寝言を言っている場合ではありません。日銀法改正をマニフェストに盛り込んで票をかせぐことばかりに腐心している場合でもありません。なにを置いても真っ先に着手しなければならないことです。また、そういうすばやい動きをする政治家に国民は次の清き一票を投じるはずです。そうは思われませんか。心ある政治家たちよ、決断を!












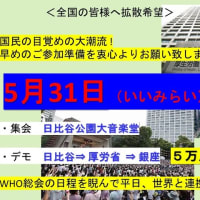














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます