長谷川三千子『神やぶれたまはず』について(その1)
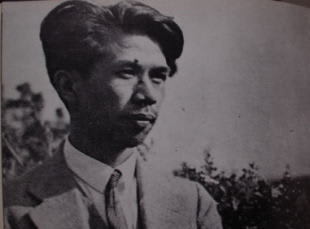
詩人・伊東静雄
かつて私は、当ブログで木下恵介の『陸軍』を論じたことがあります。http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/7ad13147688249e05a2d76171e2ec640 そのおり、当作品には本当の意味での反戦文学の契機が存すると述べました。また私たちが、反戦の意味を本気でつかもうと思うのならば、大東亜戦争の真っ只中に飛び込んでいって、かつての日本人たちとともに戦い、ともにもみくちゃになり、ともに敗戦のときを迎えるよりほかはないという意味のことを述べました。そうしてそれは、戦争を経験していない者にとっては、本質的に想像力の問題である、とも。戦後において流通している俗流歴史観によれば、反戦思想は、過ちの歴史を二度と繰り返さないという決意を固めることによって育まれるとされるのですが、私は、その「過ちの歴史」を何度でもくぐり抜ける観念の旅を敢行することによってしか、真の反戦思想は掴み取りえないと考えたわけです。
そこには、戦後に流通した「反戦」なる概念のまがい物性を否定的に乗り越えたいという私なりの思いがありました。もっと踏み込んで言ってしまえば、自由・平等・人権・平和などという、戦後に流通し続けてきた肯定的諸価値に対する疑念が湧いてくるのをいかんともしがたいという思いがありました。そういう諸価値に安住していられれば、どれほど楽に生きられるだろう、ということでもあります。何の因果で、かくも疑い深くなってしまったのか、自分のことながらどう考えてみてもよくわからないところがあるのです。私の場合、いわゆる保守思想にアクセスする以前からそうなのです。私には、そういう諸価値に何の疑いも持たずにそれらに基づいて言説を展開しようとする論者のナイーヴさに対する抜きがたい違和感や、さらには嫌悪感さえもがあります。そういう論者は、一種の「思想の敗戦利得者」の姿として私の目には映るのです。それは自分でも処理し難い激しい情念です。そこだけ取り出して言うならば、パリサイびとの偽善を激しく非難するイエスの気持ちが分かるほどです。
話を戻しましょう。反戦なるものにまつわって、そういうことを考えてはみたものの、そういう意味での想像力を発揮することは、実のところ言うは易く行うは難しなのです。なかなかその先へ進むことがかなわないままに、いたずらに時が過ぎていきました。
一国の歴史のうちには、ちやうど一人の人間の人生のうちにおいてもさうであるやうに、或る特別の瞬間といふものが存在する。
上記は、見返しと扉をめくった本書の「序」の冒頭です。それがすっと目に飛び込んできたとき、私は心の片隅に震えのようなものを感じました。それをあえて言葉にすれば、次のようになります。「お前はこれから日本の歴史においてとても重要なことを目撃する観念の旅を始めることになる。そうしてそれは、お前が考えようとして考えあぐねていたことに大いに関係のある旅である」。珍しいことに、そういう直観が働いたのです。
幸運なことに、その直観は当たっていました。だから、本書は私にとても実り多いものをもたらしてくれました。むろん、その分大きな課題も残されました。それらが具体的にはどういうことなのかをお伝えするのが、この文章の柱となるのでしょう。
本書は、文中の「ある特別な瞬間」とは何であり、そこで実は何が起こったのかにきっちりと答えています。というより、本書の論点はあえてその一点にぎゅっと絞り込まれています。著者ご自身によれば、それに直接関連しない事柄は、思いきりよくバッサバッサと刈り込まれました。だから、本書を読み終えた者は、それを肯定的に受け入れるにしても逆に拒否するにしても、本書から輪郭のくっきりとした歴史の一瞬の鮮烈なイメージを受け取ることは間違いありません。その意味で、本書は「読み手に、伝えたいことの核心だけを伝える」という書き手の姿勢が感じられて実に清々しいし、言っていることの責任の所在がはっきりしてもいます。それに対して批判的なアプローチが可能なのは分かりますが、私は、むしろ著者の潔いスタンスを諒とする者です。知性なるものは、懐疑においてよりもむしろ他を捨ててひとつのことを選ぶ決断においてこそ高度に発揮されるものであると思うからです。別言すれば、考えることは一定の決断に向けて開かれたものであることが必要である。なぜなら、そうであってこそ、言論の本当の意味での責任が生まれるからである。そう思うのです。
「ある特別な瞬間」とは何であり、そこで実は何が起こったのかについてとりあえずさわり程度に触れておきましょう。
「ある特別な瞬間」とは、一九四五年八月十五日正午に日本国民がラジオで昭和天皇の「終戦の詔書」を聴いたときに、国民の心のなかで起こったことを指しています。では、いったい何が起こったのでしょうか。著者は、それを語り切るために、戦後日本の選りすぐりの思想家たちとの語らいに十年の歳月をかけました。もちろん、ずっとかかりっきりというわけではなくて、気長に折に触れてという形だったのでしょうが、本書と取り組みはじめてから十年の歳月が流れたのは確かなことです。本書には、それだけの膨大な時間が織り込まれているのです。三〇五ページの、分厚いとは言えないほどの分量なのですが、読後、もっと大部の本を読んだような感触が残るのは、そういう事情があるからなのではないでしょうか。その歳月分の重みを尊重するならば、先の「国民の心のなかで起こったこと」をあっさりとここで言ってしまうことを、私はいささかためらってしまいます。もったいぶるわけではなくて、そうしてしまうと、それをはじめてご覧になった方(それを想定して、この文章を書いています)は、おそらく字面だけは追えるものの本当のところ何が何だかわからないのではないかと思われるからです。それではあまりにもったいない。
そこで、必要最小限のまわり道をして、著者の対話の相手となった思想家たちとのやり取りのポイントを順次押さえながら、そのとき「国民の心のなかで起こったこと」に肉薄して行こうと思います。そんな流れをたどることで、読み手が、本書の提示した鮮やかなイメージを等身大で受けとめることが可能になれば、私としては本望です。むろん、それを受け入れるにしろ、拒否するにしろ、ということです。そうして、それは私自身の問題でもあるので、出来うる限りそのイメージに対する私のスタンスも明らかにするよう心がけましょう。また、その一連の試みが、本書の単なる祖述に終わってしまったのではつまりませんから、折に触れて私見を織り込むことにします。もしもウザイと感じられたならば、そこは読み飛ばしていただいてもけっこうです。
著者の対話の相手を、掲載順に列挙しましょう。折口信夫、橋川文三、桶谷秀明、河上徹太郎、太宰治、伊東静雄、磯田光一、吉本隆明、三島由紀夫、そうしてデリダ。
あらかじめ申し上げておけば、吉本隆明や三島由紀夫との対話が最大のポイントになります。また、それらの重要性をくっきりとあぶり出すために、著者は、デリダの『死を与える』に焦点を当てようとします。その過程で図らずも、思想家としての吉本の価値と三島の『英霊の聲』の評価をめぐって、読み手は重大な視線変更を余儀なくされます。むろん、そのほかの思想家についても同じことが言えます。その意味で本書は、戦後においてもっとも考えるべきことをどこまで深く考えているかという観点から、戦後の諸思想家の大胆な読みかえ作業、さらには、戦後思想のパラダイム変更を敢行しているともいえるでしょう。本書は、思想書としてとても刺激的で挑戦的な本なのです。
それでは、そろそろ本文に入ってゆきましょう。
本文の冒頭に登場するのは、折口信夫が戦後まもなくに書いた詩「神 やぶれたまふ」です。
「神やぶれたまふ」
神こゝに 敗れたまひぬ─。
すさのをも おほくにぬしも
青垣の内つ御庭(ミニハ)の
宮出でゝ さすらひたまふ─。
くそ 嘔吐(タグリ) ゆまり流れて
蛆 蠅(ハヘ)の、集(タカ)り 群起(ムラダ)つ
直土(ヒタツチ)に─人は臥(コ)ひ伏し
青人草(アヲヒトグサ) すべて色なし─。
村も 野も 山も 一色(ヒトイロ)─
ひたすらに青みわたれど
たゞ虚し。青の一色
海 空もおなじ 青いろ─。
著者は、「ここには、絶望の極まつた末の美しさ、酸鼻のきわみのはてに現はれる森と静まりかえつた美しさといふものがあ」り、「昭和二十年八月十五日正午の、『あのシーンとした国民の心の一瞬』のかたち」があると評します。「あのシーンとした国民の心の一瞬」とは、河上徹太郎が敗戦後ほどなく書いた「ジャーナリズムと国民の心」の一節であり、後に桶谷秀明によって『昭和精神史 戦後篇』(平成十二年)に再録されることになったものでもあります。詩の終末部の青のイメージには、八月十五日の快晴のそれが織り込まれています。そのイメージは、詩人・伊東静雄の日記の次の一節にもはっきりと顔をのぞかせています。
十五日陛下の御放送を拝した直後。
太陽の光は少しもかはらず、透明に強く田と畑の面を木々を照し、白い雲は静かに浮かび、家々からは炊煙がのぼつてゐる。それなのに、戦は敗れたのだ。何の異変も自然に起こらないのが信ぜられない。 (101頁)
この一節に込められた不可思議な激情が、時の風化作用を経てなおも遠く残響として残ったときに、それは、次のような世にも美しい叙情詩として結晶しました(この詩は本書からの引用ではありません)。
夏の終り
夜来の颱風にひとりはぐれた白い雲が
気のとほくなるほど澄みに澄んだ
かぐわしい大気の空をながれてゆく
太陽の燃えかがやく野の景観に
それがおほきく落とす静かな翳は
……さよなら……さやうなら……
……さよなら……さやうなら……
いちいちさう頷く眼差のやうに
一筋ひかる街道をよこぎり
あざやかな暗緑の水田(みずた)の面を移り
ちひさく動く行人をおひ越して
しづかにしづかに村落の屋根屋根や
樹上にかげり
……さよなら……さやうなら……
……さよなら……さやうなら……
ずっとこの会釈をつづけながら
やがて優しくわが視野から遠ざかる
(詩集『反響』創元社・一九四七年 より)
「気のとほくなるほど澄みに澄んだ/かぐわしい大気の空をながれてゆく」「白い雲」。このイメージの淵源は、上記の日記の一節の「太陽の光」が「透明に強く田と畑の面を木々を照」す中に「静かに浮か」ぶ「白い雲」に求めることができるでしょう。動いているかとどまっているかの印象の違いはありますが、前者に〈時の流れ〉を織り込めば後者になると解釈すると、両者はスムーズにつながるのではないでしょうか。
私が頭をつっこみかけているのは一種の作品論ですから、異論があるのは承知していますが、要は、伊東静雄にとって、八月十五日の森とした青空のイメージが、一種のアーキタイプ(元型)のようなものとして心の奥深くに貼り付いてしまったことが確認できれば、私としてはそれでいいのです。そうでなければ、「夏の終わり」のような決定的で鮮やかな印象を与える叙情詩を書くことは不可能であると思います。
そうして、その同じ事態が、伊東静雄のみならず、折口信夫にも、橋川文三にも、桶谷秀明にも、太宰治にも、吉本隆明にも、三島由紀夫にも、それぞれ個性の数だけのバリエーションを伴いながらも、シンクロニシティ(意味のある偶然の一致)の形で起こった。本書は、そのように読み手に語りかけ、そのことの深い意味合いの気づきに読み手を誘い込んで行こうとするのです(磯田光一を外したのには、後述しますが、訳があります)。
流石に折口は、著者によれば、敗戦のアーキタイプの意味をきちんとつかんでいます。彼は、敗戦の只中から、新しい神学を打ち立てる必要性を悟り、学生たちに「あなたがたの中に、神道の建設に情熱を向ける者が出てもらいたい」と熱をこめて語りかけているのです。
しかし折口の「新しい神学」を打ち立てる試みは挫折しました。それは何故なのでしょうか。その理由を語るには、彼の愛弟子の春洋(はるみ)のことに触れないわけにはいません。
本書によれば、石川県能登半島生まれの「藤井春洋は二十一歳のときから折口の家に身を寄せ、出征まであしかけ十六年間、生活をともにしつつ折口の薫陶を受けた、文字通りの愛弟子」です。折口の同性愛的な傾向を考えれば、当然肉体関係もあったのでしょう。そんな存在であった春洋が、一九四三年、二度目の召集を受け、金沢歩兵聯隊に入営し、四四年七月、硫黄島に着任し、陸軍中尉を拝命するのですが、同月に、折口信夫の養子として入籍します。本書によれば、「氏にとって藤井春洋氏を失ふといふことは、我が子を失ふことであると同時に自らの学問の後継者を失ふことであり、また自らの生活そのものを失ふことでもあった」とあります。まったくもって、そのとおりだったことでしょう。四五年三月十九日、春洋は硫黄島にて戦死しますが、それを知った後の折口の取り乱しぶり、落胆ぶりは、身も世もないほどのものだったようです。そうして彼は、死に至るまでついにその精神的な打撃から回復することがかなわなかったようでもあります。折口は春洋の故郷の能登一ノ宮に父子の墓を建て、次のような碑文を刻んでいます。
もっとも苦しき たたかひに 最もくるしみ 死にたる
むかしの陸軍中尉 折口春洋 ならびにその 父 信夫の墓
この碑文は、折口の心にぽっかりと空いた傷口が遂にふさがらないまま鮮血を流し続けたことを生々しく伝えています。こうしたことを踏まえたうえで、長谷川氏は次のように述べます。
折口信夫氏は、明らかにその(すなわち、大東亜戦争の――引用者補)「絶対的なもの」を垣間見てゐた。さもなければ、あの「神 やぶれたまふ」のやうな詩が書けたはずもないし、また「神道宗教化」を言ひ出したはずもない。しかし、氏にとって、その「絶対的なもの」をそれとしてつかみ出すのは、ほとんど構造的に不可能なことであつた。単に、折口氏が自らの悲歎をのりきることができず、それを見つめる勇気に欠けてゐた、といふのではない。実は、本来それを為すべき者は折口氏ではなしに、「息子」の春洋氏であつた。
長谷川氏は、ここで一見謎めいたことを言っています。ここで述べられていることをまっすぐに受けとめるならば、著者は、″新たな神学を打ち立てるのは、折口信夫にとってはなはだしい難事であって、実は「息子」の春洋にしかできないのだ″と言っているように読めますね。それは、いったいどうしてなのでしょうか。その謎解きは、デリダの『死を与える』を論じるときまで待たなければなりません。デリダはそこで『旧約聖書』の「イサク奉献」を取り上げるのですが、その詳細については、そこで説明しようと思います。(*と言いましたが、いま取り組み中の「その4」三島由紀夫編で、先取りしています。2013・12・25 記す)とりあえず端的に、著者は″イサクの父は、実のところ神学の真髄の内側に入ることができない。それができうるのは、息子のイサクである。折口信夫はあくまでも「イサクの父」の立場にあり、藤井春洋こそが「息子のイサク」立場にある。だから、折口が新らしい神学を打ち立てるのは構造的に不可能なのだ″と言っている、とだけ申し上げておきましょう。
次に対話者として登場するのは橋川文三です。長谷川氏によれば、橋川文三は、″「戦争体験」を「絶対的な戦争をやつた経験」として語らうとした人″です。私としても、それに異論はありません。保田与重郎を排撃・無視しようとする戦後の風潮のなかで『日本浪漫派批判序説』(一九五九年)を世に問い、自分はなにゆえ戦時中保田に強く惹かれ続けたのかをきちんと述べようとした橋川の心に、〈絶対的なものとしての大東亜戦争〉という観念があったことは間違いないと思われるからです。
橋川文三には、戦前と戦後をどうつなぐかという課題をめぐっての遠大な構想があったようです。彼は、戦前と戦後とを分断している、先の大戦と敗北という結末そのものの内に「超越的な価値」を見出そうとしました。つまり、戦前と戦後とを分断しているものの核心に両者をつなぐものを見出そうとしたのです。その分かりにくい難事を成し遂げなれば、両者はつながらないという確信が彼にはあったのでしょう。彼は、日本人が体験した戦争・敗戦と「イエスの死」とを対比させて、その分かりにくいことがらの重要性をなんとか伝えようとします。
私は、日本の精神伝統において、そのようなイエスの死の意味に当たるものを、太平洋戦争とその敗北の事実に求められないか、と考える。イエスの死がたんに歴史的事実過程であるのではなく、同時に、超越的原理過程を意味したと同じ意味で、太平洋戦争は、たんに年表上の歴史過程ではなく、われわれにとっての啓示の過程として把握されるのではないか。 (「『戦争体験』論の意味」)
著者の言葉を使うならば、橋川はここで、太平洋戦争とその敗北の事実を「神学的な領域」として把握し、そこに踏み込む入口に立っています。「イエスの死」を持ち出すことによって、彼がそのことをはっきりと自覚していたことが分かります。そういうアプローチをしなければ、その歴史過程を「超越的原理過程」としてつかみ取ることはかなわないことを、言いかえれば、戦前と戦後とをつなぐことはかなわないことを、彼はよく分かっていたのです。
しかるに、この論考が書かれてからおよそ二十年後の昭和五四年に、橋川は、次のような言葉をもらしています。
結局あの戦争はあったことはあったが、なかったといっても少しもかわらないことになる。 (41頁)
謎めいていて、また、相当に過激でもあるこの言葉を、著者は、次のように受けとめます。
これは、橋川氏の「戦争体験論」そのものの敗北宣言である。戦争体験のうちに「超越的意味」をさぐらうと求めつづけて、つひにその試み自体がつひえ去つたことを自ら認めた宣言である。(中略)けれども、見方を変へれば、橋川氏は自らのあの企てを忘れ去つてはゐなかつたのだ、といふことにもなる。「あの戦争」に、なにか超越的な意味をさぐらうとしつづけた人間でなければ、このやうなことは決して言へない。 (41頁~42頁)
自分の試みがどういう性格のものであるか十分に分かっていたはずなのに、橋川の試みはなにゆえ失敗してしまったのでしょうか。それは、「あの戦争」を太平洋戦争と呼んでしまったところに、致命的な誤りがあると著者は言います。著者によれば、この呼称を選んだ段階で、橋川はあらかじめ「戦争体験」をその内側からとことん掘り下げる道筋を放棄しているのです。
それは、橋川氏がいかなるイデオロギイ、いかなる歴史観にくみしてゐるか、といふこととは直接にかかはらない。それは、ただ端的な事実――「太平洋戦争」を体験した日本人はゐないといふ事実――によるのである。自ら積極的に戦争に参加した人であれ、不満をかかへつつそれを横目でながめてゐた人であれ、すべての日本人は「大東亜戦争」を体験したのであつて、それ以外ではない。 (40頁)
たかが呼称、されど呼称なのです。「あの戦争」について正鵠を射た問題意識を持ちながらも、橋川が呼称の問題につまずいて、戦争体験を徹底的に内側から掘り下げる道をまえもって自分から塞いでしまったという思想の悲劇に、私は、戦後の言語空間の歪みの強度のはなはだしさをあらためて感じる思いがします。
十月二十日に、私は、著者の長谷川三千子氏を交えての本書の読書会に参加しました。そのとき、当ブログに本書の書評をお書きになった由紀草一氏が、「自分が『軟弱者の戦争論』(2006)を書いたとき、大東亜戦争という呼称を使うのに、けっこう勇気が要った。それがいまでは、その呼称を使っても、そのときほどの抵抗感がない。そこに、時代の変化を感じる」という意味のことを言っていました。私なりの言い方をすれば、いまは以前とくらべると戦後の言語空間の歪みからいささかなりとも距離を置くことが可能になったのではないかと思われます。本書もまた、それを可能とすることに大いに貢献しているのではないでしょうか。私たちは、もう二度と、橋川文三の思想的悲劇を繰り返してはならないのです。 (続く)
長谷川三千子『神やぶれたまはず』について(その2)

私は、長谷川氏の文章にとても惹かれます。旧仮名遣いが特徴的なその文章には、独特の、読み手の身体性に心地よくなじむゆるやかなリズムがあって、いちどハマったらクセになってしまう、危険な文体でもあります。なんというか、読み進みながら、すぐ傍らで著者自身が丁寧に朗読している声が聴こえてくるような雰囲気が感じられるのです。それで、読書会のときに、ご本人にご自分の書き進めている文章は朗読して出来具合を確認していらっしゃるのかどうか訊いてみました。すると、「いい気になって書いた文章を翌日みると『ああダメだ』とガッカリしてしまうことがしょっちゅうです。何度も読み返してみて、こういう感じかなという感触が得られるところまで直します」という意味のことをおっしゃいました。それで、いま述べた、氏の文章を読み進めるときの自分の感触がこういうものだと正直に言ったところ、「そういう感じなら、私の読み返しはなんとか成功したのでしょう」とのお答えでした。氏の見事な文章の陰には、無限の推敲があることを知って、感慨を新たにしました。
さて、本文に戻りましょう。次に登場するのは、桶谷秀明の『昭和精神史』と『昭和精神史 戦後編』です。これらは、合わせると文庫版で約1300ページという膨大な量の書物であるのみならず、内容の点でも、昭和を生きた日本人の心の歴史を考えるうえで到底無視し得ない存在です。その意味で、桶谷のライフ・ワークとも言えるでしょうし、戦後の広い意味での思想史においても、ひとつの「事件」と形容しても過言ではなかろうと思われます。私が主宰している読書会でもかなり力を入れて取り上げたことがあり、読書仲間とかなり突っ込んだ話をし、その詳細にもいろいろと触れはしましたが、いまもっとも鮮やかに残っているのは、なぜか、桶谷の思想家としての孤独な精神の立ち姿です。お会いしたこともないし、いまどんな顔をしているのかもよく分からないのですが、それは確かなことです。
そういえば、その孤独な立ち姿は、どこか橋川文三のそれに通じるところがあるような印象があります。その印象には、おそらく根拠があって、ともに〈大東亜戦争の絶対性〉という神学的リアリティを懐深く抱いて戦中をくぐり抜け、そのまま戦後という精神的異空間に放り出された者に特有の孤独を刻印されている、ということなのでしょう。
いささか脇道にそれますが、それで思い出したのは、当ブログでも触れたことのある小野田寛郎氏の存在です。彼もまた、「〈大東亜戦争の絶対性〉という神学的リアリティを懐深く抱いて戦中をくぐり抜け、そのまま戦後という精神的異空間に放り出された者」のひとりです。ただし、彼の場合、本当にいきなり放り込まれた点と、戦後という精神的異空間が高度に確立された只中に放り込まれた点が、彼らとは違います。心の準備が一切できない状態で唐突に暴力的に放り込まれたのです。それを思うと、彼が抱いた孤独感には、到底余人にはうかがい知れない凄まじいものがあっただろうことが、戦争を知らない者にもじゅうぶんに分かるのではないでしょうか。と思うのですが、小野田氏が祖国に帰還してから一年足らずでそこを後にしたことを当時非難した者が少なからずいたそうです。それは、人の心をまったく思いやらない、野蛮で想像力のかけらもない言動にほかなりません。小野田氏のことについては、後にふたたび触れることがあるような気がします。
では、桶谷氏の敗戦時の精神の風景はどのようなものであったのでしょうか。長谷川氏は、次のような桶谷の印象深い文章にスポット・ライトを当てます。
敗戦の年、わたしは、北陸の山村にいて、芋がゆをすすりながら幼い弟妹を抱えていた母と、家族の生命を支えるために山の斜面のわずかな畠を耕す生活を送っていた。わたしは中学の二年になっていたが、数ヵ月前、中学を退学していた。乏しい食糧と農民の卑小な頑ななエゴイズムにとりかこまれた日常はやり切れなかった。召集された父はもはや帰らないと覚悟していた。じぶんについてはこの先どのようにして何年生きるなどという算段は問題外であった。
中学を退いたことをべつに残念ともおもわなかった。日本が永遠に亡びないと断定することは、わたしに生きることが無意味ではいと信じさせるに充分だった。
わたしは、この山村にいて、近く、竹槍をもって米ソの侵入軍と一戦をまじえ死ぬだけなのである。わたしの死地はこのやり切れない日常の世界であるはずだった。しかし、その日には、この日常世界は一変し、わたしたち日本人のいのちを、永遠に燃あがらせる焦土と化すであろう。わたしはそれを待っていた。 (本書96頁・『土着と情況』所収「原体験の方法化について」昭和37年 より)
ここには、耐えがたい日常を忍びながら、それが「わたしたち日本人のいのちを、永遠に燃あがらせる焦土と化す」ときを息を凝らすようにして待っているひとりの皇国少年がいます。桶谷は、皇国少年であることを脱した後においても、その姿をある確信を持って描き出しています。″あのときはオレもいっぱしの皇国少年でね″などと頭を書きながら弛緩した精神で描き出しているのではありません。では、その「確信」とは何なのでしょう。長谷川氏は、次の文章を引用することで、それを説明しています。
現在、わたしのモチーフの究極のところにあるのは、いかに強力な史観、いかに優勢な時代精神のもとにあろうと、ひとりの人間の原体験は、それらと同等の独立した価値をもつという確信である。(本書100頁・従前)
ここで桶谷は、思想なるものに何かしらの形で関わろうとする者にとって、きわめて重要なことに触れています。彼が言わんとしていることを私なりに言いかえると、次のようになります。すなわち、″戦後は、命至上主義の世界であり、その考え方が圧倒的に優勢を占めている。しかるに、自分が皇国少年であった戦中においては、いかに死ぬかということが何より大事であった。それは、戦後思想からすれば、一顧だにされる必要のない、唾棄すべき全否定の対象となるほかはない。しかし、戦中における自分の精神の相貌には、自分の全存在の重量がかかっていた。そのことが自分にとって決定的な何かであることは間違いない。それゆえ、ものごとを突き詰めて考える場合、必ずといっていいほどに、自分の心はそこへ舞い戻る。その不可避の精神の在り処を自分は原体験と呼ぶほかはない。それを戦後思想的価値観に無造作に譲り渡すことは、自分で自分の首を締める振る舞いに等しい。そんなことは断じてできない″私は、桶谷の言葉をそういうものとして受けとめます。
そういう確信を持っているからこそ、桶川は、伊東静雄が日記に記した神話的な〈八月十五日のアーキタイプ〉について、次のように述べることができるのではないでしょうか。
この(伊東静雄の日記に記された神話的な原風景における――引用者補)内部感覚は、八月十五日からこの半月のあひだに、詔書を奉じ、国体護持を信じて生の方へ歩きだした多くの日本人と、すべてがをはつたと思ひ生命を絶つた日本人との結節点を象徴してゐるやうに思はれる。 (本書103頁・『昭和精神史』より)
この箇所について、長谷川氏は次のように述べています。
敗戦後の日本人をこのやうに二分法でとらへた人を、私はほかに知らない。あとで見るとほり、多くの人々が戦後の日本人のあり方をさまざまに分類し、評論してきたのであるが、言ふならば、それはすべて「生の方へ歩きだした」日本人のなかでの分類にすぎない。「生の方へ歩きだした」日本人を丸ごとひとまとめにして、敗戦後に生命を絶つた日本人と並べ置くといふ対比の仕方は、他に例を見ないものと言つてよい。 (本書104頁)
管見の限りですが、私もほかには知りません。この二分法は、〈大東亜戦争の絶対性〉がキー・ワードになるものと思われます。つまり桶谷は、大東亜戦争の最中にその絶対性に殉じた戦死者に、戦後において自ら命を絶つことで連なった日本人と、そうすることなく「生の方へ歩きだした」日本人とを対比させているのです。ここでひとつお断りしておきたいのは、私はなにも、大東亜戦争における戦死者が皆その絶対性に殉じたといいたいのではなくて、戦後において大東亜戦争を意識しながら自ら命を絶った日本人の心中には、その戦争の最中にその絶対性に殉じた戦死者の姿があっただろうことが申し上げたいだけです。さらには、どっちがいいとかわるいとかの問題ではないことも、誤解を恐れるがゆえに付け加えておきます。
長谷川氏は、この二分法をとても重視しているように感じます。つまり、敗戦という歴史的な事実に、〈大東亜戦争の絶対性〉に殉じた、広い意味での戦死者の存在が内在していることに対する感度があまり鋭くない思想家や文学者を、著者は、あまり評価していないように感じられるのです。その感度を、戦友感覚と言いかえると、少なくとも『戦後史の空間』の磯田光一には戦友感覚があまり感じられないし、石原慎太郎に至ってはまったくと言っていいほどに感じられないとして、本書においてかなり厳しい評価を下しているのです。彼らは、〈大東亜戦争の絶対性〉の問題をそれほどあるいはまったくといっていいほどに引きずることなく戦後空間に歩みだしているようなのです。それに対して、これまで取り上げた思想家や文学者には、鋭い戦友感覚があるとして高く評価しています。また、これから取り上げることになる太宰治や吉本隆明や三島由紀夫にも鋭い戦友感覚があるとされ、本格的な検討の対象になっているのです。彼らの戦後とは、敗戦のもたらした精神的な麻痺との悪戦苦闘の歴史であると申し上げても過言ではない、ということです。著者は、どうやら彼らのそこに向けて目を凝らしているようなのです。
桶谷秀明に、話を戻しましょう。桶谷は、先ほど述べたような敗戦の原風景に関する「確信」をさらに大きく独特の歴史観の形に広げて、『昭和精神史』と『昭和精神史 戦後篇』を著しました。これらの著書で、桶谷は八月十五日をどう描いたのでしょうか。著者が引用した箇所を孫引きしましょう。
八月十五日正午、昭和天皇の終戦の詔勅を聴いて、多くの日本人がおそはれた″呆然自失″といはれる瞬間、極東日本の自然民族が、非情な自然の壁に直面したかのやうな、言葉にならぬ、ある絶対的な瞬間について考へた。そのとき、人びとは何を聴いたのか。あのしいんとした静けさの中で何がきこえたのであらうか。
『天籟』(てんらい)を聴いたのである、と私は(『昭和精神史』の第二〇章で――引用者補)書いた。天籟とは、荘子の『斉物論』に出てくる言葉で、ある隠者が突然、それを聴いたといふ。そのとき、彼は天を仰いで静かに息を吐いた。そのときの彼の様子は、『形は槁木の如く、心は死灰の如く』『吾、我を喪ふ』てゐるやうであつたといふ。
そういう状態でなければ『天籟』は聞こえない、と荘子は隠者の口を通して語つてゐる。 (本書61頁 『昭和精神史 戦後篇』より)
桶谷は、八月十五日正午、日本人は、昭和天皇が終戦の詔書を読み上げるのを聴きながら、音なき音としての「天籟」を聴いた、と言うのです。ふつうに考えれば、そう言われて「そうですか」と素直に納得してうなずく読み手はいないでしょう。平成三~四年当時の人々は、この言葉に触れて、はじめはキョトンとし、やがて、著者に対して憐憫の情を抱くか、何もなかったことにするかのいずれかだったでしょう。たとえ、他の箇所に大いに感動していたとしてもです。
私自身、読書会でつぶさに内容を検討した気でいましたが、残念ながら「天籟」という言葉の印象はあまり残っていなくて、せいぜい、桶谷好みのレトリックが使われているのだろうくらいにしか受け取らなかったと思います。桶谷自身、「だから、どうしたといふのか。そんな怪訝をともなふ反感あるいは薄ら笑ひを、私はたびたび経験したが、賛意をつたへてくれた人はひとりもゐなかつた」と言っているくらいです。さらには、「私のいつてゐることは独断妄念にすぎないのであらうか」とまで突き詰めています。ここで桶谷は、孤独な想念を抱いた者が不可避的に襲われる不安を率直に語っています。
その不安を払拭するかのように、桶谷は、「天籟」という言葉で自分が指し示そうとした事態に同じように気づいたと思われる四人の文章を引用します。それは、昭和二十年九月五日の朝日新聞の社説の筆者と伊東静雄の前回引用した日記の一節と河上徹太郎の文章と太宰治の小説「トカトントン」です。
河上徹太郎の名とその文章のごく一部分は、前回の当文章に出てきましたが、とても重要なものなので、ここできちんと掲げておきましょう。
国民の心を、名も形もなく、ただ在り場所をはつきり抑へねばならない。幸ひ我々はその瞬間を持つた。それは、八月十五日の御放送の直後の、あのシーンとした国民の心の一瞬である。理屈をいひ出したのは十六日以後である。あの一瞬の静寂に間違ひはなかつた。又、あの一瞬の如き瞬間を我々民族が曾て持つたか、否、全人類の歴史であれに類する時が幾度あつたか、私は尋ねたい。御望みなら私はあれを国民の天皇への帰属の例証として挙げようとすら決していはぬ。ただ国民の心といふものが紛れもなくあの一点に凝集されたといふ厳然たる事実を、私は意味深く思ひ起こしたいのだ。今日既に我々はあの時の気持ちと何と隔たりが出来たことだらう! (本書50頁 「ジャーナリズムと国民の心」より)
河上徹太郎の文章を真正面から受けとめるならば、桶谷が「天籟」という言葉によって指し示そうとした何かとても重要なことが、八月十五日には確かにあるようです。それは、伊東静雄が詩的直観によって神話的なアーキタイプとして定着したイメージともどうやら深い関連がありそうでもあります。そこまでは、おぼろげながら私にも分かってきました。
長谷川氏は、現存する思想家ではおそらくただひとり、桶谷の「天籟」という言葉には、八月十五日の謎を解明するうえで極めて重要な手がかりがあることを直観し、深く洞察し、それを読み手がきちんと読めば分かる表現にまで十年の歳月をかけてゆっくりと練り上げたのです。それが、本書の価値の核心をなすものです。しかし、私たちがそこにしっかりとした足取りでたどり着くまでには、太宰治、吉本隆明、三島由紀夫という三つの山を越えた後、『旧約聖書』の「イサク奉献」という峠を越えなければなりません。太宰治の「トカトントン」については、次回に取り上げることにして、差し当たり、次の引用をしておきましょう。文章中の「佐藤氏」とは、『八月十五日の神話』を書いた佐藤卓巳のことです。
佐藤氏は、竹山昭子氏の『玉音放送』を引用して、「この放送の祭儀的性格」を指摘する。すなわち、それは単なる「降伏の告知」ではなく、「各家庭、各職場に儀式空間をもたらした」出来事であり、この放送を通じて国民全体が「儀式への参加」をした。だからこそそれが「忘れられない集合的記憶の核として残った」のだ、と佐藤氏は述べるのである。さらに氏は「この場合、昭和天皇が行使したのは、国家元首としての統治権でも大元帥の統帥権でもなく、古来から続いた祭司王としての祭祀大権であった」と述べて、この八月十五日の玉音放送が徹頭徹尾〈神学的〉な出来事であつたことを指摘してゐるのである。
これはきはめて重要な正しい認識であり、あの「シーンとした国民の一瞬」の謎を考へる上でも、出発点とすべきところである。 (本書69頁)
「八月十五日の玉音放送が徹頭徹尾〈神学的〉な出来事であつた」というキー・センテンスを手放さないようにしながら、私たちは次の「その3」で、太宰の「トカトントン」の音に耳を澄ませてみることにしましょう。 (続く)
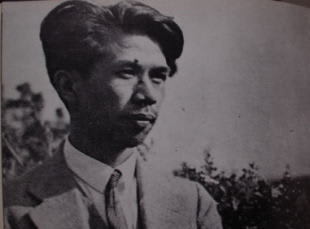
詩人・伊東静雄
かつて私は、当ブログで木下恵介の『陸軍』を論じたことがあります。http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/7ad13147688249e05a2d76171e2ec640 そのおり、当作品には本当の意味での反戦文学の契機が存すると述べました。また私たちが、反戦の意味を本気でつかもうと思うのならば、大東亜戦争の真っ只中に飛び込んでいって、かつての日本人たちとともに戦い、ともにもみくちゃになり、ともに敗戦のときを迎えるよりほかはないという意味のことを述べました。そうしてそれは、戦争を経験していない者にとっては、本質的に想像力の問題である、とも。戦後において流通している俗流歴史観によれば、反戦思想は、過ちの歴史を二度と繰り返さないという決意を固めることによって育まれるとされるのですが、私は、その「過ちの歴史」を何度でもくぐり抜ける観念の旅を敢行することによってしか、真の反戦思想は掴み取りえないと考えたわけです。
そこには、戦後に流通した「反戦」なる概念のまがい物性を否定的に乗り越えたいという私なりの思いがありました。もっと踏み込んで言ってしまえば、自由・平等・人権・平和などという、戦後に流通し続けてきた肯定的諸価値に対する疑念が湧いてくるのをいかんともしがたいという思いがありました。そういう諸価値に安住していられれば、どれほど楽に生きられるだろう、ということでもあります。何の因果で、かくも疑い深くなってしまったのか、自分のことながらどう考えてみてもよくわからないところがあるのです。私の場合、いわゆる保守思想にアクセスする以前からそうなのです。私には、そういう諸価値に何の疑いも持たずにそれらに基づいて言説を展開しようとする論者のナイーヴさに対する抜きがたい違和感や、さらには嫌悪感さえもがあります。そういう論者は、一種の「思想の敗戦利得者」の姿として私の目には映るのです。それは自分でも処理し難い激しい情念です。そこだけ取り出して言うならば、パリサイびとの偽善を激しく非難するイエスの気持ちが分かるほどです。
話を戻しましょう。反戦なるものにまつわって、そういうことを考えてはみたものの、そういう意味での想像力を発揮することは、実のところ言うは易く行うは難しなのです。なかなかその先へ進むことがかなわないままに、いたずらに時が過ぎていきました。
一国の歴史のうちには、ちやうど一人の人間の人生のうちにおいてもさうであるやうに、或る特別の瞬間といふものが存在する。
上記は、見返しと扉をめくった本書の「序」の冒頭です。それがすっと目に飛び込んできたとき、私は心の片隅に震えのようなものを感じました。それをあえて言葉にすれば、次のようになります。「お前はこれから日本の歴史においてとても重要なことを目撃する観念の旅を始めることになる。そうしてそれは、お前が考えようとして考えあぐねていたことに大いに関係のある旅である」。珍しいことに、そういう直観が働いたのです。
幸運なことに、その直観は当たっていました。だから、本書は私にとても実り多いものをもたらしてくれました。むろん、その分大きな課題も残されました。それらが具体的にはどういうことなのかをお伝えするのが、この文章の柱となるのでしょう。
本書は、文中の「ある特別な瞬間」とは何であり、そこで実は何が起こったのかにきっちりと答えています。というより、本書の論点はあえてその一点にぎゅっと絞り込まれています。著者ご自身によれば、それに直接関連しない事柄は、思いきりよくバッサバッサと刈り込まれました。だから、本書を読み終えた者は、それを肯定的に受け入れるにしても逆に拒否するにしても、本書から輪郭のくっきりとした歴史の一瞬の鮮烈なイメージを受け取ることは間違いありません。その意味で、本書は「読み手に、伝えたいことの核心だけを伝える」という書き手の姿勢が感じられて実に清々しいし、言っていることの責任の所在がはっきりしてもいます。それに対して批判的なアプローチが可能なのは分かりますが、私は、むしろ著者の潔いスタンスを諒とする者です。知性なるものは、懐疑においてよりもむしろ他を捨ててひとつのことを選ぶ決断においてこそ高度に発揮されるものであると思うからです。別言すれば、考えることは一定の決断に向けて開かれたものであることが必要である。なぜなら、そうであってこそ、言論の本当の意味での責任が生まれるからである。そう思うのです。
「ある特別な瞬間」とは何であり、そこで実は何が起こったのかについてとりあえずさわり程度に触れておきましょう。
「ある特別な瞬間」とは、一九四五年八月十五日正午に日本国民がラジオで昭和天皇の「終戦の詔書」を聴いたときに、国民の心のなかで起こったことを指しています。では、いったい何が起こったのでしょうか。著者は、それを語り切るために、戦後日本の選りすぐりの思想家たちとの語らいに十年の歳月をかけました。もちろん、ずっとかかりっきりというわけではなくて、気長に折に触れてという形だったのでしょうが、本書と取り組みはじめてから十年の歳月が流れたのは確かなことです。本書には、それだけの膨大な時間が織り込まれているのです。三〇五ページの、分厚いとは言えないほどの分量なのですが、読後、もっと大部の本を読んだような感触が残るのは、そういう事情があるからなのではないでしょうか。その歳月分の重みを尊重するならば、先の「国民の心のなかで起こったこと」をあっさりとここで言ってしまうことを、私はいささかためらってしまいます。もったいぶるわけではなくて、そうしてしまうと、それをはじめてご覧になった方(それを想定して、この文章を書いています)は、おそらく字面だけは追えるものの本当のところ何が何だかわからないのではないかと思われるからです。それではあまりにもったいない。
そこで、必要最小限のまわり道をして、著者の対話の相手となった思想家たちとのやり取りのポイントを順次押さえながら、そのとき「国民の心のなかで起こったこと」に肉薄して行こうと思います。そんな流れをたどることで、読み手が、本書の提示した鮮やかなイメージを等身大で受けとめることが可能になれば、私としては本望です。むろん、それを受け入れるにしろ、拒否するにしろ、ということです。そうして、それは私自身の問題でもあるので、出来うる限りそのイメージに対する私のスタンスも明らかにするよう心がけましょう。また、その一連の試みが、本書の単なる祖述に終わってしまったのではつまりませんから、折に触れて私見を織り込むことにします。もしもウザイと感じられたならば、そこは読み飛ばしていただいてもけっこうです。
著者の対話の相手を、掲載順に列挙しましょう。折口信夫、橋川文三、桶谷秀明、河上徹太郎、太宰治、伊東静雄、磯田光一、吉本隆明、三島由紀夫、そうしてデリダ。
あらかじめ申し上げておけば、吉本隆明や三島由紀夫との対話が最大のポイントになります。また、それらの重要性をくっきりとあぶり出すために、著者は、デリダの『死を与える』に焦点を当てようとします。その過程で図らずも、思想家としての吉本の価値と三島の『英霊の聲』の評価をめぐって、読み手は重大な視線変更を余儀なくされます。むろん、そのほかの思想家についても同じことが言えます。その意味で本書は、戦後においてもっとも考えるべきことをどこまで深く考えているかという観点から、戦後の諸思想家の大胆な読みかえ作業、さらには、戦後思想のパラダイム変更を敢行しているともいえるでしょう。本書は、思想書としてとても刺激的で挑戦的な本なのです。
それでは、そろそろ本文に入ってゆきましょう。
本文の冒頭に登場するのは、折口信夫が戦後まもなくに書いた詩「神 やぶれたまふ」です。
「神やぶれたまふ」
神こゝに 敗れたまひぬ─。
すさのをも おほくにぬしも
青垣の内つ御庭(ミニハ)の
宮出でゝ さすらひたまふ─。
くそ 嘔吐(タグリ) ゆまり流れて
蛆 蠅(ハヘ)の、集(タカ)り 群起(ムラダ)つ
直土(ヒタツチ)に─人は臥(コ)ひ伏し
青人草(アヲヒトグサ) すべて色なし─。
村も 野も 山も 一色(ヒトイロ)─
ひたすらに青みわたれど
たゞ虚し。青の一色
海 空もおなじ 青いろ─。
著者は、「ここには、絶望の極まつた末の美しさ、酸鼻のきわみのはてに現はれる森と静まりかえつた美しさといふものがあ」り、「昭和二十年八月十五日正午の、『あのシーンとした国民の心の一瞬』のかたち」があると評します。「あのシーンとした国民の心の一瞬」とは、河上徹太郎が敗戦後ほどなく書いた「ジャーナリズムと国民の心」の一節であり、後に桶谷秀明によって『昭和精神史 戦後篇』(平成十二年)に再録されることになったものでもあります。詩の終末部の青のイメージには、八月十五日の快晴のそれが織り込まれています。そのイメージは、詩人・伊東静雄の日記の次の一節にもはっきりと顔をのぞかせています。
十五日陛下の御放送を拝した直後。
太陽の光は少しもかはらず、透明に強く田と畑の面を木々を照し、白い雲は静かに浮かび、家々からは炊煙がのぼつてゐる。それなのに、戦は敗れたのだ。何の異変も自然に起こらないのが信ぜられない。 (101頁)
この一節に込められた不可思議な激情が、時の風化作用を経てなおも遠く残響として残ったときに、それは、次のような世にも美しい叙情詩として結晶しました(この詩は本書からの引用ではありません)。
夏の終り
夜来の颱風にひとりはぐれた白い雲が
気のとほくなるほど澄みに澄んだ
かぐわしい大気の空をながれてゆく
太陽の燃えかがやく野の景観に
それがおほきく落とす静かな翳は
……さよなら……さやうなら……
……さよなら……さやうなら……
いちいちさう頷く眼差のやうに
一筋ひかる街道をよこぎり
あざやかな暗緑の水田(みずた)の面を移り
ちひさく動く行人をおひ越して
しづかにしづかに村落の屋根屋根や
樹上にかげり
……さよなら……さやうなら……
……さよなら……さやうなら……
ずっとこの会釈をつづけながら
やがて優しくわが視野から遠ざかる
(詩集『反響』創元社・一九四七年 より)
「気のとほくなるほど澄みに澄んだ/かぐわしい大気の空をながれてゆく」「白い雲」。このイメージの淵源は、上記の日記の一節の「太陽の光」が「透明に強く田と畑の面を木々を照」す中に「静かに浮か」ぶ「白い雲」に求めることができるでしょう。動いているかとどまっているかの印象の違いはありますが、前者に〈時の流れ〉を織り込めば後者になると解釈すると、両者はスムーズにつながるのではないでしょうか。
私が頭をつっこみかけているのは一種の作品論ですから、異論があるのは承知していますが、要は、伊東静雄にとって、八月十五日の森とした青空のイメージが、一種のアーキタイプ(元型)のようなものとして心の奥深くに貼り付いてしまったことが確認できれば、私としてはそれでいいのです。そうでなければ、「夏の終わり」のような決定的で鮮やかな印象を与える叙情詩を書くことは不可能であると思います。
そうして、その同じ事態が、伊東静雄のみならず、折口信夫にも、橋川文三にも、桶谷秀明にも、太宰治にも、吉本隆明にも、三島由紀夫にも、それぞれ個性の数だけのバリエーションを伴いながらも、シンクロニシティ(意味のある偶然の一致)の形で起こった。本書は、そのように読み手に語りかけ、そのことの深い意味合いの気づきに読み手を誘い込んで行こうとするのです(磯田光一を外したのには、後述しますが、訳があります)。
流石に折口は、著者によれば、敗戦のアーキタイプの意味をきちんとつかんでいます。彼は、敗戦の只中から、新しい神学を打ち立てる必要性を悟り、学生たちに「あなたがたの中に、神道の建設に情熱を向ける者が出てもらいたい」と熱をこめて語りかけているのです。
しかし折口の「新しい神学」を打ち立てる試みは挫折しました。それは何故なのでしょうか。その理由を語るには、彼の愛弟子の春洋(はるみ)のことに触れないわけにはいません。
本書によれば、石川県能登半島生まれの「藤井春洋は二十一歳のときから折口の家に身を寄せ、出征まであしかけ十六年間、生活をともにしつつ折口の薫陶を受けた、文字通りの愛弟子」です。折口の同性愛的な傾向を考えれば、当然肉体関係もあったのでしょう。そんな存在であった春洋が、一九四三年、二度目の召集を受け、金沢歩兵聯隊に入営し、四四年七月、硫黄島に着任し、陸軍中尉を拝命するのですが、同月に、折口信夫の養子として入籍します。本書によれば、「氏にとって藤井春洋氏を失ふといふことは、我が子を失ふことであると同時に自らの学問の後継者を失ふことであり、また自らの生活そのものを失ふことでもあった」とあります。まったくもって、そのとおりだったことでしょう。四五年三月十九日、春洋は硫黄島にて戦死しますが、それを知った後の折口の取り乱しぶり、落胆ぶりは、身も世もないほどのものだったようです。そうして彼は、死に至るまでついにその精神的な打撃から回復することがかなわなかったようでもあります。折口は春洋の故郷の能登一ノ宮に父子の墓を建て、次のような碑文を刻んでいます。
もっとも苦しき たたかひに 最もくるしみ 死にたる
むかしの陸軍中尉 折口春洋 ならびにその 父 信夫の墓
この碑文は、折口の心にぽっかりと空いた傷口が遂にふさがらないまま鮮血を流し続けたことを生々しく伝えています。こうしたことを踏まえたうえで、長谷川氏は次のように述べます。
折口信夫氏は、明らかにその(すなわち、大東亜戦争の――引用者補)「絶対的なもの」を垣間見てゐた。さもなければ、あの「神 やぶれたまふ」のやうな詩が書けたはずもないし、また「神道宗教化」を言ひ出したはずもない。しかし、氏にとって、その「絶対的なもの」をそれとしてつかみ出すのは、ほとんど構造的に不可能なことであつた。単に、折口氏が自らの悲歎をのりきることができず、それを見つめる勇気に欠けてゐた、といふのではない。実は、本来それを為すべき者は折口氏ではなしに、「息子」の春洋氏であつた。
長谷川氏は、ここで一見謎めいたことを言っています。ここで述べられていることをまっすぐに受けとめるならば、著者は、″新たな神学を打ち立てるのは、折口信夫にとってはなはだしい難事であって、実は「息子」の春洋にしかできないのだ″と言っているように読めますね。それは、いったいどうしてなのでしょうか。その謎解きは、デリダの『死を与える』を論じるときまで待たなければなりません。デリダはそこで『旧約聖書』の「イサク奉献」を取り上げるのですが、その詳細については、そこで説明しようと思います。(*と言いましたが、いま取り組み中の「その4」三島由紀夫編で、先取りしています。2013・12・25 記す)とりあえず端的に、著者は″イサクの父は、実のところ神学の真髄の内側に入ることができない。それができうるのは、息子のイサクである。折口信夫はあくまでも「イサクの父」の立場にあり、藤井春洋こそが「息子のイサク」立場にある。だから、折口が新らしい神学を打ち立てるのは構造的に不可能なのだ″と言っている、とだけ申し上げておきましょう。
次に対話者として登場するのは橋川文三です。長谷川氏によれば、橋川文三は、″「戦争体験」を「絶対的な戦争をやつた経験」として語らうとした人″です。私としても、それに異論はありません。保田与重郎を排撃・無視しようとする戦後の風潮のなかで『日本浪漫派批判序説』(一九五九年)を世に問い、自分はなにゆえ戦時中保田に強く惹かれ続けたのかをきちんと述べようとした橋川の心に、〈絶対的なものとしての大東亜戦争〉という観念があったことは間違いないと思われるからです。
橋川文三には、戦前と戦後をどうつなぐかという課題をめぐっての遠大な構想があったようです。彼は、戦前と戦後とを分断している、先の大戦と敗北という結末そのものの内に「超越的な価値」を見出そうとしました。つまり、戦前と戦後とを分断しているものの核心に両者をつなぐものを見出そうとしたのです。その分かりにくい難事を成し遂げなれば、両者はつながらないという確信が彼にはあったのでしょう。彼は、日本人が体験した戦争・敗戦と「イエスの死」とを対比させて、その分かりにくいことがらの重要性をなんとか伝えようとします。
私は、日本の精神伝統において、そのようなイエスの死の意味に当たるものを、太平洋戦争とその敗北の事実に求められないか、と考える。イエスの死がたんに歴史的事実過程であるのではなく、同時に、超越的原理過程を意味したと同じ意味で、太平洋戦争は、たんに年表上の歴史過程ではなく、われわれにとっての啓示の過程として把握されるのではないか。 (「『戦争体験』論の意味」)
著者の言葉を使うならば、橋川はここで、太平洋戦争とその敗北の事実を「神学的な領域」として把握し、そこに踏み込む入口に立っています。「イエスの死」を持ち出すことによって、彼がそのことをはっきりと自覚していたことが分かります。そういうアプローチをしなければ、その歴史過程を「超越的原理過程」としてつかみ取ることはかなわないことを、言いかえれば、戦前と戦後とをつなぐことはかなわないことを、彼はよく分かっていたのです。
しかるに、この論考が書かれてからおよそ二十年後の昭和五四年に、橋川は、次のような言葉をもらしています。
結局あの戦争はあったことはあったが、なかったといっても少しもかわらないことになる。 (41頁)
謎めいていて、また、相当に過激でもあるこの言葉を、著者は、次のように受けとめます。
これは、橋川氏の「戦争体験論」そのものの敗北宣言である。戦争体験のうちに「超越的意味」をさぐらうと求めつづけて、つひにその試み自体がつひえ去つたことを自ら認めた宣言である。(中略)けれども、見方を変へれば、橋川氏は自らのあの企てを忘れ去つてはゐなかつたのだ、といふことにもなる。「あの戦争」に、なにか超越的な意味をさぐらうとしつづけた人間でなければ、このやうなことは決して言へない。 (41頁~42頁)
自分の試みがどういう性格のものであるか十分に分かっていたはずなのに、橋川の試みはなにゆえ失敗してしまったのでしょうか。それは、「あの戦争」を太平洋戦争と呼んでしまったところに、致命的な誤りがあると著者は言います。著者によれば、この呼称を選んだ段階で、橋川はあらかじめ「戦争体験」をその内側からとことん掘り下げる道筋を放棄しているのです。
それは、橋川氏がいかなるイデオロギイ、いかなる歴史観にくみしてゐるか、といふこととは直接にかかはらない。それは、ただ端的な事実――「太平洋戦争」を体験した日本人はゐないといふ事実――によるのである。自ら積極的に戦争に参加した人であれ、不満をかかへつつそれを横目でながめてゐた人であれ、すべての日本人は「大東亜戦争」を体験したのであつて、それ以外ではない。 (40頁)
たかが呼称、されど呼称なのです。「あの戦争」について正鵠を射た問題意識を持ちながらも、橋川が呼称の問題につまずいて、戦争体験を徹底的に内側から掘り下げる道をまえもって自分から塞いでしまったという思想の悲劇に、私は、戦後の言語空間の歪みの強度のはなはだしさをあらためて感じる思いがします。
十月二十日に、私は、著者の長谷川三千子氏を交えての本書の読書会に参加しました。そのとき、当ブログに本書の書評をお書きになった由紀草一氏が、「自分が『軟弱者の戦争論』(2006)を書いたとき、大東亜戦争という呼称を使うのに、けっこう勇気が要った。それがいまでは、その呼称を使っても、そのときほどの抵抗感がない。そこに、時代の変化を感じる」という意味のことを言っていました。私なりの言い方をすれば、いまは以前とくらべると戦後の言語空間の歪みからいささかなりとも距離を置くことが可能になったのではないかと思われます。本書もまた、それを可能とすることに大いに貢献しているのではないでしょうか。私たちは、もう二度と、橋川文三の思想的悲劇を繰り返してはならないのです。 (続く)
長谷川三千子『神やぶれたまはず』について(その2)

私は、長谷川氏の文章にとても惹かれます。旧仮名遣いが特徴的なその文章には、独特の、読み手の身体性に心地よくなじむゆるやかなリズムがあって、いちどハマったらクセになってしまう、危険な文体でもあります。なんというか、読み進みながら、すぐ傍らで著者自身が丁寧に朗読している声が聴こえてくるような雰囲気が感じられるのです。それで、読書会のときに、ご本人にご自分の書き進めている文章は朗読して出来具合を確認していらっしゃるのかどうか訊いてみました。すると、「いい気になって書いた文章を翌日みると『ああダメだ』とガッカリしてしまうことがしょっちゅうです。何度も読み返してみて、こういう感じかなという感触が得られるところまで直します」という意味のことをおっしゃいました。それで、いま述べた、氏の文章を読み進めるときの自分の感触がこういうものだと正直に言ったところ、「そういう感じなら、私の読み返しはなんとか成功したのでしょう」とのお答えでした。氏の見事な文章の陰には、無限の推敲があることを知って、感慨を新たにしました。
さて、本文に戻りましょう。次に登場するのは、桶谷秀明の『昭和精神史』と『昭和精神史 戦後編』です。これらは、合わせると文庫版で約1300ページという膨大な量の書物であるのみならず、内容の点でも、昭和を生きた日本人の心の歴史を考えるうえで到底無視し得ない存在です。その意味で、桶谷のライフ・ワークとも言えるでしょうし、戦後の広い意味での思想史においても、ひとつの「事件」と形容しても過言ではなかろうと思われます。私が主宰している読書会でもかなり力を入れて取り上げたことがあり、読書仲間とかなり突っ込んだ話をし、その詳細にもいろいろと触れはしましたが、いまもっとも鮮やかに残っているのは、なぜか、桶谷の思想家としての孤独な精神の立ち姿です。お会いしたこともないし、いまどんな顔をしているのかもよく分からないのですが、それは確かなことです。
そういえば、その孤独な立ち姿は、どこか橋川文三のそれに通じるところがあるような印象があります。その印象には、おそらく根拠があって、ともに〈大東亜戦争の絶対性〉という神学的リアリティを懐深く抱いて戦中をくぐり抜け、そのまま戦後という精神的異空間に放り出された者に特有の孤独を刻印されている、ということなのでしょう。
いささか脇道にそれますが、それで思い出したのは、当ブログでも触れたことのある小野田寛郎氏の存在です。彼もまた、「〈大東亜戦争の絶対性〉という神学的リアリティを懐深く抱いて戦中をくぐり抜け、そのまま戦後という精神的異空間に放り出された者」のひとりです。ただし、彼の場合、本当にいきなり放り込まれた点と、戦後という精神的異空間が高度に確立された只中に放り込まれた点が、彼らとは違います。心の準備が一切できない状態で唐突に暴力的に放り込まれたのです。それを思うと、彼が抱いた孤独感には、到底余人にはうかがい知れない凄まじいものがあっただろうことが、戦争を知らない者にもじゅうぶんに分かるのではないでしょうか。と思うのですが、小野田氏が祖国に帰還してから一年足らずでそこを後にしたことを当時非難した者が少なからずいたそうです。それは、人の心をまったく思いやらない、野蛮で想像力のかけらもない言動にほかなりません。小野田氏のことについては、後にふたたび触れることがあるような気がします。
では、桶谷氏の敗戦時の精神の風景はどのようなものであったのでしょうか。長谷川氏は、次のような桶谷の印象深い文章にスポット・ライトを当てます。
敗戦の年、わたしは、北陸の山村にいて、芋がゆをすすりながら幼い弟妹を抱えていた母と、家族の生命を支えるために山の斜面のわずかな畠を耕す生活を送っていた。わたしは中学の二年になっていたが、数ヵ月前、中学を退学していた。乏しい食糧と農民の卑小な頑ななエゴイズムにとりかこまれた日常はやり切れなかった。召集された父はもはや帰らないと覚悟していた。じぶんについてはこの先どのようにして何年生きるなどという算段は問題外であった。
中学を退いたことをべつに残念ともおもわなかった。日本が永遠に亡びないと断定することは、わたしに生きることが無意味ではいと信じさせるに充分だった。
わたしは、この山村にいて、近く、竹槍をもって米ソの侵入軍と一戦をまじえ死ぬだけなのである。わたしの死地はこのやり切れない日常の世界であるはずだった。しかし、その日には、この日常世界は一変し、わたしたち日本人のいのちを、永遠に燃あがらせる焦土と化すであろう。わたしはそれを待っていた。 (本書96頁・『土着と情況』所収「原体験の方法化について」昭和37年 より)
ここには、耐えがたい日常を忍びながら、それが「わたしたち日本人のいのちを、永遠に燃あがらせる焦土と化す」ときを息を凝らすようにして待っているひとりの皇国少年がいます。桶谷は、皇国少年であることを脱した後においても、その姿をある確信を持って描き出しています。″あのときはオレもいっぱしの皇国少年でね″などと頭を書きながら弛緩した精神で描き出しているのではありません。では、その「確信」とは何なのでしょう。長谷川氏は、次の文章を引用することで、それを説明しています。
現在、わたしのモチーフの究極のところにあるのは、いかに強力な史観、いかに優勢な時代精神のもとにあろうと、ひとりの人間の原体験は、それらと同等の独立した価値をもつという確信である。(本書100頁・従前)
ここで桶谷は、思想なるものに何かしらの形で関わろうとする者にとって、きわめて重要なことに触れています。彼が言わんとしていることを私なりに言いかえると、次のようになります。すなわち、″戦後は、命至上主義の世界であり、その考え方が圧倒的に優勢を占めている。しかるに、自分が皇国少年であった戦中においては、いかに死ぬかということが何より大事であった。それは、戦後思想からすれば、一顧だにされる必要のない、唾棄すべき全否定の対象となるほかはない。しかし、戦中における自分の精神の相貌には、自分の全存在の重量がかかっていた。そのことが自分にとって決定的な何かであることは間違いない。それゆえ、ものごとを突き詰めて考える場合、必ずといっていいほどに、自分の心はそこへ舞い戻る。その不可避の精神の在り処を自分は原体験と呼ぶほかはない。それを戦後思想的価値観に無造作に譲り渡すことは、自分で自分の首を締める振る舞いに等しい。そんなことは断じてできない″私は、桶谷の言葉をそういうものとして受けとめます。
そういう確信を持っているからこそ、桶川は、伊東静雄が日記に記した神話的な〈八月十五日のアーキタイプ〉について、次のように述べることができるのではないでしょうか。
この(伊東静雄の日記に記された神話的な原風景における――引用者補)内部感覚は、八月十五日からこの半月のあひだに、詔書を奉じ、国体護持を信じて生の方へ歩きだした多くの日本人と、すべてがをはつたと思ひ生命を絶つた日本人との結節点を象徴してゐるやうに思はれる。 (本書103頁・『昭和精神史』より)
この箇所について、長谷川氏は次のように述べています。
敗戦後の日本人をこのやうに二分法でとらへた人を、私はほかに知らない。あとで見るとほり、多くの人々が戦後の日本人のあり方をさまざまに分類し、評論してきたのであるが、言ふならば、それはすべて「生の方へ歩きだした」日本人のなかでの分類にすぎない。「生の方へ歩きだした」日本人を丸ごとひとまとめにして、敗戦後に生命を絶つた日本人と並べ置くといふ対比の仕方は、他に例を見ないものと言つてよい。 (本書104頁)
管見の限りですが、私もほかには知りません。この二分法は、〈大東亜戦争の絶対性〉がキー・ワードになるものと思われます。つまり桶谷は、大東亜戦争の最中にその絶対性に殉じた戦死者に、戦後において自ら命を絶つことで連なった日本人と、そうすることなく「生の方へ歩きだした」日本人とを対比させているのです。ここでひとつお断りしておきたいのは、私はなにも、大東亜戦争における戦死者が皆その絶対性に殉じたといいたいのではなくて、戦後において大東亜戦争を意識しながら自ら命を絶った日本人の心中には、その戦争の最中にその絶対性に殉じた戦死者の姿があっただろうことが申し上げたいだけです。さらには、どっちがいいとかわるいとかの問題ではないことも、誤解を恐れるがゆえに付け加えておきます。
長谷川氏は、この二分法をとても重視しているように感じます。つまり、敗戦という歴史的な事実に、〈大東亜戦争の絶対性〉に殉じた、広い意味での戦死者の存在が内在していることに対する感度があまり鋭くない思想家や文学者を、著者は、あまり評価していないように感じられるのです。その感度を、戦友感覚と言いかえると、少なくとも『戦後史の空間』の磯田光一には戦友感覚があまり感じられないし、石原慎太郎に至ってはまったくと言っていいほどに感じられないとして、本書においてかなり厳しい評価を下しているのです。彼らは、〈大東亜戦争の絶対性〉の問題をそれほどあるいはまったくといっていいほどに引きずることなく戦後空間に歩みだしているようなのです。それに対して、これまで取り上げた思想家や文学者には、鋭い戦友感覚があるとして高く評価しています。また、これから取り上げることになる太宰治や吉本隆明や三島由紀夫にも鋭い戦友感覚があるとされ、本格的な検討の対象になっているのです。彼らの戦後とは、敗戦のもたらした精神的な麻痺との悪戦苦闘の歴史であると申し上げても過言ではない、ということです。著者は、どうやら彼らのそこに向けて目を凝らしているようなのです。
桶谷秀明に、話を戻しましょう。桶谷は、先ほど述べたような敗戦の原風景に関する「確信」をさらに大きく独特の歴史観の形に広げて、『昭和精神史』と『昭和精神史 戦後篇』を著しました。これらの著書で、桶谷は八月十五日をどう描いたのでしょうか。著者が引用した箇所を孫引きしましょう。
八月十五日正午、昭和天皇の終戦の詔勅を聴いて、多くの日本人がおそはれた″呆然自失″といはれる瞬間、極東日本の自然民族が、非情な自然の壁に直面したかのやうな、言葉にならぬ、ある絶対的な瞬間について考へた。そのとき、人びとは何を聴いたのか。あのしいんとした静けさの中で何がきこえたのであらうか。
『天籟』(てんらい)を聴いたのである、と私は(『昭和精神史』の第二〇章で――引用者補)書いた。天籟とは、荘子の『斉物論』に出てくる言葉で、ある隠者が突然、それを聴いたといふ。そのとき、彼は天を仰いで静かに息を吐いた。そのときの彼の様子は、『形は槁木の如く、心は死灰の如く』『吾、我を喪ふ』てゐるやうであつたといふ。
そういう状態でなければ『天籟』は聞こえない、と荘子は隠者の口を通して語つてゐる。 (本書61頁 『昭和精神史 戦後篇』より)
桶谷は、八月十五日正午、日本人は、昭和天皇が終戦の詔書を読み上げるのを聴きながら、音なき音としての「天籟」を聴いた、と言うのです。ふつうに考えれば、そう言われて「そうですか」と素直に納得してうなずく読み手はいないでしょう。平成三~四年当時の人々は、この言葉に触れて、はじめはキョトンとし、やがて、著者に対して憐憫の情を抱くか、何もなかったことにするかのいずれかだったでしょう。たとえ、他の箇所に大いに感動していたとしてもです。
私自身、読書会でつぶさに内容を検討した気でいましたが、残念ながら「天籟」という言葉の印象はあまり残っていなくて、せいぜい、桶谷好みのレトリックが使われているのだろうくらいにしか受け取らなかったと思います。桶谷自身、「だから、どうしたといふのか。そんな怪訝をともなふ反感あるいは薄ら笑ひを、私はたびたび経験したが、賛意をつたへてくれた人はひとりもゐなかつた」と言っているくらいです。さらには、「私のいつてゐることは独断妄念にすぎないのであらうか」とまで突き詰めています。ここで桶谷は、孤独な想念を抱いた者が不可避的に襲われる不安を率直に語っています。
その不安を払拭するかのように、桶谷は、「天籟」という言葉で自分が指し示そうとした事態に同じように気づいたと思われる四人の文章を引用します。それは、昭和二十年九月五日の朝日新聞の社説の筆者と伊東静雄の前回引用した日記の一節と河上徹太郎の文章と太宰治の小説「トカトントン」です。
河上徹太郎の名とその文章のごく一部分は、前回の当文章に出てきましたが、とても重要なものなので、ここできちんと掲げておきましょう。
国民の心を、名も形もなく、ただ在り場所をはつきり抑へねばならない。幸ひ我々はその瞬間を持つた。それは、八月十五日の御放送の直後の、あのシーンとした国民の心の一瞬である。理屈をいひ出したのは十六日以後である。あの一瞬の静寂に間違ひはなかつた。又、あの一瞬の如き瞬間を我々民族が曾て持つたか、否、全人類の歴史であれに類する時が幾度あつたか、私は尋ねたい。御望みなら私はあれを国民の天皇への帰属の例証として挙げようとすら決していはぬ。ただ国民の心といふものが紛れもなくあの一点に凝集されたといふ厳然たる事実を、私は意味深く思ひ起こしたいのだ。今日既に我々はあの時の気持ちと何と隔たりが出来たことだらう! (本書50頁 「ジャーナリズムと国民の心」より)
河上徹太郎の文章を真正面から受けとめるならば、桶谷が「天籟」という言葉によって指し示そうとした何かとても重要なことが、八月十五日には確かにあるようです。それは、伊東静雄が詩的直観によって神話的なアーキタイプとして定着したイメージともどうやら深い関連がありそうでもあります。そこまでは、おぼろげながら私にも分かってきました。
長谷川氏は、現存する思想家ではおそらくただひとり、桶谷の「天籟」という言葉には、八月十五日の謎を解明するうえで極めて重要な手がかりがあることを直観し、深く洞察し、それを読み手がきちんと読めば分かる表現にまで十年の歳月をかけてゆっくりと練り上げたのです。それが、本書の価値の核心をなすものです。しかし、私たちがそこにしっかりとした足取りでたどり着くまでには、太宰治、吉本隆明、三島由紀夫という三つの山を越えた後、『旧約聖書』の「イサク奉献」という峠を越えなければなりません。太宰治の「トカトントン」については、次回に取り上げることにして、差し当たり、次の引用をしておきましょう。文章中の「佐藤氏」とは、『八月十五日の神話』を書いた佐藤卓巳のことです。
佐藤氏は、竹山昭子氏の『玉音放送』を引用して、「この放送の祭儀的性格」を指摘する。すなわち、それは単なる「降伏の告知」ではなく、「各家庭、各職場に儀式空間をもたらした」出来事であり、この放送を通じて国民全体が「儀式への参加」をした。だからこそそれが「忘れられない集合的記憶の核として残った」のだ、と佐藤氏は述べるのである。さらに氏は「この場合、昭和天皇が行使したのは、国家元首としての統治権でも大元帥の統帥権でもなく、古来から続いた祭司王としての祭祀大権であった」と述べて、この八月十五日の玉音放送が徹頭徹尾〈神学的〉な出来事であつたことを指摘してゐるのである。
これはきはめて重要な正しい認識であり、あの「シーンとした国民の一瞬」の謎を考へる上でも、出発点とすべきところである。 (本書69頁)
「八月十五日の玉音放送が徹頭徹尾〈神学的〉な出来事であつた」というキー・センテンスを手放さないようにしながら、私たちは次の「その3」で、太宰の「トカトントン」の音に耳を澄ませてみることにしましょう。 (続く)












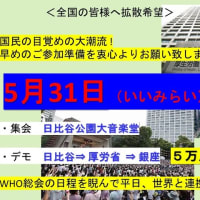















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます