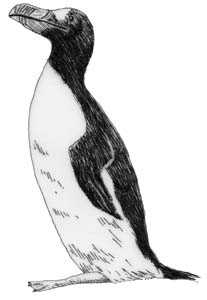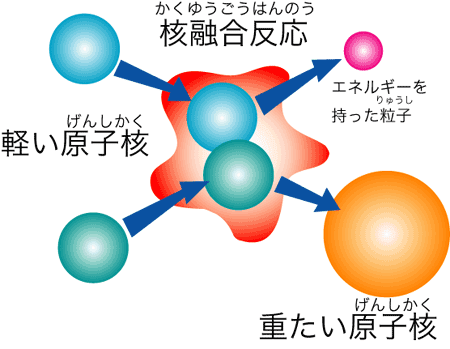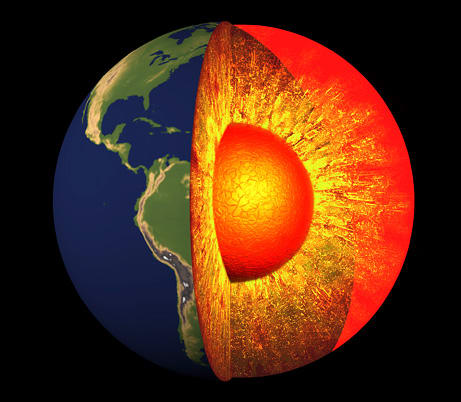いまさら、という気がしないでもないのですが、みなさんとごいっしょに小保方晴子氏の二〇一四年四月九日の記者会見のハイライトを観直してみたいと思います。その前に、踏まえるべき背景や最低限の基礎知識に触れておきたいと思います。
同会見のポイントはいろいろあるとは思いますが、当時の一般人からすれば、「STAP細胞なるものが本当にあるのかないのか、本人の口からじかに聞きたい」というのが本音でしたから、最大のポイントは「STAP細胞の有無」でしょう。
アメリカのハーバード大学が世界各国で特許を出願していることが判明した現段階において、「STAP細胞の有無」問題に関しては決着がついているというよりほかはありません。世界トップレベルの頭脳集団が、ありもしないものを特許申請するとは到底考えられないからです(ちなみに理研は、二〇一四年六月二六日、STAP細胞の存在をはっきりと否定しています。それが理研の公式見解ですhttp://www.nikkei.com/article/DGXLASGG26H0W_W4A221C1MM0000/ )。
小保方氏は、当記者会見でも、また、今年の一月二八日に上梓した手記『あの日』においても、終始一貫して、STAP細胞は存在すると主張しています。
「私が発見した未知の現象は間違いがないものであったし、若山研で私が担当していた実験部分の『STAP現象』の再現性は確認されていた」(238ページ)
http://www.huffingtonpost.jp/2016/01/28/obokata-note_n_9104078.html
では、氏が主張しつづけてきた「STAP細胞」とは、いったい何なのでしょうか。
哺乳類(ほにゅうるい)の体細胞に外部から刺激を与えるだけで、未分化で多能性を有するSTAP細胞に変化するというもの。これまで発見されたES細胞(胚性幹細胞)やiPS細胞(人工多能性幹細胞)といった多能性細胞と比較して作製法が格段に容易であり、またこれらの細胞にはない胎盤への分化能をも有することで、今後、再生医療等への貢献の可能性が大きいと期待された。
(コトバンク「STAP細胞 とは」より)
マウスの脾臓から取り出した「T細胞」と呼ばれる細胞を弱酸性の溶液に浸した後に培養すると、一週間で多能性を持つ細胞になり、それがSTAP細胞と名付けられたのです。
で、STAP細胞のままでは増殖せず、再生医療へ応用できないため、増殖する能力を持つSTAP「幹」細胞を培養する必要があります。
前者を担当したのが小保方氏であり、後者を受け持ったのが氏の上司であった若山照彦氏でした。小保方氏は、後者の『STAP「幹」細胞』と区別される前者の『STAP細胞』の実在を主張し続けてきたのです。
以上を踏まえたうえで、動画をごらんください。
小保方晴子 「STAP細胞はあります!」 会見まとめ (HD)
どうでしょうか。氏が、世間の攻撃的な好奇の視線の矢を受けとめながら、気力を振り絞って、自分の心からの思いを吐露していることが、いまなら多くの人にも分かるのではないでしょうか。有名な「STAP細胞はあります!」という宣言をした直後、記者の無責任な空っとぼけた質問を受けときにも、再現性の重要性に触れるほどの科学者としてのまっとうな理性をキープしているのは、正直驚きです。研究への情熱だけが、そのときの氏を支えていたのではないでしょうか。当時の世間は、やれ役者だとか、やれ妄想はもうやめろとか、空っとぼけるなだとか、ずいぶんひどい言葉を孤軍奮闘の氏に投げつけていたのです。
FB友達の今井進氏が、長時間の同会見を観終わって私が抱いた感想といまの思いを代弁してくれています。ご紹介します。
私は、小保方さんの会見を見て「あぁ、この人は真っ直ぐな人だ。嘘はつかない人だ」と感じていました。やはり、そうでした。嘘つきか嘘つきでないか?それを見る「目」を備えることなく、マスコミやご立派な肩書の持ち主の言うことに騙される人の多さに驚きます。嫉妬がエネルギー源の每日新聞の須田記者、NHKの捏造番組を制作したクズ、その番組に雁首を並べてごにゃごにゃ話していたロクでもない「大学教授」という肩書のアホ達。こいつらが揃って日本を代表する科学者笹井さんを自殺に追いやってしまいました。特に、決定打となったNHKの番組。重罪です。
「でも、小保方氏は、記者会見後に何度も再現実験を試みて失敗しているのだろう?」という疑問が残りますね。
それについて、理研・バカマスコミ総がかりの「小保方バッシング」の動きに終始一貫抗し続けてきた武田邦彦氏が、次のようなことを音声動画で言っています。すなわち《若山氏は、マウス細胞をスライスする超一級の腕前を持っていて、それが小保方氏に提供される。つまり「STAP細胞」は、ふたりの共同作業の賜物なのだ。ところがなぜか、検証のための再現実験のとき、すでに若山氏は理研を去っていて、同氏の協力が得られないまま、小保方氏は事実上ひとりで検証実験を実施しなければならなかった。その段階ですでに、検証の結果は、失敗が運命づけられていたのだ》というふうに。つまり理研は、その段階ですでに、組織防衛のために小保方氏の科学者としての生命を断つことに決めていたのです。そういう理研のひどさについては、もうすこしきちんと勉強してから発表したいと思っております。日本のために、また日本の科学のために、理研は一度潰してしまわなければならないのではなかろうか、という思いを強めております。