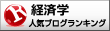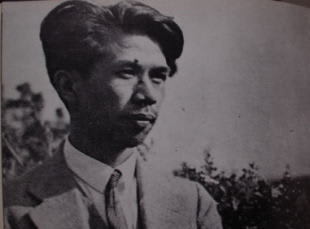三島由紀夫『葉隠入門』(新潮文庫)について(その2)
特攻隊は犬死か
前回、三島由紀夫にとって『葉隠』は、戦中・戦後を通じての「座右の書」であった、というより、戦後においてこそますますその存在は、三島にとって光を放つものとなった、という意味のことを述べました。
三島のそのような言葉は、実のところ極めて反時代的なものであって、戦後社会は『葉隠』をほとんど禁書として扱ってきたのも同然である、と言っても過言ではありません。そのことと平行して、戦後社会は、神風特攻隊を「もっとも非人間的な攻撃方法」とし、それによって命を失った「青年たちは、長らく犬死の汚名をこうむって」きました。最近は、『永遠の0』がベスト・セラーになることで、そういう空気になにがしかの変化が起こっているような気がしますが、ここに至るまでずっとそういう扱いがなされてきたのは歴史的な事実である、と申し上げてよろしいかと思われます。
そのことを踏まえたうえで、三島は、特攻隊がほんとうに犬死なのかどうかを『葉隠』の読み込みを通して突き詰めて考えています。それに触れる前に、『葉隠』のもっとも有名な箇所から引きましょう。その後に、現代語訳も添えておきます(笠原伸夫訳 『葉隠入門』所収)。
武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。二つ二つの場にて、早く死ぬはうに片付くばかりなり。別に仔細なし。胸すわつて進むなり。図に当らぬは犬死などといふ事は、上方風の打ち上りたる武道なるべし。二つ二つの場にて、図に当ることのわかることは、及ばざることなり。我人(われひと)、生くる方がすきなり。多分すきの方に理が付くべし。若し図にはづれて生きたらば、腰抜けなり。この境危ふきなり。図にはづれて死にたらば、犬死気違なり。恥にはならず。これが武道に丈夫なり。毎朝毎夕、改めては死に改めては死に、常住死身になりて居る時は、武道に自由を得、一生越度(おちど)なく、家職を仕果(しおう)すべきなり。
(訳)武士道の本質は、死ぬことだと知った。つまり生死二つのうち、いづれを取るかといえば、早く死ぬほうをえらぶということにすぎない。これといってめんどうなことはないのだ。腹を据えて、よけいなことは考えず、邁進するだけである。″事を貫徹しないうちに死ねば犬死だ″などというのは、せいぜい上方ふうの思い上がった打算的武士道といえる。とにかく、二者択一を迫られたとき、ぜったいに正しいほうをえらぶということは、たいへんにむずかしい。人はだれでも、死ぬよりは生きるほうがよいに決まっている。となれば、多かれすくなかれ、生きるほうに理屈が多くつくことになるのは当然のことだ。生きるほうをえらんだとして、それがもし失敗に終わってなお生きるとすれば、腰抜けとそしられるだけだろう。このへんがむずかしいところだ。ところが、死をえらんでさえいれば、事を仕損じて死んだとしても、それは犬死、気ちがいだとそしられようと、恥にはならない。これが、つまりは武士道の本質なのだ。とにかく、武士道をきわめるためには、朝夕くりかえし死を覚悟することが必要なのである。つねに死を覚悟しているときには、武士道が自分のものとなり、一生誤りなくご奉公し尽くすことができようというものだ。
言い方は表面上ごくあっさりとしているかのようですが、『葉隠』の話者としての山本常朝(じょうちょう)は、ここでとても微妙なこと、いいかえれば、ちょっとでも言い方がずれると受けとめられかたが違ってしまうようなことを、言葉を慎重に選びながらもなるべく率直に語ろうとしています。それを十二分に受けとめたうえで、三島は、こう言います。「人間は死を完全に選ぶこともできなければ、また死を完全に強いられることもできない」と。いいかえれば、「死の形態には、その人間的選択と超人間的運命の暗々裏の相剋が、永久にまつわりついている」というのです。
この言い方のわかりにくさを踏まえたうえでのことと思われますが、三島は、さまざまな例を挙げて、読み手を説得しようとします。
例のひとつめ、「葉隠」の死。上の引用で暗示されているような死は、一見、強制された死とは無限に遠い、選ばれた死であるかのようです。しかし、三島はそうではないと言います。すなわち、「葉隠」は選びうる行為としての死へ向かって、わたしたちの決断を促そうとしているのではありますが、その促しの裏には、山本常朝という「殉死を禁じられて生きのびた一人の男の、死から見放された深いニヒリズムの水たまりが横たわっている」というのです。いいかえれば、「選ぶ」という行為の積極的な価値を無に帰しかねないものとの相剋が、常朝の内面にはあったということです。ここで三島は、文学者らしい妄想を膨らまして世迷言を開陳しているわけではありません。次に引くのは、「葉隠」の文章であって、ほかのだれかの文章ではありません。
人間一生誠に纔(わづか)の事なり。好いた事をして暮すべきなり。夢の間の世の中に、すかぬ事ばかりして苦を見て暮すは愚なることなり。この事は、悪しく聞いては害になる事故、若き衆んどへ終に語らぬ奥の手なり。我は寝る事が好きなり。今の境界相応に、いよいよ禁足して、寝て暮すべしと思ふなり。
定朝はここで、次のように言っています。「人間の一生なんてほんとうに短いものだ。だから、好きなことをしてくらすがよい。夢のようにはかなく過ぎるこの浮世で、好きでもないことをして苦しい思いをして暮らすのは馬鹿げている。これは誤解されるとろくなことがないので、若い人びとへ語らずに終わった秘伝のようなもの。わたしは寝ることが好きだ。いまの自分の境遇にふさわしい形で、なるべく家の中にとじこもって、寝て暮らそうと思っている」
これは、たとえば、俳人・小林一茶が六〇歳のときに阿弥陀様に「これから自分を荒凡夫(あらぼんぷ)として生きさせてほしい」と願い出た心持ちに通じるところがあります。つまり、定朝はここで、ニヒリズムとすれすれのふうわりとした生の肯定感をすんなりと吐露しているのです。この構えがあってこそ、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という死への覚悟の決め方が、豊かな身体性を伴った言葉として鮮烈にわたしたちに迫ってくるのではないでしょうか。
例のふたつめ、死刑。死刑は強いられた死としての極端な例であるかのようですが、三島によれば、「精神をもってそれに抵抗しようとするときには、それはたんなる強いられた死ではなくなるのである」。この視点は、三島が良質な文学的感性の持ち主であることを十分に物語っているのではないでしょうか。いいかえれば、三島はここで、文学なるものの存在根拠を、真正面からではなく側面から指し示しているのです。私はここに、福田恆存が「一匹と九九匹」という言葉で文学の本質を表そうとした心持ちに一脈通じるものを感じます。
例のみっつめ、自殺。これは、三島自身の死に方に大いに関わるものなので、私としても少なからず興味関心を喚起されます。三島は、「自由意思の極地のあらわれと見られる自殺にも、その死へいたる不可避性には、ついに自分で選んで選び得なかった宿命の因子が働いている」という言い方をしています。ここに、後の三島の死に様に関する予言的なものを読み取るのは、私だけではないでしょう。また、太宰治の死に様にも、その言い方が当てはまるように感じるのも、私ひとりではないでしょう。もっと言ってしまえば、すべての自殺に、その死を選び取ったひとびとの「宿命の因子」の所在を感じ取ることができるのではないでしょうか。私には、そのように感じられます。
例のよっつめ、病死。三島は、病死について「またたんなる自然死のように見える病死ですら、そこの病死に運んでいく経過には、自殺に似た、みずから選んだ死であるかのように思われる場合が、けっして少なくない」という言い方をしています。これで思い出すのは、私の母方の祖母のケースです。私事にわたって恐縮ですが、述べさせていただきます。祖母は、五〇年ほど前に胃がんで亡くなりました。まわりの人々は、当時その死をめぐって以下のような言い方をしました。
祖母は祖父とともに田舎でいわゆる万事(よろず)屋を営んでいました。だから祖母は、家事や客対応や業者とのやり取りや隣近所からの来客のもてなしで忙しくて、落ち着いてご飯を食べる時間的な余裕がほとんどなかった。で、その食生活のスタイルは、時間がちょっと空いたときにササッと済ますという形になってしまった。そのことが、胃がんにおおいに関係がある。まわりの人々は、そういう言い方をしたのです。そこには、自分の体をそっちのけにして、献身的によそ様のために働き続けた祖母の死を悼むひとびとの思いが込められていました。つまり、胃がんという病死は、いかにも祖母らしい死に方であるとひとびとは受けとめたのです(内輪ぼめのようで、あまり説得力がないのかもしれませんが、祖母は本当にとてもいい人だったのです)。
以上のように、死をめぐる選択性と不可避性・強制性の問題を具体例に即して検討したうえで、三島はこう述べます。
すなわち、「葉隠」にしろ、特攻隊にしろ、一方が選んだ死であり、一方が強いられた死だと、厳密にいう権利はだれにもないわけなのである。問題は一個人が死に直面するときの冷厳な事実であり、死にいかに対処するかという人間の精神の最高の緊張の姿は、どうあるべきかという問題である。
それを私なりに言いかえると、こうなります。すなわち、
ひとりひとりの死は、それがどのような形をとろうとも、100%の選択性や100%の不可避性・強制性として現象することはありえない。すべての死は、その両極の中間領域のどこかしらに位置する。その場合、問題として残るのは、人間としての尊厳を賭けた自由が、どこにどういう形で存する余地があるのか、ということなのである、と。それを三島流に「正しい目的にそうた死というものは、はたしてあるのだろうか」と言い直しても、基本は同じことでしょう。
三島は、『葉隠』の読み解きに即して、この問いに答えることはひとりの人間の判断を超えている、言いかえれば、それに答えようとすることは、「煩瑣な、そしてさかしらな」行為であると言います。その理由は端的に「われわれは死を最終的に選ぶことはできないからである」と述べられます。これまでの死をめぐる三島の議論を基本的に是とするならば、この理由づけもまた是とされるよりほかはないでしょう。ここで、三島はとても微妙なもの言いをしています。
だからこそ「葉隠」は、生きるか死ぬかというときに、死ぬことをすすめているのである。それは決して死を選ぶことだとは言っていない。なぜなら、われわれにはその死を選ぶ基準がないからである。われわれが生きているということは、すでに何ものかに選ばれていたことかもしれないし、生がみずから選んだものでない以上、死もみずから最終的に選ぶことができないのかもしれない。
三島は、死をめぐって何かを断言しようとしているわけではありません。むしろ断言しえないことをこそ、読み手に伝えようとしているようです。戦後思想批判の文脈に即するならば、戦後思想がひたすらに生の方向にのみ積極的な意義を見出し、死の問題を本腰を入れて考えようとせず、死の不可避性の問題と全身全霊で取り組んだ末に、決然として死に赴いた特攻隊員たちの秘められた胸の内に本気になって思いを致そうとしない態度の断定性・断言性に対して、三島は、生死観の根本から異議申し立てをしようとしているのです。『葉隠』のなかの「図に当たらぬは犬死などと」したり顔に言いたがる「上方風の打ち上がりたる武士道」とは、戦後思想にこそふさわしい形容である、という三島の声が聴こえてきそうです。「図に当た」る死とは、現代風に言い直せば、「正しい目的のために正しく死ぬ」ということであって、そういう主張は、空疎な不可能事であると、三島は言っているのです。
われわれは、一つの思想や理論のために死ねるという錯覚に、いつも陥りたがる。しかし「葉隠」が示しているのは、もっと容赦ない死であり、花も実もないむだな犬死さえも、人間としての尊厳を持っているということを(常朝は――引用者補)主張しているのである。もし、われわれが生の尊厳をそれほど重んじるならば、どうして死の尊厳をも重んじないわけにいくであろうか。いかなる死も、それを犬死と呼ぶことはできないのである。
「容赦ない」。この言葉ほど、「死」なるものにふさわしい形容句をほかに探すのはむずかしいような気がします。だからこそ、不可避的に有限性の意識を持った人間存在は、「死」に対して、ある姿勢を取らざるをえなくなる。″そのことの余儀なさにこそ、人間なるものの、言葉では言い表し難い尊厳が存する。そこに着目すれば、特攻隊を犬死であるなどとは、口が腐っても言えなくなる。そういう振る舞いは、死に直面しえない脆弱な思想の愚かしい不遜さにほからないない″と三島が言っているように、私の耳には響きます。これほどにまっとうな言葉を、一九六七年という戦後の真っ只中で表出しえた三島を、私は掛け値なしにたいしたものだと褒め称えたい。 (次回に続く)
特攻隊は犬死か
前回、三島由紀夫にとって『葉隠』は、戦中・戦後を通じての「座右の書」であった、というより、戦後においてこそますますその存在は、三島にとって光を放つものとなった、という意味のことを述べました。
三島のそのような言葉は、実のところ極めて反時代的なものであって、戦後社会は『葉隠』をほとんど禁書として扱ってきたのも同然である、と言っても過言ではありません。そのことと平行して、戦後社会は、神風特攻隊を「もっとも非人間的な攻撃方法」とし、それによって命を失った「青年たちは、長らく犬死の汚名をこうむって」きました。最近は、『永遠の0』がベスト・セラーになることで、そういう空気になにがしかの変化が起こっているような気がしますが、ここに至るまでずっとそういう扱いがなされてきたのは歴史的な事実である、と申し上げてよろしいかと思われます。
そのことを踏まえたうえで、三島は、特攻隊がほんとうに犬死なのかどうかを『葉隠』の読み込みを通して突き詰めて考えています。それに触れる前に、『葉隠』のもっとも有名な箇所から引きましょう。その後に、現代語訳も添えておきます(笠原伸夫訳 『葉隠入門』所収)。
武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。二つ二つの場にて、早く死ぬはうに片付くばかりなり。別に仔細なし。胸すわつて進むなり。図に当らぬは犬死などといふ事は、上方風の打ち上りたる武道なるべし。二つ二つの場にて、図に当ることのわかることは、及ばざることなり。我人(われひと)、生くる方がすきなり。多分すきの方に理が付くべし。若し図にはづれて生きたらば、腰抜けなり。この境危ふきなり。図にはづれて死にたらば、犬死気違なり。恥にはならず。これが武道に丈夫なり。毎朝毎夕、改めては死に改めては死に、常住死身になりて居る時は、武道に自由を得、一生越度(おちど)なく、家職を仕果(しおう)すべきなり。
(訳)武士道の本質は、死ぬことだと知った。つまり生死二つのうち、いづれを取るかといえば、早く死ぬほうをえらぶということにすぎない。これといってめんどうなことはないのだ。腹を据えて、よけいなことは考えず、邁進するだけである。″事を貫徹しないうちに死ねば犬死だ″などというのは、せいぜい上方ふうの思い上がった打算的武士道といえる。とにかく、二者択一を迫られたとき、ぜったいに正しいほうをえらぶということは、たいへんにむずかしい。人はだれでも、死ぬよりは生きるほうがよいに決まっている。となれば、多かれすくなかれ、生きるほうに理屈が多くつくことになるのは当然のことだ。生きるほうをえらんだとして、それがもし失敗に終わってなお生きるとすれば、腰抜けとそしられるだけだろう。このへんがむずかしいところだ。ところが、死をえらんでさえいれば、事を仕損じて死んだとしても、それは犬死、気ちがいだとそしられようと、恥にはならない。これが、つまりは武士道の本質なのだ。とにかく、武士道をきわめるためには、朝夕くりかえし死を覚悟することが必要なのである。つねに死を覚悟しているときには、武士道が自分のものとなり、一生誤りなくご奉公し尽くすことができようというものだ。
言い方は表面上ごくあっさりとしているかのようですが、『葉隠』の話者としての山本常朝(じょうちょう)は、ここでとても微妙なこと、いいかえれば、ちょっとでも言い方がずれると受けとめられかたが違ってしまうようなことを、言葉を慎重に選びながらもなるべく率直に語ろうとしています。それを十二分に受けとめたうえで、三島は、こう言います。「人間は死を完全に選ぶこともできなければ、また死を完全に強いられることもできない」と。いいかえれば、「死の形態には、その人間的選択と超人間的運命の暗々裏の相剋が、永久にまつわりついている」というのです。
この言い方のわかりにくさを踏まえたうえでのことと思われますが、三島は、さまざまな例を挙げて、読み手を説得しようとします。
例のひとつめ、「葉隠」の死。上の引用で暗示されているような死は、一見、強制された死とは無限に遠い、選ばれた死であるかのようです。しかし、三島はそうではないと言います。すなわち、「葉隠」は選びうる行為としての死へ向かって、わたしたちの決断を促そうとしているのではありますが、その促しの裏には、山本常朝という「殉死を禁じられて生きのびた一人の男の、死から見放された深いニヒリズムの水たまりが横たわっている」というのです。いいかえれば、「選ぶ」という行為の積極的な価値を無に帰しかねないものとの相剋が、常朝の内面にはあったということです。ここで三島は、文学者らしい妄想を膨らまして世迷言を開陳しているわけではありません。次に引くのは、「葉隠」の文章であって、ほかのだれかの文章ではありません。
人間一生誠に纔(わづか)の事なり。好いた事をして暮すべきなり。夢の間の世の中に、すかぬ事ばかりして苦を見て暮すは愚なることなり。この事は、悪しく聞いては害になる事故、若き衆んどへ終に語らぬ奥の手なり。我は寝る事が好きなり。今の境界相応に、いよいよ禁足して、寝て暮すべしと思ふなり。
定朝はここで、次のように言っています。「人間の一生なんてほんとうに短いものだ。だから、好きなことをしてくらすがよい。夢のようにはかなく過ぎるこの浮世で、好きでもないことをして苦しい思いをして暮らすのは馬鹿げている。これは誤解されるとろくなことがないので、若い人びとへ語らずに終わった秘伝のようなもの。わたしは寝ることが好きだ。いまの自分の境遇にふさわしい形で、なるべく家の中にとじこもって、寝て暮らそうと思っている」
これは、たとえば、俳人・小林一茶が六〇歳のときに阿弥陀様に「これから自分を荒凡夫(あらぼんぷ)として生きさせてほしい」と願い出た心持ちに通じるところがあります。つまり、定朝はここで、ニヒリズムとすれすれのふうわりとした生の肯定感をすんなりと吐露しているのです。この構えがあってこそ、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という死への覚悟の決め方が、豊かな身体性を伴った言葉として鮮烈にわたしたちに迫ってくるのではないでしょうか。
例のふたつめ、死刑。死刑は強いられた死としての極端な例であるかのようですが、三島によれば、「精神をもってそれに抵抗しようとするときには、それはたんなる強いられた死ではなくなるのである」。この視点は、三島が良質な文学的感性の持ち主であることを十分に物語っているのではないでしょうか。いいかえれば、三島はここで、文学なるものの存在根拠を、真正面からではなく側面から指し示しているのです。私はここに、福田恆存が「一匹と九九匹」という言葉で文学の本質を表そうとした心持ちに一脈通じるものを感じます。
例のみっつめ、自殺。これは、三島自身の死に方に大いに関わるものなので、私としても少なからず興味関心を喚起されます。三島は、「自由意思の極地のあらわれと見られる自殺にも、その死へいたる不可避性には、ついに自分で選んで選び得なかった宿命の因子が働いている」という言い方をしています。ここに、後の三島の死に様に関する予言的なものを読み取るのは、私だけではないでしょう。また、太宰治の死に様にも、その言い方が当てはまるように感じるのも、私ひとりではないでしょう。もっと言ってしまえば、すべての自殺に、その死を選び取ったひとびとの「宿命の因子」の所在を感じ取ることができるのではないでしょうか。私には、そのように感じられます。
例のよっつめ、病死。三島は、病死について「またたんなる自然死のように見える病死ですら、そこの病死に運んでいく経過には、自殺に似た、みずから選んだ死であるかのように思われる場合が、けっして少なくない」という言い方をしています。これで思い出すのは、私の母方の祖母のケースです。私事にわたって恐縮ですが、述べさせていただきます。祖母は、五〇年ほど前に胃がんで亡くなりました。まわりの人々は、当時その死をめぐって以下のような言い方をしました。
祖母は祖父とともに田舎でいわゆる万事(よろず)屋を営んでいました。だから祖母は、家事や客対応や業者とのやり取りや隣近所からの来客のもてなしで忙しくて、落ち着いてご飯を食べる時間的な余裕がほとんどなかった。で、その食生活のスタイルは、時間がちょっと空いたときにササッと済ますという形になってしまった。そのことが、胃がんにおおいに関係がある。まわりの人々は、そういう言い方をしたのです。そこには、自分の体をそっちのけにして、献身的によそ様のために働き続けた祖母の死を悼むひとびとの思いが込められていました。つまり、胃がんという病死は、いかにも祖母らしい死に方であるとひとびとは受けとめたのです(内輪ぼめのようで、あまり説得力がないのかもしれませんが、祖母は本当にとてもいい人だったのです)。
以上のように、死をめぐる選択性と不可避性・強制性の問題を具体例に即して検討したうえで、三島はこう述べます。
すなわち、「葉隠」にしろ、特攻隊にしろ、一方が選んだ死であり、一方が強いられた死だと、厳密にいう権利はだれにもないわけなのである。問題は一個人が死に直面するときの冷厳な事実であり、死にいかに対処するかという人間の精神の最高の緊張の姿は、どうあるべきかという問題である。
それを私なりに言いかえると、こうなります。すなわち、
ひとりひとりの死は、それがどのような形をとろうとも、100%の選択性や100%の不可避性・強制性として現象することはありえない。すべての死は、その両極の中間領域のどこかしらに位置する。その場合、問題として残るのは、人間としての尊厳を賭けた自由が、どこにどういう形で存する余地があるのか、ということなのである、と。それを三島流に「正しい目的にそうた死というものは、はたしてあるのだろうか」と言い直しても、基本は同じことでしょう。
三島は、『葉隠』の読み解きに即して、この問いに答えることはひとりの人間の判断を超えている、言いかえれば、それに答えようとすることは、「煩瑣な、そしてさかしらな」行為であると言います。その理由は端的に「われわれは死を最終的に選ぶことはできないからである」と述べられます。これまでの死をめぐる三島の議論を基本的に是とするならば、この理由づけもまた是とされるよりほかはないでしょう。ここで、三島はとても微妙なもの言いをしています。
だからこそ「葉隠」は、生きるか死ぬかというときに、死ぬことをすすめているのである。それは決して死を選ぶことだとは言っていない。なぜなら、われわれにはその死を選ぶ基準がないからである。われわれが生きているということは、すでに何ものかに選ばれていたことかもしれないし、生がみずから選んだものでない以上、死もみずから最終的に選ぶことができないのかもしれない。
三島は、死をめぐって何かを断言しようとしているわけではありません。むしろ断言しえないことをこそ、読み手に伝えようとしているようです。戦後思想批判の文脈に即するならば、戦後思想がひたすらに生の方向にのみ積極的な意義を見出し、死の問題を本腰を入れて考えようとせず、死の不可避性の問題と全身全霊で取り組んだ末に、決然として死に赴いた特攻隊員たちの秘められた胸の内に本気になって思いを致そうとしない態度の断定性・断言性に対して、三島は、生死観の根本から異議申し立てをしようとしているのです。『葉隠』のなかの「図に当たらぬは犬死などと」したり顔に言いたがる「上方風の打ち上がりたる武士道」とは、戦後思想にこそふさわしい形容である、という三島の声が聴こえてきそうです。「図に当た」る死とは、現代風に言い直せば、「正しい目的のために正しく死ぬ」ということであって、そういう主張は、空疎な不可能事であると、三島は言っているのです。
われわれは、一つの思想や理論のために死ねるという錯覚に、いつも陥りたがる。しかし「葉隠」が示しているのは、もっと容赦ない死であり、花も実もないむだな犬死さえも、人間としての尊厳を持っているということを(常朝は――引用者補)主張しているのである。もし、われわれが生の尊厳をそれほど重んじるならば、どうして死の尊厳をも重んじないわけにいくであろうか。いかなる死も、それを犬死と呼ぶことはできないのである。
「容赦ない」。この言葉ほど、「死」なるものにふさわしい形容句をほかに探すのはむずかしいような気がします。だからこそ、不可避的に有限性の意識を持った人間存在は、「死」に対して、ある姿勢を取らざるをえなくなる。″そのことの余儀なさにこそ、人間なるものの、言葉では言い表し難い尊厳が存する。そこに着目すれば、特攻隊を犬死であるなどとは、口が腐っても言えなくなる。そういう振る舞いは、死に直面しえない脆弱な思想の愚かしい不遜さにほからないない″と三島が言っているように、私の耳には響きます。これほどにまっとうな言葉を、一九六七年という戦後の真っ只中で表出しえた三島を、私は掛け値なしにたいしたものだと褒め称えたい。 (次回に続く)