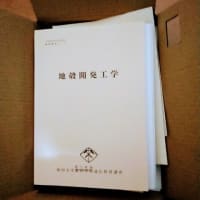この作品は銭形平次の作者として有名な野村胡堂が、捕物小説について述べたエッセイである。割と有名なことだが胡堂さんは旧制一高から東大法学部に進んだが、父親が死亡し学費が続かなくなったので中退している。要するに当時のエリート(少なくともその候補)とも言えるだろう。
だから自ら書いている捕物小説にはかなりのプライドをもっているようだ。まずこのような記述がある。
捕物小説の構成上の制約は実に大きい。第一に、ピストルも青酸加里も使えない。ビルディングで活躍することも出来ない。時間の問題にしても、ゴーンと鳴る鐘の音にしか頼るべきものがない。この様に非常に極限された制約のなかで、人間と人間 ― 心と心のふれ合いの中に、ただ、人情の機微の中にトリックが生まれ出なければならない。
要するに、捕物小説は普通の探偵小説より高尚だと言っているのだ。
胡堂さんの探偵小説家以外の一般の作家たちに対する評価は厳しい。本作品には次のようにある。
探偵小説には、純粋に論理的な知性が絶対に必要である。曾て、徳田秋声と田山花袋が「一つ大衆小説を書いてみようじゃないか、ハッハッハ」と話し合ったということであるが、秋声や花袋は大作家ではあるが大衆文芸はかけなかったように、俺も一つ探偵小説を書いて見ようといった作家たちを、私は軽蔑する。早い話が、数学で落第点を採るような頭で探偵小説を書こうなどとは言語道断である。
ここでは例として徳田秋声と田山花袋が例に挙げられている。秋声や花袋が本当にそんなことを言ったかどうか知らないが、この部分に特に胡堂さんのプライドが透けてみえるような気がするのだが。
☆☆☆☆