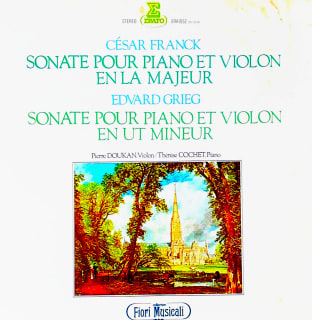ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第7番/第10番
ヴァイオリン:ヨーゼフ・シゲティ
ピアノ:クラウディオ・アラウ
発売:1976年
LP:キングレコード SOL 5040
“ヨーゼフ・シゲティの芸術”(全4巻)と名付けられたこのLPレコードは、第2次世界大戦の中の1944年(昭和19年)に、米国ワシントンの国会図書館で3回にわたって行われた、ヴァイオリンのヨーゼフ・シゲティ(1892年―1973年)とピアノのクラウディオ・アラウ(1903年―1991年)のよる「ベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ全曲演奏会」のライブ録音盤である。当時、シゲティは50歳代の初めの最盛期にあり、シゲティの真の姿を伝える貴重な録音と言える。シゲティは“ヴァイオリン界の革命児”とも言える存在である。シゲティ以前のヴァイオリン演奏は、ヴィルトオーゾ風の誇張された演奏スタイルか、あるいはヴァイオリンの音色を極限にまで美しく歌い上げる演奏スタイルがほとんどを占めていた。これに対し、シゲティのヴァイオリン演奏は、曲の核心に向かってひたすら演奏し続け、曲の持つ隠された価値を表現するという演奏スタイルをとる。ヴァイオリンの美音に馴れた耳には、シゲティの奏でるヴァイオリンの音は、最初は違和感を持つが、しばらくするとシゲティのひた向きに曲に対峙する姿勢に共感を覚え、聴き終えるとヴァイオリンの音色には拘らなくなっている自分を発見することになる。それほど、シゲティのその曲に対する思い入れは激しいものがある。シゲティの演奏は、その曲に対する自分の解釈をストレートにリスナーに伝えるという求道的な姿勢に貫かれている。ヨーゼフ・シゲティは、ハンガリー・ブタペストの出身。このLPレコードでのシゲティの演奏は、シゲティの特徴である、曲の核心に向かってぐいぐいとつき進むさまが聴き取れる。録音のレベルは、今と比べれば良い状態とは言えないが、1944年のライヴ録音としては、よく音を捉えていると言っていいだろう。第7番の演奏でシゲティは、ベートーヴェンの作品らしく、あくまで力強く、同時に深遠な精神的広がりを持つ、この曲の特徴を如何なく表現し尽す。これほど、この曲の持つ奥の深さを表現し得た演奏は、現在に至るまでないのではないか。聴き終えると、少なくともこの曲に関する限り、ヴァイオリン特有の美音なんて必要でないとまで思ってしまうほど、シゲティの演奏内容は強烈な印象をリスナーに残す。一方、第10番は第9番までの曲とは作曲時期が離れており、後期の作品に近い。このため、通常の演奏は、ややもすると牧歌的な面や悟りに近い表現を取る。しかし、シゲティの演奏だけは違う。第9番までの曲と同じく、力強く内面にぐいぐい食い込む.。シゲティの実演が聴ける貴重な録音。(LPC)