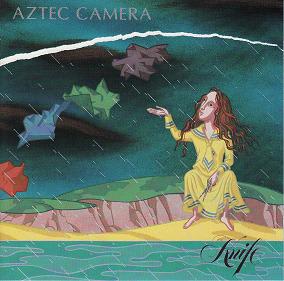VELVET UNDERGUROUND(以下、VUと呼ぶ)の結成は、1965年、なんと私の誕生年なのである。今、こうして彼らの音楽について語っているのも、何かの縁かもしれない。
VUのデビューアルバムが、この「VELVET UNDERGUROUND AND NICO」なのであるが、なんと、このアルバムのプロデュースは、あのポップアートの巨匠、アンディ・ウォーホルなのである!
まあ、そういうことをことさら強調するのは、彼らに対して失礼なのかもしれない。プロデューサーが誰であれ、VUの音楽はVUが作った音楽なのであるから。
このアルバムは、美と破滅をごった煮にしたような作品群で彩られている。
オープニングの「SUNDAY MORNINNG」は、これ以上ないというくらい美しい旋律の曲に、ささやくようなルーのヴォーカルがからむ名曲である。
かと思ったら、2曲目の「I’M WAITING FOR THE MAN」は、泥くさいロックンロール色の強い曲。
3曲目の「FEMME FATALE」で穏やかなメロディにニコの不安定なヴォーカルを乗せてインパクトを掴んで、5曲目の「VENUS IN FURS」で、悩ましい旋律にルーの語りのようなヴォーカルを乗せて聴く者を不安に陥れ、たと思いきや、6曲目の「RUN RUN RUN」でいかにもチープなロックロールで気分を軽めておいた挙句、7曲目の「ALL TOMORROW’S PARTY」で、怪しげなニコのヴォーカルで聴く者を不気味な世界へ引きずりこむ・・・。そして極めつけは「HEROIN」。この曲はルーがその後も事あるごとに歌っている曲で、アンダーグランドをホームグランドの持つVUらしく、薬をうった者の感覚を歌うという、反社会的な曲である。ここがこのアルバムのピークであって、次の2曲で軟着陸を想定させておいて・・・10曲目の「THE BLACK ENGEL’S DEATH SONG」で不要和音を鳴らして、聴く者を不安定にさせるておいて、ラストの「EUROPIAN SON」で、精神をかき乱すようなノイズミュージックを展開して終わるのである。
この作品、非常に素晴らしいアルバムなのであるが、聴き終わったあとのなんとも言えない精神の乱れ・・・これこそが、アンディ・ウォーホルが演出した、現代芸術的ポップミュージックの真髄なのかもしれない。