今回の旅行でどうしても行きたい場所が2つあった。その一つがパスクァラティハウスPasqualatihausである。住所は、1区、Moelker Bastei 8番地。ベートーベンが1804年から15年にかけて暮らしていた住居である。パスクァラティは宮廷御用商人で古くからのベートーベンの後援者である。この家で、交響曲の第5・6・7番やオペラ「フィデリオ」など多くの傑作が生みだされた。建物の5階(4.Stock)にあり、目の前にはウィーン大学が見える。ベートーベンも何度も目にしたことだろう。
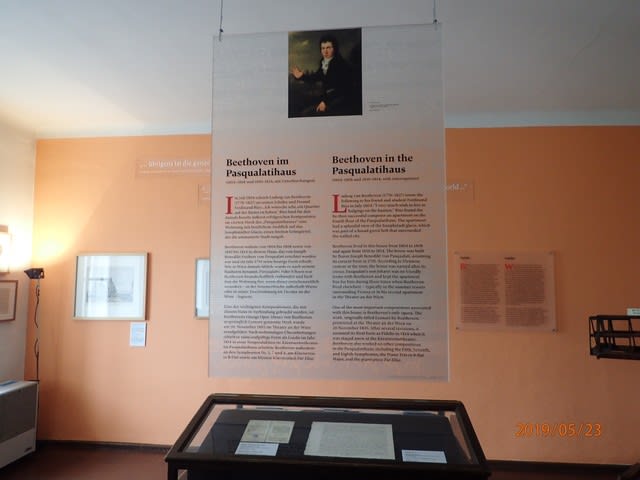
窓から見えるウィーン大学。訪れた日は雨だった。

ベートーベンの肖像画。

尊敬していた祖父の肖像画。ボンから取り寄せたという。

ここではどんな生活をしていたんだろう。床は歩くと、みしみしいう。ベートーベンは、生涯に70回以上引っ越しをしたという。ここはその中でも結構長く使っていたようだ。こんな言葉が残されている。

ここでは写真撮影は自由にできた。

5階へは螺旋階段を使っていく。こんな具合だ。


ベートーベンも毎日上り下りしたのだろうか。引きこもっていた日もあったことだろう。入口はこんな具合。

離れたところからだと、

というふう。
実は住所はわかっていても、地図を見ながらだったが、人に聞いたりしてやっと発見した。近辺には、亡くなったシュヴァルツシュパニエルの場所同様、少しも表示案内などない。
建物を見上げるとこんな感じ。

この一番上に住んでいた。建物は角にある。

帰りは、近道があることを知った。これが目印。

この裏手の坂を上ったところにこの建物はある。通りの前はウィーン大学である。

目印の裏の坂を上ったところにベートーベンの住居がある。ベートーベンもこの坂を上り下りしたことだろう。

この日はウィーンを離れる、旅の終りの前日。ツアーの人たちと一緒に食事をする最後のディナーの日。それで夜は、ホテルから少し行ったところのミシュラン星のいくつか付いたところで食事をした。このとき出されたデザートを美味しくいただいた。いよいよ明日はもうひとつのどうしても行きたかった場所へ。

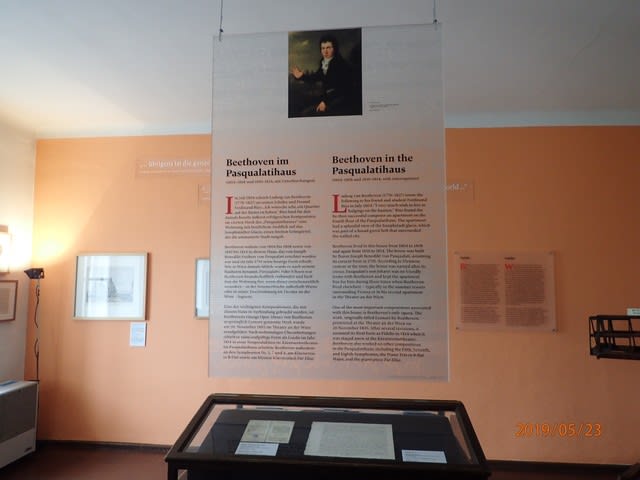
窓から見えるウィーン大学。訪れた日は雨だった。

ベートーベンの肖像画。

尊敬していた祖父の肖像画。ボンから取り寄せたという。

ここではどんな生活をしていたんだろう。床は歩くと、みしみしいう。ベートーベンは、生涯に70回以上引っ越しをしたという。ここはその中でも結構長く使っていたようだ。こんな言葉が残されている。

ここでは写真撮影は自由にできた。

5階へは螺旋階段を使っていく。こんな具合だ。


ベートーベンも毎日上り下りしたのだろうか。引きこもっていた日もあったことだろう。入口はこんな具合。

離れたところからだと、

というふう。
実は住所はわかっていても、地図を見ながらだったが、人に聞いたりしてやっと発見した。近辺には、亡くなったシュヴァルツシュパニエルの場所同様、少しも表示案内などない。
建物を見上げるとこんな感じ。

この一番上に住んでいた。建物は角にある。

帰りは、近道があることを知った。これが目印。

この裏手の坂を上ったところにこの建物はある。通りの前はウィーン大学である。

目印の裏の坂を上ったところにベートーベンの住居がある。ベートーベンもこの坂を上り下りしたことだろう。

この日はウィーンを離れる、旅の終りの前日。ツアーの人たちと一緒に食事をする最後のディナーの日。それで夜は、ホテルから少し行ったところのミシュラン星のいくつか付いたところで食事をした。このとき出されたデザートを美味しくいただいた。いよいよ明日はもうひとつのどうしても行きたかった場所へ。
































 ザルツブルグにはカラヤンの生家があります。ザルツブルク市内見学の時に家の脇の道を通りました。
ザルツブルグにはカラヤンの生家があります。ザルツブルク市内見学の時に家の脇の道を通りました。 ザルツブルクを流れるザルツァッハ川に架かるマカルト小橋の近くにあります。庭には、カラヤンの指揮をする姿の像があり、すぐ目に付きます。
ザルツブルクを流れるザルツァッハ川に架かるマカルト小橋の近くにあります。庭には、カラヤンの指揮をする姿の像があり、すぐ目に付きます。


