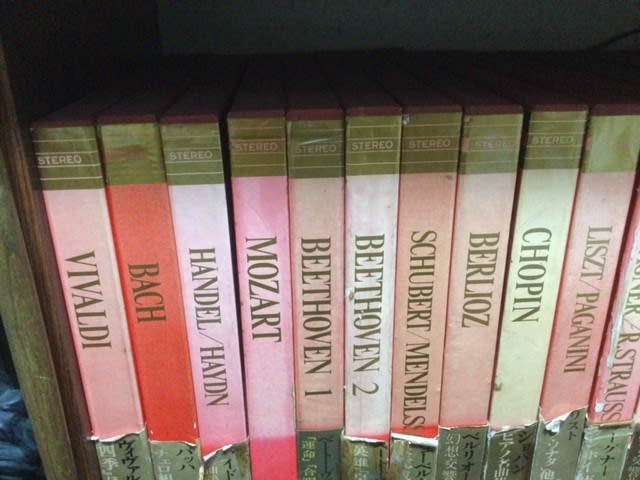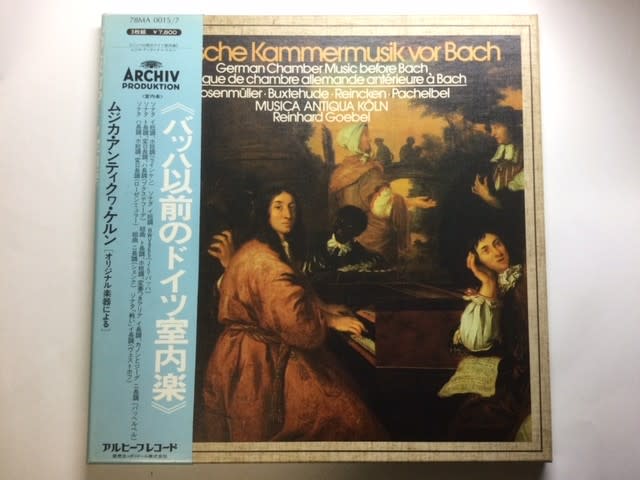ヘンデルは、長く英国で活動していたが、1727年2月イギリスに帰化することになった。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルからジョージ・フレドリック・ハンデルとなったのである。そしてジョージ1世は、彼をただちに「王室礼拝堂作曲家」および「宮廷作曲家」に任命した。
《水上の音楽》は1736年にも演奏された。ジョージ1世を継いだジョージ2世(在位の長男でプリンス・オブ・ウェールズのフレドリック・ルイスとザクセン=ゴータ王女オーガスタとの結婚においてである。

ヘンデルの作品で最も有名な作品と言えば、「ハレルヤ・コーラス」を含む「メサイア」だろう。アイルランドのダブリンで1742年4月13日に初演された。ロンドン初演は、翌1743年3月23日に行われた。この時、来臨していた国王ジョージ2世が、「ハレルヤ・コーラス」が歌われた時、立ち上がり、聴衆もそれに習い一斉に立ち上がったという逸話がある。今でもその習慣は残されているという。日本で、日本人指揮者が日本人の楽団でこのオラトリオを演奏した時、20人ほどのお客さんが立ち上がったという。日本人が真似することはなかろう、それがいやで何年も「メサイア」を聴きに行かないでいた、とある音楽評論家が書いていた。10年以上前のことである。
「メサイア」のロンドン初演と同じ年の6月27日、オーストリア継承戦争(1740~48)中にジョージ2世がデッティンゲンでフランス軍に大勝をおさめるという出来事が起こった。これは王の乗った馬が大砲の音に驚き、敵中に突進したことで得られた勝利だったが、それまで国王や宮廷に対し無関心だった英国民は態度を改めたということである。ヘンデルは、この戦勝記念のために《デッティンゲン・テ・デウム》および《デッティンゲン・アンセム》を作曲し、この年11月27日に初演された。
《水上の音楽》と並んで有名な作品に《王宮の花火の音楽》がある。オーストリア継承戦争がアーヘンの和(1748年)で終結を見せ、戦場が遠方であったため国民の関心が薄く、ジョージ2世が国民に戦勝を示すためにヘンデルに祝賀のための音楽を依頼して作曲されたものだ。1749年4月27日火曜日バッキンガム宮殿北のグリーン・パークで演奏されることになっていた。音楽とともに花火が打ち上げられるはずであったが、《花火の音楽》は演奏されたが、あいにくの雨で花火は点火しても思うようにいかない。そして木造の建物に火が付いた後、ジョージ2世像や平和を象徴するネプチューン増などにも火が付き焼け落ちたということである。
スポーツ大会での優勝者を讃える「優勝賛歌」やコマーシャルでおなじみの「オンブラ・マイ・フ」、これらはヘンデルのオラトリオやオペラからのものである。バッハとともにバロック音楽の2大巨匠と言われるヘンデルは、私たちに心に焼き付く音楽を残してくれたのだった。1759年4月14日亡くなり、ウェストミンスター寺院に埋葬された。
《水上の音楽》は1736年にも演奏された。ジョージ1世を継いだジョージ2世(在位の長男でプリンス・オブ・ウェールズのフレドリック・ルイスとザクセン=ゴータ王女オーガスタとの結婚においてである。

ヘンデルの作品で最も有名な作品と言えば、「ハレルヤ・コーラス」を含む「メサイア」だろう。アイルランドのダブリンで1742年4月13日に初演された。ロンドン初演は、翌1743年3月23日に行われた。この時、来臨していた国王ジョージ2世が、「ハレルヤ・コーラス」が歌われた時、立ち上がり、聴衆もそれに習い一斉に立ち上がったという逸話がある。今でもその習慣は残されているという。日本で、日本人指揮者が日本人の楽団でこのオラトリオを演奏した時、20人ほどのお客さんが立ち上がったという。日本人が真似することはなかろう、それがいやで何年も「メサイア」を聴きに行かないでいた、とある音楽評論家が書いていた。10年以上前のことである。
「メサイア」のロンドン初演と同じ年の6月27日、オーストリア継承戦争(1740~48)中にジョージ2世がデッティンゲンでフランス軍に大勝をおさめるという出来事が起こった。これは王の乗った馬が大砲の音に驚き、敵中に突進したことで得られた勝利だったが、それまで国王や宮廷に対し無関心だった英国民は態度を改めたということである。ヘンデルは、この戦勝記念のために《デッティンゲン・テ・デウム》および《デッティンゲン・アンセム》を作曲し、この年11月27日に初演された。
《水上の音楽》と並んで有名な作品に《王宮の花火の音楽》がある。オーストリア継承戦争がアーヘンの和(1748年)で終結を見せ、戦場が遠方であったため国民の関心が薄く、ジョージ2世が国民に戦勝を示すためにヘンデルに祝賀のための音楽を依頼して作曲されたものだ。1749年4月27日火曜日バッキンガム宮殿北のグリーン・パークで演奏されることになっていた。音楽とともに花火が打ち上げられるはずであったが、《花火の音楽》は演奏されたが、あいにくの雨で花火は点火しても思うようにいかない。そして木造の建物に火が付いた後、ジョージ2世像や平和を象徴するネプチューン増などにも火が付き焼け落ちたということである。
スポーツ大会での優勝者を讃える「優勝賛歌」やコマーシャルでおなじみの「オンブラ・マイ・フ」、これらはヘンデルのオラトリオやオペラからのものである。バッハとともにバロック音楽の2大巨匠と言われるヘンデルは、私たちに心に焼き付く音楽を残してくれたのだった。1759年4月14日亡くなり、ウェストミンスター寺院に埋葬された。