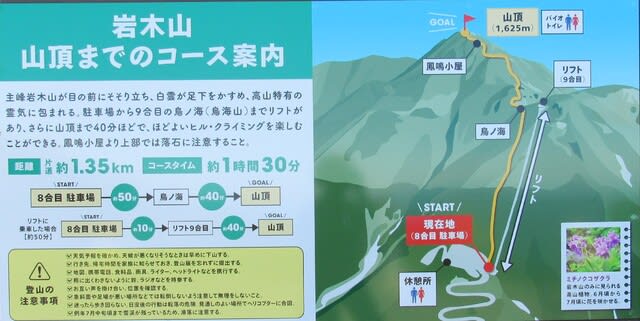4月21日(月)に鞍掛山(くらかけやま 897m)に登った様子を、新・分県登山ガイド[改訂版]2岩手県の山(山と渓谷社)(以下ガイドブック)の記述に沿いながら紹介します。【 】内は私の感想などです。
鞍掛山は岩手山南東部裾野にコブ状に盛り上がる山で、宮沢賢治の詩「くらかけの雪」にも登場する名山である。山域の登山コースは道標なども整備され、初心者にもお勧めの山である。
岩手山を背景に鞍掛山 令和3年4月22日撮影

岩手山の六合目付近からの鞍掛山 令和6年7月27日撮影
登山口となる相の沢キャンプ場の駐車場から西側コースへ続く松林を進む。雑木の混じる登山道は春、マイヅルソウの群落やキクザキイチリンソウ、シラネアオイなどが咲く。
【現地の案内板では山頂まで2時間とありますが、ガイドブックでは1時間であり、この日は休憩を含めて1時間27分でした。】


【キクザキイチリンソウが数株咲いていただけで、他の花は観られませんでした。】
咲いて間もないと思われるキクザキイチリンソウ

次第に右に巻きながら下草の刈り払われた明るい登山道を登る。新コースとの分岐を過ぎると林越しに残雪の岩手山がちらりと望める。
【直進すれば新コースですが右に進みます】

【残雪が現れましたが今日は長靴を履いてきたので安心です】

なだらかに盛り上がるカラマツ林の道は火山砂礫で、マイヅルソウやベニバナイチヤクソウなどがスズランとともに生えている。
【残雪に覆われています】

眺めの良い高台展望台で休憩しよう。眼下の牧場から牛の声が聞こえ、ゆったりと時間が流れている。
【牛の声は聞こえませんでしたが、木々の隙間から姫神山が見えました】

姫神山

平坦な林の道から急な階段を下ると水場もある小沢の橋を渡り、分岐に着く。
右から登ってくる道はキャンプ場へ通じる東側コース。山頂へはカタクリの群生するこの分岐から左へ登っていく。
【例年は咲き始める頃ですが今年は遅れています】

ムシカリの咲く林を登りきると突然視界が開け、岩石が散乱する稜線に出る。北に岩手山が大きくそびえている。ダケカンバやミネザクラなどの林の稜線道を登る。
【ピンクのテープは積雪期の目印と思います】

【大きくそびえているのは姫神山です】

山頂への急斜面に設置された階段を登りつめるとベンチもある鞍掛山の山頂にたどり着く。



北西に大きく立ちはだかる岩手山の鬼又沢が荒々しく印象的だ。西方に連なる峰は秋田駒ケ岳にはじまり、秋田県境の和賀岳や焼石連峰などの山々が南へ続く。
【鬼又沢は中央やや右の深い沢だと思います】

【秋田駒ケ岳は木々に隠れ、焼石連峰は雲の中、辛うじて確認できたのは和賀岳だけです】
東方の北上高地には早池峰山や姫神山を見渡せる大パノラマだ。
【早池峰山は見えませんでした】

【山頂には11時19分から30ほど滞在し、パンとジュースで簡単に腹ごしらえしました】
下山は往路の小沢の流れる分岐点まで戻り、そこから東側コースを下ろう。幅広い林の斜面に咲くエンレイソウやスミレの花が楽しめる。新緑の木々の間を曲がりくねって下るとキャンプ場へ続く牧野との間の林道に出る。右へ林道を進むとキャンプ場前を通過して登山口の相の沢駐車場に戻る。
下山を始めて間もなくの絵にかいたような根開きと長靴


【東側のコースは日当たりが良いだろうと、ガイドブックとおり下山し林道を歩いていると諦めていたカタクリを見つけました】


【エンレイソウもスミレも咲いていませんでしたが、キクザキイチリンソウが綺麗でした】



9時52分に西側のコースから登って、東側のコースを下りて林道に合流し、無事駐車場に戻ってきたのは13時24分でした。

小休止を含む所要時間は、登りが1時間27分で下りが1時間36分でした。これは撮影時間の差によるもので、下山時に疲れが出たり足を痛めたりしたのではありません。
なお、ガイドブックのコースタイムは、登りが1時間で下りが45分ととんでもない数字です。
カタクリが見頃となったころ又出かけてみます。