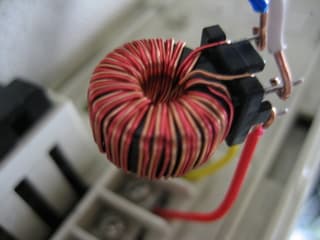アイホン社から頼んでおいたLPFとHPFが届きました。
CQ誌2003年5月号でJI1CYX太田OMが紹介されているフィルターと同型と思われます。
苦言を一つ
私も会社人ですので事情は何となく判りますが
フィルター4個送るのに、なんで30cmサイズのダンボール箱で送って
来るのでしょう?送料が高くなるのはユーザー負担だから構わない、と
お考えでしょうか?(宅配業者に1500円払いました)
折角迅速に無償で対策部品提供いただいて喜んでいたのが、つまらない事で
いい評価がパーです。
早速試してみます・・・・が、VP6TD/DBが聴こえそうで・・・・
CQ誌2003年5月号でJI1CYX太田OMが紹介されているフィルターと同型と思われます。
苦言を一つ
私も会社人ですので事情は何となく判りますが
フィルター4個送るのに、なんで30cmサイズのダンボール箱で送って
来るのでしょう?送料が高くなるのはユーザー負担だから構わない、と
お考えでしょうか?(宅配業者に1500円払いました)
折角迅速に無償で対策部品提供いただいて喜んでいたのが、つまらない事で
いい評価がパーです。
早速試してみます・・・・が、VP6TD/DBが聴こえそうで・・・・