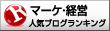事業計画に関連するアドバイスを経済産業省認定支援機関は担います。
そしてその関わり方は各認定支援機関によって違うものです。
では、あらためて認定支援機関は何がご支援出来るのか?
その役割についてふれてみたいと思います。
1、会社のお目付け役(会社・経営者のコントロール)(公平性を保つ)
2、実態把握(グループのビジネス、実態純資産の把握、内部・外部環境)
3、各金融機関行のポジション(担保設定状況、保全・非保全、設定利率)の把握→弁済スケジュールの立案(信用プロラタ・残高プロラタ)
※プロラタとは「按分比率」の事
4、合理的な経営改善計画の作成支援(会社計画PLの合理性・実現可能性検証、単体BS、PL、CF作成、(連結BS、PL、CF作成)、つまり達成可能なPL計画に基づく、弁済原資の算定)
5、再生スキームの具体案の立案
6、経営改善計画案の取りまとめ(実態BS、経営者責任、計画3表、計画3表説明資料、金融支援依頼内容)
7、全金融機関への説明補佐、計画合意までのフォロー、全金融機関訪問、バンクミーティングの開催、電話・メール・QAシートでの質問対応、各行の要望とりまとめ・検討、妥協案の提示と理由
つまり数値計画の実行性を説明補佐する役割を担うのが、「経済産業省 認定支援機関」と言えます。
例えば、ある会社が次のような状況にあるとします。
「返済を半年猶予してほしい」「今を乗り切れば期日通りに返済できる」
金融機関にどのように理解してもらおうか?悩んでいます。
恐らく説明出来る範囲としては、経営者の長年のカン、楽観的な景気観測、経営者としての面子、金融機関との長い付き合いを強調したりします。
これでは金融機関は相談に乗ってくれません。
達成可能・合理的な経営計画、関係者の支援要請、貸付債権の回収期間、他の金融機関との公平性などの「経営者の頭の中」を見える化するのが、経済産業省 認定支援機関の役割なのです。
金融機関に金融支援を求めるためには、その必要性を数値的に示す必要があります。また、経営改善の可能性を示し、それを達成していくことで、金融機関の債権者区分を上方遷移させることが出来ます。
また条件変更であっても、金融機関の支店の担当者レベルで判断出来るものでは無く、本庁審査部、ひいては金融庁による検査の対象になる可能性があります。
その為、計画はあいまいなものではなく、合理的で実現可能な計画である必要があります。
認定支援機関はそれらの計画書作成のご支援を通して健全経営を社長と一緒に目指します。
次回は、より具体的に事業計画書作成にふれていきます。
この経営改善計画書を作成してみましょうシリーズでも2順目の内容となりますので、皆さんのご理解がもっと進む内容で説明していきたいと思っています。
よろしくお願いします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
そしてその関わり方は各認定支援機関によって違うものです。
では、あらためて認定支援機関は何がご支援出来るのか?
その役割についてふれてみたいと思います。
1、会社のお目付け役(会社・経営者のコントロール)(公平性を保つ)
2、実態把握(グループのビジネス、実態純資産の把握、内部・外部環境)
3、各金融機関行のポジション(担保設定状況、保全・非保全、設定利率)の把握→弁済スケジュールの立案(信用プロラタ・残高プロラタ)
※プロラタとは「按分比率」の事
4、合理的な経営改善計画の作成支援(会社計画PLの合理性・実現可能性検証、単体BS、PL、CF作成、(連結BS、PL、CF作成)、つまり達成可能なPL計画に基づく、弁済原資の算定)
5、再生スキームの具体案の立案
6、経営改善計画案の取りまとめ(実態BS、経営者責任、計画3表、計画3表説明資料、金融支援依頼内容)
7、全金融機関への説明補佐、計画合意までのフォロー、全金融機関訪問、バンクミーティングの開催、電話・メール・QAシートでの質問対応、各行の要望とりまとめ・検討、妥協案の提示と理由
つまり数値計画の実行性を説明補佐する役割を担うのが、「経済産業省 認定支援機関」と言えます。
例えば、ある会社が次のような状況にあるとします。
「返済を半年猶予してほしい」「今を乗り切れば期日通りに返済できる」
金融機関にどのように理解してもらおうか?悩んでいます。
恐らく説明出来る範囲としては、経営者の長年のカン、楽観的な景気観測、経営者としての面子、金融機関との長い付き合いを強調したりします。
これでは金融機関は相談に乗ってくれません。
達成可能・合理的な経営計画、関係者の支援要請、貸付債権の回収期間、他の金融機関との公平性などの「経営者の頭の中」を見える化するのが、経済産業省 認定支援機関の役割なのです。
金融機関に金融支援を求めるためには、その必要性を数値的に示す必要があります。また、経営改善の可能性を示し、それを達成していくことで、金融機関の債権者区分を上方遷移させることが出来ます。
また条件変更であっても、金融機関の支店の担当者レベルで判断出来るものでは無く、本庁審査部、ひいては金融庁による検査の対象になる可能性があります。
その為、計画はあいまいなものではなく、合理的で実現可能な計画である必要があります。
認定支援機関はそれらの計画書作成のご支援を通して健全経営を社長と一緒に目指します。
次回は、より具体的に事業計画書作成にふれていきます。
この経営改善計画書を作成してみましょうシリーズでも2順目の内容となりますので、皆さんのご理解がもっと進む内容で説明していきたいと思っています。
よろしくお願いします。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。