
パラダイムシフトについて
多くの会社で取組の割には成果が出ているかわからないとおっしゃっているのが、社内研修だと思います。
これらの根本的原因は3つあります。
1、研修参加者のモチベーション
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチ
3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)
細かい要因はあるにせよ、だいたいこの範囲でおさまります。
まずは参加者のモチベーションですが、これは如何ともしがたいです。
しかしそうも言ってられないので、パラダイムシフトとからめて解決の方向性をお示ししましょう。
1、研修参加者のモチベーションについて
過去に詰め込み型の研修に参加してうんざりした経験があるとか、もともと研修に嫌悪感のある、研修では1円ももうからないから実務をやらせて欲しい、などといったモチベーションが研修からは得られないと思っている、など様々な要因が複雑にからみあっています。
解決するには、各自のパラダイムタイプを見定めて、彼らに合う参加の促し方が必要です。
共感型パラダイムの方は《誰が言っているか》がとても重要です。
理性的パラダイムの方は、論理的に参加が必要であると感じる必要があります。
反応的パラダイムの方は、世の中の動きや宇宙や真理的なものとからませて説明する必要があります。
一つずつ見て行きましょう。
誰が言っているのかに影響を受けるという事は、共感型パラダイムの特徴です。
過去にあるアドバイスを受け、それにより飛躍的に成果が向上したという経験があれば尚の事、次のアドバイスに対してはほぼ無条件に「Aさんのアドバイスはすごい」と思い込みます。さらにそのことを他にも伝えてまわるという現象にも発展していきます。
そのぐらい人から影響を受けます。
ですから、共感的パラダイムの方に伝える際には《誰が言っているのか》はとても重要です。
論理的説明がとても心に響く方もいます。
「なるほど」と思わず納得してしまうので、その状態であれば研修参加もモチベーション高く参加してくれる事でしょう。
理性的パラダイムのキラーワードは《あなたならどうする?》です。
一番説明が厄介なのが、宇宙や真理的なものとからませる説明が必要な反応的パラダイムの方です。この方への説明は超人的領域なので、他の方の付け焼刃な対応ではまかないきれないかもしれません。しかし(若干オーバーに)社運をかけているとか、転換点、世の中を変えるといった言葉で反応的パラダイムの方に訴え続けて、私と一緒に取り組んで欲しいと共感的パラダイムの方が言えば、重い腰を上げてくれるかもしれません。
なぜなら、反応的パラダイムの方は実は共感的パラダイムの方と仲良くしていきたいという願望があります。
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチについて
課題のミスマッチについては、事前の意見収集が重要なファクトとなります。
研修講師の中には、自分の伝えたい事だけをお伝えする方がいらっしゃいます。
その道のプロと言われる方に多いタイプです。
しかし、その会社毎に話す内容を変えて、すべてをご提供するだけではなく、一緒に考えていただいたり、わざと参加者からご指摘をいただくように、参加者が課題を認識出来るようにしてから、内容を深めたりして研修を進行するべきです。
また、研修の内容はとかく経営者の想いがこもっている事があげられます。
普段から問題意識を社長は持っていますが、それが従業員とシェア出来ていない場合、いきなり研修と言われても従業員はなんのこっちゃ?となってしまうのです。
3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)について
これは私にとっても非常に身につまされる事です。
振り返る事で講師がレベルアップを図るしかありませんが、とかく自分の話したい事だけを話すタイプの講師は、まったくこのような事は意に介しません。
参加者の未来に責任を持って、導いていく強い姿勢のない方は講師には向いていないように思われます。
以上のような要因から、成果が出る以前の問題も多くはらんでいます。
事前のディスカッションを多く持っていただける研修講師であれば上記の問題を回避できるかもしれません。
内容だけに惑わされる事なく、しっかりと研修講師を選んでいきたいものですね。
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチについてと3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)についての説明内容を見てどのように皆さん思いましたでしょうか?
2についても3についても、相手のパラダイムタイプを無視する事で研修成果が下がる事をご理解いただけると思います。
そのぐらいパラダイムが与える影響はとてつもなく大きいのです。
今回はパラダイムシフトについての解説でしたね。
相手のモチベーションを高める為にも、パラダイムタイプを知っている事は重要です。
その上で、自分のパラダイムタイプもより変化させる必要が出て来ます。
なぜなら共感的パラダイムの人は、エビデンスなどを用いてAならばBである的な論理的に説明する事がとても苦手です。
ですが、ある程度訓練する事で論理的な説明は出来るようになってきます。
普段から、その理由は3つですといった感じでプレゼンしていると共感的パラダイムの方であっても理性的パラダイムの一端を担う事が可能になって来ます。
面白いもので、後天的に備えた理性的パラダイムはあなたを大いに助けます。
それは社会が数字であふれていますし、物事の善悪をしっかりと示す必要にいつもさらされているからです。
共感的パラダイムだけでは、とても乗り越える事は出来ませんし、酷くなると病んでしまうかもしれません。
このように置かれた状況によりパラダイムを変化させる事は可能です。
では具体的にパラダイムを変化させる事(パラダイムシフト)を行う際に必要な事を皆さんと考えて行きたいと思います。
改善のヒントは普段の習慣になります。
【次回→(続)パラダイムシフトについて】
ブログに関するご質問やご意見は以下のメールにお願いします。
info@irodori-pro.jp
多くの会社で取組の割には成果が出ているかわからないとおっしゃっているのが、社内研修だと思います。
これらの根本的原因は3つあります。
1、研修参加者のモチベーション
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチ
3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)
細かい要因はあるにせよ、だいたいこの範囲でおさまります。
まずは参加者のモチベーションですが、これは如何ともしがたいです。
しかしそうも言ってられないので、パラダイムシフトとからめて解決の方向性をお示ししましょう。
1、研修参加者のモチベーションについて
過去に詰め込み型の研修に参加してうんざりした経験があるとか、もともと研修に嫌悪感のある、研修では1円ももうからないから実務をやらせて欲しい、などといったモチベーションが研修からは得られないと思っている、など様々な要因が複雑にからみあっています。
解決するには、各自のパラダイムタイプを見定めて、彼らに合う参加の促し方が必要です。
共感型パラダイムの方は《誰が言っているか》がとても重要です。
理性的パラダイムの方は、論理的に参加が必要であると感じる必要があります。
反応的パラダイムの方は、世の中の動きや宇宙や真理的なものとからませて説明する必要があります。
一つずつ見て行きましょう。
誰が言っているのかに影響を受けるという事は、共感型パラダイムの特徴です。
過去にあるアドバイスを受け、それにより飛躍的に成果が向上したという経験があれば尚の事、次のアドバイスに対してはほぼ無条件に「Aさんのアドバイスはすごい」と思い込みます。さらにそのことを他にも伝えてまわるという現象にも発展していきます。
そのぐらい人から影響を受けます。
ですから、共感的パラダイムの方に伝える際には《誰が言っているのか》はとても重要です。
論理的説明がとても心に響く方もいます。
「なるほど」と思わず納得してしまうので、その状態であれば研修参加もモチベーション高く参加してくれる事でしょう。
理性的パラダイムのキラーワードは《あなたならどうする?》です。
一番説明が厄介なのが、宇宙や真理的なものとからませる説明が必要な反応的パラダイムの方です。この方への説明は超人的領域なので、他の方の付け焼刃な対応ではまかないきれないかもしれません。しかし(若干オーバーに)社運をかけているとか、転換点、世の中を変えるといった言葉で反応的パラダイムの方に訴え続けて、私と一緒に取り組んで欲しいと共感的パラダイムの方が言えば、重い腰を上げてくれるかもしれません。
なぜなら、反応的パラダイムの方は実は共感的パラダイムの方と仲良くしていきたいという願望があります。
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチについて
課題のミスマッチについては、事前の意見収集が重要なファクトとなります。
研修講師の中には、自分の伝えたい事だけをお伝えする方がいらっしゃいます。
その道のプロと言われる方に多いタイプです。
しかし、その会社毎に話す内容を変えて、すべてをご提供するだけではなく、一緒に考えていただいたり、わざと参加者からご指摘をいただくように、参加者が課題を認識出来るようにしてから、内容を深めたりして研修を進行するべきです。
また、研修の内容はとかく経営者の想いがこもっている事があげられます。
普段から問題意識を社長は持っていますが、それが従業員とシェア出来ていない場合、いきなり研修と言われても従業員はなんのこっちゃ?となってしまうのです。
3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)について
これは私にとっても非常に身につまされる事です。
振り返る事で講師がレベルアップを図るしかありませんが、とかく自分の話したい事だけを話すタイプの講師は、まったくこのような事は意に介しません。
参加者の未来に責任を持って、導いていく強い姿勢のない方は講師には向いていないように思われます。
以上のような要因から、成果が出る以前の問題も多くはらんでいます。
事前のディスカッションを多く持っていただける研修講師であれば上記の問題を回避できるかもしれません。
内容だけに惑わされる事なく、しっかりと研修講師を選んでいきたいものですね。
2、経営者の思っている課題と参加者のミスマッチについてと3、講師の技量不足(内容の充実度、スピーカーとしての能力等)についての説明内容を見てどのように皆さん思いましたでしょうか?
2についても3についても、相手のパラダイムタイプを無視する事で研修成果が下がる事をご理解いただけると思います。
そのぐらいパラダイムが与える影響はとてつもなく大きいのです。
今回はパラダイムシフトについての解説でしたね。
相手のモチベーションを高める為にも、パラダイムタイプを知っている事は重要です。
その上で、自分のパラダイムタイプもより変化させる必要が出て来ます。
なぜなら共感的パラダイムの人は、エビデンスなどを用いてAならばBである的な論理的に説明する事がとても苦手です。
ですが、ある程度訓練する事で論理的な説明は出来るようになってきます。
普段から、その理由は3つですといった感じでプレゼンしていると共感的パラダイムの方であっても理性的パラダイムの一端を担う事が可能になって来ます。
面白いもので、後天的に備えた理性的パラダイムはあなたを大いに助けます。
それは社会が数字であふれていますし、物事の善悪をしっかりと示す必要にいつもさらされているからです。
共感的パラダイムだけでは、とても乗り越える事は出来ませんし、酷くなると病んでしまうかもしれません。
このように置かれた状況によりパラダイムを変化させる事は可能です。
では具体的にパラダイムを変化させる事(パラダイムシフト)を行う際に必要な事を皆さんと考えて行きたいと思います。
改善のヒントは普段の習慣になります。
【次回→(続)パラダイムシフトについて】
ブログに関するご質問やご意見は以下のメールにお願いします。
info@irodori-pro.jp










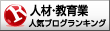

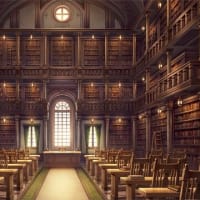







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます