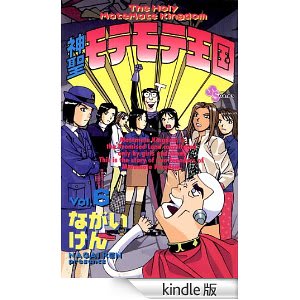
■はじめに■
第二回です。
ここからご覧になった方は、前回からお読みになることをお勧めします。
兵頭新児による二次創作、「ぼくのかんがえた『モテモテ王国』最終回」です。
いや、読みましたよ、『第三世界の長井』。
しかし正直難解すぎてよくわからん!
小ネタとかキャラクターの奇行という「笑いどころ」は『モテモテ王国』と同様に抑えているはずなのに、あの捉え難さは何なのか。例えば『モモ王』は小学生読者が読んでもかなり笑えたと思うけど、『長井』はそういう感じでもなし、コアな読者以外はどう対処してるのか……と言いつつ、女の子の可愛さは格段に上がっていて、それだけで客が呼べそうな辺り、やっぱり漫画はずるいですな。ラノベだとそうはいかん(仮に萌え絵師をつけたとしても、劇中で「機能を果たす」だけのキャラに読者が萌えるものかどうか……)。
さて、それでは。
* * *
「こんな……!?」
眼下の景色に、オンナスキーはただただ信じられない思いで息を飲んでいた。
――知佳さんに連れられ、オンナスキーとファーザー、そしてブタッキーは「軌道エレベータ」に乗って、あの塔を昇っていった。
そしてその窓から眼下を見下ろした時、オンナスキーの目に飛び込んできたのは、ひたすらに広がる荒廃した砂漠であった。
自分たちの乗っているこの「エレベータ」は、その砂漠の中にぽつんと生えている一本の巨木の幹の中を走っているようなものだ。そして、自分たちの住んでいた街は、この巨木の根っこのようなものだった。
――確かにぼくは町田を出たことがない。
しかしその外にもずっと街が続いているはずだ。
はずではあるが、そのことは知識としては持っていたが、しかし街を出た記憶は、考えると確かにぼくにはなかった。
「おい、見ろよ!?」
隣のファーザーの肩を叩くが――しかしファーザーはただ惚けたような顔をしているのみだ。
――仕方ない、コイツはナオンのこと以外は見事なくらい何も考えてないからな――。
オンナスキーは思うが、しかし。
一瞬、既視感に襲われる。
この街の様子、以前にどこかで見たような――そうだ、コイツが漫画に描いた「エレガントシティ」。
町田の姿は、まるで「エレガントシティ」だ。町境から先は、まるでカットしたケーキのように何もなく、後は砂漠となっているという、不可解な姿。
――まさか……コイツはこの町田の真の姿を知っていて?
いや、そんなバカな……。
思っていると、エレベータは停車した。
「着いたの?」
オンナスキーの問いに、知佳さんは首を横に振る。
「このまま当車両は宇宙ロケットに接続いたしまぁす。そして宇宙をさぁっと飛びまして――そして、モテモテ王国へようこそ、といった具合でございます」
少しおどけて、彼女は言った。
「ホールミータイ」
バルコニーの上から、眼下の大広間に集まる何百人もの女性へと、ファーザーが呼びかける。
「あのー、ここに忠良なる汝ら臣民に告ぐ。ジークナオーン!」
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「ファー様ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
何百人もの女性たちの黄色い声が大広間にこだまする。
「ここがモテモテ王国……」
圧倒されるオンナスキー。
ファーザーから何度となく聞かされ、妄想だと信じきっていた「モテモテ王国」へと、今、彼は訪れていた。
「セーットアーップ!!」
ファーザーは広間に降り立つと、目隠しをしてナオンたちと鬼ごっこに興じ始める。
「わあ、ええやんけーええやんけー」
ファーザーを追って広間に降り立ったオンナスキーにもブタッキーにも、等しくナオンは群がってくる。
まさにここはナオンとぼくらだけの蜜あふるる約束の地。
神に約束されたきらめきラブ国家――。
しかしオンナスキーの心に、嬉しさは沸き上がっては来ない。
相変わらず、うるさそうにわずらわしそうにナオンを足蹴にしているブタッキーの気持ちが、今はわかる気がした。
「いかがかしら……?」
知佳さんが歩み寄ってくる。
「一体ここは……これはどういうわけなんです?」
オンナスキーに尋ねられ、知佳さんは答える。
「見た通り。男なら誰もが夢見た愛と徳による絶対王制の、大いなる千年王国――それがここ、モテモテ王国よ」
「そんなの、説明にも何にもなってないです! 町田の外には何故何もないんですか? そして何故、月にモテモテ王国があるんです!?」
――そう、ここは月面上であった。
あの軌道エレベータで人工衛星にまで到達した後、一同は宇宙船に乗り換え、月にまでやって来たのだ。
「いくら何でも信じられるもんか、今までずっとあの小さい町で暮らしてきて……それがいきなり月面基地って……!」
しかしオンナスキーの言葉に、知佳さんは大きく首を横に振る。
「そうかしら? ファーザーさんがどこから来たか、考えてみたこと、ある?」
はっとなるオンナスキー。
二人の出会いは、オンナスキーがナオンに声もかけられずしょげかえっていた時、ファーザーが墜落してきたことがきっかけだ。
ファーザー自身、「生き別れの息子を求めて」「大気圏突入」を敢行したのだと言っている。UFOの所持を匂わせたこともあった。
もちろんいつもの妄想だと決めつけて、オンナスキーはまともに取りあったことはなかったのだが、しかし……。
「それについては、わしから説明するんじゃよ、うなずきトリオひく二人君」
すっと、タイミングよく、ファーザーが現れる。
「お前……ナオンとの鬼ごっこは……?」
オンナスキーの問いかけを無視し、ファーザーは進み出てきた。
「DQNがモテる!」
【怒鬼癒�埖(ドキュン)(DQNネーム)】
見ればファーザーはいかにもDQNといった風体に変装している。
「男としての野生のオーラをぷんぷんと漂わせるDQNこそがナオンの求める究極形態じゃよ?」
「それは……」
思わず言葉につまるオンナスキー。
確かに学校に行けば、いわゆるオタクに比べてそういったヤツがモテている。
もちろん、そういう連中よりも勉強していい大学に行き、いい会社に入ったヤツが最終的には勝ち組になる。そう信じて青春を謳歌しているDQNたちを横目で見て、ぼくは今まで生きてきた、はずだ。
もっとも、こう世の中の景気が悪くては、果たしてそうしたビジョンにどれだけ意味があるのか、わからなくなってきているが……。
思い悩むオンナスキーには構わず、ファーザーは続けた。
あらまし:20XX年。「ジェンダー大戦」後の、フェミニスト国家「にっぽん」。そこはナオンとわしだけの理想国家、蜜あふるる神との約束の地となるはずであった。
だが、ナオンたちの欲求は満たされなかった。彼女らはやはり、人生のパートナーとしての男を欲した。
自分たちが殲滅した「男」を今一度復活させ、理想的な状態へと育て上げよう――そう、ナオンにモテる男性「DQN」再生プロジェクトである。
ナオンはDQNと共に、今度こそ真の理想国家「神聖モテモテ王国」を築き上げるはずであった――。
「おい、まだその話続いてるのか――」
呆れるオンナスキーだが、しかし知佳さんは首を横に振った。
「彼の言ったことは、全部事実よ」
「え゛……?」
あまりのことに、オンナスキーの脳がフリーズする。
「ちょっと待って……じゃあ、その、ジェンダー大戦とかも……?」
知佳さんは頷く。
(声:三石琴乃)
「ジェンダー大戦により、地球は壊滅的打撃を受けた。男性と呼ばれる種はその時に、一度滅んでいるの。急進派のフェミニストが作り出した男性だけを殺す兵器、フェミリカイザーによってね――生き残った僅かな女性が、当時開発が進められていた月面都市へと移住した――それが、ここよ」
「ちょっと待って!」
泡を食って、オンナスキーが問いただす。
「滅んだって、そんなバカな! だってぼくの周りにはむしろファーザーとかトーマスとか、男ばかりが――いや、それだけじゃない! 近所には男子校だってあったし――!」
「彼らは人為的にY染色体を組み込んだ、『レプリカ』と呼ばれる、言わば人造男性。女たちは一度男を滅ぼして、その上でレプリカとして再生させた。でも、当初産み出されたレプリカはことごとくがどういうわけか『草食系男子』、『オタク』と呼ばれるような男性性に欠けた者たちばかりだったの」
思わず、うつむくオンナスキー。
いずれもクラスの女子たちが自分をからかって呼びつけた呼称だ。
「女たちは過去を辿り、女性が『ナオン』と呼ばれていた時代が、女性を『ナオン』と呼んでいた男子たちこそが、最も女性の欲求を満たしていたのだと結論した。
そしてそうした男性たち、いわゆるDQNたちの思考、行動パターンをロボットに組み込み、少年たちの父親役に仕立て上げることを立案したの。
【Dominatable Quondam Numbers】。
直訳すれば支配力を発揮する、過去の人々。
それが女たちの求めた、かつての理想の男性像。
それを求めてDQN再生プロジェクトは開始された。
少年たちに『アパートの一室』を与え、ロボットと共に住まわせることにしたのよ――」
「え゛……っっ!?」
再び、驚きに声をつまらせるオンナスキー。
まじまじと、ファーザーを見つめる。
と、またファーザーは惚けたような顔をしていた。
「コイツは……ロボット……?」
「えぇ、恋愛教育プログラム『Love Admiral(恋愛大将)』を搭載した、『LSM(恋愛シミュレーションマシーン)』。といっても有機体で作られた、構造としては人間に近しいものだけどね――。
LSMを父親にして少年を教育する計画、プロジェクト・ファーザーは一応の成功を見たの。あなたの側にもいるはずよ、女性にモテている男の子が――」
「え?」
考えるオンナスキー。
モテる男と言うと、一人しか思いつかない。
ふと見れば、ブタッキーが群がる女たちを煙たそうにあしらっている。
「あいつが……」
頷く知佳さん。
「わかるでしょ? 『イケメンに限る』というのは俗説。
真理は『ただしDQNに限る』なの――」
しかし、それだと説明のつかないことがある。
「でも、その理屈だと、ロボットを与えられたぼくもモテているはずでは?」
「そうね――いっちゃん、あなたにも本来は正常なLSMが与えられるはずだった。
でも、何らかのアクシデントで、あなたの前にはあのファーザーさんが現れた。試作型として作られ、失敗作として廃棄されていたあのファーザーさんが……」
つまり壊れたロボット?
ダメ少年の下に送り込まれてきた、未来の世界のダメロボットのように?
「じゃ……じゃあぼくは、ナオンの勝手な都合で育てられてきた存在だと?」
オンナスキーが激昂する。
「しかも……壊れた父親ロボットを宛がわれて、どう頑張ってもモテるはずもないムダな努力をさせられてきたと……!?」
「いっちゃん……あなたが薄々感じていたように、私たちも一時期、あなたとファーザーさんを引き離そうかとも考えた。でもね、思ったの……ファーザーさん、そして大王さんたちがあなたにとって必要な存在ではないかって。だから、私はプロジェクト上層部に進言した。あなたを、しばしファーザーさんや大王さんたちとの暮らしの中に置いてやりたいって……」
それは、以前にも彼女の口から発せられたセリフだ。
「ふむ。ナオンにモテない同士は、未知の力でひかれ合うというからにゃあ。お幸せに暮らすがいいぜー」
吐き捨てるファーザーに、オンナスキーが突っ込む。
「バカ、お前もその一人だ」
そして再び知佳さんへと向き直り、続けた。
「どうしてです!? いずれにせよぼくは勝手な意図で教育されてきた存在かも知れない。でも、それならばまだしも、壊れていないロボットに養育された方が――!!」
「確かに、そう考える人たちもいたわ――プロジェクト・ファーザーの上層部はそう考えて、あの人をアパートに送り込んだ……」
「あの人?」
「キャプテン・トーマスよ」
「え……!?」
「そう、トーマスさんこそ本来の機能を果たす、正常なLSM」
「バカな!!」
オンナスキーは嫌悪感を露にする
「あいつは平気で下着泥をやるようなやつで!! ナオンに対しても欲望をぶちまけてるだけのヤツで!! しかも……ヘビトカゲみたいな見るからにバカそうなヤツを子分にまでして……!!」
「そうね……でも、モテるってそういうことよ?」
「う……っ!!」
反論できないオンナスキー。
そもそもDQNプロジェクト自体がDQNを再生させる計画。
となれば、トーマスのようなヤツこそが理想の男性ということになるのかも知れない。
「でも、あいつはヘビトカゲを騙して金まで取って――」
「あは、優しいんだ、いっちゃんは……でもね、女から見た理想の男性って考えればどう? 女を強引に引っ張ってくれると同時に、他の男からは弱肉強食の世界で資産を奪い取り、それを女に還元してくれる――それが理想の男性だって思わない?」
知佳さんは、寂しげに微笑む。
「事実ね、かつての日本において長らく不況が続き、非婚化が問題になった時期があった……男性たちは草食化し、オタク化し、あまり女の子たちと遊んでくれなくなった……それはまるで、いっちゃんたちみたいに――」
「い……いや、ぼくは好きでコイツや大王たちとつるんでたわけじゃ……」
「そうかな? 『早くファーザーを回収してトーマスを深田一郎の部屋に送り込め』が上層部の意向だったのを、私が進言して試験期間を設けてもらったのね、トーマスさんとかかわった時、いっちゃんがどんな反応を示すかを。そして私の想像通り、いっちゃんはトーマスさんのことを好まなかった……」
「そりゃ……あんなヤツ、好きになれるもんか……!」
「でしょう? もし私がファーザーさんとトーマスさんのどちらを選ぶかと尋ねたら、きっといっちゃんはファーザーさんを選ぶ」
「……………」
「私は、その選択を尊重したかった……そして、きっとファーザーさんもいっちゃんのことが……」
「それは……!」
オンナスキーは、大きく首を振った。
確かに、今の知佳さんの言葉を受け容れれば、いろんなことに説明がつく。
ファーザーが何故かトーマスと度々意気投合していたこと。
そしてファーザーもロクなものではないとは言え、トーマスの容赦のなさよりマシだったのは、彼が「できそこないのロボット」だったからだ。
「ぼくは……コイツのことなんか、好きでも何でもないです。ただ、モテてみたかった……でも一人じゃナオンに声もかけられないし……友だちもいなかったし、だから……」
ふと、知佳さんが破顔する。
「そう、友だちみたいなものだったんだよね、いっちゃんにとって――」
「そんなことないです!!」
大きく首を振るオンナスキー。
――確かに知佳さんの言葉が正しければ、謎は全て解ける、気がした。
でも。
「最後にわからないことが残った」
オンナスキーは口を開く。
「ファーザーがレプリカの養育係だってことは、ということは……ぼくも……?」
知佳さんはふと目を伏せる。
「そんなバカな! どういうことです!?」
「いっちゃん……あなた、自分がいくつだかわかる?」
いきなり、彼女はそんなことを尋ねてきた。
「え? 十五歳ですよ?」
「じゃあ中学生? 高校生?」
「あ……? わ、わからない……」
ぼくは確かに学校へと行っている。
休みがちではあっても行っている。
そこには担任の先生も、クラスメートの女子も――しかし今のオンナスキーにとって、学園生活の記憶はかつての記憶同様に曖昧な、おぼろげなものと化していた。
あれは中学だったのか、高校だったのか……。
「わからなくて当然。正解を言うと、あなたの年齢は一歳で、中学生でも高校生でもないの」
「……って、いくら何でもそれはないですよ! 一歳でこんだけ成長してメガネかけてるなんて、あり得ない!」
「いっちゃん……あなたはね、科学者によって作られたの。そう、人工的に作られたレプリカなのよ……」
「そんな……」
あまりのことに、茫然となるオンナスキー。
しかし思い当ることもある。
以前ファーザーが「子供は科学者に作られている」と言っていたこと。
――ぼくは……何だか勝手な理屈で勝手に産み落とされて、たった一人、アパートに押し込められて、ナオンたちの望む男に育てられるため養育ロボットを宛がわれ――いや、そうじゃない。
まともな養育ロボットすら与えられず、壊れた機械を親代わりにされて今まで徒労を重ねてきたんだ――。
がっくりと、オンナスキーはその場に崩れ落ちた――。









