前の記事で、コード奏法についてのたくさんのメリットを書きましたが、コード奏法にもデメリットはあります。
それは、微妙な音の流れや複雑なパッセージなどが伝えられないこと。
演奏の内容は演奏者にまかされるということになるので、音楽性の高い演奏をコード譜面だけで表現するためには、本来 楽譜に書き込まれるべき内容を 楽譜なしで演奏できる、演奏者の高いセンスや高度な技量が必要ということになります。
YouTubeや街ピアノなどで「弾いてみた」や「街ピアノで○○を弾いたら人だかりがして驚かれた」など「どや!」をアピールしてる人がたくさんいます。
コード奏法や耳コピを駆使して、自分の好きなユーチューバーの演奏を真似したり、自分のできる範囲のテクニックの中で最大限に盛った演奏をしてる人たちが目につく。
でもね、ヒバリ先生から見ると(聴くと)、独りよがりな演奏してる人が多いなあ、と思うことが多い。
コードには書き表されない、多声部の絡み合いや微妙な内声の旋律、ダイナミクスの表情などが ピアノの醍醐味なんだけど、そういったものがない単純な構成。もっと丁寧に、曲の魂が伝わるように弾いてほしいなあ、とか、スピードさえ出してればかっこいいとか名人とか思うのは勘違いだよ、とか。
生徒のみんながそういう演奏を見て、かっこいい!と思ったり、真似して弾いたりして、もうこれでピアノはマスターできた!なんでも弾ける!と思っちゃったら残念だなと思います。
もうなんでもできる、と思った時点で、ピアノの上達も成長も止まってしまいます。
ちょっと一つ前の記事を見てもらっていいですか。「コード奏法のメリット」のひとつ「コード奏法によって、好きな歌や知っている曲を弾くことも可能になる」というメリット。よく見てね。それは、「初心者にとって」なんだからね。
「好きな曲が弾ける」って、いくら超スピードで、技巧満載な曲を大音量で弾いていても、独りよがりな演奏では ピアノ精神はしょせん「初心者」なのよ?
本人がそれ止まりで満足ならそれでいいけど、ピアノはすごーく奥が深いので、そのことに気づいた人は、どこまでいっても「もうこれで頂点に達した」などとは思わないです。
まあ、現代のメディアの発達によって、音楽の裾野(すその)が大きく広がった、というのは良いことだよ。
「技巧のある『初心者』がたくさん増えた」って言ったら辛辣(しんらつ)すぎるかな。
軽く愉快にピアノを楽しむ人と、奥深い音楽の森に進んでいく人と、二分化してるってことなのかしらね?
今後の日本のピアノの流れが興味深いところです
HP HIBARIピアノ教室
Youtube HIBARI PIANO CLASS










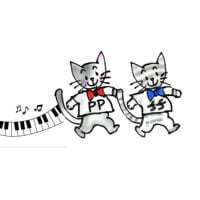

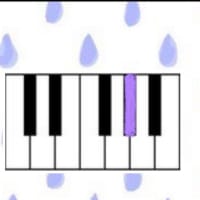







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます